ピックアップ記事
SmartHR Mag.は、人事・労務にまつわるお役立ち情報をお届けし、「働く明日が、もっとよくなる」ための一歩を後押しするメディアです。
最新記事
- 更新日

New


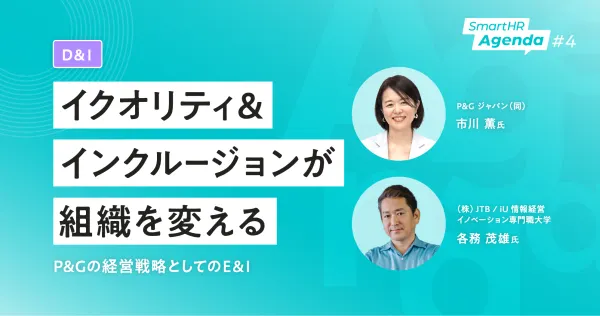

人気の記事
おすすめ記事
人事・労務
経営・組織
働き方
SmartHRガイド
SmartHRの具体的な使い方や運用のヒントをご紹介します。活用から生まれた成果やストーリー、ユーザーと交流できる「コミュニティ」レポートも集めました。
SmartHR Mag.は、人事・労務にまつわるお役立ち情報をお届けし、「働く明日が、もっとよくなる」ための一歩を後押しするメディアです。

New


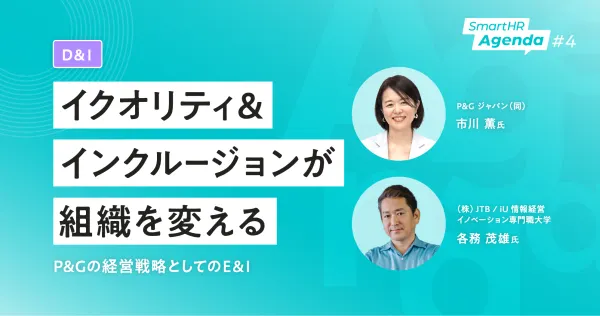

SmartHRの具体的な使い方や運用のヒントをご紹介します。活用から生まれた成果やストーリー、ユーザーと交流できる「コミュニティ」レポートも集めました。