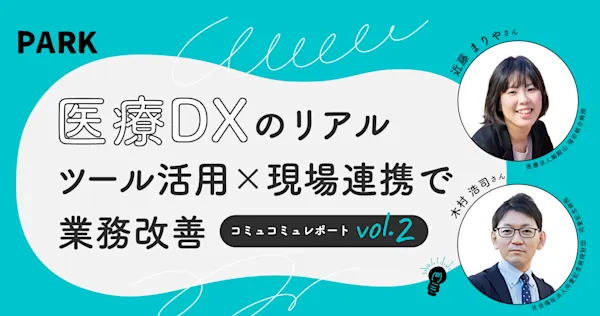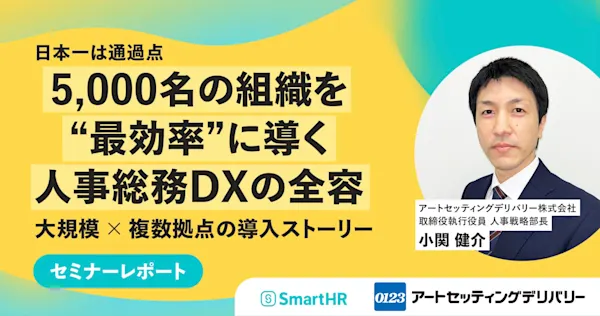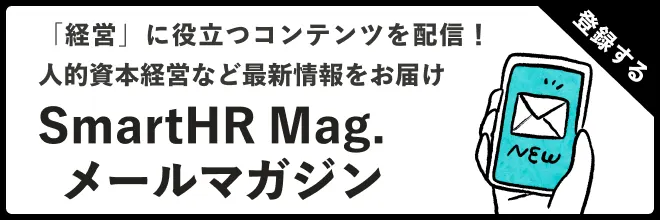従業員数10,000名超えの人事領域DXへ。アダストリアによるSmartHR活用
- 公開日

目次
SmartHRでは経営者・人事担当者の皆さまを対象とした少人数制のセミナー・交流会を定期的に開催しています。今回登壇したのはアパレルや雑貨、飲食など35以上のブランドを国内外に約1,500店舗展開する株式会社アダストリアの方々です。
同社では、DX本部主導のもと人事部と共同したバックオフィスの業務効率化プロジェクトを推進。ペーパーレス化だけではなく、SmartHRで回収したデータを既存システムへ自動連携するシステムの開発まで取り組まれています。
組織におけるDXの実践について、同社DX本部の岩佐さん、人事部の蒲生さんにお話を伺いました。本記事では講演内容をお届けします。
 登壇者岩佐 忠明さん
登壇者岩佐 忠明さん株式会社アダストリア DX本部 チーフマネジャー
大手百貨店グループにて、販売系システムの刷新など幅広いシステム開発を担当。2019年6月株式会社アダストリアに入社し、主に基幹システム、会員・ポイント基盤、店舗業務アプリ等の刷新を担当。現在は、販売系、コーポレート系(経理・人事・その他)の統括リーダーを務め、さらなるDX戦略推進に取り組んでいる。
 登壇者蒲生 良希さん
登壇者蒲生 良希さん株式会社アダストリア 人事部
2018年10月 株式会社アダストリア 入社。人事部にて、主に労務業務を担当
社員が「ワクワク」して働ける環境へ。アダストリアによる“働き方の変革”
はじめにDX本部の岩佐さんがアダストリアにおけるDXの全体像、人事領域のDX化の取り組みについて紹介してくださいました。
アダストリアのDXの土台はコーポレートミッションの「Play fashion!」。ファッションを通じてお客様だけでなく、従業員も毎日ワクワクする新しいものをつくっていく。それぞれの人生を楽しむ。これらをを実現するため、以下2つの変革を進めてきました。
- 顧客体験の変革:世の中を「ワクワク」させるサービスを提供し続ける
- 働き方の変革:社員、スタッフが「ワクワク」して働ける環境をつくる
後者の「働き方の変革」について、岩佐さんが取り組みを開始した2015年の状況を振り返ります。
岩佐さん
利用する業務システムがバラバラで業務ごとに部分的に最適化された状態で、同じ情報を複数システムに登録する必要がありました。さらに紙書類で提出される情報も多く、複数の業務システム間の情報連携を、人力で担っているような状況でした。
着実に変革していくために、以下の3つのステップを設定しました。
- ビジネスインフラの刷新:人が繋ぐのではなくデータ連携して業務を繋ぐ
- コア業務へのシフト:倉庫の機械化やRPA導入により、従業員がコア業務に使える時間を増やす
- 業務の高度化:AIやデータ活用を推進できる状態にする
営業システムについては3つ目の段階に進んでいますが、人事領域を含むバックオフィス系のシステムはまだ1つ目の段階に差し掛かった状態と捉えています。

人事DXに向けて、人事申請・手続きのデジタル化に着手
人事領域のDXについては「管理部門全体のDXとして捉え、社内で取り組みを推進した」と岩佐さんは話します。
具体的にはデジタル化の三本柱を設定。紙や人力に頼っている状態を変えたいというDX部門の思いとユーザー部門の思いを一致させ、経営にアピールし、取り組みをスタートさせたそうです。
- 業務プロセスのデジタル化
- コミュニケーションのデジタル化
- データの蓄積・活用基盤の確立
岩佐さん
当時の人事部門の課題としてシステムの老朽化がありました。保守を引っ張り続けてきた結果、システムの老朽化・保守の限界が迫っていたんです。
また、入社手続きなども紙運用が中心。本社と複数店舗間の紙のやりとりにより配送料もかかります。紙運用による申請ミスや提出漏れも発生していました。
さらに当時の人事部門では、手続きや集計作業、採用状況の確認など、あらゆる作業で複数のシステムを見る必要があり、非効率な状態でした。
システムごとにデータが分断され、従業員の情報を共通で管理できませんでした。データの集計はできても、その先の分析までは及びませんでした。
人事領域のDXに向けて、アダストリアではシステム導入・バージョンアップを推進してきました。目的は「人事申請・手続きのデジタル化」と「人事基幹システムの刷新」です。
岩佐さん
1つ目の「人事申請・手続きのデジタル化」にはSmartHRを導入しました。入社や異動の手続きなど各種人事申請のデジタル化やプラットフォーム統合を進め、アナログからの脱却により店舗の作業工数を削減したいと考えました。また従業員側がスマートフォンで操作できる環境を整え、従業員側の利便性を向上させたいという思いもありました。
2つ目の「人事基幹システムの刷新」については、サポート切れが迫っていたためバージョンアップを進めました。採用管理から労務管理、人材管理、制度にいたるまで、人事関連のシステム全体をプロットし、どのシステムに手を入れる必要があるのかを整理していきました。
システムの導入はDX部門と人事部の2部門で推進しました。システムはシステム部門、人事は人事部門という体制ではなく、人事とDX本部で一緒になって同じプロジェクトを進めたからこそ相互理解が深まり、最適な進め方・仕組みを築けたのではないかと思います。
雇用契約や入社手続き、各種証明書の発行をSmartHRで電子化
続いてSmartHR導入前の課題や活用について人事部の蒲生さんが紹介しました。
アダストリアではパートタイマーの従業員が多く、全体で常時15,000人以上を雇用しています。うち約10,000人が有期のパートタイマーで入退者数も非常に多く、入退社が年間6,000件ほど発生。従業員数や入退者数の多さによる雇用契約の更新作業の負担が大きな課題だったと蒲生さんは振り返ります。

SmartHR導入前の運用では、システム・業務プロセス・コミュニケーションの3つの面で課題があったそうです。
蒲生さん
システム面では、人事系システムが分散していることで運用保守の工数やコストが増加し、システム間のデータ連携は手動対応によるタイムラグが発生していました。
業務プロセス面では、多くの提出書類を紙ベースで管理していたため、店舗での書類確認から本部への送付まで大きな業務負担となっていました。とくに社内メール便は週1回しかなく、書類の発送から受け取りまでに1週間ほどかかっていました。これにより提出が遅れて手続きが長期化するケースや、書類の紛失リスクもありました。
さらにコミュニケーション面では、店舗勤務者に個人のアカウントがなく、店舗の共有アカウントで管理していたため、個人情報に関わる連絡が困難でした。たとえば年末調整の確認が必要な場合は、その方の勤務時間に合わせて電話をかけたり、店長経由で伝言を頼んだりと、非効率な対応を取らざるを得ませんでした。
加えて特徴的なのは特定子会社の役割。アダストリアグループの障害者雇用を担う特例子会社で年金手帳や扶養関係書類といった紙書類の到着確認の仕分けをし、人事に連携する体制をとっていました。
蒲生さん
元の運用の課題は、物理的な書類のやり取りから生じる問題でした。「送ったのに届いていない」「送ったのが1週間遅かった」といった状況が日常的に発生し、後から確認すると単純なコミュニケーションエラーだったということも少なくありませんでした。
SmartHR導入後は雇用契約書の締結・合意や入社書類の回収を電子化。紙書類のやりとりが不要な運用フローを実現しました。
蒲生さん
具体的な流れは、まず店長が雇用契約申請を実施し、人事が承認します。ここまでは従来と同じですが、ここから先が変わりました。
承認した情報をもとに人事側で入社招待や雇用契約書などの文書配付を実施し、本人がSmartHRで文書に合意をし、招待フォームから回答します。
特例子会社との連携も変わりました。これまで紙の書類をチェックしていた作業が、Webの画面での確認に変わりました。
ですが、まだまだ理想的な形にはたどり着いていません。最終的には、雇用契約管理システムで申請をして承認したものが人事基幹システムに自動で連携され、それがSmartHRにAPI連携される。そしてSmartHR内で文書を作成し、雇用契約などを配付して、本人が合意する。このような自動化された流れを目指しています。
もう1つ具体的な例として、蒲生さんは就労証明書の発行をめぐる運用について紹介します。従来は社内メール便での対応により2週間かかっていました。返送期日が迫っている場合は追跡サービス付きで自宅郵送する必要があり、追加のコストも発生。「社内メール便では間に合わないので直接送っていいですか」という電話も頻繁にあったそうです。
蒲生さん
SmartHR導入後は、申請フォームで「就労証明書」や「在籍証明書」など必要な書類を選択できるようになっています。
また、デジタル庁の方針を踏まえて思い切って押印を原則省略しました。代わりに内容確認のため配付書類は合意文書として、右上にスタンプが出る形の文書配付を使用しています。明らかに押印が必要なケースや自治体から求められる場合は別途対応しています。
印刷が必要な場合の対応方法含めて丁寧に共有したことで、従業員にも混乱なく受け入れられていますし、市区町村からも「押印がないけど大丈夫ですか」といった問い合わせは一切ありません。
さらに、労務担当者がテレワークでも証明書の作成処理ができるようになりました。働き方に柔軟性をもたせるという意味でも大きな変化だったと感じています。
人事DXのゴールはデータドリブンな人財最適活用とエンゲージメント向上
最後に蒲生さんから今後の展望やSmartHRへの期待をお話いただきました。
蒲生さん
今後の計画は大きく2つあります。まずシステム面として、文書配付APIのリリースと従業員情報収集APIのリリースに取り組んでいます。ここが自動で連携されれば業務工数が大幅に減らせると考えています。
次に業務運用面です。現在もGoogleフォーム・メール・書面が一部残っている人事申請をSmartHRに順次移行していきたいです。機能面の課題もあるため現在精査しているところです。
岩佐さんからは、人事領域のDXが最終的に目指すものとして「人事プラットフォーム」の構築について紹介いただきました。
岩佐さん
組織管理から採用、社員受け入れ、教育関連、評価、人事管理をすべて同一のIDで統合管理できる状態を目指しています。それによりオペレーションを効率化していきたいです。同一のプラットフォームで管理できるとデータドリブンな戦略人事も実現していけるのではないかと考えています。
人事領域のDXによって目指すのは、従業員が安心して生き生きと能力発揮できる環境の整備と、従業員の満足度向上。自社の社員がどのようなスキルを持っているのか、どういう顔が見える人材なのかが見える化された環境を整え、より戦略的な人材活用を実現したいです。

DX推進に向けて登壇者、参加者同士で交流!
講演後はテーブルディスカッションを実施。講演内容や自社でのDX推進方法について議論が盛り上がりました。

テーブルディスカッションの後は食事と飲み物を挟んだ交流会へ。参加者の緊張もほぐれ、活発にお話される様子が伺えました。


(デモブースも設置し、SmartHRの機能や使い方などを紹介しました)
今後もSmartHRではDXの推進など、人事領域の課題やテーマにした場をお届けしています。ぜひイベント情報もチェックしてみてください。