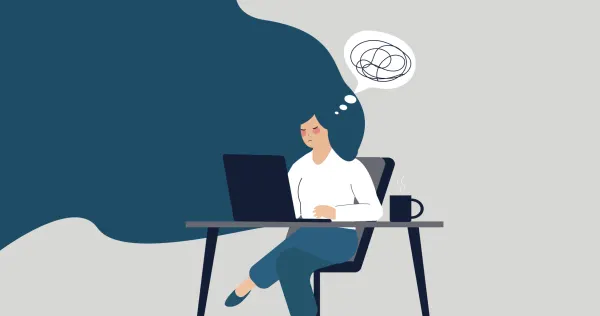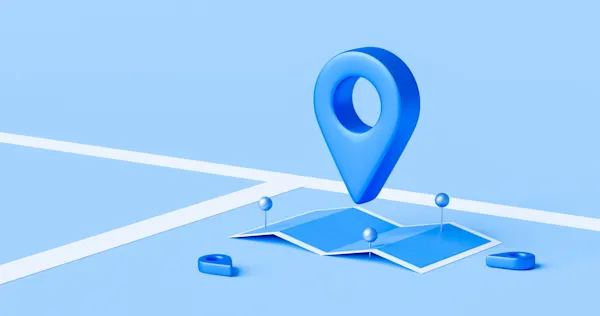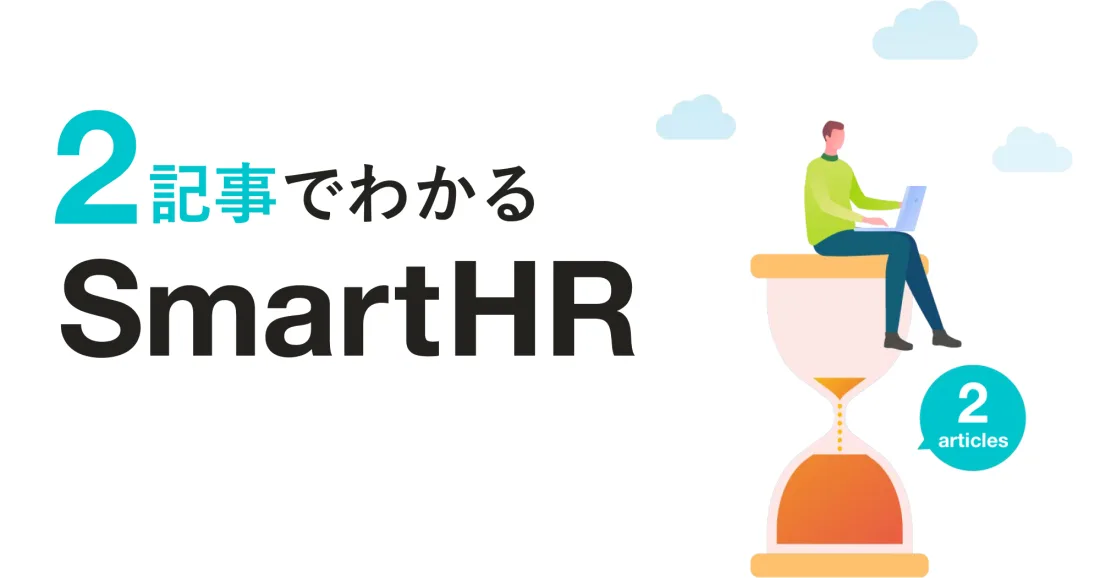職場管理や業務に活かすために人事評価制度を変え続ける〜人事評価の現在地 #09

「人事評価制度がうまく運用できていない」「現場の評価への不満が収まらない」。こういった人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。
本連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者・被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。
最終回は「従業員と管理者にとって有意義な人事評価制度のあり方と、人事担当者と経営者が果たすべき役割」について考察します。
競技スポーツと人事評価
ビジネスパーソンや経営者にとって、競技スポーツの世界は、単にそれが好きだからということとは無関係に、何かと気になることのようだ。活躍する組織や個人が、多くの人々の「私もかくありたい」という目的意識や、「それに引き換えうちの組織は……」という落胆を生んできた。組織や人が何かを成し遂げるということに関する、極めて本質的・根源的な部分が現れていることが、強い関心を生むのだろうか。
人事評価に関連した事例として、いささか旧聞に属するが、2023年にプロ野球セントラルリーグのペナントレースを制したのは阪神タイガースについて挙げたい。一部メディアの報道のとおりであるならば、優勝の背景には、岡田彰布監督(当時)の「人事評価改革」というべきものがあったようだ。野手の年俸の算定基準として、フォアボール(四球)の獲得数を入れるように岡田氏がフロントに掛け合い、それが実現した。結果として野手のフォアボール獲得数、ひいては出塁率や得点数が高まり、長打に頼りすぎない攻撃が実現したという。
このことは、経営の目標や戦略に即した人事評価基準を設け、それを運用することが、組織や個人の業績に少なからず影響することを示している。しかし、この連載でたびたび示してきたように、企業における人事評価の現場では、そうしたポテンシャルは十分に生かされていないか、真剣に受け取られていないことが多い。
「競技スポーツは特殊」とされることも多いが、本当にそうなのだろうか。そのズレをどう理解し、埋めてゆけばよいのだろうか。
前回は、従業員(被評価者)の業績向上のために管理者(評価者)が種々の支援を行う業績管理が人事評価以上に重要であること、そして人事評価制度は業績管理の有効なツールになることを指摘した。今回は、従業員と管理者にとって有意義な人事評価制度のあり方について、人事担当者と経営者が果たすべき役割についての検討を交えつつ考えたい。
「わかりにくい成果」に向き合う
競技スポーツの世界が特殊とされる理由の一つに、「成果のわかりやすさ」が挙げられることが多い。しかし、本当にそうなのだろうか。
選手のプレー(例えば打撃、走塁、守備、投球)の特徴、すなわち成果を数値化し、彼らの活用や処遇に活かす「セイバーメトリクス」が野球界に登場して数十年になる。送りバントの有効性を統計的に否定するなど、サイバーメトリクスは、「いいプレー」「選手の優秀さ」に関する通念の実態のなさを、次々と示して(暴き出して)きた。それと共に、様々なデータを創出、組み合わせることで、チームの成績に結びつくプレーに関するより妥当性の高い指標を数多く生み出してきた。別の言い方をすると、データに基づいて人事評価の基準を磨き上げてきた。
ここから企業の人事評価が学ぶべき点はいくつかある。まず、セイバーメトリクスでは、指標のわかりやすさよりも妥当性が優先される。慣習的に着目されてきた「わかりやすい成果」の一部を遠ざけ、複雑な指標を新たに構築し、証拠に裏付けられたものとして押し出してきた。「わかりにくい成果」が意味するところやチームへの貢献について情報公開し、選手を含む周囲の理解を得ようとしてきた。
選手からしたら、理解できない評価基準については納得しようがない。球団からの働きかけがあってはじめて、はじめはわかりにくかった指標が、徐々にわかる指標になってくる。企業としても、証拠をもとに成果指標を編み出し、その指標の内容や価値について従業員に理解してもらえるように努めることは有意義だろう。
成果指標を更新する
セイバーメトリクスの価値は、成果を示す特定の指標に留まらない。経営における費用対効果の向上のため、最適な指標を開発・採用し、そうでない指標を破棄し続ける球団側の姿勢には、特定の指標以上の価値がある。競争的な経営環境においては自組織の優位性はすぐに競合に模倣されるため、特定の指標にこだわるべきではない。実際、こうした統計学的手法は、ビリー・ビーンが初めてオークランド・アスレチックスで導入した時には多くの抵抗に直面したが、一度その成果が認められると他球団に模倣され、アスレチックスの成績は再度低迷し、ビーンも状況に合わせて別の指標を再開発した。
新たな指標が開発・採用される中、従来は優秀だと評されてきた選手がそうでもなかったこと、凡庸だと評されてきた選手が実は優秀だったこと、が度々生じてきた。球団は、一部の選手との軋轢が生じる中、契約解消の可能性も見据えつつ、時に年俸調停を行いながら、所属選手との合意を形成する。球団側のこうした姿勢は、各選手に何を目指し、改め、徹底させるべきかを指し示すことになる。
追求する目標や戦略の変化に合わせて人事評価の基準を柔軟に更新することは、一般企業にも当てはまる経営の原則だろう。その基準は、企業に適合する人々とそうでない人々を峻別し、基準を受け入れる人々の基準達成へのモチベーションを生む(Gerhart and Rynes, 2003)。そしてそれが、結果として、企業の目標や戦略を達成するための人々の強いまとまりや緊密なコミュニケーションを生み出す(Barnard, 1938)。
評価基準から見て自組織と適合しない人々を企業としてどれだけ抱え込むのかどうか。こうした峻別につながる評価基準の作り込みをどれだけ行うか。各企業の決断・判断が求められる。
作り込み不足の人事評価制度の問題
多くの日本企業において、人事評価制度で定められた評価基準は、競技スポーツ、とりわけセイバーメトリクスの世界と比べると、遥かに「ざっくり」したものであった。
それは例えば、成果も含めた業績一般についての期待値や達成度について、計量的に測定しきれない点に見て取れる。ただし、企業で従業員が従事する仕事の特徴を考えると、そうなっても仕方がない部分はあるため、これに付随して生じる問題は、必ずしも本質的なことではない。
また、従業員間で明確に異なる評価基準を適用しないのも特徴的である。もちろん、社内等級や社員区分ごとに、評価基準に関する文言が異なることが一般的である。しかし、その内容を検討してみたら、企業が従業員に期待する貢献の量や質における本質的な違いが一体どこにあるのか、分からなくなることは少なくない。
とりわけ、職能資格制度が適用されている企業のもとでは、職務や職種ごとでの評価基準の違いが設けられることは少ない。様々な作業・タスクが企業内にあり、実際に従業員に割り振られるものの、企業の目標や戦略に基づいた役割期待の明確さには至らないことが少なくない。基準が曖昧であるため、いかようにも読める反面、何も読み取れないということにもなりやすいのである。
こうした中では、従業員は、自分が何をすることが組織への本質的な貢献につながるのかが見えないまま、与えられた仕事に臨みがちとなろう。従事すべき作業・タスクは多くある。しかし、なぜそれを自分がなさなければならないのか、それを達成することが組織のどのような付加価値にどうつながり、それに対する対価がどのようなものなのか、理解しにくいのだ。仕事の能率性の観点から見た場合、このことは問題視されうる。
もちろん、職場の上司である評価者が、大まかな評価基準について、その時々の状況を踏まえて各従業員への貢献期待として理解できるように翻案して伝える、ということはありうる。人事制度が従業員の貢献期待を個別的、かつ詳細に定義しきることは不可能なので、そうした翻案は、むしろ不可欠である。
しかし、あらかじめ存在する人事評価基準があまりに大まかだと、翻案に伴う評価者の負担が大きなものになるし、評価者ごとで翻案の質の良し悪しがばらついてしまう。そこでは、評価者の往往にして無意識のバイアス(アンコンシャス・バイアス)が人事評価に混入し、性別・人種・学歴などの表層的な要素に紐づいた差別がなされかねない。そして、人事評価に対する多くの被評価者の不満や不公正感が生まれやすくなる。それは企業経営全体の能率性を損ねかねない。
新たな組織内合意としての
「変わり続ける人事評価制度」
被評価者による腹落ち、仕事上の指針としての確からしさ、そして評価者による運用のしやすさを重んじるなら、人事評価制度には、
- 同じ社内等級や社員区分でも職種や職務などに応じて評価基準を分化させる、
- 企業の目標や戦略の達成に資する役割期待が明確になるような評価基準を定める、
- 経営環境や目標・戦略の変化に応じて評価基準を柔軟に変更する、
といったことが求められる。
例えば2〜3年ごとといった評価基準の頻繁な変更は、日本企業で働く多くの被評価者と評価者にとって不慣れなものであろう。しかし、柔軟かつ作り込まれた人事評価制度の中で創出される被評価者の特徴や強み・弱みを表すリアルな情報は、被評価者本人や評価者の目前の仕事の能率の向上に資する。「評価基準は状況に応じて変わるものだ」「変わるか変わらないかではなく、変化の質を問うべきだ」といった想定を被評価者や評価者に持ってもらうことは、必ずしも無理筋ではない。
さらには、柔軟かつ作り込まれた人事評価制度における情報は、企業として被評価者の配置転換やキャリア開発を行う際の有力な情報源になる。逆に、硬直的で作り込み不足の人事評価制度における情報は、人事管理上の意思決定におけるカン・コツ・経験を代替するには至らないだろう。
日本で職能資格制度が創出され、普及しだした1970年前後、その立役者の一人であった人事コンサルタントの楠田丘氏は、絶えざる作り込みを行わない人事評価制度はすぐに形骸化する、といった警鐘を鳴らしていた(楠田, 2004)。しかし、実際には、多くの日本企業がそれらとは真逆のアプローチをとってきた。分化の度合いが低い曖昧な評価基準が、20年以上改定されることなく適用され続けることも珍しくない。そのため、不透明な、あるいは年功的な制度運用が現れた。
この30年ほど、「成果主義」や「ジョブ型」など、透明化や脱・年功の切り札とされる様々な考えや人事制度が登場した。しかし、もしこうした対応が、明確で分化した評価基準を刷新しつづけるという、人事評価制度の「本質」から目を背ける中で現れたのだとしたら、期待された成果は得られないのかもしれない。
人事担当者や経営者への期待
人事評価制度の変更を通じて従業員にその時々で最適な役割期待を伝える、という大筋が形骸化しないことが、変更を被評価者や評価者が受容する条件となる。
そのため、人事担当者は、第一に、経営の目標や戦略について、その背景や組織的な達成プロセスも含めて深く理解しなければならない。第二に、様々な立場の従業員のどういう貢献が経営の目標や戦略の達成に寄与するのか、社内外の様々な事例から見通しを立てなければならない。第三に、貢献内容に関する評価基準について、従業員や彼らの上司(評価者)に理解してもらい、有意味なものと受け取ってもらわなければならない。
経営者には、人事評価制度が変わり続けることに対し、被評価者、評価者、人事担当者が前向きになれるよう、制度変更の指針を示さなければならない。特に、人事評価基準の根底にある経営の目標や戦略を、従業員の貢献意欲をかき立てるようなものにしなければならない。自らの経営者目線について人事担当者と擦り合わせた上で、彼らに業務上の裁量を多く与えることも有効だろう。
【参考文献】
Barnard, C. I. (1938). The Functions of the executive. Harvard University Press. (山本安次郎・田杉競・飯野春樹訳『新訳 経営者の役割』ダイヤモンド社, 1968)
Gerhart, B., and Rynes, S. (2003). Compensation: Theory, evidence, and strategic implications. Sage.
楠田丘 (2004).『賃金とは何か: 戦後日本の人事・賃金制度史』中央経済社.