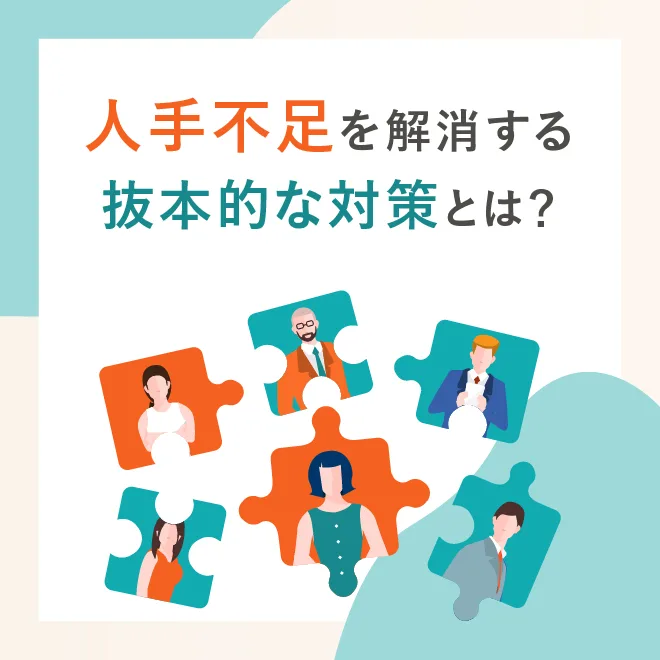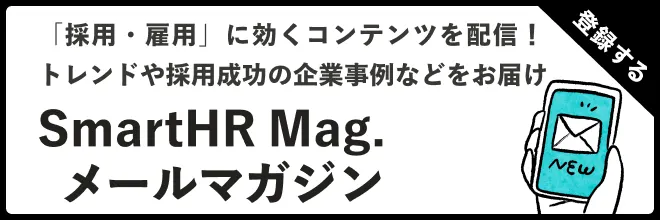【テンプレート付き】採用計画の立て方、立案前後にやるべき重要なポイントも解説!
- 公開日

目次
採用計画とは?事業戦略に必要な人材を採用するための計画

採用計画は、企業において必要な人材を、適切なタイミングで採用するための計画です。経営方針・事業戦略をもとに、目標人数や配属部署、時期などを具体的に定めます。必要な人材を採用するための土台となる計画で、以下の項目などが含まれます。
- 採用の目的と目標
- 採用数と採用時期
- 採用対象と人材要件
- 採用手法と採用媒体
- 選考プロセスと評価基準
- 予算とスケジュール
- 入社後の教育体制
- フォローアップ施策
採用計画は企業の要員計画の1つの手段です。課題や制約状況に応じて「採用」「育成」「配置転換」「外部委託」の適切な手段と組みあわせて検討する必要があります。
(参考)曽和利光 - 『人事と採用のセオリー 成長企業に共通する組織運営の原理と原則』
要員計画について詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひあわせてご覧ください。
採用計画が重要視される理由
自社に適した人材の効率的な採用
採用計画の設計が不十分だと、目的や採用ニーズが明確化されないまま選考を進めることになります。その結果、人材のミスマッチによる早期離職を招き、応募者・企業の双方にとって時間と労力の損失となるでしょう。
経営方針や事業戦略にもとづいた綿密な採用計画の立案が、中長期的な経営戦略や事業展開に必要な人材像を明確にします。採用基準にもとづく一貫した選考が可能になり、採用活動の効率化につながります。
採用市場の変化への対応
近年、人材確保が難しくなり採用難に苦しむ企業が多くなっています。とくに中小企業は今まで以上に人材確保の工夫を求められている状況です。
さらに、2018年には経団連によって「採用選考に関する方針」が廃止され、就職活動に関するルールの取り決めが政府主導に移行。新卒採用の広報・採用活動のタイミングが以前と比べて数か月後ろ倒しとなりました。
新卒採用の選考にかけられる期間が短くなったことから、より計画的な採用の必要性が高まっています。
採用活動の進捗度の可視化
具体的な目標設定により、達成度の把握や課題の早期発見が容易になります。また、採用チーム全体で方針を共有し、選考基準の明確化や評価の一貫性も確保できるでしょう。
また、計画にもとづく採用活動は、採用後のミスマッチ防止や定着率の向上にも寄与します。入社後の人材育成を見据えた採用により、組織全体の生産性向上が可能です。
採用計画を立てる前に取り組むべき3つのこと

(1)自社の事業計画を把握する
採用計画は経営方針や事業計画と密接に連動します。まずは経営層やマネジメント層へヒアリングをとおして、中期経営計画や事業目標、目指すべき組織体制について十分な理解を得ることが重要です。
次に、事業計画の実現に必要な人材の数と質を見極めましょう。具体的には要員計画による必要人数の算出、人員計画に寄る適切な配置・異動の検討、人材育成計画にもとづき教育体制を整備します。これらの計画が採用計画を立案する基礎です。
(2)自社の採用課題を把握する
これまでの採用実績を振り返り、企業説明会への参加者数、求人への応募数、選考通過率、採用目標達成率、入社後の定着率など、自社の採用に関するデータを集めて整理します。
採用目標数に対する採用充足率、スキル、人物面などの満足度等から各選考段階において、自社が抱えている採用課題や改善点が把握でき、より効果的な採用計画を立案できます。
(3)採用市場の調査
効果的な計画を立てるには、求職者の傾向、競合他社の採用傾向、新卒採用スケジュールなど、市場環境の把握が不可欠です。
求職者の傾向は景気や社会情勢で変化します。厚生労働省の「雇用動向調査」や民間の調査「求職者の動向・意識調査」などを参考に、求職者が重視する要素や就職活動の特徴を理解しましょう。
競合分析においては、求人票や求人広告から「訴求ポイント」「給与水準」「福利厚生」を比較検討します。
また、転職エージェントに自社の競合となりやすい企業の特徴や採用手法のトレンドをヒアリングするのも有効です。採用市場では同業種だけが競合とは限りません。職種や勤務条件、待遇、地域、採用条件など多様なニーズによって競合が生まれます。幅広い視点での市場分析が重要です。
新卒採用と中途採用における採用計画の違い
新卒の採用計画は"母集団"を意識
新卒採用の場合、特定の時期に膨大な数のエントリーシートが一斉に提出され、母集団が形成されます。
エントリーシートの評価基準を明確に定め、どのような学生を選考対象とするか、選考の各段階でどの程度の人数を通過させるかを計画に盛り込んでおきましょう。
また、実務経験のない学生に自社や仕事の魅力を伝えるのも重要です。企業説明会や会社訪問、インターンシップなど、複数の接点を設けて相互理解を深めるため、中途採用と比べて内定までのプロセスは長期化する傾向にあります。
中途の採用計画は現場の責任者と実施する
中途採用では多くの場合、配属先が決まっています。そのため、配属予定部署の責任者と、求めるスキルレベルや人材像、採用時期などの要件を明確にしておきましょう。
また中途採用者の入社時期は現職での状況に左右されます。退職通知から実際の退職までの期間や引き継ぎにかかる時間を考慮し、余裕をもったスケジュールを組みましょう。
加えて転職エージェントの有無も中途採用と新卒採用の大きな違いです。エージェントを利用する場合は自社に適切な人材を紹介してもらうための連携が非常に重要になります。
(参考)曽和利光 - 『人事と採用のセオリー 成長企業に共通する組織運営の原理と原則』
採用計画の立て方8つのステップ

ステップ1:自社の中長期的な採用ニーズを確認する
採用計画は、経営戦略や事業戦略にもとづいて策定されます。「この組織をどのような方向に導きたいのか」「そのためにどのような人材が必要」という視点で、中長期的な視点で採用ニーズを見極めましょう。
この段階では、経営層や各部署の責任者との対話を通じて、事業戦略と人材戦略の整合性を確認します。部門ごとの成長計画や、組織体制の変化なども考慮に入れます。
ステップ2:採用目標、人材要件を明確化する
ヒアリングした経営方針や事業計画から逆算し、採用目標を具体化します。「期日(いつまでに)」「配属先(どの部署に)」「採用人数(何名程度必要か)」を洗い出し、数値目標を設定しましょう。
同時に「業務内容」を洗い出し、そのために必要な人材のペルソナを明確にします。
ここで重要なのは「自社でキャリアを築くために必要不可欠な資質は何か」にもとづき要件を絞り込むこと。漠然とした理想のスペックを描くのは避けましょう。
既存のハイパフォーマー人材の特徴を分析し、その要素を人材要件に反映させるのも効果的です。
ステップ3:採用人数を決定する
事前準備で作成しておいた要員計画、人員計画にもとづき具体的な採用人数を算定します。ここではマクロとミクロの両面からアプローチして決定しましょう。
マクロ視点では、人件費総額や労働分配率から採用可能な人数を割り出します。これにより経営状況を踏まえた現実的な採用規模を把握できます。
ミクロ視点では、各部門へのヒアリングをもとに必要人数を積み上げていきます。現場の必要人数から逆算して全体の採用人数を決めるので過不足が出づらくなります。
両者のバランスを図りながら、最適な採用人数を決定しましょう。
ステップ4:雇用形態を決定する
正社員や契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど、多様な雇用形態の特性を理解し、必要な人材にあわせて選択しましょう。
特徴 | 考慮点 | |
|---|---|---|
正社員 |
|
|
契約社員 |
|
|
派遣社員 |
|
|
パート・アルバイト |
|
|
【参考】Lepak&Snell 人的資源アーキテクチャモデル
雇用形態を含む、人材の組み合わせの考え方については「雇用ポートフォリオ戦略」「人材ポートフォリオ論」が参考になります。
(参考)各務晶久 - 『最適な雇用形態の組み合わせは? 「人的資源アーキテクチャー理論」/人事のモヤモヤがスッキリする学術理論③』
たとえばLepak&Snellが提唱した人的資源アーキテクチャは、人材の特性を「人的資源の企業特殊性」と「人的資源のコア・コンピタンスにたいする価値」で4つのグループに分けます。
縦軸の「人的資源の企業特殊性」は人材が労働市場で採用しやすいかどうか。横軸の「人的資源のコア・コンピタンスにたいする価値」は企業におけるポジションの重要性を示しています。

ステップ5:採用手法(募集媒体)を決定する
自社サイトでの募集や求人広告の出稿、人材紹介会社の活用、リファラル採用など。採用手法は年々多様化しています。採用ターゲットの特性や自社の採用予算を考慮しながら、最適な手法を選択しましょう。下記に代表的な採用手法と適した場面の例を挙げます。
採用手法 | 適している場面の例 |
|---|---|
自社サイトでの募集 |
|
求人広告の出稿 |
|
人材紹介会社の活用 |
|
リファラル採用 |
|
ステップ6:選考方法を検討する
選考方法は会社が求める人材を正確に見極めるために重要なプロセスです。採用の規模やターゲット像を踏まえ、必要な能力・適性・意欲を評価できる選考方法を設計します。
基本的な選考ステップとして、絶対に必要な要素、あると望ましい要素などに細かく分類しておきましょう。
- 書類選考:応募者の能力や仕事に対する意欲を読み取る。履歴書/職務経歴書、エントリーシート、自己PRなど
- 筆記試験:知識や適性などを測る。一般常識試験、適性検査、小論文、専門知識試験など
- 面接選考:応募者の総合的な人物像を直接評価できる。個人面接、集団面接、グループディスカッションなど
面接官によって評価するポイントが異なる可能性があるため、採用基準となる合格ラインを設定し、面接チェックシートに反映させましょう。
ステップ7:採用スケジュールの策定
「必要な人材をいつまでに確保するか」の目標から逆算し、スケジュールを組み立てましょう。
一般的な採用活動は「計画策定」「求人開始」「選考」「内定」「入社」の流れです。近年の採用市場では、優秀な人材ほど複数の企業を同時に検討し、内定が出た順に決めていく傾向が強まっています。
そのため、選考から内定までのスピードが成功の鍵です。応募者とのコミュニケーションが遅れたり、全応募者の面接完了を待って合否を決定したりすると、優秀な人材を逃してしまう恐れもあります。計画段階でこうしたリスクも想定しておきましょう。
ステップ8:採用計画、スケジュールを可視化する
採用計画には経営者、現場のマネージャーやスタッフ、求人会社など多くのメンバーがかかわります。進捗やタスクを共有するため、決定内容を採用計画書や管理ツールなどにまとめ、関係者で共有しましょう。
採用計画書のテンプレート例
採用計画書に記載する一般的な項目は以下のとおりです。
大項目 | 小項目 |
|---|---|
1. 採用概要 |
|
2. 応募要件 |
|
3. 採用スケジュール |
|
4. 採用手法 |
|
以下のテンプレートを活用することで、採用計画をスムーズに検討できます。

採用計画を立てた後にやるべき4つのこと
(1)関係者間で情報共有する
採用スケジュールや実施する内容を、採用活動にかかわる全員で共有できる環境を整え、役割分担などの認識をあわせておきましょう。
採用選考が進むと、受け入れ部署の部門長や役員などが面接官を担うため、あらかじめスケジュールを確保しておきます。採用戦略や採用基準について打ち合わせも実施しましょう。
(2)現場社員の協力体制を確立する
採用要件策定時のヒアリングや採用サイトに掲載する社員インタビューや内定者フォローなど。採用担当以外の従業員の協力が必要になる場面は多々あります。
協力が必要な理由を丁寧に説明し、理解を得ておきましょう。優秀な人材を採用できたとしても、配属先の受け入れ態勢が整っていなければ早期離職につながってしまう可能性があります。入社後のオンボーディングがスムーズに進むように取り組んでおきましょう。
(3)自社採用サイト、SNSを更新する
求職者の多くは応募前にコーポレートサイトやSNSなどを通じて応募企業について調べます。
自社サイトや採用ページ、SNSなどの内容が、自社が求めている人材要件や自社の魅力などが正確に伝わる内容になっているかを点検し、必要に応じて更新しましょう。応募者の目線に立って入社後のイメージが膨らむコンテンツや、会社の想いを伝えると効果的です。
(4)採用計画の振り返りと見直しを行う
採用計画を遂行した後は、振り返りも大切です。スケジュールに余裕はあったか、応募者とのやり取りはスムーズだったか、内定辞退者の理由など、成功した点や計画どおりにいかなかった点などを振り返り、ブラッシュアップを図りましょう。
従業員データを分析して採用計画を磨き込む
採用計画を実効性の高いものにするには、経営方針や事業戦略と連動させるだけでなく、従業員データの客観的な分析が有用です。
部署ごとの人員構成や分布、採用実績、定着・パフォーマンスにまつわるデータを複合的に分析すれば、必要な人材要件の明確化や、より精度の高い採用数の算出が可能になります。また過去の採用活動の成功パターンを特定し、効果的な採用手法の選択にも活用できるでしょう。
SmartHRでは、人事・労務業務を通して従業員データを自然と収集・蓄積できます。蓄積した最新かつ正しい人事データを、人材育成や人員配置など多様な場面で活用できます。
とくにHRアナリティクス機能では「部署×保有資格」でマトリクス分析をして、事業運営に必要な資格保持者が部署ごとに何人いるかを把握できます。資格保有者の偏りや充足状況にあわせて採用・育成や人員配置の検討も可能です。
HRアナリティクス機能について詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。

お役立ち資料
3分でわかる!SmartHRのHRアナリティクス
SmartHRの「HRアナリティクス」は、人事データをさまざまな掛け合わせで分析し、組織づくりの示唆が得られる機能です。SmartHRなら、業務を通じて自然と正確な人事データが蓄積されるため、活用したいときにすぐ人事データの分析ができます。