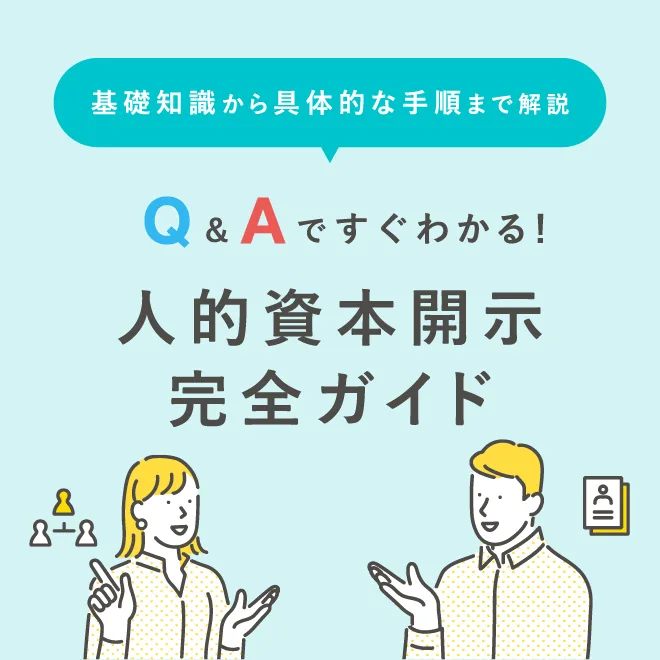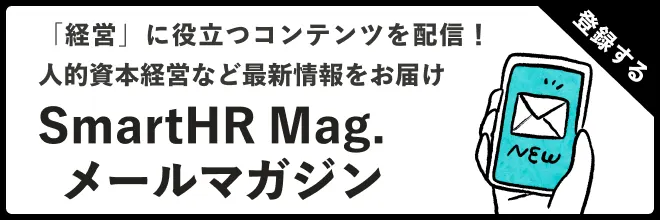「リベンジ退職」の増加から考える、人材定着戦略のこれから
- 公開日

目次
こんにちは。アヴァンテ社会保険労務士事務所の小菅です。
近年、SNSなどで「リベンジ退職」という言葉を目にする機会が増えています。これは、職場環境への不満や成長機会の不足などの理由から、従業員が意思表示として退職を選択するケースを指します。
本稿では、リベンジ退職が組織に及ぼす影響と、その予防アプローチについて、解説します。従業員一人ひとりの成長に寄り添う視点から、持続可能な組織づくりのヒントを考えていきましょう。
リベンジ退職とは
リベンジ退職とは、 会社に不満をもつ従業員が意思表示の手段として退職することを指します。退職の意思表示そのものは従業員の正当な権利行使であり、会社は原則として受け入れる必要があります。しかし、会社への不満から退職に至る状況は、会社と従業員の双方にとって本来望ましくない事態であり、労使間の関係構築や円満に働ける仕組みづくりが求められます。
米国では職場環境や評価への不満に対する意思表示として退職するケースが多く見られるなか、日本ではハラスメントや長時間労働による就業困難から退職代行を利用するなどの特徴が見られます。一方で、日本の雇用環境は大きな転換期を迎えており、終身雇用が崩壊した現在、同じ会社で長く働くことよりも成長できる環境を選択する人が増えています。
リベンジ退職が注目されている背景には、雇用慣行の変化とキャリア形成や働き方に対する従業員の意識の変化があり、今後は日本でも意思表示の手段としての退職が増えていく可能性があります。
リベンジ退職が組織にもたらすリスク
リベンジ退職は、単なる人材の流出以上に、組織に大きな影響を及ぼす可能性があります。従業員の不満が表面化された退職は、以下のようなリスクをもたらします。
(1)突発的な人材流出による業務への支障
不満が限界に達した従業員は、十分な引き継ぎ期間を設けずに退職する傾向があります。その結果、引き継ぎが不十分となり、残された従業員の負担が急増します。新たな人材採用にも一定の時間がかかるため、組織パフォーマンスの低下に至ることも考えられます。
(2) 採用・育成コスト増大
突発的に生じた欠員の補充は、通常の採用活動以上のコストがかかります。たとえば、転職エージェントに委託して相応のスキルをもつ人のヘッドハンティングを検討せざるを得ないかもしれません。
(3) 退職者のSNS発信による企業イメージ低下
不満を抱えた従業員がSNSで職場環境の問題を発信することで、企業イメージが急速に悪化する可能性があります。とくにハッシュタグによる投稿が広がると、同様の経験をもつ人々が反応し、瞬く間に拡散される傾向にあります。さらに、投稿内容が労働基準法違反やハラスメントの告発にあたる場合、企業は法的な調査や是正勧告の対象となる可能性もあります。
(4)残留する従業員のモチベーション低下
退職理由や不満が表面化することで、残された従業員が会社へのネガティブな印象をもつ可能性があります。とりわけ似たような境遇にある従業員は、自身の将来に不安を感じ、業務に対するモチベーションが低下する恐れがあります。
(5)組織文化の悪化
会社では、それまで当たり前に行われてきた仕事のやり方やコミュニケーションなどが文化や常識になることがあります。こうした文化や常識に疑問を投げかけるリベンジ退職は、従来の組織の価値観や行動規範を揺るがします。これにより、組織の一体感が損なわれ、新たな不信感が生まれる可能性があります。

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
リベンジ退職の本質的な課題
リベンジ退職の背景には、従業員の期待と労働環境のギャップ、コミュニケーション不足、成長やキャリア形成の機会不足、そして評価に対する不満など、大きく4つの課題が存在します。これらの課題に向き合い、適切な対策を講じることが重要です。
(1)従業員の期待と労働環境のギャップ
労働環境において入社後に期待とのギャップが生じるケースは少なくありません。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「早期離職の背景と離職後の就業状況」によると、初職が正社員であった離職者が初めての勤務先を辞めた理由として、「労働時間や労働条件」が上位を占めています。このことから、従業員の期待と現実の労働環境とのギャップは、不満の蓄積につながり、最終的に退職を選択する大きな要因となるといえます。

(2)コミュニケーション不足や意識のズレ
コミュニケーション不足は、組織における大きな課題の1つです。上司と部下のあいだで職務や立場、年代や価値観の違いから、双方の意識にズレが生じることがあります。具体的には、上司からの依頼が部下から一方的な命令と受けとられたり、理解してくれていると思っていることが実際には伝わっていなかったりするケースです。また、私が企業向けに実施している管理職研修で、「若手社員とのコミュニケーションのとり方がわからない」という悩みを抱える方もいます。
こうしたズレが積み重なることにより「この人とは話しにくい」「一緒に仕事をしたくない」といったネガティブな感情に発展することもあります。そして、次第に上司と部下の信頼関係が損なわれ、チームの一体感が失われていき、最終的には退職につながることもあります。
(3)従業員の成長やキャリア形成の機会不足
従業員のキャリアに対する意識は多様化しています。待遇や福利厚生だけでなく、新しい仕事にチャレンジできる機会や、自身の描くキャリアを実現できる環境を求める声が高まっています。従業員一人ひとりが積極的にチャレンジできる環境づくりが重要ですが、こうした機会をうまく提供できていないケースが多く見受けられます。従業員にとって自身の描くキャリアと現実のギャップを埋められない状況は将来への不安や閉塞感につながり、最終的に「成長機会を求めて」という形で退職を選択するケースもあるでしょう。
(4)評価に対する不満
経営学者の服部泰宏氏は、自身の著書『組織行動論の考え方・使い方』のなかで、「上司や経営者の評価は必ずしも従業員の能力を正確に反映しているとは限らず、組織における公正の欠如が人材の定着に深くかかわっている」と述べています。
評価に対する従業員と企業の認識には、ズレが生じることがしばしばあります。企業が重視する数値化しやすい成果と、従業員が評価してほしいと考える日々の努力のプロセスや創意工夫とのあいだにギャップが生まれやすいのが原因の1つです。この認識のズレが解消されないままでは、従業員のモチベーションを損ない、ときとして組織への不信感につながることがあります。
リベンジ退職を予防する4つのアプローチ
リベンジ退職を予防するには、最初から完璧な組織づくりを目指すのではなく、できるところから着実に改善を進めていく姿勢が重要です。また、従業員にも完璧を求めすぎず、それぞれのペースでの成長を支援できれば、地道な環境改善につながります。ここでは4つのアプローチを紹介していきます。

(1)労働環境の改善
従業員の期待と労働環境のギャップを解消するには、どこにギャップがあるのかを正確に把握することが重要です。日常的なコミュニケーションを通じて従業員の声に耳を傾け、具体的な改善につなげていく必要があります。
たとえば、「健康な社会の実現に貢献する」という会社のビジョンに共感して入社した従業員が、実際は休暇がとりにくい労働環境だったことから退職してしまうという事例がありました。その企業は問題を真摯に受け止め、従業員の勤務状況を可視化し、課題を把握しました。そのうえで計画的な休暇取得を全社的に周知・推進した結果、職場環境が改善されました。このようにデータ分析とコミュニケーションを通して、ギャップを埋めて改善することが、入社後のミスマッチによる早期離職防止策になります。
(2)コミュニケーション促進とメンタルヘルスケア
上司と部下の間のコミュニケーション不足や意識のズレは、従業員の心理的な負担を増やし、適切に解消されないことで退職を選択してしまうケースもあります。
こうしたリスクを軽減するための実践例として、1on1ミーティングを効果的に活用することがあげられます。指導や評価の場だけではなく、上司や先輩社員が新入社員の悩みや不安に寄り添い、信頼関係を築く機会として活用するとよいでしょう。また、日々の挨拶や雑談、チーム内での情報共有など、普段からのカジュアルなコミュニケーションも、職場の心理的安全性を高める重要な要素となります。
円滑にコミュニケーションをとれるようになれば、従業員の心の不調のサインを早期に察知できます。適切にサポートし従業員が安心して働ける環境を整えられれば、退職リスクの軽減にもつながります。
(3)成長機会の創出と支援
従業員の成長やキャリア形成の機会不足は、モチベーション低下の大きな要因です。そうならないために、会社は多様な視点をもち、従業員が創造性を発揮できる余裕を生み出す必要があります。これは新しいアイデアの源泉となるだけでなく、従業員の自発的な成長も促します。
一例ですが、私が代表を務めるフットサルチームは20代前半から40代後半までの幅広い年齢層のメンバーで構成され「挨拶の実践」と「ミスから学ぶ姿勢」を大切にしています。エイミー・C・エドモンドソンが『恐れのない組織』で指摘するように、優秀なチームはミスの数が少ないのではなく、報告の数が多いのです。こうした心理的安全性の確保が、メンバー一人ひとりの主体的な成長を支える土台となっています。
(4)プロセスの評価の実施
評価基準の偏りや、そこから生じる評価に対する従業員と企業の認識のズレは、従業員のモチベーション低下につながる深刻な問題です。評価制度は、結果だけでなくそこに至るまでのプロセスも適切に評価できる仕組みをつくるとよいでしょう。これにより、従業員は自身の成長を実感でき、モチベーションの維持・向上が期待できます。
また、過程を評価できれば、成果につながる有効なフィードバックにもなり組織パフォーマンス向上も期待できます。『図解でわかる!人事制度の作り方』では、自社の状況や従業員の目指す姿に合わせた評価基準であるほど企業の目的達成にも近づくとしています。
これをふまえ、「目標設定型」「行動評価型」といった評価方法を組み合わせるなど、従業員のさまざまな努力を適切に評価できる制度の導入が、リベンジ退職の予防において重要な役割を果たすと考えられます。
持続可能な組織づくりに向けて
リベンジ退職を予防することは、単なる人材流出の防止策ではなく、持続可能な組織づくりそのものといえます。そのためには、従業員と企業が描くキャリアと働き方のミスマッチを防ぎ、適切な労務管理と成長支援の両面から取り組むことが重要です。すべての課題を一度に解決しようとするのではなく、丁寧に現状を把握し、優先順位の高い課題から着実に改善を進めていくのがよいでしょう。
従業員との対話を通じて期待と現実のギャップを把握し、心理的安全性を確保しながら、一人ひとりの成長をサポートしていく。そして、努力のプロセスを適切に評価する仕組みを整えることで、従業員が長期的なキャリアを描ける組織となっていくのです。
このように、リベンジ退職への対策は、結果として組織の成長と従業員のエンゲージメント向上につながります。それは、多様な個性をもつ従業員がそれぞれの強みを活かして活躍できる、真に持続可能な組織づくりの第一歩となるはずです。
参考文献
- 労働政策研究・研修機構『早期離職の背景と離職後の就業状況』
- 服部 泰宏,2023,『組織行動論の考え方・使い方-第2版-』有斐閣
- エイミー・C・エドモンドソン,2021,『恐れのない組織』英治出版
- 津留 慶幸,2024,『図解でわかる!人事制度の作り方』ビジネス教育出版社

お役立ち資料
知らぬ間に拡大する「静かな退職」は早めに対策を!
この資料でこんなことが分かります
- 「静かな退職」とは?
- 「静かな退職」を放置することの問題点
- 「静かな退職」を生み出さないために
- 従業員の声を収集する「従業員サーベイ」のポイント

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
- 読者の76%が「メルマガの内容を自身やチームの実務に取り入れている」と回答
- 限定コンテンツの閲覧や、有識者・同業者の方との交流イベントへの参加も
あなたの「気づき」につながる情報を、厳選してお届けします!