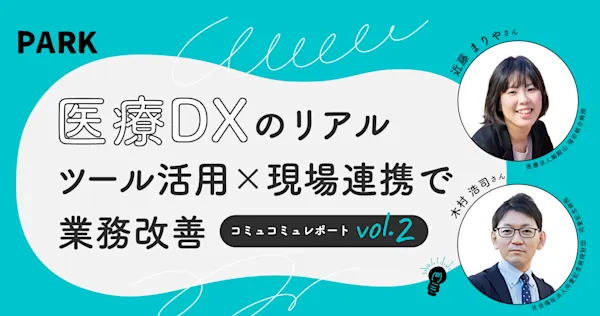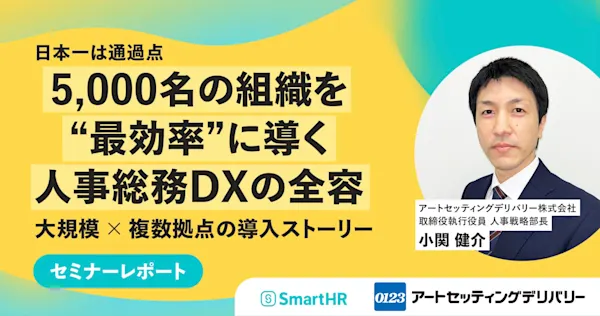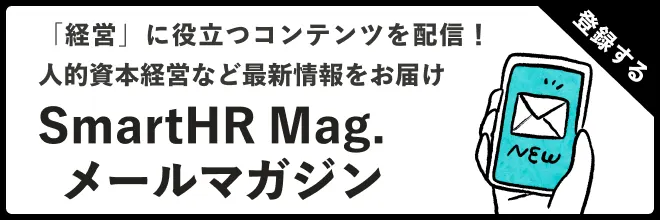タレントマネジメント、どう始めるのが正解?SmartHRユーザー企業が交流会で徹底議論
- 公開日

目次
SmartHRでは特定のトピックをテーマに取り上げ、ユーザーさま同士の意見交換や交流を目的としたオンラインイベントを開催しています。
「タレントマネジメントの始め方」をテーマにした今回のイベントでは、従業員数が1,000名~1万名の大手企業・人事関連部門で人材活用に携わる8社10名のユーザーさまにお集まりいただきました。この記事では、当日のエッセンスをご紹介いたします。

兼松株式会社 人事部 人事企画課 兼 人材開発課
2018年に兼松株式会社に入社、人事部給与厚生課にて給与計算、全社人件費、勤怠管理、働き方改革などに従事。その後、総務部を兼任し本社移転プロジェクトに携わり、東京本社移転を完遂。日経ニューオフィス-経済産業大臣賞を受賞。現在は人事部の人事企画課と人材開発課を兼務し、人事システムの刷新、人的資本経営、タレントマネジメント、人事制度改定、HRBPなどに従事。
ミニプレゼンでは兼松の「タレントマネジメントの始め方」が明らかに
最初のコンテンツであるミニプレゼンにご登壇いただいたのは、兼松株式会社人事部の田中さん。同社におけるSmartHR導入までの経緯や導入の効果、具体的なタレントマネジメントの進め方などをお話しいただきました。
「業務改善」と「形式知化」でゼロからの地盤固め
田中さん
兼松株式会社は1889年創業で、今年で136周年を迎える商社です。2024年度から3か年の中期経営計画では「人的資本」「社会関係資本」「知的資本」という3つの無形資産とビジネスモデルの関係性を明確化し、なかでも人的資本を最重要視して人材の能力が十分に発揮される組織づくりに注力しています。
こうした背景のもと、人事労務を中心とした「管理人事」から人的資本経営やタレントマネジメントを中心とした「戦略人事」へのシフトを目指すなかでSmartHRの導入に至りました。
田中さん
当社が「戦略人事」へのシフトで目指す姿として設定したのは、下記の2点です。
- 正確かつ安定的かつ効率的に人事労務・給与業務を遂行できる環境を整備する。
- 人的資本経営やタレントマネジメントにより注力して「戦略人事」へと組織を改革していく。
戦略を立てて仮説と検証を繰り返すには、その基礎となる業務プロセスが整理され、データが集まる環境が整っていなければなりません。「人的資本経営を実現する」という抽象的で大きなミッションだからこそ、まずはこうした地盤固めを重視しました。
具体的には「業務改善」「形式知化」という2つのキーワードをプロジェクトメンバー間で頻繁に共有しました。「業務改善」とは従来のやり方にこだわらず、ゼロベースでよりよい運用方法を模索する姿勢です。ときにはシステムにあわせて業務変革をしていく「Fit to Standard」も心がけました。
一方で「形式知化」とは業務のブラックボックス化・暗黙知化を徹底的に防ぎ、人事部のみならず誰が見てもわかりやすい状態を維持することです。こうした取り組みによって、目指す姿へと着実に歩みを進めていきました。

業務にシステムを合わせるのではなく、システムに業務を合わせる
目指す姿を策定したうえで人事部の現状を分析したところ、次の2つの課題が浮かび上がってきたそうです。
- 人事業務の属人化
- システムの複雑化
田中さん
1つめは、人事業務の属人化です。当社では特定の社員が長年にわたって人事システムを担当していたため、その社員にしかわからない業務が多数存在していました。これでは該当社員が退職した途端に安定的な人事業務ができなくなってしまいます。
2つめは、システムの複雑化です。システムを業務に合わせる形で追加開発を繰り返したために、システムの種類がいたずらに増えていたのです。その結果、データがあちこちに散在し、非効率な連携が多くなっていました。インポートやエクスポート、加工、活用にも多大な労力がかかります。
そうしているうちに法改正や制度改定があり、また追加開発が必要になるという悪循環に陥っていました。わかりにくい画面でたくさんのシステムを使い分けなければならない状態は、従業員の利便性を考えてもよくありません。システム利用への抵抗感からか思うようにDXが進まず、人事部への問い合わせも増えていきました。
こうした課題を解決するために、兼松さまでは人事に関わるシステムを根底から見直すことになりました。
田中さん
最初に考えたことは、オンプレミス or SaaSの検討でした。もちろんどちらにもメリットとデメリットがありますが、下記のメリットを重視してSaaSを選びました。
- 制度や運用がシステムに沿ったシンプルなものとなり(Fit to Standard)、将来の運用コスト(人件費・開発費)の削減を期待できる
- システムの複雑化を避けられ、業務の属人化が起こりにくいため、組織内での担当替えや人事ローテーションが容易
- 法改正や制度改定に対応したアドオン開発が不要となることによるシステム運用コストの削減
- 追加機能の実装スピードが速く、時代のトレンドに合わせた機能が利用可能
- ダッシュボード機能の実装により、業務負荷の軽減が期待できる
- ベンダーの提供するマニュアルを従業員向けに転用できるケースが多く、操作方法に関する対応業務を削減できる
- 資産管理の必要がない
既存データの徹底的な見直しでタレントマネジメントをスムーズに開始
兼松さまが数あるSaaS製品からSmartHRを選ばれたのには、いくつかの理由がありました。
田中さん
まず、さまざまなデータを一元管理できたからです。 評価はAシステム、勤怠はBシステム、給与明細はCシステム……というバラバラ状態から脱却するには、1つのシステムにデータを集めてできる限りたくさんの領域をカバーできたほうがいいと考えました。
運用にかかる手間をどれくらい削減できるかという点も、同じくらい大事にしました。従業員みずからが人事・労務に関する申請を簡単にできれば、運用負担を大幅に減らせるはずです。そのためには従業員から人事システムへの導線がシームレスであり、わかりやすいUIであることが必須条件でした。

導入にあたっては、1年かけて運用までのシミュレーションを行ない、従業員に展開するまでに約半年の準備期間を設けて十分にテストを重ねたうえでリリースをされたそうです。
田中さん
準備期間に行なっていたのは、既存データの見直しです。これまでの体制の延長線上ではなく、まったく新しい体制へと革新するためのよい機会にしたい。そう考えて、既存のデータが本当に必要なのか、重複や抜け漏れがないか、保存や管理業務を効率化できないかといった細かい確認作業に時間をかけました。
既存のデータを徹底的に見直すために、人事・労務の業務担当者全員に業務の手順書や引き継ぎ書を作ってもらい、業務を棚卸ししたりもしました。
データベースの確認、社会保険の手続き、人事評価、サーベイへの回答。従業員が何かをするときに「まずは〇〇を見に行こう」という場所がある状態が理想でした。導入後の今、SmartHRはまさにそういう存在です。給与計算には他社のツールも使っているものの、従業員との窓口を一本化するという当初の目標は達成しつつあると考えています。

こうして徐々に従業員情報の一元管理の体制が整い、タレントの"見える化”が進み、「戦略人事」ための地盤が固まっていきました。特定の人材の勘や経験、経歴を重視したアナログな人材配置を脱却し、全員が同じ情報を共有したうえで、全体を見て適切な配置の判断ができる仕組みが整っていったのです。
田中さん
まだまだこれからではありますが、焦らず丁寧に地盤固めを行なったことで、スムーズにタレントマネジメントを始められたと思います。今後は今まで以上に社内の隅々にまで入り込み、人事として事業の発展に寄与できる体制を整えていきます。あらゆる人事関連の意思決定を支えるべく、積極的にタレントマネジメントに取り組んでいきたいと考えています。
課題解決の糸口が見つかる。グループディスカッション&交流会も白熱
ミニプレゼン終了後のグループディスカッション&交流会では、とくに次のようなテーマで議論が盛り上がりました。
従業員データの属人化
人事部と各部門責任者との間に、情報の非対称性があらわれている。従業員データへのアクセス権限がなく、利活用が難しい。こうした従業員データの属人化に悩む声が多くあがりました。意見交換を経て、誰もが従業員情報を取得・活用できる環境づくりには、システム面の改善が有効だという示唆が得られたようです。
ソフトスキルの管理・基準化について
専門的な知識や技術、資格などを指すハードスキルに比べて、リーダーシップや共感力、創造力といったソフトスキルを可視化するのは難しいものです。管理方法が煩雑化しているという悩みも多く、皆さん試行錯誤中のようでした。
印象的だったのは、360度評価の導入を検討する企業の多さです。単に専門性やスキルを評価するのではなく、自社の基準で成果を測って評価したいという強い思いを感じました。参加者のみなさんが悩んでいるポイントには、少なからず共通点がありました。今回のようなイベントで定期的に情報交換をすることは、こうした悩みを解消しつつ相互に高め合うためのよい機会になるはずです。
データアナリティクス人材の登用について
ピープルアナリティクスの活用には高い専門性が必要になるため、検討段階が続いているというお悩みの声もあがりました。ひとつの選択肢として、専門の人材を登用するために新しいポジションをつくることも視野に入れているという意見もありました。
タレントマネジメントのシステムを入れる際の上申方法
タレントマネジメントのシステムの導入を社内で検討する際、データの可視化+業務効率化を上申の説得材料にしている人が多かったのが印象的でした。正確な算出が難しいことから、費用対効果(ROI)を説得材料に上申するケースは少ないようです。
ユーザー目線での機能比較や導入効果、問い合わせの件数の削減によるコスト効果などを訴えた例もありました。最終的なゴールから逆算して達成したいイメージを明確にするとともに、コスト削減効果を示しながら機能拡張性もアピールすることが、システム導入への近道と言えそうです。
タレントマネジメントシステムにデータ入力をしてもらう難しさ
タレントマネジメントシステムを活用する際の壁となるのが、個人情報の入力です。セキュリティ意識の高まりから、従業員が情報の入力や提供に抵抗感を示すという声がありました。利用方法を明確化したり、丁寧な説明ではじめの入力ハードルを下げることが抵抗感を弱めるサポートになるかもしれません。利便性の向上など導入後の効果をわかりやすく伝えることで、従業員の理解を得られたという体験談もあがりました。
イベントの満足度は100%を記録し、「今後も同様の機会があれば参加したい」「人事施策の取り組み方法や結果についてもっと情報がほしい」というご感想も。ディスカッションは「タレントマネジメントの目的って何だろう?」「データの可視化することの意義とは?」という根本的な問いにまで辿り着き、大きな示唆となりました。
各社が取り組みを進めようとしているなか、同じ悩みを持った人事担当者どうしが真摯に向き合っていることが伝わる、非常に前向きな会となりました。