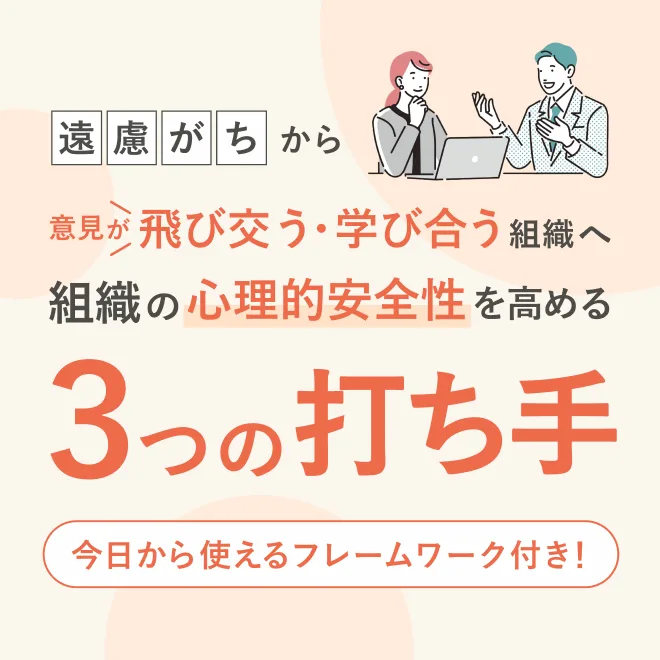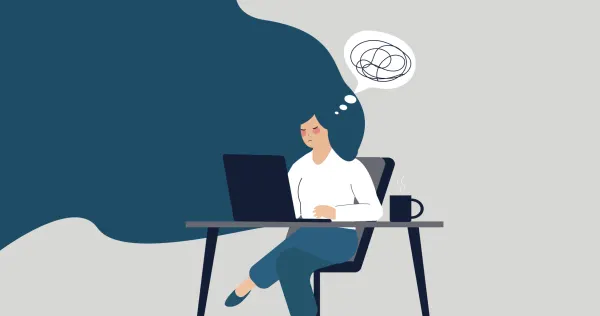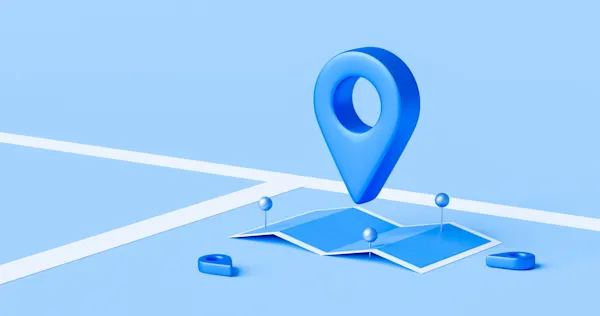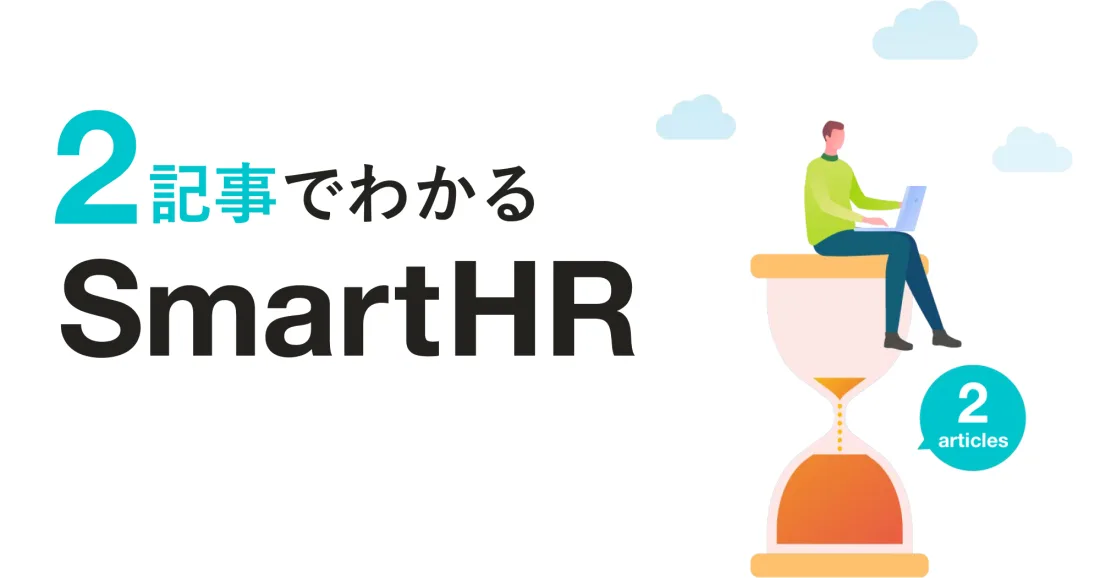「競業避止義務」の概要。具体的効力や裁判例を解説
- 公開日

目次
転職や起業をしようと思ったとき、多くの方が今までに身につけたスキルや経験を活かせる同業他社への転職や、同業種での起業を考えるのではないでしょうか。
やはり未経験の分野に挑戦することは勇気がいりますし、同業種であれば比較的スムーズに働くことができることができるでしょう。
しかし、そこで気にするべきなのが「競業避止義務」です。
就職時や退職時に「競業行為」を行わないことを誓約する誓約書を提出することがあるので知っている方も多いと思いますが、簡単にいうと、所属していた(している)会社にとって不利益になる行為をしてはいけませんという決め事です。
とは言うものの、どこからが競業行為なのか、何をやったらダメなのかの線引きはなかなか難しいのが現実です。
「競業避止義務」とは?
改めて競業避止義務を説明すると、在職中の会社と事業内容が重複・競合する会社に就職し、または競合する会社を自ら立ち上げて設立するなど、現在の会社事業の競業行為を行ってはならないという義務のことです。
競業会社を自ら立ち上げた上、同僚や部下を引き抜く行為、従前会社の顧客を引き抜く行為も広い意味で含まれますので注意が必要です。
一般的に、在職中も労働契約における付随的義務として競業避止義務を負うと考えられています。
更に取締役は会社法上、在任中は取締役会の承認なしに会社の営業の部類に属する業務を行うことが禁止されています。
退職後でも「競業避止義務」は生じるの?
一方で、退職後の場合は、退職者の職業選択の自由の観点から競業禁止義務は原則生じないとされています。
ですので、使用者が退職後の労働者にも競業避止義務を課す場合には、就業規則や個別契約などにおいて必要かつ合理的な範囲で法的根拠を明示する必要があります。
この契約は専門的な職務に就く場合や、事業の機密性が高く、営業秘密の漏えいが会社経営に直接影響を与えるおそれがある会社などで、社員との間で競業避止義務を定めるケースが多いです。
競業行為を行った元社員への法的措置はむずかしい?
元従業員と会社との間で、契約上明確に、または付随的な義務として競業避止義務が認められる場合には、損害賠償請求や差し止めが可能な場合があります。
競業避止義務が認められるためには、契約上禁止された元従業員の競業行為の範囲が合理的か、代償措置による補填など従業員側の不利益が甘受できる限度内かどうかといった事情から判断されます。
競業行為の対応も考慮され、引き抜き行為がどの程度行われたか、誘われた側の社員の意思決定に与えた影響の程度、会社業務への影響、顧客など営業基盤となる機密事項の使用の有無なども判断材料となります。
競業行為の態様の悪質性が高いほど、競業避止義務違反も肯定されやすくなります。競業行為によって損害賠償請求できるのは、因果関係がある損害だけとなりますが、その立証は簡単ではありません。
競業避止義務に関する「具体的な裁判例」
最後に、過去のいくつか著名な裁判例を簡単にご紹介します。
(1)競合他社の役員に就任した例
フォセコ・ジャパン・リミティッド事件
会社:各種冶金用副資材を製造・販売する企業元社員:研究部に所属し、工場での製品管理や鋳造本部で販売業務の従事競業内容:顧客が競合する同業他社の役員に就任その他事情:1. 制限期間2年間と比較的短期間2. 会社事業が特殊分野で制限の対象は比較的狭い3. 代償措置なし4. 在職中に機密保持手当支給あり
判決:競業制限は合理的な範囲内
(2)無効の例
東京リーガルマインド事件
判決概要:競業避止特約における禁止の内容や程度が必要最小限でなく、代償措置も不十分な場合は無効
(3)競業禁止が許された期間の例
新大阪貿易事件:3年間を有効フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン事件:5年間の競業制限を有効
(4)競業避止義務違反の損害認容額例
日本コンベンションサービス事件:400万円エープライ事件:316万円東京学習協力会事件:376万円チェスコム秘書センター事件:500万円
以上のように実際に裁判において競業行為を行った人に対して損害賠償が認められたケースもありますが、立証が難しいことには変わりありません。
トラブルを防ぐためには入社や役員就任時に書面で競業避止義務の範囲を明確に規定するとともに、もしも問題が起きた場合は早めに弁護士に相談することをオススメします。