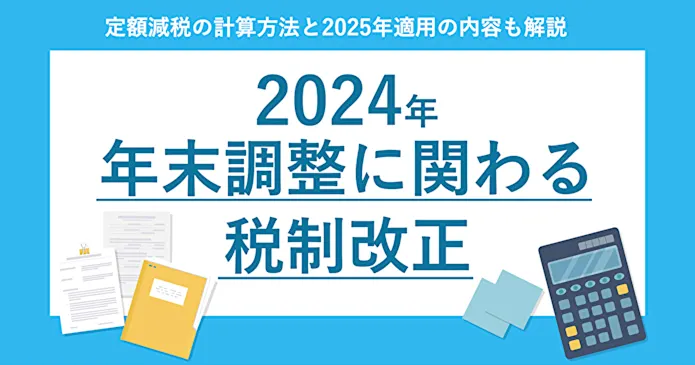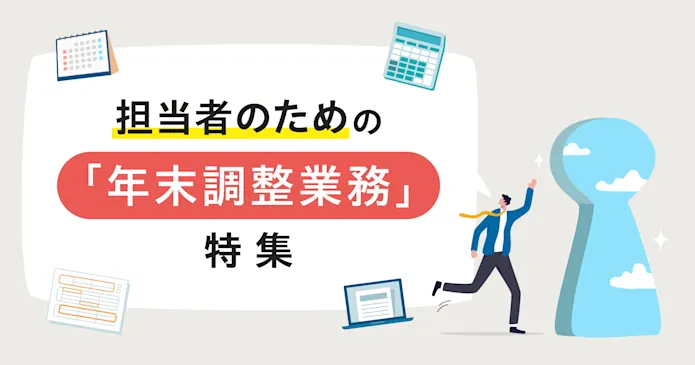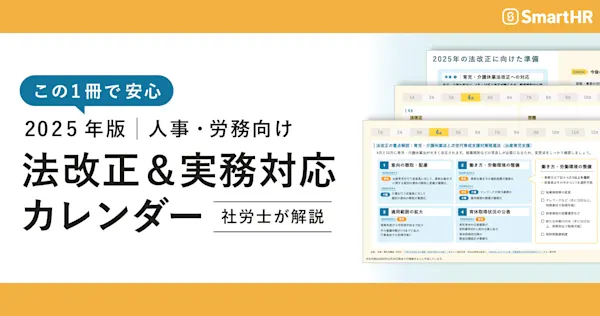給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入例。注意点を税理士が解説
- 更新日
- 公開日

目次
こんにちは、税理士法人ビジネスナビゲーションの木所です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与所得者が毎年の年末調整時と、期中に異動事項のあった際に会社に作成・提出するものです。こちらの書類は、毎年の制度改正の影響により、微妙に記載内容や要件が変わります。
今回は、令和7年の扶養控除等申告書をベースに、制度改正による注意点にも触れながら、その書き方を網羅的に解説したいと思います。なお、本解説の前提となる法令は、令和6年7月1日現在の所得税法等の関係法令をベースとしております。
給与所得者とは(概要説明)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除申告書)は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などを受けるために行う手続きです。
年収2,000万円以上といった別途確定申告が必要な人を除き、たとえ、独身者等で扶養する対象者がいない場合であっても、給与所得者である限り、原則全員がこの申告書を提出する必要があります。
提出時期は、その年の最初の給与支払日の「前日」まで(中途就職なら、就職後の最初の給与支払日の前日)とされ、また、提出後に記載内容に「異動」があった場合にも、その異動後の最初の給与支払日の「前日」までに、給与支払者に提出する必要があります。
令和7年版 扶養控除等(異動)申告書のポイント
簡易な扶養控除等申告書
源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき次の事項がその年の前年の申告書に記載した事項から異動がない場合には、その異動がない旨の記載をすれば良いこととされました。
この前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。

出典:国税庁「簡易な扶養控除等申告に関するFAQ(源泉所得税関係)」
書き方の解説(ステップ1~4)

ステップ1:「基本情報」欄
名前、生年月日、世帯主氏名、続柄、マイナンバー、住所・居所、配偶者の有無について記入します。
また、「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄は、この申告書(主たる給与の支払先に提出するもの)以外に、従たる給与の支払先にも別途に提出している場合に〇印を付けます。
本来的には、主たる給与の支払先1ヶ所のみに提出すればいいのですが、例外的に、それ以外の給与支払先(従たる給与の支払先)にも提出する場合があることから、この欄が存在しています。
ステップ2:「主たる給与から控除を受ける」欄
A.源泉控除対象配偶者
源泉控除対象配偶者とは、所得者(令和4年中の所得の見積額が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者(一定の事業専従者などは除く)で、令和4年中の所得の見積額が95万円の人をいいます。
この者について、氏名、マイナンバー、続柄、生年月日、所得の見積額、住所・居所などについて記入します。また、非居住者である親族である場合には、〇印を付けるとともに、関係書類の提出も必要となります。
B.控除対象扶養親族(16歳以上)
(1) まず、扶養親族とは、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族又はいわゆる里子や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 所得の見積額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2) そして、本欄で記入する「控除対象扶養親族」とは、上記の扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。これらの各者の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日を記入します。
(3)次に、これらの各者について、老人扶養親族(同居老親等orその他、の別)又は特定扶養親族に該当する場合には、各欄にチェックを入れます。
※1:老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※2:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
なお、同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者などと別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとすることができます。ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
※3:特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
(4)さらに、これらの各者について、所得の見積額、住所・居所などについて記入します。また、非居住者である親族である場合には、〇印と、「生計を一にする事実」としてその年の送金額などを追記するとともに、関係書類の提出も必要となります。
C.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生
以下の各項目に該当する場合には、該当欄にチェックを入れます。
(1) 障害者
給与所得者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除(障害者控除)を受けることができますので、各欄の該当箇所にチェックを入れ、扶養親族の場合には人数も記入します。
※1 同一生計配偶者とは、所得者本人と生計を一にする配偶者(一定の事業専従者などを除く)で、所得の見積額が48万円以下である者をいいます。
※2 障害者控除における扶養親族は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されますので、注意してください。
(2)寡婦、ひとり親
前述のとおり、令和2年度の税制改正で、「寡婦、ひとり親」の2分類となりました。該当する箇所にチェックしてください。
(3)勤労学生
勤労学生とは、所得者本人が次の3つの要件の全てに当てはまる者です。
- 大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 所得の見積額が75万円以下(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下)で、かつ、そのうちの勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
(4)「障害者又は勤労学生の内容」欄
例えば、障害者であれば、「氏名、身体障害〇級、交付年月日」といった記載をします。
ステップ3:「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄
共働きなどで同居している家族内に二人以上の所得者がいる場合、扶養親族はどちらか一方の所得者でしか控除は受けられません。
本人が「扶養しない」場合には、この欄に、対象となる「扶養しない」子供などの氏名、続柄、生年月日、住所・居所、その子供等の「扶養者となっている他の所得者」の氏名、続柄、住所・居所などを記入します。
ステップ4:住民税関係
1.「16歳未満の扶養親族」欄
上記ステップ2のB欄のとおり、所得税(国税)上の扶養控除の対象となるのは16歳「以上」の扶養親族ですが、住民税(地方税)の計算上は、16歳「未満」の扶養親族の情報も必要となります。このため、その者の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日、住所・居所、その者が国外に住居を有しない扶養親族の場合は「控除対象外国外扶養親族」欄に〇印、所得の見積額などをここに記載します。
記入時に特に注意したいポイント
マイナンバー
従業員本人、控除対象となる配偶者および控除対象扶養親族などのマイナンバーの記載は、原則として、毎回必要です。ただし、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者(会社など)が従業員などのマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている者のマイナンバーの記載は不要となっています。
提出先の会社などがこの要件に該当しているかどうかは、給与担当者などにご確認をいただければと思います。
おわりに
年末調整の事務や関係書類の作成は、毎年のルーティンワークではありますが、ほぼ例外なく毎年の制度改正の影響を受け、控除の要件や記載方法が大なり小なり常に変更がなされています。
小さなミスや誤解も、人数が多くなるとそれを訂正するのに手間がかかってしまいます。日頃から法改正の情報等をキャッチしながら、事務の効率化にも取り組んでいただければと思います。
年末調整Q&A
Q. 扶養控除申告書の提出義務は?
「扶養控除等申告書」を会社に提出しないと、年末調整を受けられません。独身者や配偶者などの扶養となっている場合でも提出する必要があります。
Q. 扶養控除申告書提出しないとどうなる?
控除を受けられないため、翌年の源泉徴収税額が大幅に高くなり、給与の手取り額が大幅に減る可能性があります。

お役立ち資料
3分でわかる!ペーパーレス年末調整
書類配布、従業員からの質問対応、締め切り内での回収…と、年末調整シーズンの業務は特に膨大で、つい残業が多くなってしまいませんか? 「次回の年末調整はもっと楽に効率よく行いたい!」というご担当者さまには、ペーパーレス年末調整をおすすめします。 3分で概要がわかる資料をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください。
【こんなことがわかります】
- ペーパーレス年末調整とは?
- ペーパーレス年末調整の3ステップ
- お客様の声

メールマガジン「週刊SmartHR Mag.」
社会保険労務士や弁護士など、人事・労務の専門家による実務に活かせる生の情報を発信していきます。メールマガジンでしか読めない専門家のこぼれ話なども掲載中です!