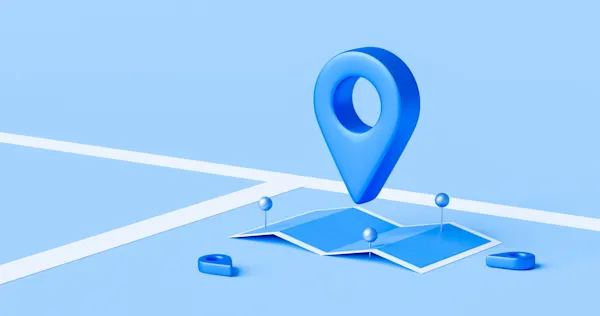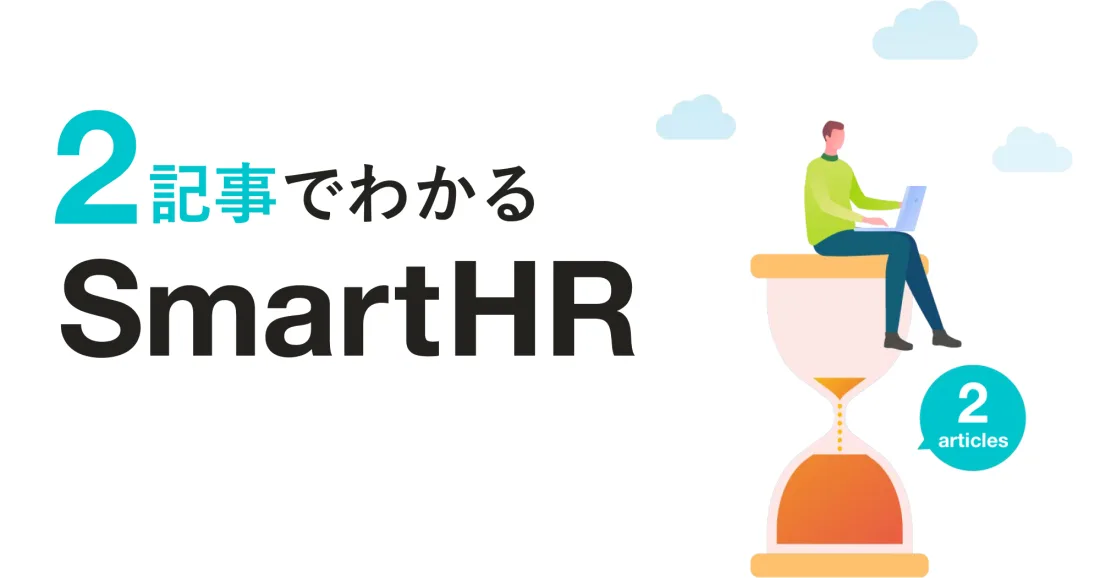納得感を目指した「現実解」(1)〜純粋に個人を評価する難しさを知る〜人事評価の現在地 #06
- 公開日
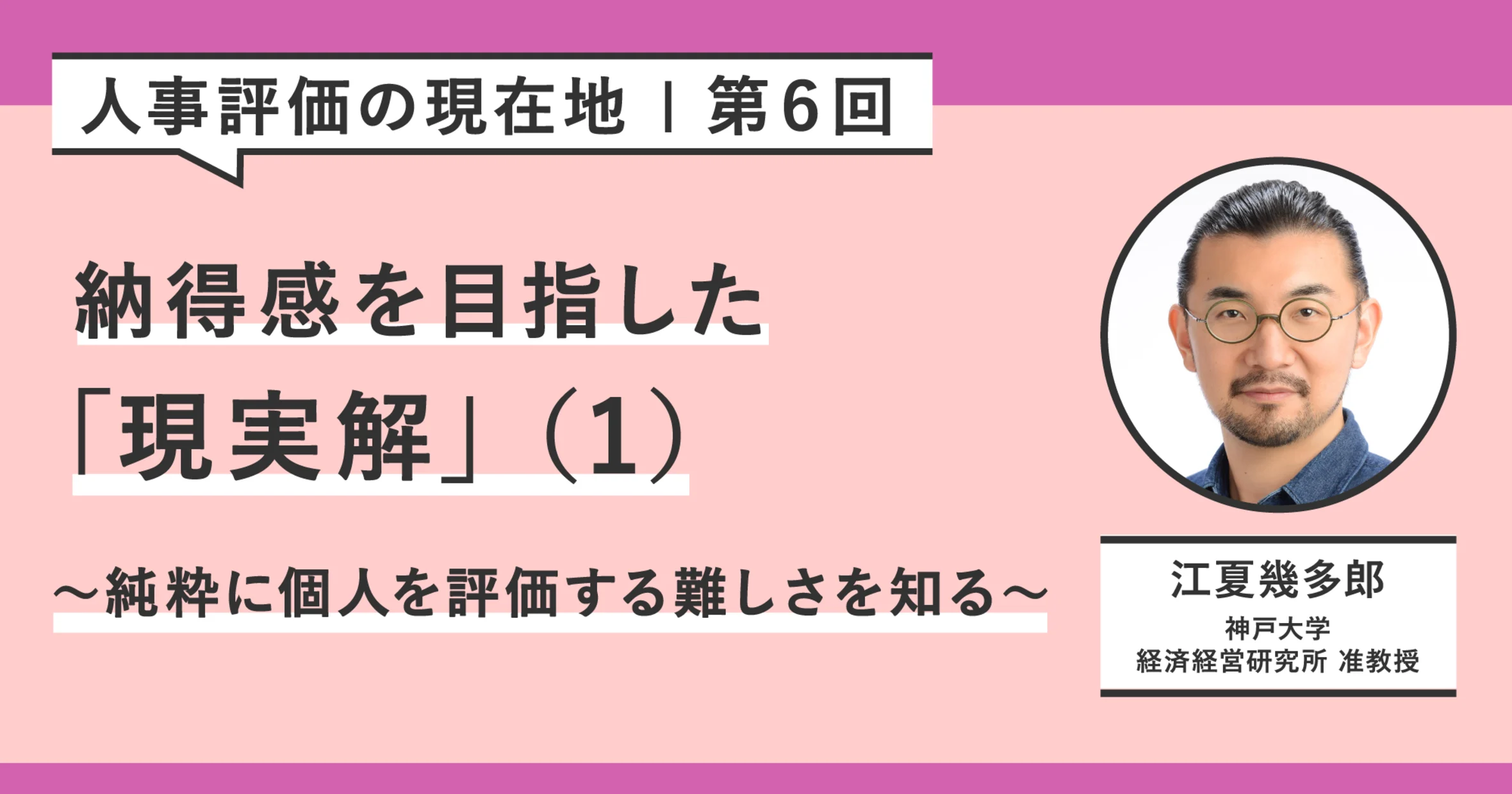
この記事でわかること
- 被評価者からの納得を得るためのポイント
- 人事評価システムをフル活用するためのコツ
- 自身の評価に納得している従業員の評価・処遇・職務環境の捉え方
目次
「人事評価制度がうまく運用できていない」、「現場の評価への不満が収まらない」。人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。
この連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者、被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。
第6回目は「人事評価の運用の原理原則にこだわらない形で形成される納得感」について考察します。
「納得感のための公正性」とは言うものの……
人事評価においては、報酬原資の制約、さらには正確な運用の難しさから、すべての従業員に満足してもらうことは難しい。そのなかでも、「より多くの従業員に納得してもらう人事評価」を受け入れてもらう手がかりとなるのが、公正性の確保である。
公正性についての研究によると、実際に提供された評価や報酬が「もらいたい」という水準を下回っていたとしても、自らの貢献に企業や評価者が可能な限り配慮していると知覚される場合、被評価者は評価や処遇に納得する。
また、「評価者から人格的に尊重されたり情報公開を受けたりすること」、「発言や質問の機会が設けられること」など、企業や評価者から自身へのコミットが明らかであれば、被評価者は人事評価に納得しやすくなる。
しかし実際の人事評価では、公正性すら実現が容易ではない。多くの従業員が、自分の評価や処遇の絶対的あるいは相対的な水準について、合理的な理由を見出せずにいる。また、不透明さを覚えたり、評価者の判断の誤り、責任の回避を指摘したりする。
人事評価への被評価者の納得感を得るために、企業、評価者、人事担当者は何ができるだろうか。
人事評価の公正性を阻む「評価者の繁忙」
本連載の第4回目で紹介したように、正確な人事評価は実現が困難である。もし従業員の貢献を包括的に捉えようとする場合、評価項目は多岐に渡り、かつ曖昧になりがちである。体系立った測定尺度を用いて従業員の貢献を定量的に把握しようとするほど、真の貢献を捉えきれない「数字の一人歩き」が生じかねない。
高度専門職やホワイトカラーが典型だが、複雑な業務、自己完結的に実行しにくい業務について評価するとき、こうした困難が生じやすくなる。
また、人事評価が階層の異なる複数の評価者により複数回にわたって評価され、さらには評価者間で協議される場合、評価結果の根拠が見えにくくなり、被評価者へのフィードバックが難しくなる。
複雑な人事評価システムをフルに活用するためには、「評価の作業に時間をかけ、被評価者について深く考えを巡らせること」、「被評価者や他の評価者との関わりに時間を割くこと」が評価者には求められる。それは、人事評価の正確性のみならず、公正性のためにも必要である。しかし多くの評価者が、被評価者と十分に関われていないようだ。
「管理者の時間の使い方」に課題がある?
産業能率大学が管理者(課長)を対象に2020年に実施した調査によると、「本来割くべきなのに割けていない活動」として多く列挙されるのが、
- 戦略や方針の策定
- 部下とのコミュニケーション
- 他部署とのコミュニケーション
である。また、「資料作成(社内向け)」、「会議」、「承認業務」に必要以上の時間や労力を奪われている。

(出典)産業能率大学(2020)「日本企業のミドルマネジャー調査報告書」より筆者が作成
※時間を割いている順に第1位から第3位のそれぞれの比率を筆者が合算
日本の多くの企業では、各従業員の職務範囲の規定を曖昧にする傾向がある。同僚などとの調整のなかで自身がなすことを決める結果、従業員のタスクが時と場合に応じて柔軟に変化する。そこでは、事前の個人成果や貢献の定義が難しくなる。
評価者は、被評価者と日常的に関わりをもちながら、被評価者の働きぶりについて観察したり、彼ら自身に尋ねたりしながら、評価情報を蓄積する。さらには現実的な評価基準の策定も求められる。しかし、それが難しいことをこの調査結果は示している。
評価者にとって被評価者の業務の調整に関与することは、評価情報の蓄積という観点から見て有効である。しかし、調整業務の大変さ、また、その結果としてしばしば生じる一部業務の引き取り(プレイングマネジャー化)が、人事評価への集中を難しくもする。
職場における上司・部下関係の多くは、人事評価における評価者・被評価者の関係である。この関係性が希薄であることは、評価者が被評価者の日々の働きぶりや貢献を十分に知ることを妨げ、被評価者から見た評価者の信頼感の構築を難しくする。
そして関係性の希薄さが、人事評価の正確性あるいは公正性を通じた従業員の納得感の醸成を難しくする。
評価者の主体的決定を妨げる「人事評価の決定構造」
もっとも、評価者の業務に余裕ができ、被評価者の日々の働きぶりを観察し、人事評価情報を蓄積できれば、人事評価の正確性や公正性が増すとも言い切れない。
その背景には、評価者が自らの考えを人事評価に十分に反映させるのを阻む「人事評価の決定構造」がある。こうした制約は、とりわけ日本企業においては顕著になりがちである。
日本企業では、他国と比べ、採用・配属・育成・処遇・退出などのさまざまな人事機能について、決定権限が本社人事部門に集中する傾向がある。たとえば、新卒一括採用に見られるように、本社人事部門が従業員を一旦本社で採用した後に、さまざまな事業部門や地域の職場に従業員を配属する。
部門をまたぐような人事異動も、従業員を送り出す部門と受け入れる部門の間の協議ではなく、本社人事部門の差配により実施される。入社年次や年齢などに応じた従業員の一律的な管理を本社人事部門が担うこともある。
処遇、すなわち人事評価や報酬の決定・配分についても、同様の集権性が見られる。多くの企業では、個別の人事評価に先んじて、人件費や昇進・昇格枠など、報酬原資の総枠を本社人事部門が決定する。そして報酬原資は、所属人数などの基準で、部門などの配分単位のそれぞれに配分する。人事評価の甘辛判定や分散を揃えるため、評点分布のあり方を本社人事部門があらかじめ規定する場合もある。
人事評価への不満の温床としての決定構造
評価者は、自らの部門に割り当てられた報酬原資を前提に、被評価者の人事評価を決定しなければならない。しかし「与えられる」報酬枠は、評価者が被評価者を日々観察した結果として導き出される被評価者全体に「与えたい」報酬枠と、往々にして一致しない。後者が前者を上回ることが多い。
このようなとき、評価者は、顕著な貢献をした被評価者に貢献に見合った報酬を与えられなくなる。そのため、実際の貢献と報酬の間の歪な関係について、明確なフィードバックをしにくくなる。この現象が被評価者の不満や疑心暗鬼の温床になりやすい。
これらは、評価者の主体的な判断、または不作為の結果ではなく、評価者から見ても不本意で、無力感を抱かせるものである。
人事評価の現実を知り、過度な期待を寄せない被評価者
こうした現実、人事評価を取り巻く構造的な制約は、よほどの高収益で、かつ収益を従業員にふんだんに還元するような企業でない限り免れない。その事実への理解がない被評価者は、人事評価、さらには評価者や所属企業に対して強い不満をもちやすいだろう。
もちろん、構造的要因を理解したからといって、評価や処遇に満足できるようになるわけではない。実際の評価が、自らの「もらいたい評価」を大きく下回らないことが前提になるだろう。また、そこでの納得も、職務に対して前向きになるようなものではなく、「モチベーションを大きく下げない程度」のものになるだろう。
しかし、現実の雇用関係を考えると、企業としては、従業員の職務上のモチベーションが評価や処遇で上下しすぎることは、望ましいことではない。むしろ、従業員を動機づける人事評価ではなく、従業員の動機を大きく損ねない人事評価の実現を模索しつつ、他の動機づけ要因の確立に注力すべきだろう。
そうすることで、理想どおりに進まない人事評価に対して、従業員の注意も向きにくくなるのではないか。
不十分な人事評価にも納得する従業員
筆者が過去に実施した調査(江夏,2014)や、勤務先に学生として通う実務家とのインフォーマルなやりとりからは、成果主義のような人事評価や処遇の方針が実現しているかがはっきりしないにもかかわらず、評価に納得している人々が、人事評価、処遇、さらには職務環境について、以下のように捉えていることが発見された。
人事評価の困難さへの理解 |
|
報酬そのものへの一定の満足 |
|
職務環境における魅力への着目 |
|
前向きな将来展望 |
|
上記の指摘に共通しているのは、まず、「人事評価の理想にこだわりすぎることが、目先の出来事への不満につながりやすい」と被評価者が理解していることであった。そのうえで、そういった「罠」に陥らないように、被評価者が自ら心掛けていることであった。
「罠」を回避する手がかりとして指摘されたのが、業務内容の充実や、評価者を含む周囲の人々との人間関係の良好さであった。これらの手がかりは、人事評価制度の改善とは別の側面である「職場風土」、「管理者のリーダーシップや管理行動」、「職場内コミュニケーションの改善」によって、多くの従業員が手にしやすいものだろう。
また、現状の人事評価や処遇における好ましくない点について、「永続的に続くものではない」、「将来時点で解消可能である」と捉えている従業員もいる。こうした「将来に対する前向きな展望」を評価者がどう醸成していけるかについて、次回は検討する。
- 参考文献
- 江夏幾多郎(2014)『人事評価の「曖昧」と「納得」』NHK出版.
- 産業能率大学 (2020)「日本企業のミドルマネジャー調査報告書」

お役立ち資料
経営の未来をつくるカギは人事評価にある
人事評価が「従業員の能力や業績を評価して、待遇・賃金を検討するための仕組み」であることは言うまでもありません。しかし、人事評価が影響する範囲は大きく、自社の経営の未来をつくる存在でもあります。
本資料では、見落とされがちな経営戦略と人事戦略を連動させる重要性について解説しています。