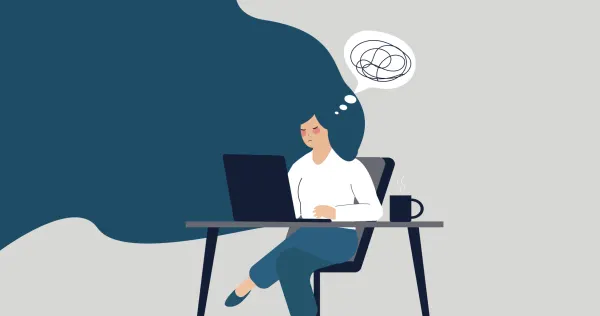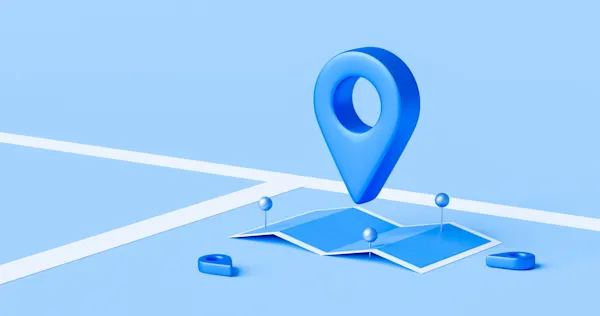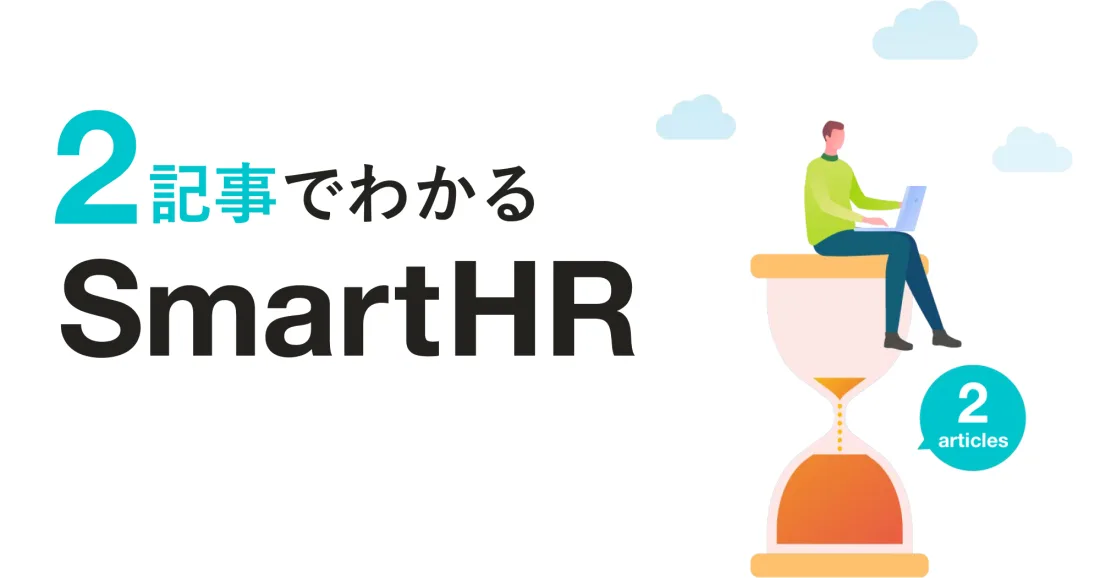変革の鍵は対話にある。宇田川先生と読み解く“構造的無能化”からの脱却
- 公開日
目次
SmartHRでは経営層の方々を対象に、ゲストスピーカーを招いた講演と情報交換の場を提供する少人数制のオフライン交流会を開催しています。
今回は、埼玉大学経済経営系大学院 准教授の宇田川元一氏をお迎えし、宇田川先生の新著『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』を読み解きながら、現状の課題や今後の打ち手について語り合うイベントを開催。
本記事では宇田川先生による当日と講演の様子を中心にお届けします。

埼玉大学経済経営系大学院 准教授
経営学者。埼玉大学 経済経営系大学院 准教授 1977年、東京都生まれ。立教大学経済学部卒業後、同大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、長崎大学経済学部講師・准教授、西南学院大学商学部准教授を経て、2016年より埼玉大学人文社会科学研究科(通称:経済経営系大学院)准教授。 専門は、経営戦略論、組織論。 対話を基盤とした企業変革について研究を行っている。また、大手企業やスタートアップ企業における企業変革やイノベーションの推進に関するアドバイザーとして、その変革を支援している。
企業変革が進まないのは悪意のある犯人がいるから?
これまで私は『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』『組織が変わる——行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法2 on 2』『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』と、3つの書籍を執筆しました。一貫したテーマは「対話」であり、対話をベースに組織の課題をどう解決するかを考えてきたと捉えています。
「対話」と聞くと、1on1や特別なワークショップをイメージする方もいるかもしれません。ですが私は他者の視線を媒介にして自分を捉え直し、みえてきたものに応答することが「対話」と考えています。それこそが企業変革の鍵ではないかと思うのです。
企業変革が進まないとき、よくあるのは「変革をストップしている悪意ある人間がいる」といった議論です。私自身、企業の若手社員や中堅社員の方から『経営層はわかっていない』『変えるつもりがないんだ』とよく聞いていました。
では実際に経営層はどう思っているのか。ありがたいことに2冊の書籍を出して以来、経営層の方々とお話しする機会をいただくことが増えました。話してみると、皆さん拍子抜けするくらい人格者。変えるつもりがないどころか「会社を変えなければいけない」と真剣に思い、悩んでいらっしゃったんです。
もう1つ気づきがありました。「経営層から現場がどうみえているか」を伺うと「意識が低いのでは」と思っている方が多いことです。自分の若いころは部長や課長にアイデアを提案し、手助けしてもらいながら事業を形にした。だが、今は若手も手を上げてこない。若手の新しい発想や創意工夫への期待を語られる方も少なくないんです。

では実際に現場の方の意識は低いのでしょうか。私は決してそうではない気がします。決して意識が低いわけではなく、日々の業務や予算達成に追われている。
つまり変革が進まないのは、犯人がいるからではない。それぞれの思いがあって真剣に仕事に取り組んでいる。だけど噛み合わず互いに疑心暗鬼になっている。非常に悲しいことだなと思うわけです。
今すぐ手術は必要ないが、健康を損なう“企業の慢性疾患”
経営危機にはいたっていないし足元の業績は悪くはない。けれど、何となく全員が噛み合わず、緩やかに衰退していく気がする。かといった明確な問題はわからないし、問題意識も共有されていない——。そんな状況に置かれている企業は少なくないと思います。
これは長年の生活習慣によって組織が「慢性疾患」にかかり、健康を喪失しているような状態と捉えています。何となく頭が痛かったり、熱が出ていたりするけれど、今すぐ命にかかわるものではない。けれど根本的な原因はわからない状態です。
高血圧症を例に考えてみましょう。薬で血圧を一時的に下げることはできても、根本的な解決は難しいと言われている症状です。手の付け所で悪化は防げるし寛解もできるけれど、完治は難しい。外科手術で治るものでもありませんから。不都合の要因を少しずつ探りながら、必要な手立てを施していくしかないのです。

企業組織の慢性疾患も同様です。表層的な問題の奥にある複雑に入り組んだ要因から、解くべき課題を発見し、必要な手立てを探っていくしかない。その試行錯誤の過程こそが、企業変革なのではないかと思っています。
誰も悪くない「構造的無能化」は組織の宿命
本書では、企業の変革を妨げるメカニズムとして「構造的無能化」を取りあげています。これは、組織の考えたり実行したりする能力が合理的に下がっていく現象を指します。誰か悪い人がいてそうなるのではありません。成熟した組織にとって宿命であり、無能化にどう抗うかが問われます。「構造的無能化」はなぜ、どのように起きるのか。「断片化」「不全化」「表層化」で捉えられます。
断片化
成熟した企業は一度事業の基盤を整えると、分業やルーティーン構築によって効率化を図ります。例えば同じ営業でも「インサイドセールス」や「アウトバウンドセールス」に分けたり、人事を「労務管理」と「人材・組織開発」に分けたりする。分業によって効率性や専門性が増すのはもちろんよいことです。
ですが、分業によって全体像がみえないなかで割り振られた仕事をこなすだけといった「断片化」が起こります。一人ひとりが職種の範囲で物事をみるようになってしまうわけです。
不全化
断片化が起き、狭いスコープのなかでしか環境を捉えられなくなると、人は現在の枠組みの外の環境変化や新たな兆しを見るのが難しくなってしまいます。新しい事業の構築や実行ができない組織になる「不全化」が起こります。
表層化
不全化が進むと、一人ひとりが狭い認知のなかで解決策を探り、実行し始めます。構造的に問題が起きているのに表層的な問題に取り組んでしまう「表層化」が進むのです。
例えば「離職が多い」という課題に対して根本的な課題を捉えず「とりあえず1on1を実行する」という解決策を出す。「1on1をやらない人がいる」という課題に対して「やったことを記録するシートを用意する」という解決策を出す。これが繰り返されると、ただ現場の負担が増えてしまう。人事部門はできる範囲で解決策を探っているのに、人事部門をよく思わない人も出てきてしまうのです。

このように構造的無能化において「無能な個人」や「悪い個人」がいるわけではありません。お互いの視界が違っている状態です。
視界が違うからこそ「どう橋を架けていくのか」が重要です。例えば、企業の経営層や人事の方から「エンゲージメントの数値を上げたい」とよく相談を受けます。人的資本開示で数値を上げたいけれど、エンゲージメントの低い部署ほど何も取り組んでくれないといった相談です。
これも現場の人の立場ではに立つと、別の景色がみえてきます。まず、そもそも現場の人は「エンゲージメント」という抽象概念には困っていないんです。予算達成しないといけないとか、部下が辞めちゃうとか、競合との戦いが苦しいとか。そうした困りごとを抱えている。いずれもエンゲージメントの数値を上げることには直接関わるものではないと考えている。だから自発的に取り組む理由がないんです。変革を進めるには、相手にとっての意味は何なのかを丁寧に見出していくことが大切になります。
表層化した課題の背後を探究する「ケア」の観点
表層化を踏まえて、私は「ケア」という概念が企業変革においても重要と捉えています。
ケア的な観点では、正論を言っても始まりません。表層的な問題の背後に複雑な問題が起きているのだという前提に立ちます。鉄欠乏症の女性が鉄を飲まないのをどうするか。うつの患者が鬱の薬を飲まないのをどうするかがケアの世界です。相手の世界を知らないと手の付けどころもみえない。僕はこの概念と実践のあり方を、精神障害者支援の世界にフィールドワークするなかで見出しました。
興味深い例を紹介しましょう。北海道浦河町には『べてるの家』と呼ばれる精神障害などをかかえた当事者の地域活動拠点があります。統合失調症や過食嘔吐や双極性障害など、重めの精神障害をもつ人がケアのコミュニティを形成しています。
べてるの家で実践されているのが「当事者研究」という取り組み。専門家ではなく当事者が自分たちにできることを探っていく対話実践です。
とある過食嘔吐の人の当事者研究を紹介します(※)。過食嘔吐は命にもかかわる病気ですが、周囲がやめようとさせても簡単に治らない難治性の症状です。当事者研究では「どうしたら治るか」は話しません。代わりに当事者同士でその問題について色々な角度から眺めてみることをします。その中のひとつに「どういう食べ吐きが成功か」を考えたそうです。そうすると「ストレスが溜まって過食嘔吐をした後『顔色悪いけど大丈夫?』と心配してもらったときが成功した食べ吐き」といった答えが出てきたそうです。
※浦河べてるの家(2005)『べてるの家の当事者研究』医学書院
つまり過食嘔吐が「心配してほしい」というSOSの発信になっている。食べ吐きをとりあげるとコミュニケーション手段が奪われてしまうのです。表にみえている問題は過食嘔吐だけれど、背後には「自分の辛さをわかってほしい」という思いがある。二重性のある問題で、表象的な課題だけを解決してもどうにもならない。
表層的な問題を解決するのをやめて、どうやってそのスキルを身につけたかを研究する。背後にある苦しみを対話によって探る取り組みによって自発性のある紐解きが実現できるのではという学びを得ました。
先ほどのエンゲージメント向上の例において、表層的な問題は「現場の部門長が協力的ではない」です。これに対して「エンゲージメントは高い方がいいのに、なぜやらないのだ」と正論を言ってもはじまらない。部門長が何か困っていることが背後にあるからだ。その背後に複雑な現象があるはずだと捉え直せば、何かがみえてくるかもしれません。
問題の二重性と向き合い、変革に向かう6つの視点
ここまでお話ししたとおり、問題は二重に発生しています。私たちは、ついわかりやすい解決策を求めてしまいますが、それでは埒が明きません。なんとか紐解いて一歩ずつ変革しないといけない。最後に、その際に大切な要点を紹介したいと思います。
(1)変革の過程のほぼすべてては、課題が何であるかがわかることである
長年支援しているとある企業があります。そこで一度「これが課題だ」と考えて解決に取り組むと、5年後くらいに「こっちが本当の課題だったんだ」とわかる。そしてまた次の5年で、新しい“本当の課題”がみえる。同じことを繰り返しているようですが、5年やると「だいぶ遠くまできたね」という感覚が得られます。
変革の施策を打ってうまくいかないときは変革が進んでいる証拠です。頓挫したときも変革が進んでいます。「なぜそれが起きているのか」を紐解くのが変革であると覚えておいてほしいです。
(2)問題のある部署・人・能力がない部署がいるのではない。彼らの課題をわかっていない我々がいる
変革する側は、相手に対して「あの人達はわかっていない」と思ってしまいがちです。「会社の状況が厳しいのになぜ役員はわからないんだ」と。でも、そうではありません。私たちが「相手の課題がわかっていないという状況」に直面しているだけなんです。
(3)困った人は、困っている人である
これはかつて依存症のパンフレットに書かれていた言葉です。酒を飲んで暴れる人は困った行動です。支援者にとっても家族にとっても困った人です。けれど、なぜお酒を飲んで暴れるかというと、家庭や仕事など、語られないの複雑なストレスで困っているからだったりする。そういう視座をもつと、これまでと異なる方法・視点から変革に取り組めると思います。
(4)足りないパーツがあるならばそれを作らねばならない。パーツが充足する構造へと組織を機能させなければならない
変革のために足りないパーツがあるなら、買ってきたらいいと思うかもしれません。でも「なぜパーツがないのか」という構造に目を向けると解決の糸口がみえます。
たとえば新規事業が育たないときにM&Aするのも一つの手です。でもなぜ育たないのかは構造的な問題があるはずなので、そこに目を向けるのが大事です。
(5)今起きている課題に、新たな目を向けなければならない
今ある課題に“今の視点”だけで向き合っていると、いずれ行き詰まります。表層化の罠にハマってしまう。先ほどの「困った人は困っている人である」的な視点など、少し違う視点を導入することで、別の何かがみえてくるはずです。
(6)何が問題なのかがわかるためには、様々なアプローチが不可欠である。理屈が通ることと、問題がわかることは全く次元が異なることを理解しないといけない
最近は多くの企業が立派な統合報告書を公開しており、マテリアリティなどが書かれています。ですが、変革の進まない企業は矢印同士がつながっていないと感じます。「なぜ課題Aと課題Bがつながっているのか」について、図表では理屈が通っているけれど「本当にそうか?」と思ってしまう。理屈上はつながっていても、従業員が自発性をもって取り組むレベルかというと、そうでない場合もあります。説明責任を果たすということと実際に組織が動くことは別次元の話なのだと捉えておく必要があります。
最後に、今回の書籍を執筆するうえで再読したピーター・ドラッカーの言葉を紹介させてください。彼は戦時中のヨーロッパでユダヤ人として共産主義とファシズムから逃れるために、米国に亡命しました。
彼が「なぜ独裁政権が滅びるのか」について政治学者として執筆したのが『産業人の未来』。本著からの引用をもって、講演の締めくくりとさせてください。
「完璧な青写真なるものは、二重に人を欺く。それは、問題を解決できないだけでなく、問題を隠すことによって、本当の解決を難しくする」
「われわれは大胆でなければならない。しかし、大胆さのための大胆であってはならない。 分析においては革新的、理念においては理想的、 方法においては保守的、行動においては現実的でなければならない」

イベントの後半では宇田川先生によるファシリテーションで、少人数グループでのディスカッションを実施。書籍や講演の感想にはじまり、各社の企業変革をめぐる課題や考えについて共有し合いました。
ディスカッション終了後にはドリンクと軽食をいただきながらの懇親会。なごやかな雰囲気の中で宇田川先生と参加者の歓談もはずみました。