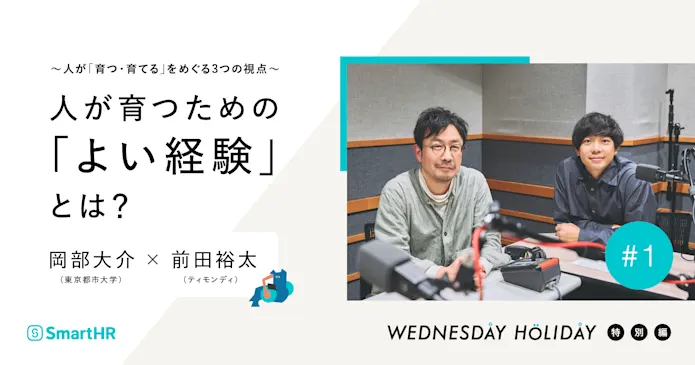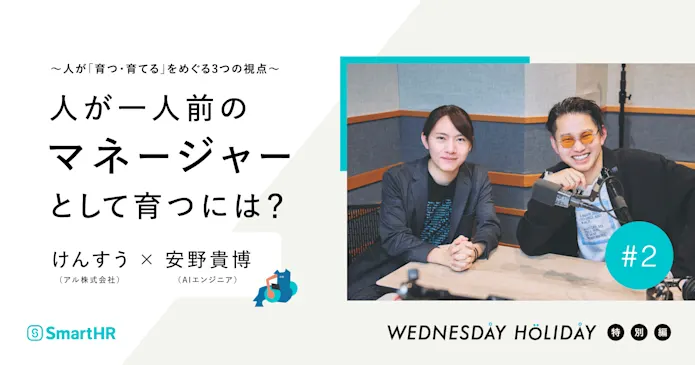「メンタルブロックを外す」 4世代が共存する組織で“育て合う”には?
- 公開日
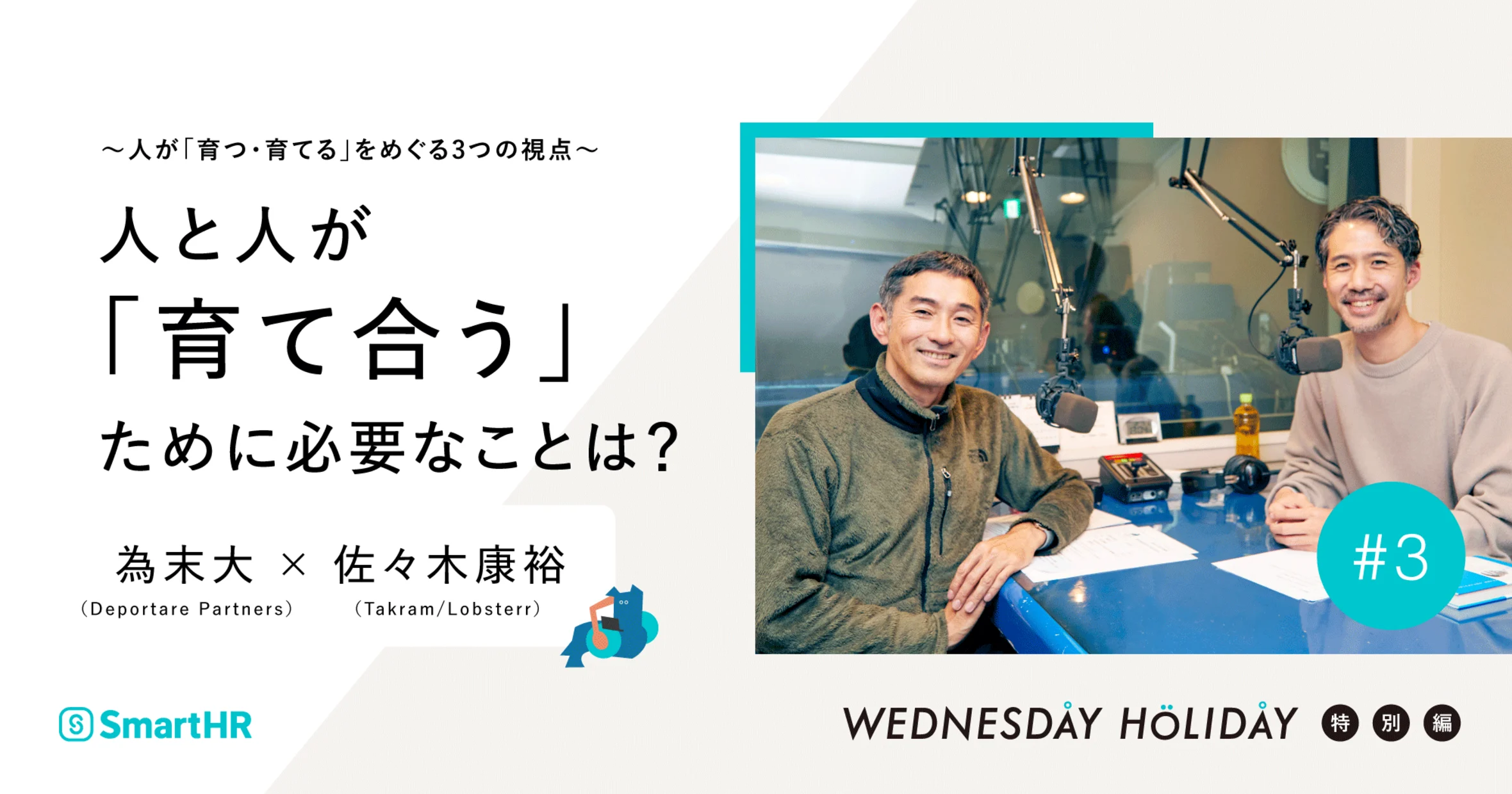
目次
SmartHRが「“働く”を語る水曜日の夜」をコンセプトに配信するポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』。今回は、100回を記念して配信された「人が『育つ・育てる』をめぐる3つの視点」のレポートをお届けします。
第3回のパーソナリティを務めたのは、アスリートであり、教育の実践者として活躍される為末大さんと、クリエイティブとビジネスを越境するビジネスデザイナーの佐々木康弘さんです。番組では、「人と人が『育て合う』ために必要なこと」をテーマに対話が進みました。
- 為末 大
Deportare Partners代表
1978年広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得者。男子400メートルハードルの日本記録保持者(2025年1月現在)。現在はスポーツ事業を行うほか、アスリートとしての学びをまとめた近著『熟達論:人はいつまでも学び、成長できる』を通じて、人間の熟達について探求する。その他、主な著作は『Winning Alone』『諦める力』など。
- 佐々木 康裕
Takram フューチャーズ・リサーチャー / Lobsterr Another Editor-in-Chief
カルチャーや生活者の価値観の変化に耳を澄まし、企業やブランドが未来に取るべきアプローチについて考察・発信を行っている。そうしたアプローチを基にした著書に『パーパス 「意義化」する経済とその先』『D2C 「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略』〈ともにNewsPicksパブリッシング〉、『いくつもの月曜日』〈Lobsterr Publishing〉などがある。Takramでは、未来洞察や生活者理解のためのプロジェクトを数多く実施している。2019年3月より、カルチャーやビジネスの変化の兆しを世界中から集めて発信するスローメディア「Lobsterr」を主宰。
AIとデジタル化がもたらす「教える・教わる」の変化
「世代や立場を超えて、知識や技術をシェアする場面が増えている」と切り出す為末さん。そこから、組織における学びの関係性変化について考えを深めます。
為末さん
AIのことは、20代の人から教わることが多いですし、スポーツ界でもYouTubeで学び「球が150キロ出るようになりました!」という選手が出てきています。知識や技術の習得方法が変わるなか、従来の「教える側・教わる側」という固定的な関係が、大きく変わってきています。
佐々木さん
相互に育て合う時代に注目したいのが「メンターン」(※)という概念です。「メンター」と「インターン」を掛け合わせた言葉は、年長者が自身の経験で培った知恵を若手に教えながら、自分自身も若手から新しい知識や視点を得ていく考え方です。年長者もインターンのように、オープンマインドで学んでいこう!という姿勢は、双方向の成長を促します。
※チップ・コンリー著『モダンエルダー 40代以上が「職場の賢者」を目指すこれからの働き方』で紹介

世代間の育て合いを阻む「メンタルブロック」
メンターンのようなマインドセットは、「年長者を敬い、経験を重んじる価値観が根強く残る日本の組織ではそう簡単にはいかないのでは?」と疑問を投げかける為末さん。
為末さん
儒教的な価値観を背景にもつ東アジア・日本では、経験や年齢重視のコミュニケーションが一般的ですよね。そういう環境で育つと、それ以外の関係性づくりが難しくなってしまうのではないでしょうか。
佐々木さん
まさに。結局「DQとEQを交換すること」に行き着くのかなと。DQ(デジタル知能指数)、つまりデジタルリテラシーは若い世代が圧倒的にもっている。一方で、事業を成長させるためのコーディネーションなど、EQ(心の知能指数)に関わる部分は、年長者が豊富な経験をもっている。これらを互いに教え合おうというものです。
ただ、そこに到達するには解決すべき課題があって。年長者側の「自分の方が知らないといけない」という思い込み、さらには年下に教わることへの抵抗感、こういった「メンタルブロック」(※)を取り除かないと、本当の意味での育て合いは難しいのではないでしょうか?
※メンタルブロック:人が何かの行動を起こそうと思った際に、自分には無理なのではないか、人から批判されるのではないか、などと思う否定的な思考のこと。

「弱さとの折り合い」ミドル世代の成熟度を測るバロメーター
世代間の育て合いには意識変革が不可欠だと指摘する佐々木さん。これを受けて為末さんは、年長者が抱える不安について、踏み込んだ考察を展開します。
為末さん
メンタルブロックの裏側には、自分の存在意義への恐れがあるように感じます。気軽に話したり、相手の意見を受け入れたりすることで、自分自身が尊敬されなくなってしまうんじゃないか、そういう恐れもあるのではないでしょうか。
佐々木さん
たしかに。自分の弱さや恥とどのように向き合うのかを研究しているブレネー・ブラウンさんが提唱する「弱さの力(Power of Vulnerability)」が参考になりそうです。「尊敬されなくなるんじゃないか」「権威が失われるんじゃないか」という不安は、恥の感情と結びついている。これからの時代、組織の中でパワーをもつ人が、こういった感情とどう折り合いをつけていけるのか。ミドル世代の成熟度を測るバロメーターになっていくのではないでしょうか。
組織における「育て合い」の実践例
組織ではどのような取り組みが始まっているのでしょうか。お二人の経験もまじえ、具体的な事例を紹介します。
佐々木さん
Googleには「Googler-to-Googler(g2g)」(※)と呼ばれる制度があります。社員同士で学び合う仕組みですね。私たちの会社でもそれを参考に「T2T」という制度を導入しています。立場に関係なく「このトピックなら自分が先生になれます」「このトピックは知らないので学びたいです」という形で参加する。そこで双方向の学び合いが起きています。
※Googler-to-Googler(g2g):Google社内で展開される従業員主導のピアトレーニングプログラム。Google社員(Googlers)が自ら得意とするスキルや知識を共有することで、同僚の成長やキャリア開発をサポートしている。
為末さん
素晴らしいですね。一方で、普段の業務のなかで、世代や立場を超えて対話をするには難しい面もありますよね。どのような工夫をされていますか?
佐々木さん
グッドクエスチョンですね!よくやるのが、議論の前に宿題を出すことです。たとえば、会社の将来についてディスカッションする際は、事前に各自の思いを吐き出してもらう。それを議論の場で明らかにして、「みんな考え方が違いますね」とそれぞれの主張を可視化してから対話を始めます。いきなり平場で議論すると、どうしても偉い人の意見に合わせてしまいますよね。
中間管理職・管理職の方は、自分の発言とか振る舞い、存在自体がその場にバイアスを与えていることを自覚した方がいいです。それをどういう風に外せるのか、そういう力学が働かない仕組みが大事ですね。
為末さん
一人ひとりの本音を引き出すのは簡単ではないので、こういった工夫が必要ですね。

何を軸に育てる?世代間の価値観の違いに向き合う
お二人の議論は、育成において知識やスキルの共有を超えて浮かび上がる課題、「世代間の価値観の違い」について展開します。
為末さん
私たちの世代は「成長するには必死になって得た経験が必要だ」と思っていたりしますが、今の若い世代は、仕事は6〜7割くらいでと考えていたりしますよね。「いつかわかるから、今はこれをやるべき」という私たちの経験則は、もしかしたら通用しないかもしれない。「働く」における価値観も多様化し、確証ももてないなかで、何を軸に育てていけばいいのか。 これはミドル世代の大きな悩みではないでしょうか。
佐々木さん
本当にそうですね。最近の若い人たちと話をしていると、「仕事は手段であって目的じゃない」という声をよく聞きます。人生の方が目的で、友達との関係を深めたり、親の介護が必要なときはそちらにリソースを割いたり。ベースとなるOS、つまり仕事への向き合い方が、私たちの世代とは違うんです。
私たちは「成果を出す人間になってほしい」「成功してほしい」というピュアな思いでアドバイスをするのですが、そこに価値観のズレを感じることが増えてきました。
そこで私が最近試みているのは、年の離れた友人を作ること。「リバースメンタリング」という考え方があって、年下から学ぼうというものです。キャリアの関係性を超えて友人になり、フラットにコミュニケーションを取ることで、自然と価値観の違いが理解できるようになっていく。
為末さん
数十歳離れた人と接点があって、濃密なインタラクションができるのは本当に貴重ですよね。育て合うという話の前に、こういった日常的なコミュニケーションで、自身の価値観をアップデートしていくことが大切だと感じています。

4世代が共存する組織に求められる「育て合い」とは
世代間の価値観の違いを乗り越え、どのような関係性を築いていけばよいのか。対談の終盤で、未来への示唆を展開します。
佐々木さん
これからは、定年が70歳、75歳になっていきますよね。22歳で新入社員になった人と50歳以上の年齢差が生まれる可能性もある。そうなると、4世代が1つの会社に同居するような感じですよね。
為末さん
もしうまくやれたら、世界的にみてもおもしろい取り組みになりますよね。こういった多世代共存の組織は、日本企業ならではの挑戦になるかもしれません。一方向的ではなく双方向的な関係性を意識していく必要がありますね。そのためには、まず私たち自身が柔軟に変化していく姿勢をもつことが大切なのかもしれません。
佐々木さん
世代間で対立を煽られがちですが、若い人が上の人を「老害」として敵視しすぎてもいけないし、上の人も頑なになりすぎてはいけない。これは私自身も意識していることです。
この対談を通じて見えてきたのは、育て合いの具体的なヒントです。従来の「教える側・教わる側」という一方向の関係を超えて、互いの強みを活かしながら成長していく。そして何より、立場や世代を超えてつながり合える関係性を築いていく。そうした取り組みの積み重ねが必要になるのではないでしょうか。

「人と人が『育て合う』ために必要なことは?」全編の再生はこちらから
音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「育て合い」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。
ポッドキャスト番組「WEDNESDAY HOLIDAY」 について
フリーアナウンサーの堀井 美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語るトークプログラム。毎週水曜
日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。
撮影:鈴木渉
執筆:佐々木四史