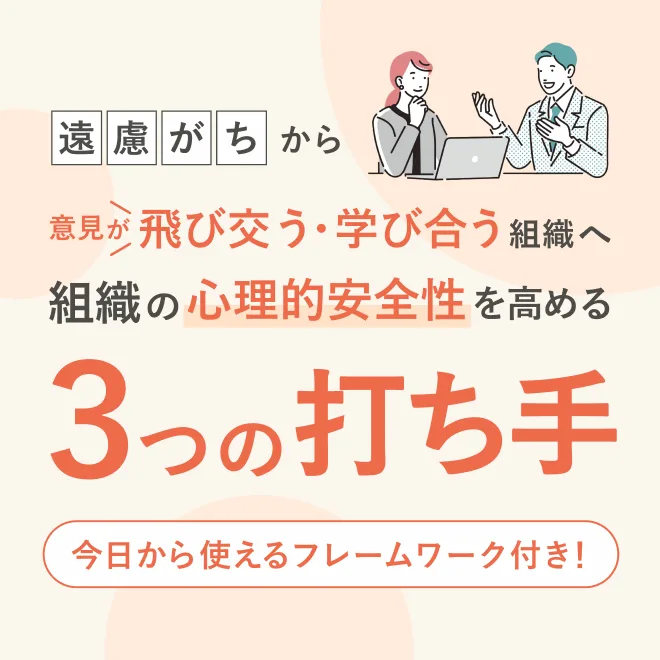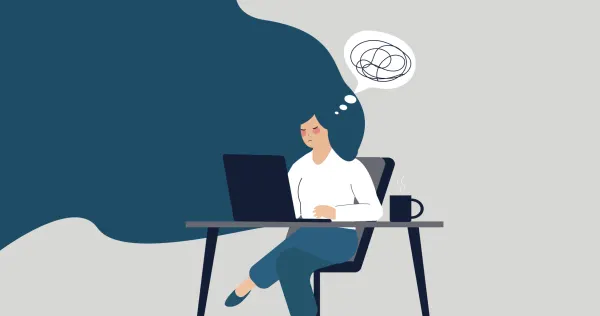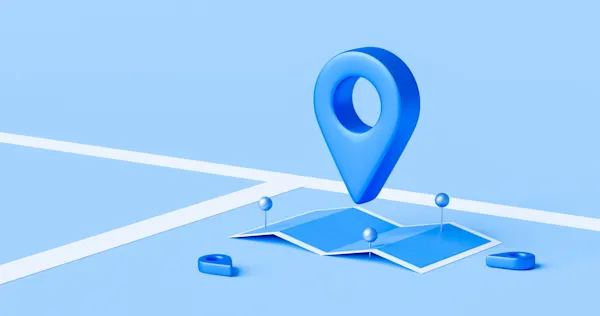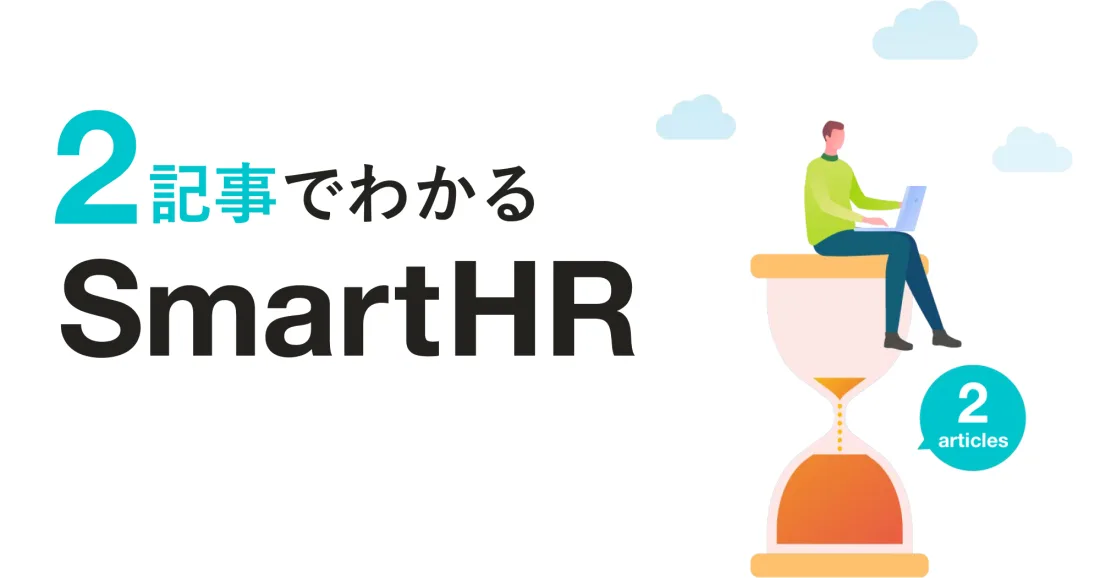コモンズとしてのオフィス。空間の再定義がもたらすもの
- 公開日

コロナ禍を経て、オフィス回帰の流れが生まれています。ただ、リモートワークの継続を求める声も一定数あり、「オフィスか、家か」という二元論がSNSで展開されることも少なくありません。
こうした議論に意味があるのかは別として、オフィスという空間について考えるタイミングに差し掛かっているのは間違いない事実。従来のように社員全員が集うことが前提にならなくなれば、「打ち合わせで使う」「作業に使う」など用途を明確にしたうえでの利用が増えるでしょう。一方で、目的がなくても集える空間にするための工夫も必要です。
これから先、オフィスにはどのような要素が必要なのでしょうか。コミュニティデザインやコモンズに詳しい都市デザイナーの内田友紀さんに聞きます。

内閣府地域活性化伝道師。グッドデザイン賞審査委員
早稲田大学建築学科卒業。メディア企業を経て、イタリア・フェラーラ大学院にてSustainable City Designを修め、イタリア・ブラジル・チリなどで地域計画プロジェクトに参画。2013年、think & do tank リ・パブリックの創業に加わり、2020年より都市・地域のトランスフォーメーションのためのリサーチ・デザインラボ YETを並行。ビジョン構築、組織開発、コミュニティデザイン等を通じて、市民・企業・行政府・大学らとともに持続可能な地域社会に向けたエコシステムの構築に携わる。書籍「あしたのしごと アジアの実践者と考える、オルタナティブな未来」(コクヨ株式会社)を共同企画・編集。
定義次第でオフィスの在り方は大きく変わる
国内外の事例を通じて、内田さんは都市デザインに関するさまざまな知見を得てこられたと思うのですが、それをオフィス設計に生かすとしたらどのようなことを考えますか?
内田
少し長いスパンで時代を眺めてみると、私たちが直面している都市社会の不具合は、さまざまな機能の集約や分化が行われてきた余波によるものだと思うんです。大量生産・効率化を目指して都市がつくられ、仕事と暮らしが分化したことで、これまでは「どうしたら労働生産性を高められるか」という点が重視されてきましたよね。その結果として働く以外のものごとが見えなくなってしまった。
でも今は、社会全体をよりよくする企業の存在が求められているし、世代が若くなるほど価値観も転換しています。それなのに20世紀の都市構造が維持され、暮らしと働く場所が離れていては、新たな仕事や企業価値のヒントは見つけづらいのではないでしょうか。
SmartHRでも、コーポレートミッションとして「well-working」というキャッチフレーズを掲げていますよね。それもまさに、これからの働き方のスタンダードをつくろうというアクションの一環だと想像します。オフィスに関しても同じで、考え方の転換が必要だと思うんです。
それは働く意味を問い直すようなことでもあるのでしょうか。
内田
もちろん働く場として機能的に満たすべき要件はありますが、その基準を満たしたうえで、会社と社会の接点を模索し、どういう場所がミッションの実現のためにつくり得るのかを考えることが必要です。
たとえばオフィスに子どもを連れてきて仕事をするのは、業務効率の観点だけで考えると理解を得るのは難しいと思いますし、本人も大変でしょう。でも、これまで仕事と切り分けてきた暮らしにかかわる問題を持ち込める場として定義しなおせば、考え方が変わってきますよね。

確かに。そうやってオフィスの在り方が変わってくると、「オフィスと家のどちらのほうが業務効率が良いか」といったよくある二元論自体が意味をなさないような気がします。また、場合によっては仕事の評価指標も変えていく必要がありそうです。
内田
そうだと思います。もっと言えば、会社の存在意義にも通じる話でもあって。
私がプロセスデザインで関わらせていただいた化粧品会社SHIRO(シロ)は、北海道砂川市に新工場を2023年にオープンしたのですが、施設内にキッズスペース、ショップ、カフェなどを併設し、さらに大きな広場や畑もつくることで、街にひらかれたコモンズ(共有地)のような場所になることを目指しています。
また、工場とオープンスペースを壁ではなくガラスで仕切ることで、お客様から製造工程をすべて見えるようにしました。そうすると、自分がつくる製品を愛する人の姿がいつも目に入り、働く人たちのものづくりに向かう意識が変わっていくんですね。それだけでなく、地方で暮らす子どもたちにとっては、地元からグローバルに愛される商品が生まれるプロセスを見るのは大きな誇りにもなります。将来的には、地元の人たちが自分たちでこのコモンズのエリアを運営していく像を描いて、プロジェクトが進んでいるんです。
クローズドな環境になりがちなオフィスを社会にひらくのはユニークですね。
内田
ただ、当初は「みんなの居場所になる、地域にひらく工場」がどのような姿か関係者も手探りでした。地元の方から「県外からたくさん人が押し寄せて自分たちは行けなくなってしまうのではないか」といった声があがったこともあります。
また、工場に備える機能へのリクエストもいろんな人から出たんですね。どの希望を叶え、どの希望を対象外にするのか、プロジェクト主体者らが地元や域内外の方と何度も何度も対話を重ね、紆余曲折しながらオープンにたどり着きました。

複数人がオーナーシップを持つことで、“私のこと”が“私たちのこと”に
どの希望を叶えて、どの希望を対象外にするかの取捨選択はどのようにしたんですか?
内田
プロジェクトビジョンの尊重はもちろんですが、さらに重視したのはオーナーシップ(当事者意識)です。
ある要望があったとして、それを本当に必要とする人がいるのか、いるとしたらどんな人なのか、実際に要望を出した人はどう関わりたいと思っているのか。それらを議論していくと、他の機能で代替できたり、物理空間ではなくプログラムで叶えることができたり、または当事者もやりたい人も見当たらないこともあるんです。そうして、やることやらないことを明確にしてきました。
組織にも地域にも言えるのは、メンバー全員がやる気に満ちた状態で前に進むことはないということです。オーナーシップが強い人もいれば、そうでない人もいる。ただ、何かしらのアクションを起こそうとする人の多くは、自身の願望と社会に対する理想や課題が結びついたときに大きく動きます。そして、同じ願望を持つ人が複数出てくると、“私のこと”が“私たちのこと”になって場が育っていく兆しが見えてくるんですね。
内田さんはその実践を複数の場所で行ってきたと思いますが、人々への動機づけはどのようにしているのでしょうか。
内田
さまざまなアプローチがあるのですが、社会人をこなしてきた人は自然と殻をかぶっていることが多いので、本音を引き出せるような心理的安全性の高い場所をつくることが大切です。また、相手が上辺だけで話していると感じたら「それって本当?」と指摘して、隠された意図を掘り起こすこともあります。
そのうえで動機づけを促すためには、本人が課題やテーマに対するリアリティを持つことが不可欠です。情報やデータを調べれば、社会で何が起きているかを知ることはできます。でも、それだけでは自分事化するのは難しいんですね。だから、フィールドリサーチを通じて、世の中の現場では実際に何が起きているのかを体感したり、課題を抱える当事者へのインタビューやエスノグラフィックリサーチを実施したりしながら、自然と問題に向き合える状況をつくっていきます。

サービスの受け手から担い手へのチェンジを
会社の規模が大きくなっていくほど、多くの人を巻き込んで物事を進めていくのが難しくなっていくと思いますが、オフィスのように社員全員に関わりのあることはどのように進めていけばいいのでしょうか。
内田
関心を持った人がいつでも情報にアクセスできるような状態をつくることが望ましいですよね。具体例の規模が大きくなりますが、台湾政府はデジタル担当大臣のオードリー・タンさんのチームが主導するかたちでDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進したことで話題を集めました。
彼女たちは、誰もが新しいアイデアを提案できるデジタルプラットフォームを構築し、オフラインも含めてさまざまな形で政治へのアクセスを確保することで、相互信頼を構築するための解放性と透明性を促進しました。政府という大きな規模でそれを実現できているのだから、企業もそのくらいやってもいいのではないでしょうか。

そうなると、ファシリテートしていく人の重要性が高まりそうですね。
内田
おっしゃる通りです。そもそもオフィスをどうしていくかを考える会話は自然には生まれません。誰かが能動的に動いてプロジェクト化でもしないかぎり、私たちはいつまでもサービスの受け手としてオフィスを利用するにとどまり、「個別ブースがもっとほしい」「こういう備品があると便利だ」といった実利にひもづく要望ばかりに終始してしまう。これは冒頭でも話したように役割を分化してきた私たちに染みついた振る舞いだと思います。
サービスを提供する・受益するという関係の力学を変え、担い手を増やしていくためには、社員一人ひとりが互いにケアする存在であり、一緒に働く場を育んでいく仲間なんだと意識を切り替えていく必要があると思います。
そうした意識はどうすれば持てるようになるのでしょうか。
内田
会社にはいろんな属性の社員がいますが、一人ひとりに仕事をする自分、家にいるときの自分、外で趣味を楽しむ自分……とさまざまな側面があり、総体として日々の暮らしがあります。そのなかで、自分にとって働くとは何か、働くにはどういう場が理想なのかを個人が考えていくことが大切だと思います。
それらを持ち寄って、会社や社会との関係性についてメンバー同士で対話を重ねていけば、これまでのオフィスの在り方とはまったく違う議論になるのではないでしょうか。

文:肥髙茉実
撮影:小池大介
取材:村上広大
働くの実験室(仮)by SmartHRについて
本連載を企画している「働くの実験室(仮)」は、これからの人びとの働き方や企業のあり方に焦点をあてた複数の取り組みを束ね、継続的に発信するSmartHRの長期プロジェクトです。
下記ウェブサイトから最新の活動が届くニュースレターにも登録していただけます。