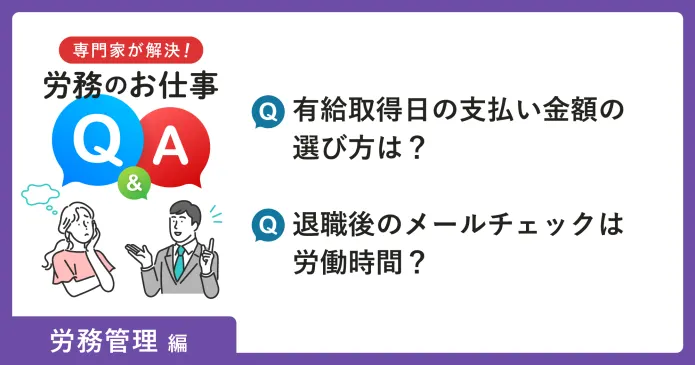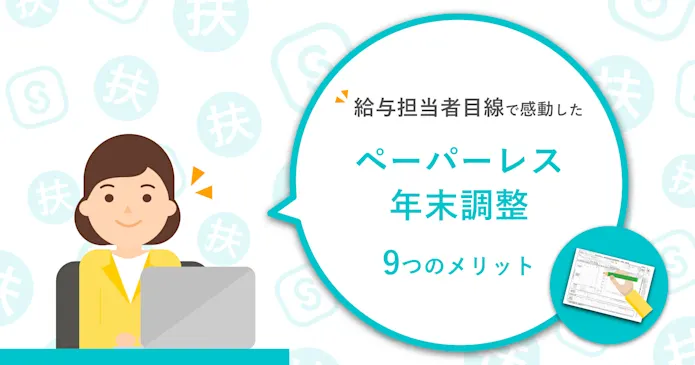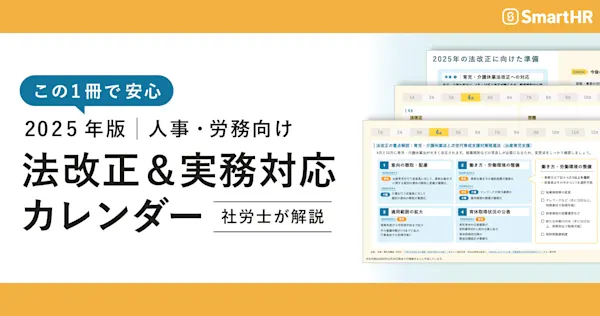通勤手当・交通費は含まれる? 「標準報酬月額」の計算“3つのポイント”
- 公開日

社員が入社したら、短時間勤務など一定の例外に該当する場合を除き、社会保険に加入させなければなりません。
SmartHRを利用すれば、社員から入力してもらった住所氏名や基礎年金番号をもとに、ほぼ自動で社会保険の加入申請書類が出来上がります。しかしながら、現時点においては手入力が必要で、少なからずの会社様が頭を悩ませている入力項目があります。
その項目は、「報酬月額」です。
「報酬月額」の欄に入力された金額をもとに、その社員の方の健康保険と厚生年金の保険料が決まるのですが、基本給だけで「まあいいや!」と申請をしてしまうと、後日、年金事務所の調査があった際などに「誤った金額で資格取得がされている」と問題になり、遡っての訂正や保険料の精算を求められてしまうことがあります。
そうすると、社員の方からも遡って社会保険料の不足分を徴収しなければならず、社員の方に負担や迷惑をかけてしまうことになってしまいかねません。
そこで、この記事では社会保険の資格を取得する際にミスが起きないよう、報酬月額を計算するにあたり、特に間違いやすい点や迷いやすい点を、3項目ピックアップして説明したいと思います。

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
(1)標準報酬月額に「通勤手当」を含める
実務上、よく質問を受けるのは「通勤手当を報酬月額に含めるべきか」ということです。
所得税の計算では通勤手当は一定額まで非課税なので、社会保険の報酬月額にも含めなくて良いと勘違いされることが多いようですが、この点、「含める」が正解です。
また、「通勤手当として一定額を払うのではなく、実費で経費精算という形なら報酬月額に含めなくても良いのか」という質問を受けることもありますが、自宅から職場までの往復のために発生する交通費は、定期代の支給であれ、実費精算であれ、定期券の現物支給であれ、報酬月額に含まれるべき金額となります。
なお、入社時に6か月分の定期代をまとめて支払うような場合は、6分の1の金額を報酬月額に加える形になります。
(2)標準報酬月額に「割増賃金」を含める
割増賃金の見込み額を報酬月額に加えるのを忘れてしまうことも、実務上少なからず発生しているミスです。
残業が何時間、休日出勤が何日くらい発生しそうなので、割増賃金は〇〇円くらいであろう、というような予測に基づいて割増賃金の額を決め、報酬月額に加算することになります。
この点、あくまでも「見込み」ですから、実績がズレる分には問題は無いのですが、割増賃金を全く報酬月額に含めずに社会保険の資格取得をしてしまったのに、恒常的に残業が発生しているような場合は、年金事務所の調査において指摘を受けやすいチェックポイントになります。
なお、基本給に「みなし残業代」が含まれていて、残業が通常は「みなし残業代」の範囲で収まる見込みの場合は、別途割増賃金を上乗せしなくても大丈夫です。
(3)「パートタイマー」の報酬月額
パートタイマーの方でも、正社員の所定労働時間の4分の3以上、かつ、所定労働日数の4分の3以上を勤務する方については、社会保険の加入義務があります。
パートタイマーの方の場合、基本給が時間給で支払われていることが多いので、どのように報酬月額を計算すれば良いか質問を受けることがあります。
この点、具体例に説明しますと、時給1,000円、1日7時間勤務、月平均18日勤務の方ということであれば、1,000円×7時間×18日=126,000円が基本給相当額になります。
ここに、通勤手当や割増賃金が発生する場合は、月給制の方と同様に加算して、報酬月額を決定するという流れになります。
業務効率化でミスを少なく
SmartHRなどのサービスによって人事・労務手続きはどんどん便利になっていきますが、頭を悩ます計算や手続きはまだまだあります。
些細なミスが大きな問題となることもありますので、ご注意してくださいね。
ミスを削減するためには、業務の効率化が鍵になります。人事・労務領域で効率化できる業務について、下記資料をご参考にしてください。

人事・労務領域 効率化すべき業務チェックリスト

お役立ち資料
2025年にかけての人事・労務政策&法令対応完全ガイド
【こんなことが分かります】
2025年には、「人材戦略の推進」と「雇用基盤の整備」の二軸で大規模な改正が実施される予定です。
出産育児支援や高齢者関連法、リスキリング支援、雇用保険法、外国人雇用、障害者雇用などにおける具体的な変更点と対応方法を解説しています。
「やることリストつき」で、人事・労務担当者が手元に置いておきたい一冊です。
- 2025年大改正が起きる背景
- 政策・法令改正の具体的な内容
- 「女性活躍・リスキリング・人権」の最新動向
- 期日つき!人事・労務担当者のやることリスト

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
- 読者の76%が「メルマガの内容を自身やチームの実務に取り入れている」と回答
- 限定コンテンツの閲覧や、有識者・同業者の方との交流イベントへの参加も
あなたの「気づき」につながる情報を、厳選してお届けします!