これだけは押さえたい。約40年ぶりの「労働基準法」改正議論のポイント
- 公開日
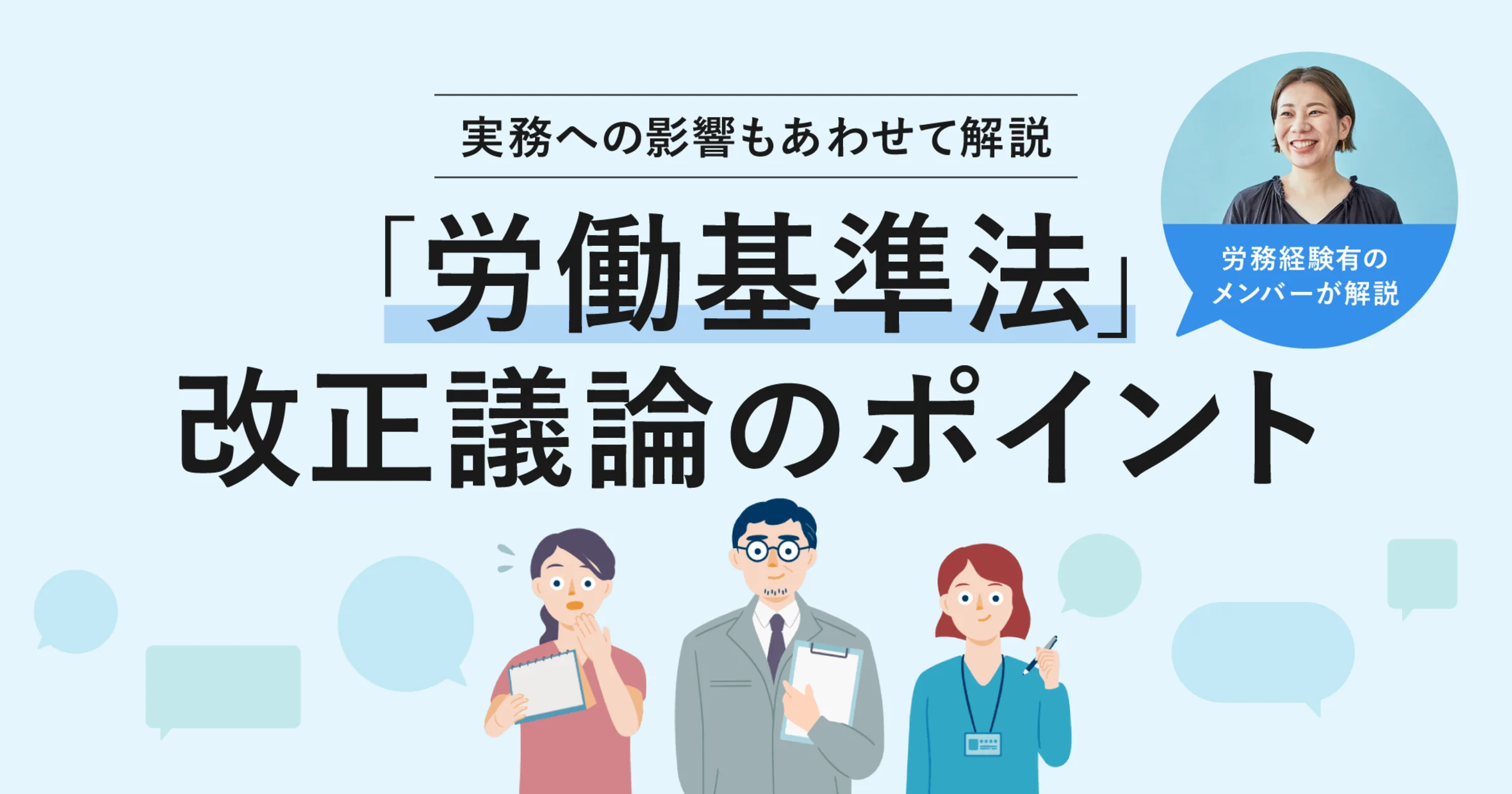
目次
近年、IT技術のさらなる進展や、テレワークや副業・兼業の普及などにより働き方は変化し続けています。現行の労働基準法で想定しない働き方が増えてきたため、労働基準法の適用範囲や規制のあり方を見直す必要性が高まっています。
今回は、きたる労働基準法の改正に向け、専門の研究会がまとめた報告書のポイントや実務に及ぼしうる影響について、SmartHRで人事・労務業務に関する最新情報を社内外へ発信している人事・労務職経験者の穴原が解説します。
※本記事で紹介している内容は弊社独自の解釈で、実際の法改正に必ず反映されるとは限りません。あらかじめご了承ください。

株式会社SmartHR ブランディング統括本部 コンテンツQA部。SmartHRのユーザーとして数社の労務担当を経験後、SmartHRの労務担当を経て現職。約10年の人事・労務経験を活かしてコンテンツの企画・監修などを行う。
労働基準関係法制研究会報告書から、今後の働き方を読み解く
労働基準法は1947年の制定以来、労働者保護の基本法として機能してきました。
過去には、1987年に「週40時間制」や「裁量労働制」の導入を含む大改正が行われましたが、その際も約10年間にわたってさまざまな検討が重ねられました。そして今回、2024年に「労働基準関係法制研究会」が設置され、包括的な議論が行われています。
労働基準関係法制研究会は、2023年の「新しい時代の働き方に関する研究会」の提言をもとに、労働基準法の長期的な方向性や、働き方改革関連法にもとづく具体的な見直しを進めることを目的としています。
同研究会で議論を重ねた結果、「労働基準関係法制研究会報告書」(厚生労働省、2025年1月8日発表)がまとめられました。まだ法改正に含まれるかどうかわからないものの、労働にまつわる今後の新しい「働き方」を読み解くヒントになるはずです。
 穴原
穴原
「労働基準関係法制研究会報告書」は50ページ以上に及ぶため、本記事では私、穴原が、これだけは押さえておきたいポイントまとめと、人事・労務担当者の業務に与える影響をご説明いたします!
ポイント(1)労働者の定義の見直し
労働基準法第9条で、「労働者」は以下のように定義されています。
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
いま、この定義の見直しに向けた議論が進められています。
【ポイントまとめ】
- 現在の「労働者」の定義が、プラットフォームワーカー(※1)の登場・拡大にともない、実態に合わなくなっている
- 「ABCテスト(※2)」や、プラットフォーム労働における労働条件の改善に関するEU指令のように、海外では新たな判断基準が議論されている
- 日本でも、プラットフォームワーカーの労働者性の判断基準を見直す動きがある
※1 プラットフォーマーを介して仕事を受ける就業者は、クラウドワーカー又はギグ・ワーカーなどとも呼ばれるが、本報告書では「プラットフォームワーカー」を統一的に用いている。
※2 アメリカの一部の州で労働者の雇用形態を判断するために用いられる基準
【想定される人事・労務担当者への影響】
- プラットフォームワーカーの管理強化
- 自社で業務委託契約を結んでいる人が、労働基準法上の「労働者」と見なされる可能性がある
- 業務委託と雇用契約の区別を明確化し、法的リスクを回避する必要がある
- 契約形態の見直し
- 労働者性の判断基準の見直しが行われた場合、契約形態の見直しが必要になる
参考資料:厚生労働省「労働基準法上の「労働者」について」
 穴原
穴原
労働者の定義の見直しは、とくにプラットフォーム経由で仕事を受ける人の管理強化だけでなく、契約形態の見直しなどにも発展する可能性があります。
海外の動向も一般知識として押さえつつ、今後の議論に注目しましょう!

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
ポイント(2)事業単位の見直し
近年、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大、IT技術の発展、働き方改革の推進などをきっかけとして、リモートワークを導入する企業が増加しました。そんななか、「事業単位の見直し」に関する議論が進められています。
【ポイントまとめ】
- 労働基準法は「事業場単位」で適用されるが、リモートワークの普及などにより適用範囲を見直す必要がある
- 企業単位や複数事業場単位での適用という選択肢も考えられる
【想定される人事・労務担当者への影響】
- リモートワークの労務管理強化
- 事業場単位ではなく、企業全体で統一された労働時間管理や就業規則が求められる可能性がある
- 「どの事業場に所属するか」に依存せず、一律の管理体制を構築する必要があるかもしれない
- 監督や指導体制の変更対応
- 労働基準監督署の監査基準が変わる可能性があり、全社的な対応方針を準備する必要がある
- リモートワーク中の従業員の労働状況を適正に管理するためのITツール活用が必須
参考資料:厚生労働省「労働基準法上の「事業」について」
 穴原
穴原
リモートワークなどをきっかけに、同じ場所で画一的な働き方をしない労働者が多くなっていることを受け、これからの企業の雇用・労務管理には「多様性を活かすこと」や「主体的なキャリア形成」などがさらに求められそうですね!
ポイント(3)労使コミュニケーションの強化
現在、増加し続ける雇用者数に対して、労働組合員数はほぼ横ばい、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は低下しています(図1参照)。これに対して、「労使コミュニケーション」の強化をめざした議論が進められています。

図1 雇用者数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合)
(出典:厚生労働省「令和6年労働組合基礎調査の概況」P3)
【ポイントまとめ】
- 労働組合の組織率が低下(2023年で16.3%)し、過半数労働組合がない事業場も多く、過半数代表者の役割・能力に課題がある
- 労使協定の締結プロセスをより透明化し、従業員の意見を反映しやすくする方針が示されている
【想定される人事・労務担当者への影響】
- 過半数代表の選出基準見直し
- 労使協定の締結プロセスが厳格化される可能性があり、適正な代表者選出方法を確立する必要がある
- 労働組合の組織化支援や、労使コミュニケーションの活性化施策を検討する必要がある
- 透明性のある協議体制の整備
- 過半数代表者の意見集約の方法を見直し、従業員の意見を反映しやすい仕組みをつくる必要がある
参考資料:厚生労働省「労使コミュニケーションについて」
 穴原
穴原
ここでは、いかに労使のコミュニケーションを促進させるかについてさまざまな報告がされています。それぞれの項目について、現行法の解釈や対応の方向性を行政が示すことをめざしているので、今後の新たな情報や発表を待ちましょう!
ポイント(4)労働時間管理の厳格化
働き方改革や時代の変化にともない、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」である労働時間もまた、さまざまな見直しが進められています。まずは以下の内容を押さえておきましょう。
【ポイントまとめ】
- 労働時間管理のさまざまな見直しの検討
- 時間外労働や休日労働の上限規制の見直し
- 企業による労働時間の情報開示
- 法定労働時間週44時間の特例措置の見直し
- テレワークに適用できる柔軟な労働時間管理
- 労働からの解放に関する規制の検討
- 休憩時間の長さや取り方などの見直し
- 13日を超える連続勤務の禁止
- 法定休日の特定
- 勤務間インターバル制度
- つながらない権利の考え方
- 年次有給休暇の賃金支払方式の見直し
【想定される人事・労務担当者への影響】
- 長時間労働の防止策強化
- 36協定の見直しや、企業による労働時間の情報開示が求められる可能性がある
- 業務効率化を目的としたITツールの導入や、労働時間の可視化が必要
- 休憩・休日の新ルールへの対応
- 見直された「労働からの解放」に関する規制に準じた就業規則の見直しが必要
- つながらない権利の整備
- 社員が業務時間外にメールやチャット対応をしないよう、明確なルール策定が必要
- 「業務時間外の対応禁止」「連絡は緊急時のみに限定」など方針の検討が必要
参考資料:厚生労働省「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」
厚生労働省「労働時間制度等に関する実態調査結果について(速報値)」
 穴原
穴原
労働時間や休憩・休日に関する変更点は、従業員の皆さまがもっとも関心のあるトピックの1つかと思います。ほかの項目と同様、いかに周知・徹底を促すかなど、少しずつ考えていきたいですね。
ポイント(5)副業・兼業の労働時間と賃金管理
2018年1月、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、企業が副業を解禁するようになって以降、副業を行う人の割合が増えています(図2参照)。これに対して、「副業・兼業の労働管理と賃金管理」に関する議論が進められています。

図2 副業者の割合(男女および年齢別)
(出典:労働政策研究・研修機構 令和5年5月19日 プレスリリース P2より)
【ポイントまとめ】
- 副業、兼業者の労働時間管理や、割増賃金の取り扱いについて、現行ルールが複雑なため、見直しが議論されている
【想定される人事・労務担当者への影響】
- 副業・兼業の労働時間管理
- 引き続き副業・兼業者の健康確保体制を整える必要がある
参考資料:厚生労働省「副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)」
 穴原
穴原
最近は副業や兼業をしている方が増えてきました! 本業でもパフォーマンスを上げていただきながら、労働時間や健康保持などの観点で懸念がないような管理方法を模索していきたいですね。
労基法の改正議論の先取りで競争力を強化しよう
いかがでしたか?この「労働基準関係法制研究会報告書」は、人事・労務担当者にとって大きな影響を及ぼす可能性があります。現在、具体的な法改正が決定したわけではないものの、今後の働き方の変化に伴い、労働時間の管理や契約形態の見直し、労使コミュニケーションのあり方など、多くの点で新たな対応が求められそうです。
特に、テレワークや副業・兼業の増加、デジタル技術の進展による労務管理の変化など、現行の労働基準法が想定していなかった働き方が急速に広がっています。このような変化を踏まえ、労働者保護と多様な働き方の両立をめざす新たな制度設計が求められています。企業としても、従業員のキャリアの多様化やワークライフバランスの実現を支援しながら、適切な労務管理を行うことが重要になるでしょう。
本報告書に目を通すことで、今後の労働環境の変化や規制の方向性を事前に把握し、必要な対応を早めに検討することができます。企業の人事・労務担当者は、これらの議論を先取りし、自社の人事戦略への影響を見極める必要があります。今後の動向を注視しつつ、柔軟かつ実効的な対応を検討・実行して、自社の競争力を強化しましょう。
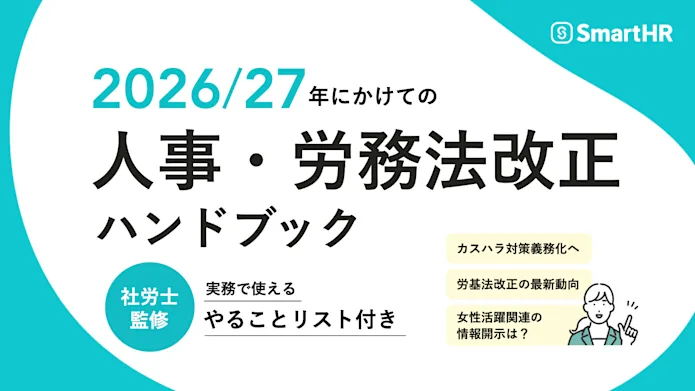
お役立ち資料
2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック
この資料でこんなことが分かります
- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正
- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正
- 人事・労務担当者 やることリスト

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
- 読者の76%が「メルマガの内容を自身やチームの実務に取り入れている」と回答
- 限定コンテンツの閲覧や、有識者・同業者の方との交流イベントへの参加も
あなたの「気づき」につながる情報を、厳選してお届けします!

























