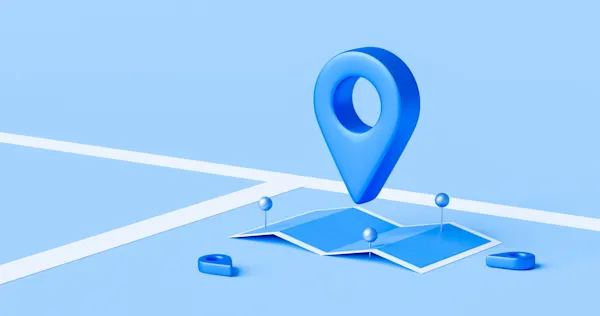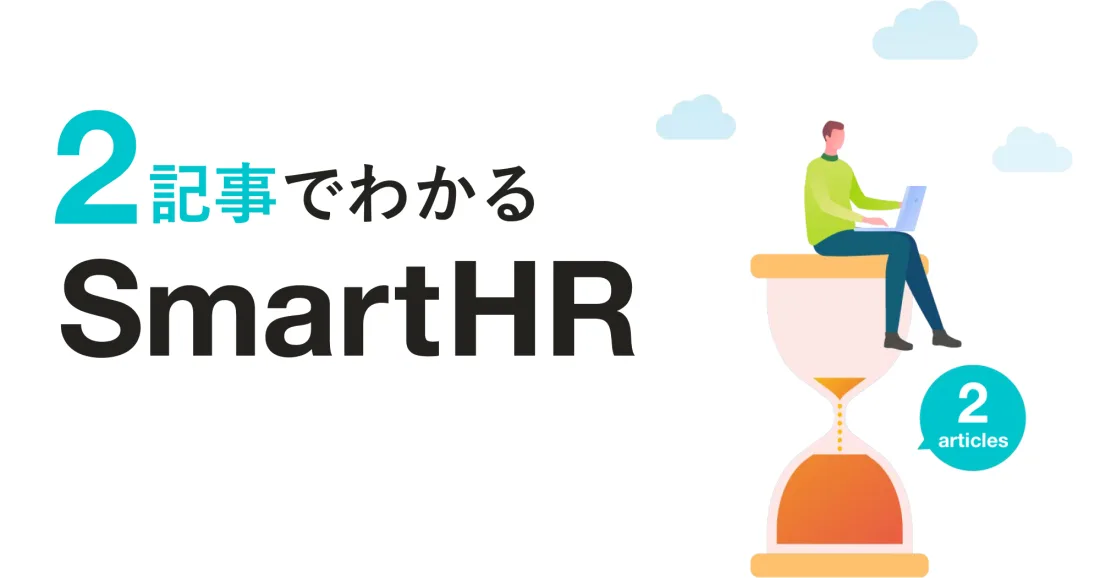労基法が定める「休憩時間」の基本ルール。「休憩時間に業務対応」はアウト?
- 公開日

目次
こんにちは、弁護士法人ALG&Associate大阪法律事務所の長田弘樹です。
「休憩時間」は、労働条件を構成する重要な内容のひとつであり、使用者が休憩時間の付与義務に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(労基法199条1号)。
労働基準法(以下「労基法」)は、「休憩時間」について、従業員へ付与すべき時間の長さのみならず、付与の仕方、また、その時間での過ごし方などを定めています。
コロナ禍を機にテレワークを導入した企業が増えるなど、多様な働き方が推進されていく今こそ、労使を問わず、休憩時間のあり方に関しても確認しておくべきでしょう。
労働基準法における「休憩時間」とは
休憩時間とは、「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭22.9.13 発基第17号)をいいます。これは、労働が一定時間継続することによって、労働者に蓄積される心身の疲労回復を目的とするもので、休憩時間の適正な確保は、作業能率の向上や災害防止につながるだけでなく、労働者の健康を守るためにも重要です。
労基法は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定めています(34条1項)。
休憩時間は、現場のマネージャーが管理しているケースもあります。適切に管理するためにも、このタイミングで管理職の方が業務に役立つ労務知識を共有してみてはいかがでしょうか。
中間管理職の方が知っておきたい労務知識は、以下の資料を参考にしてください。

社労士監修!中間管理職が知っておきたい労務知識
休憩の三原則
休憩については、付与すべき時間の長さだけでなく、位置・付与方法・利用方法についても労基法の制限があります。
(1)一斉付与の原則
原則として「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められています(労基法34条2項本文)。これは、休憩時間の効果を上げることと、労働時間や休憩時間を管理しやすくためです。一斉付与の対象は、事業場の全労働者とされており、ここには正社員のみでなく非正規社員も含まれます。
(2)途中付与の原則
休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」とされています(労基法34条1項)。労働時間の途中で与えさえすれば、いつでも休憩時間は設定できます。また、休憩時間を一括で与える必要もないので、小刻みな付与も可能です。
(3)自由利用の原則
労基法34条3項で、使用者は、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められています。これは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障する規定であり、たとえば、労働者が休憩時間中に外出することも原則自由になります。
休憩時間に関わるトラブル
休憩時間は、労基法上、労働時間と区別されています。通説・行政解釈では、労働時間を「労働者が使用者の指揮命令のもとにある時間」と定義しています。したがって、休憩時間において、労働者は使用者の指揮命令から離れていることが前提となります。
就業時間のなかで休憩時間とされている時間であっても、実質的に見て手待時間と認められれば労働時間となります。以下のケースで確認しておきましょう。
(1)休憩時間に業務対応
たとえば、会社の休憩室などで自由に休憩させつつ、まれにある来客や電話の対応をさせているような場合には、労働者は使用者の指揮命令下にあります。つまり、労働から完全に解放されているとはいえないため、手待時間となります。そのため、使用者としては、別途休憩を与える必要があります。
(2)ランチミーティングなどの会社のイベント
ランチミーティングなどの会社のイベントについては、あくまで懇親を深めることが主目的であり、業務とはいえないことがほとんどです。もっとも、参加が業務命令によって強制される場合や、任意参加としつつも参加しなければ、業務に支障を来すような場合には、労働時間に該当するおそれがあります。
休憩時間における会社のイベントは、参加を促す度合いや業務関連性などを慎重に考慮する必要があり、場合によっては、別途休憩時間を付与しなければならない可能性があるのでご注意ください。
(3)タバコ休憩
タバコ休憩は、休憩時間といえるケースがほとんどですが、その時間においても指示を受けて業務対応することがある場合には、手待時間となるおそれがあります。
休憩時間の与え方や判断の仕方について
社会情勢の変化とともに働き方も多様化していくなかで、労働時間にかかる法規制も改正されています。とくに、近年では、働き方改革関連法などの労働法改正により、残業時間の上限規制や労働時間の客観的な把握義務など、大きな変化がありました。
休憩時間と表裏の関係にある労働時間は、賃金と対応するがゆえに労使間の一大争点といえます。未払残業代訴訟などの紛争に巻き込まれないために、企業としては、自社の就業規則や労働環境などについて、最新の労働法改正に対応しているか検討することが予防法務につながります。

お役立ち資料
2025年にかけての人事・労務政策&法令対応完全ガイド〜期日がわかるやることリストつき〜
この資料でこんなことが分かります
- 2025年大改正が起きる背景
- 政策・法令改正の具体的な内容
- 「女性活躍・リスキリング・人権」の最新動向
- 期日つき!人事・労務担当者のやることリスト