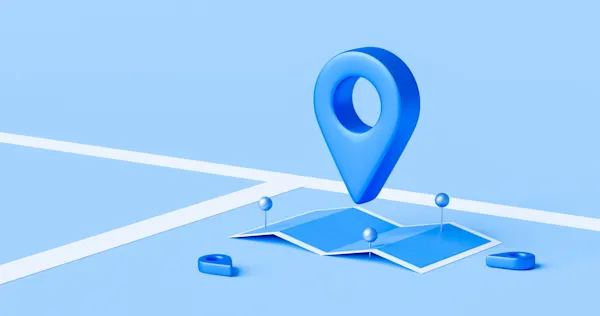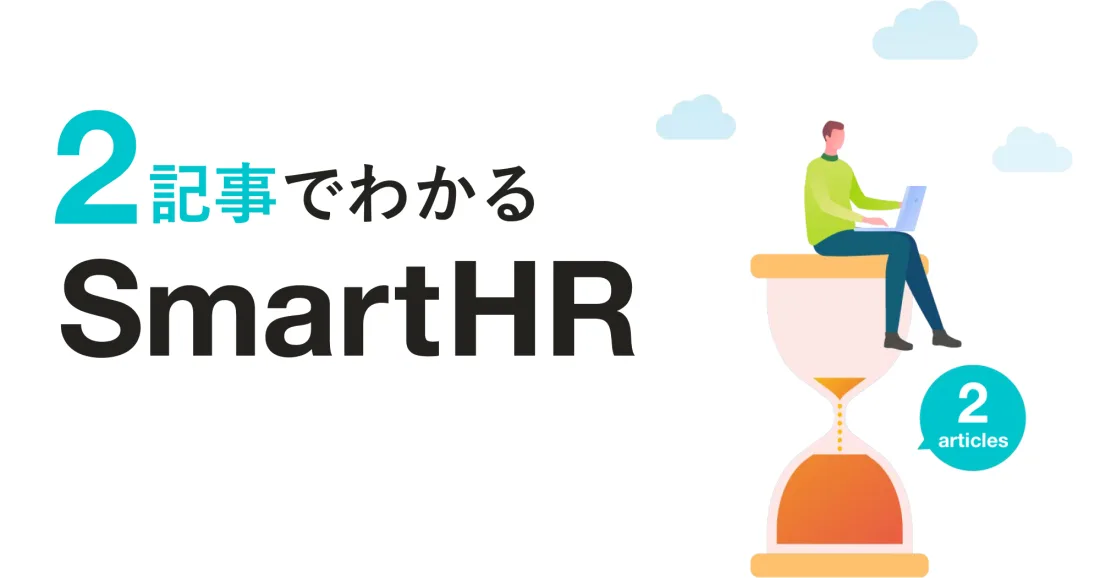正確な人事評価を目指した制度構築(2)〜評価体制と評価行動〜人事評価の現在地 #03
- 公開日
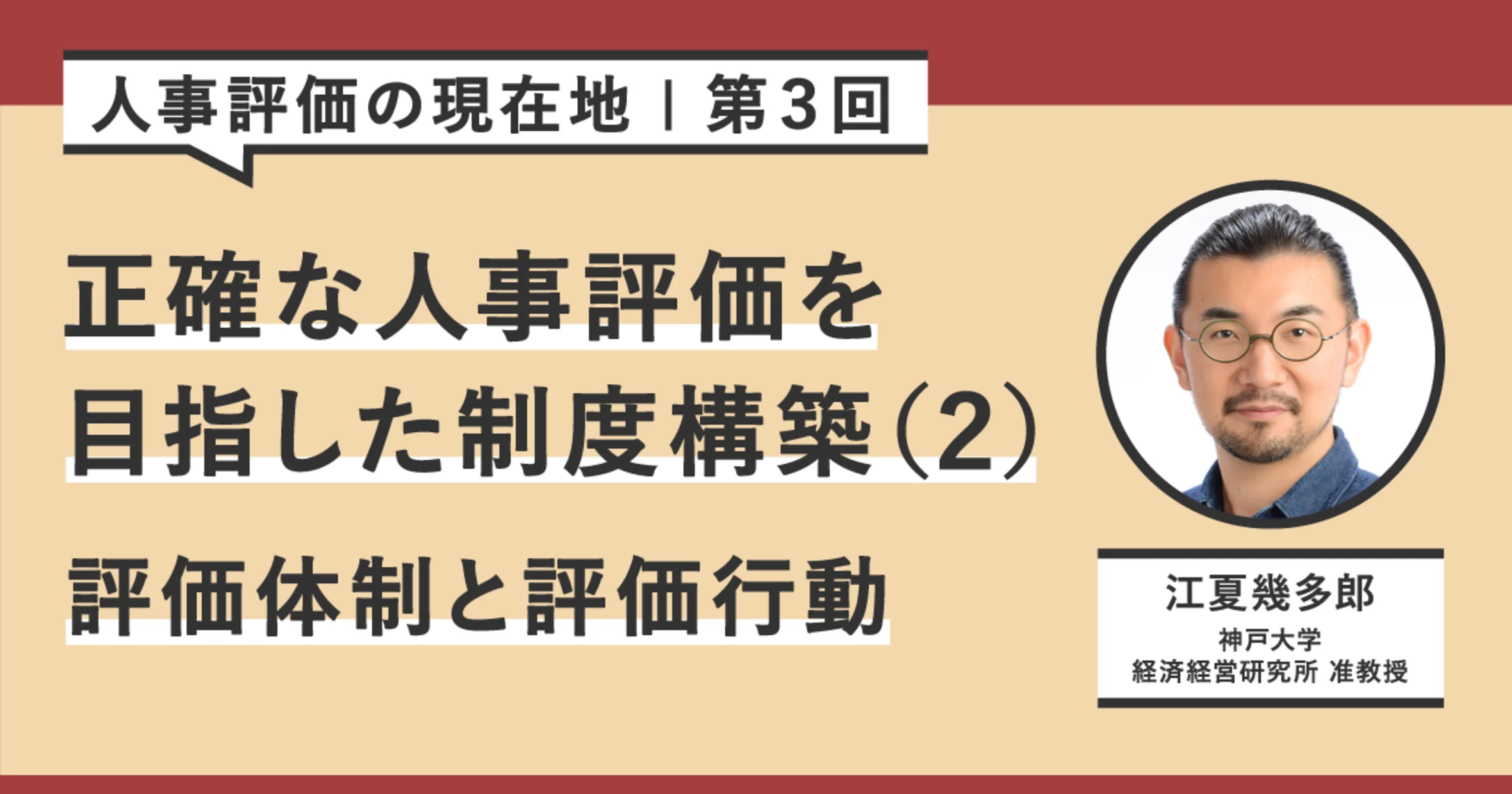
目次
「人事評価制度がうまく運用できていない」「現場の評価への不満が収まらない」。人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。この連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者、被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。
第3回目は「正確な人事評価のための評価者の関与や役割」について紹介します。
はじめに
前回は、正確な人事評価のための「評価項目と評価尺度における工夫」について紹介した。
人事評価の正確性を高める工夫により、企業が従業員の何をどう評価するのかについての指針や体系が確立される。しかし、指針や体系自体は、従業員の正確な評価を可能にするものではない。正確な人事評価の実施は、指針や体系を理解し、具現化する評価者の活動次第になる。評価者による人事評価の工夫は、評価者たちの連携の構図、そして個々人での行動に主に注目してなされる。
正確な人事評価のために、客観性が重視されることは多い。しかし、従業員の貢献についての評価尺度を用いた測定は、あくまで評価者の解釈・判断にもとづいてなされるものである。評価者の評価行動は、しばしば企業にとって望ましくないバイアスにもとづいてなされるため、評価行動を適正化しつつ、人事評価に関わる人々が連携しなければならない。
これらにより、さまざまな主観的な解釈・判断が折り重なり、人事評価における擬似的な客観性の確立が目指される。
人事評価の「正解」はどこにあるのか? 評価体制をめぐって
ある評価項目に関連した評価尺度で従業員の貢献を測定しても、それ自体が最終的な評価結果に結びつくとは限らない。
たとえば、3つの項目について「最低点1.0〜最高点5.0」で0.5点刻みでの尺度で測定するような評価制度があり、従業員Aと従業員Bのそれぞれの直属の上司(課長)が、平均点で4.5をつけたとする。しかし、上司の上司(部長)からすると、2人の従業員の職場への貢献は同じには見えない。
従業員Aは、日頃から熱心に仕事に取り組み、細部にこだわり続け、周りの支援を適宜仰ぎながら一定の結果を出したとする。
一方、従業員Bは一定の結果を出すものの、下記の問題があるように見えた。
- 問題点1:熱心さが垣間見えず
- 問題点2:細部へのこだわりが弱い
- 問題点3:マイペースの個人プレーのような振る舞いが多い
職場を預かり、俯瞰する立場からすると、従業員Aの評価者と比べて、従業員Bの評価者は部下に対して甘いといえる。
そこで、部長は従業員Bの上司(課長)と意見交換した。部長は部門全体の最適という観点から、従業員Bの3つの問題点を指摘し、平均点4.5は高すぎるから見直すよう、課長に提起した。
これを受けて課長は、従業員Bと日頃から関わるなかで培われた全体的な印象を述べた。
そのうえで、問題点1は「部長の見込み違いであること」、問題点2は「当てはまるものの、すでに存在する人事評価の項目・尺度には直接関係ないために評価に反映できないこと」、問題点3は「理解できるため関連する2つの評価項目の採点を1点ずつ下げること」をそれぞれ伝えた。そして部長は、課長の判断を受け入れた。
人事評価の正確性は多様な解釈・判断をすりあわせて高められる
このように、ある従業員の貢献の大小については、さまざまな立場の人がさまざまな観点から解釈・判断するものであり、「正解」がすぐに現れるとは限らない。人事評価とは人に対する人による解釈・判断であるため、その正確性は、多様な解釈・判断をすりあわせ、併存または統合させることで、はじめて高められる。すりあわせにより正確性が常に高まるとは限らないが、特定の人のなかにではなく、「人々の間にこそ、正確性の芽は存在している」という考え方には一定の理がある。
多段階評価・多面的評価の仕組みも正確性への寄与が期待できる
多くの企業がこうした共同的な決定を仕組み化している。たとえば、すでに示したような、直属の上司の評価結果をさらにその上司が確認・調整・修正するような「多段階評価」の仕組みである。
また、「360度評価」と呼ばれることも多い「多面的評価」が導入されることもある。これは、従業員の貢献についての視点が、上司(やその上司)のみならず、同僚や部下、さらには指揮命令系当該の従業員や、社外の人々からも表明され、評価結果に影響するか参考材料となるものである。また、いずれにおいても従業員の自己評価が参照されることもある。
評価者は人事評価にどう参加するか? 評価行動をめぐって
人事評価の研究においては、評価者の評価行動、とりわけ「従業員情報の収集→情報の整理→情報の評価尺度への関連づけ→評価結果のフィードバック」という一連の流れのあり方を決定づける要因として、評価者が持つ認知特性と社会関係に注目されてきた。
すでに示した例にあるように、評価者は固有の視点・志向・興味関心にもとづいて、評価対象について解釈・判断する。評価者が個人的に有する評価基準は、その一部は企業にとって適切であるが、一部は不適切である。
評価者の個人的な評価基準は「偏り」と評される。そもそも評価者が持つ認知特性も、特定企業の価値基準に沿っているだけであって、客観性がないという点で偏りには変わりがない。評価という行為は、どうしても評価者の主観の上に成り立つものであるため、企業としてはそれを前提に、望ましい評価基準を評価者とともにつくり上げたり、職場や評価行動の現実を踏まえて評価基準を再定義しなければならない。
自身が納得でき、組織の価値基準にマッチした評価基準が必要
評価者と非評価者は、日常的には仕事内外で深く関わりあう上司と部下の関係である。このことが評価者の評価行動、さらには認知特性に対して与える影響はさまざまである。たとえば、自分と業務上の関わりがとくに深かったり、同質性や仲間意識をとくに抱きやすかったりする従業員に、評価者は高めの評価を付与する傾向がある(Barnes-Farrell, 2001)。
評価者はある意味で職場を代表するロールモデルたりうる存在であるため、こうした評価傾向のすべてが評価上のミスやエラーの源泉になるとは限らない。また、深い関係がない従業員に対する適切な人事評価を評価者はそもそも実施できない。しかし、評価される側の従業員を含め、こうした評価行動そのものについては、多くの人々が「えこひいき」「怠慢」と受け取るだろう。
評価者は、評価経験を重ねるなかで、自らの評価基準(視点・志向・興味関心)を、自分で納得できるものであると同時に、企業の価値基準にもあうものにしなければならない。
そして、その基準にもとづく人事評価、すなわち測定尺度を活用し、評価結果やその背景を従業員に伝えなければならない(フィードバック)。
さらには、被評価者間での評価のしやすさの差ができるだけ小さくなるように、彼らとの関係性、彼らの業務や内面についての理解の水準をできるだけそろえる必要がある。
さいごに
人事評価の正確性に向けた秘訣は、評価者個人の主観を超えたところに存在するわけではない。人事評価は、評価者の主観的な解釈・判断を積み重ねて実施するしかない。だからこそ、評価の基準や行動に関する評価者の考えが、企業や被評価者も含む関係者の間ですりあっており、その考えが実現していることが望まれる。正確な人事評価は、相応の手間をかけることで初めて実現するのである。
評価者に求められるのは、被評価者と日常的に関係をもち、そのなかで評価情報を集めることである。そして、そうした「事実」にもとづく評価が、従業員一人ひとりの役割遂行、ひいては評価者自身の役割遂行や職場の目標達成につながる、という理解をもつことである。前稿で紹介した評価項目や評価尺度の設定、そして今回紹介した多面的評価や評価者訓練の仕組み化や実施は、こうした評価行動を評価者が行いやすくするものでなければならない。そして評価者の工夫により、評価の行いやすさを実現している企業も少なくない。
しかし、そうした取り組みが、適切な評価行動をかえって難しくしてしまっている側面もある。この点について次回検討する。
- 参考文献
Barnes-Farrell, J. L.(2001).Performance appraisal:Person perception processes and challenges. In M. London (Ed.), How people evaluate others in organizations(pp. 135–153). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Tziner, A., and Kopelman, R.(2002). Is there a Preferred Performance Rating Format? A Non Psychometric Perspective. Applied Psychology: An International Review, 51: 479-503.

お役立ち資料
経営の未来をつくるカギは人事評価にある
人事評価が「従業員の能力や業績を評価して、待遇・賃金を検討するための仕組み」であることは言うまでもありません。しかし、人事評価が影響する範囲は大きく、自社の経営の未来をつくる存在でもあります。
本資料では、見落とされがちな経営戦略と人事戦略を連動させる重要性について解説しています。