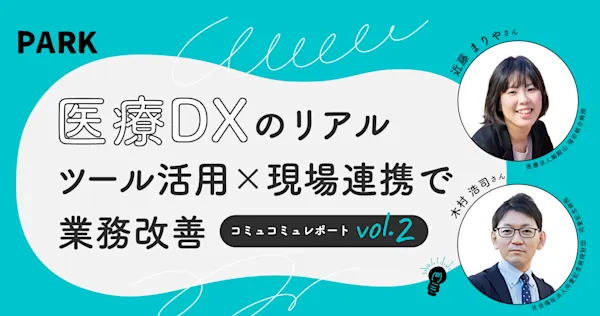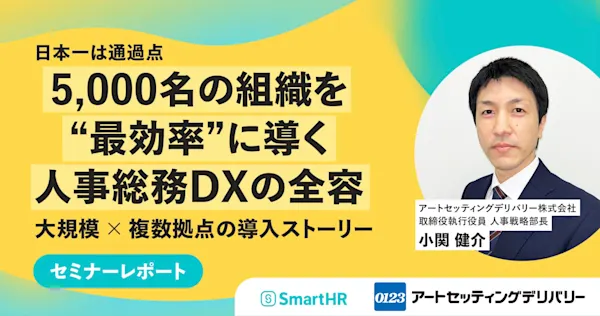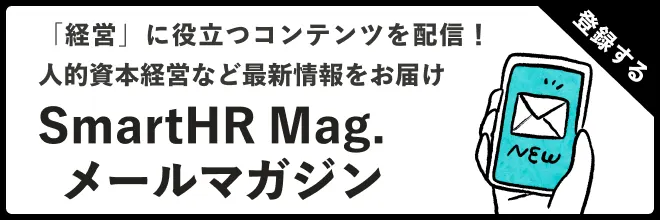10万人の従業員に届ける。全社DXを推進するすかいらーくのSmartHR活用術とは
- 公開日

目次
業務プロセスの変革を通じて、従業員や企業の大幅なパフォーマンス向上を実現する企業が増えています。SmartHRでは、経営者・人事担当者の皆さまを対象とした少人数制の講演・交流会を定期的に開催しています。
今回の登壇者は、和洋中をはじめとする各種テーブルサービスレストランを中核事業として展開する株式会社すかいらーくホールディングスで部門横断のDXを推進する飯田 恒(いいだ ひとし)氏です。10万人の従業員を擁する同社でSmartHRを活用する取り組みのほか、得られた効果について迫りました。
 スピーカー飯田 恒氏
スピーカー飯田 恒氏株式会社すかいらーくホールディングス 人財本部 人財企画グループ 人事デジタル推進チーム リーダー
すかいらーくに2001年入社、夢庵7店舗で店長職を経験。2014年より、本部情報システム部門で店舗システム運用保守や開発に従事。2020年からは人財本部にて人事系システムを担当。部門横断の本部DX推進プロジェクト「本部困り事改善プロジェクト」にも参画し、人事部門のDX化、業務効率化に取り組む。
 モデレーター今西 佑太
モデレーター今西 佑太株式会社SmartHR ブランディング統括本部 オフラインマーケティング部 マネージャー
新卒で関西の鉄道会社に入社。複合施設の開発および開業後の運営管理を担当し、集客イベントの企画、広報宣伝等のマーケティング業務を行う。2020年にSmartHRに入社し、関西支社の立ち上げに参画して、見込み顧客の獲得を中心としたマーケティング業務に従事。2023年に大手企業に特化したチームを立ち上げ、同年7月よりマネージャーに就任。

スマートフォン向けアプリを起点に店舗・本社双方の生産性を向上。店舗業務に集中できる環境づくりへ
部門横断型のDX推進プロジェクトをきっかけに、SmartHRを導入・活用しているすかいらーくホールディングスの取り組みはこちら
10万人の従業員にとって使いやすいツールかどうか
今西
本日はありがとうございます。まずは飯田さまの自己紹介をお願いします。
飯田さん
初めまして、すかいらーくホールディングスの飯田と申します。 すかいらーくグループは、ファミリーレストランの「ガスト」をはじめ20種以上の飲食ブランドを展開しています。国内外に約3,000の店舗があり、10万人の従業員数が日々サービスを提供しています。

飯田さん
私は現在、人財本部で人事系システムを担当するかたわら、本部DX推進も担当しています。部門を横断したDX推進では、生成AIの活用を促進する勉強会を企画・開催したり、人的資本経営の充実をめざした各種取り組みも担ったりしています。

株式会社すかいらーくホールディングス 飯田 恒氏
今西
幅広い業務を担われています。SmartHR導入前の課題についてお聞きしてもいいですか?
飯田さん
本部のDX推進の担当者に任命されたとき、社内の課題の洗い出しを行いました。
店舗や従業員側の視点では、やはり「紙」にまつわる課題感がありました。配布物は受け取りの手間がかかりますし、不備があったときのやりとりも大変です。また、業務ごとに違うシステムを使っているとわかりにくいだけでなく、IDやパスワードの管理も大変です。
一方、本部側の視点では、店舗や工場などの現場によって業務の依頼フローが異なるうえ、給与明細や年末調整などが紙ベースだったことで煩雑さが一層増していました。あとは、各種調査や申告で従業員の情報を効率よく収集できず、情報の一元管理がされていないのも大きな課題でした。
今西
そうした課題を解決するにあたって、まず貴社の従業員数に耐えうるツールかどうかというのも重要ですよね。
飯田さん
そのとおりです。10万人の利用を想定し、「今すぐ使いたい機能群の充実(年末調整、給与明細など)」「誰でもわかりやすい操作性や画面の見やすさ」「担当者の提案」の3点で、最終的にSmartHRを導入しました。
機能や操作性はもちろん、弊社の希望を的確に組んで提案いただいたのが印象的で、私の上長も「SmartHRさんの提案はすごく的確だった」と話していました。長いお付き合いになる企業さまですから、そうした面でストレスがなかったのも導入理由として大きいですね。
今西
私どもは中長期でお客さまに寄り添うことを意識しているので、非常にありがたいお言葉です。

株式会社SmartHRの今西 佑太
段階的なツール導入で、現場の混乱を最小限に抑える
今西
続いて、SmartHR導入後についてお話を伺えればと思います。
飯田さん
導入により、実際に年末調整や給与明細はペーパーレス化が進みました。
それ以外の部分ですと、店舗従業員とのコミュニケーションにおける利便性が向上しました。以前は「通達文書」の形で業務を依頼し、店舗の責任者が対象となる従業員に説明するなどの順序を踏んでいました。SmartHRを使えば、本部から従業員に「就労証明書をお送りします」など連絡を直接取ることもできます。
今西
情報伝達にかかるコストを抑えられたのですね。
飯田さん
退職者への関連書類のお渡しにも使えますし、職場に関する意識調査アンケートなどは配信先の絞り込みも可能です。先述した通達文書も手段としては残していますが、SmartHRはやはり「便利」という言葉に尽きます。
とくに、紙で実施していたアンケートは現場の忙しさのなかでどうしても後回しになるケースがありました。とはいえ本部にとっては社員登用や職場改善のための大事な情報収集ですから、むずかしいところだったんです。SmartHRを使うことで、本部の発信のねらいとともに、従業員に確実に情報を届けられるようになったのは大きな成果です。
今西
導入時になにか工夫されたことはありますか?
飯田さん
本部としては、従業員10万人を相手にいきなりシステムを切り替えるとなると混乱が生じると危惧していました。そこで、2022年下期に「年末調整」から活用をスタートし、徐々に利用する機能や対象となる従業員を拡げていきました。

今西
まずは、正社員の皆さまと社会保険に加入する一部のパート/アルバイトさまを対象にした「年末調整」機能の利用からスタートされたのですね。どのような反応がありましたか?
飯田さん
想定よりはスムーズでした。それで次の段階として、紙のカード型社員の替わりにSmartHRの画面を見せることで社員証としての利用をスタートしました。ねらいとしては、店舗の責任者にSmartHRにさらに慣れてもらいつつ、2023年下期から全従業員の給与明細や源泉徴収票を紙からSmartHRの機能へ切り替えていきたいと考えていました。
今西
全従業員が対象となると、さらに準備が必要になりそうですね。
飯田さん
はい。全従業員が対象となりますから、半年くらいは紙でも並行運用しつつ、1年かけて切り替えを完了しました。ちょうど紙での並行運用が終わるタイミングで本部への問い合わせが増えましたが、段階的に対象となる従業員を増やしたので、都度、本部で対応することができました。

社内のほか施策も絡めて、SmartHR利用者が増加
今西
先に店舗の責任者さまにSmartHRに慣れていただいたなど、時間をかけた切り替えが従業員の方々の不安の払拭につながったのかもしれませんね。
飯田さん
弊社には大きく以下3つの課題があったので、導入後も地道な取り組みを続けていました。

飯田さん
1つ目について、新しいシステムを利用する際はどこの企業さまでもあると思うのですが、操作やログインなどに関する問い合わせが増えると考えていました。そこで、電話対応する担当者に共有するFAQをあらかじめ作成し、実際の問い合わせ内容を踏まえて、資料をハイライトしたり、改めて利用案内を行ったりして改善につなげました。
2つ目について、従業員によってはどうしてもパソコン操作などITツールに不慣れな方もいらっしゃいます。しかし、使い慣れたスマホにインストールしてもらうアプリですと、使い勝手がよいみたいでして。実際、スマートフォン向けアプリ「SmartHR」を利用し出してからは、ログインなどに関する問い合わせも減りました。
3つ目について、2023年に給与明細機能を利用し始めたあと、「みんな自分の給与明細を見るだろう」と思っていたのですが、予想に反して利用者がそこまで増えず……。ちょうど別の施策で社員向けの「すかいらーくアプリ」で勤務時間に応じたポイント付与を行っていて、そのエントリーで必要なメールアドレスをSmartHR上で登録・集約することで利用者を増やしました。
今西
ほかの施策を絡めるなどの工夫もあったのですね。実際どのくらい利用者は増えましたか?
飯田さん
それまでは対象者の半分ぐらいしかアクティブユーザーがいなかったのですが、7〜8割ぐらいに増加しました。なにかをきっかけに利用を始め、抵抗を少なくしていってもらうのは重要だと改めて思いましたね。

ペーパーレス化で年末調整の問い合わせはほぼゼロに
今西
取り組みの結果、得られた成果をお尋ねしてもよろしいでしょうか?
飯田さん
もちろんです。初めてSmartHRで年末調整を実施したときにアンケートをお送りしました。回答の7割近くがオンラインでの年末調整を肯定的に捉えており、手応えを感じました。
また、先程「店舗従業員とのコミュニケーションにおける利便性が向上した」とお伝えしましたが、これに関連して従業員アンケートの回答率が大幅に上昇したのは特筆すべきことだと考えています。
今西
具体的に回答率はどのくらいになったのでしょうか?
飯田さん
以前、紙で実施していたころは回答率が5%あればいい方でしたが、あるアンケートを朝にお送りしたら、当日の昼には5%の回答が得られ、最終的には約70%の従業員から回答を得られました。
今西
それはすごいですね。スマートフォン向けアプリ「SmartHR」の導入ともなにか関係があるのでしょうか?
飯田さん
まちがいなくあると思います。ITに不慣れな従業員とも接点ができますし、この反応率の高さはスマートフォンへのプッシュ通知にも依ると考えています。
そのほかの定量的な成果ですとSmartHRの導入後、年末調整の申告方法ーーたとえば「記入方法がわからない」といった問い合わせはほぼゼロになりました。2年目以降は前の年の入力内容が引き継がれ、さらに便利になったという声が従業員からも寄せられましたね。
導入当初から活用を予定していた主要な機能については、ペーパーレス化が進み多大な削減効果を生み出せました。

新機能を含め、今後もSmartHR活用を進める
今西
すかいらーくさまには「メッセージ」機能をトライアル実施(2025年3月リリース)いただきました。その取り組みや得られた成果についてもお尋ねしてよろしいでしょうか?
飯田さん
弊社では社会保険や労災補償など、現場になるべく早く確実に届けたい書類や情報のやりとりにメッセージ機能を活用しました。パート・アルバイト従業員の方のなかには、たとえば週末や深夜にしか勤務されない方もいらっしゃいます。そうするとタイミングよく書類を渡したり、用件を伝えたりするのが難しいわけです。また、店舗の責任者も忙しかったり、扱うのが機微な情報だったりするとなかなかスムーズに伝達できないケースもあります。
そんなとき、本部から従業員の方にSmartHR上で直接やりとりができるようになり非常に助かっています。
今西
嬉しいフィードバックをありがとうございます。最後にSmartHRの活用や今後の展望について教えてください。
飯田さん
SmartHRに当初期待していた年末調整や給与明細だけでなく、そのほかの業務でも外部システムとの連携を行いながら、従業員データを一元管理できるSmartHRのさらなる活用を検討してまいります。