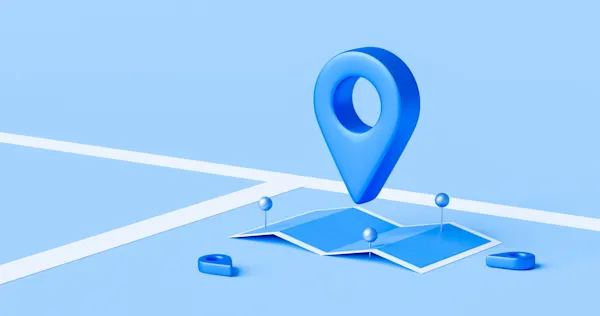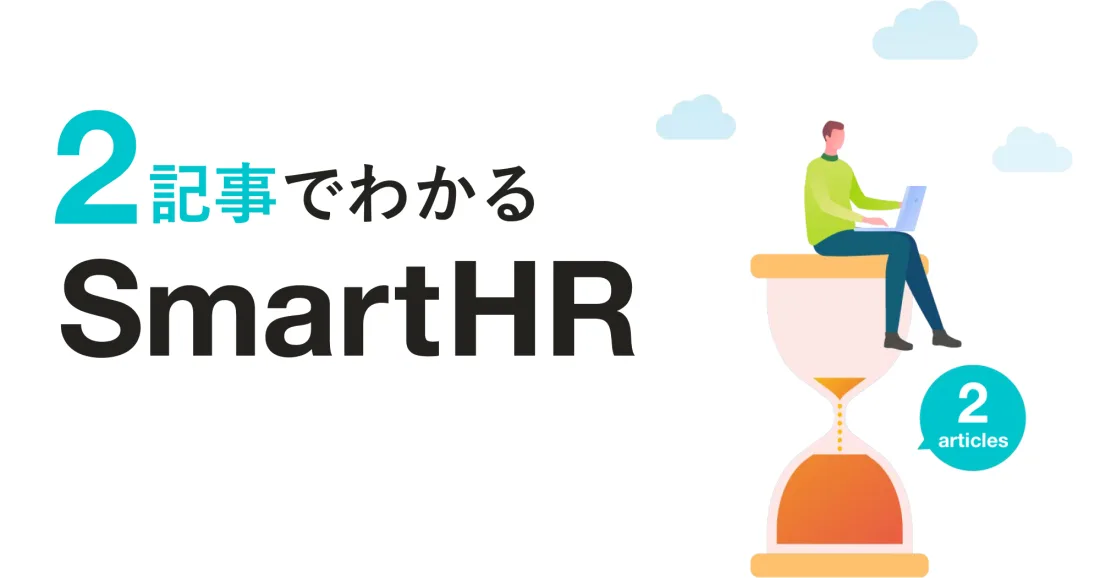これからの時代の「働く」を考えるために必要な物語とは
- 公開日

コロナ禍を経て、価値観が大きく変化した現代。消費サイクルがさらに早まりつつあるこの時代において、会社という組織に求められることも少しずつ変化してきているように思います。これからの時代、「その人らしく働く」を実現するために、企業や個人はどのような物語を紡いでいく必要があるのでしょうか。「ケア」の視点から文学作品を研究する小川公代さんに、物語が現代のなかで果たす役割について伺いました。
医学史・英文学研究者。上智大学外国語学部教授。ケンブリッジ大学政治社会学部卒業後、グラスゴー大学で博士課程修了。著書に『ケアする惑星』(講談社)、『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社)、共著に『別冊100分de名著 パンデミックを超えて』(NHK出版)などがある。医学界新聞などで連載中
ケアをする人が文学作品においてどのように描かれてきたか、小川さんは著書のなかで論じられています。では、「その人らしく働く」というテーマは、文学作品のなかでどのように扱われているのでしょうか。
小川
そのテーマを考えるうえで、そもそもですが、どこからどこまでを「働く」と捉えるのかが重要です。たとえば家族のために家事をすることも「働く」の一部でしょうし、企業においてもプロジェクトを牽引するような働き方だけでなく、同僚に頼まれてコピーを取ったり、誰かの飲んだコップを洗ったりと人をサポートするタイプの働き方もありますよね。
「働く」って実は、とても広い射程を持った言葉だと思うんです。けれど、補助的な立場で誰かのために働いている人は、当人からすればその人らしく働いていても、周りからはそう見られないことがしばしばあります。「これが私らしい働き方なんです」といくら言っても理解してもらえない。特に日本において多いように感じます。

「自己実現できていないんじゃないの?」と余計な心配をされることもありそうです。
小川
たとえばイギリスの作家エミリー・ブロンテの『嵐が丘』は、古典中の古典でタイトルや大まかなあらすじを知っている人は多いと思います。けれど、これは授業で学生に尋ねてみても毎回そうなんですが、『嵐が丘』の語り手が誰か知っている人ってほとんどいないんですよ。
この物語の語り手は、主人公のキャシーでもなければキャシーと恋愛関係になったヒースクリフでもなくて、キャシーが生まれた家で女中をしているネリーという女性なんです。彼女は家事も子どもたちの教育も一手に担っているのに、大きなプロットの前では読者に忘れ去られてしまう。
女中のネリーも「その人らしく」働いているはずなのに、読者からは存在感が薄い人物だと思われてしまうと。
小川
そうなんです。エミリー・ブロンテとその姉シャーロットの生活について綴った伝記によれば、ブロンテ姉妹は実際、自分たちの家で長年働いていた女中が怪我をして働けなくなったときにも、彼女を追い出すのではなく自分たちの手で看護し、家事も自分たちでこなすことを選んだそうです。エミリー・ブロンテにとって「働く」という行為は、生活の糧のために小説を書くことにかぎらない、もっと根源的なものだったのではないでしょうか。
もし、誰かが困ったときに精一杯のケアをすることも「働く」だとすれば、私的領域と公的領域の境界線がだんだん溶けて見えなくなっていくような気がしています。企業においても、家事や子育てをすることが反映される働き方も「その人らしく働く」ことにつながるのではないでしょうか。

「大きな物語」に絡めとられず、固有の物語を生きるために
物語と現実は合わせ鏡のような側面があります。物語が現実に影響を及ぼすこともあれば、現実が物語に影響を及ぼすこともある。そうした物語と現実の関係について、小川さんはどのように捉えていますか?
小川
「働く」というテーマに関連づけると、物語そのものが持つ力の強さについて最近よく考えているんですね。物語には人の心に寄り添い、苦しみから救ってくれるような力がある一方で、特定の正しさを前景化してしまう側面もあるなと。
たとえば、「女性/男性はこういう働き方をするのが望ましい」という大きな物語が語られたときに、それに追随しないと生きていけないような息苦しさを感じる人もいるはず。辻村深月さんのベストセラー『傲慢と善良』は、まさに物語に押しつぶされそうになる女性の話です。主人公は、社会のなかで語られるロマンチックな恋愛・結婚の物語を内面化しすぎて苦しんでいる。「マッチングアプリで出会うのはドラマがないんじゃないか」とかね(笑)。
現代社会を生きていると、物語に絡めとられて自分を見失いそうになることがしばしばあると思うのですが、社会が要請する、そんな大きな物語に「No」を突きつけてきた文学作品もたくさんあります。その筆頭がヴァージニア・ウルフだと私は思っているのですが、ウルフは相手に何かを強制するような物語を書かないんですよね。
「その人らしく働く」とか「その人らしく生きる」ということが、大きな物語に絡めとられずに自分の小さな物語を生きることだとしたら、おそらくいちばんヒントになるのはウルフの作品なんじゃないかと思います。

自分固有の小さな物語を生きていきたいと思っても、社会通念との間で引き裂かれそうになってしまうこともあるように思います。そんなとき私たちには何ができるのでしょうか。
小川
歴史を遡り、今よりももっと生きづらい社会に生きていた女性たちの物語を読んでいくことがひとつかもしれません。
たとえば、『フランケンシュタイン』を書いたイギリスの作家メアリー・シェリーは、10代のときに駆け落ちをして大陸へ渡り、文学の教育を受けて執筆活動をはじめたわけですが、当時はそれが非常にスキャンダラスな生き方だった。他方で私たちは、義務教育も与えられ、移動の自由も職業の自由も得たはずなのに、妙に忖度して生きている気がするなと。波風を立てない生き方を求めるような社会通念が、私たちの行く先をまだまだ塞いでいるんですよね。
メアリー・シェリーの時代には、自由でいることが何より大事だというイデオロギーが機能していたけれど、今はそれさえ失われてしまって、自由という言葉が「所有」に置き換えられているように思います。
自由が所有に置き換えられている、というと?
小川
冒頭の話にもつながりますが、近代以降は、意のままに自分をコントロールし、主体性を持ってやりたいことをやることこそが「自分らしさ」だと定義されすぎてきたと思うんです。お金や物を手に入れるだけで自由を得た気になってしまうという問題に、私たちはもっと自覚的になるべきだなと。本来的な自由というのは、苦しくても自分で手に入れるものじゃないでしょうか。
哲学者の小林康夫さんはそれを「ブリコラージュ的自由」と呼んだのですが、自分固有の自分らしさを得ようと思ったら、いろいろな人や本に出会い、新たな価値観を少しずつコラージュして自分のものにしていくしかないと思うんです。社会通念に抗うのは本当に難しいことだけれど、ロールモデルになるような人たちをたくさん見つけて、その人たちの声や言葉を自分の基盤にしていけたらいいのかなと。
私のなかにはロールモデル足りうる人たちが何百人もいるのですが、その人たちの言葉をブリコラージュすることで、社会通念に抗ってもいいと学んだような気がしています。

「良い物語」に投資する顧客を企業の共事者にしていく
では、これからの時代に個人が「その人らしく働く」を実現するために、企業はどのような物語を描いていくのが良いのでしょうか。
小川
消費を追い立てる社会の圧力のなかにいると、企業も短期的な利益を追い求めざるをえなくなるので、中長期的に信頼を勝ち得て成長するというビジョンが見えにくい時代なのかもしれないですね。「その人らしく働く」を実現させるためにどのような環境を整えればいいかを理解していても、現実的にリソースがないというジレンマを抱えている企業も少なくない気がします。
フェアトレード商品がその筆頭ですが、良い物語──つまり、人を人として扱うような物語はどうしても高額になる。それでも、良い物語に投資してくれる顧客は必ずいると信頼して行動していくしかないですよね。ごく短いスパンで新しいモデルが登場し、それが飽きられては次のモデルが登場するという現代の消費サイクルを生み出している一因には、生産者と顧客の共犯関係もあると思うんです。顧客がどのような選択をするかも重要ですが、顧客のリテラシーを上げていくための努力は企業側もしていくべきでしょう。
人はどうせ安いものに流れるだろうと感じることもあるかもしれませんが、「この商品やサービスがこの価格設定なのはこういった背景があるからです。みなさんのリテラシーを私たちは信頼します」というメッセージを企業はもっと出しても良いのではないでしょうか。それが通じる社会になりつつあると私自身は感じています。
企業が商品やサービスの背景を物語として発信する場合、顧客がそれを押しつけがましく感じてしまうこともあるように思います。
小川
女性向け商品の開発チームに女性が不在であるなど、当事者ではない人によって紡がれた物語に顧客が違和感を覚えるというすれ違いは常に起きていますよね。いちばん大きな問題は、企業のトップや役員に当事者を据えないことにあるように思います。
あるいは、これはローカルアクティビストの小松理虔さんの言葉ですが、当事者ではなくとも共に事を為す「共事者」でいることもできるはずです。仮に当事者と一緒に働けないとするなら、少なくともその問題に共事者として向き合う立場を明確にする。そんな物語が必要なのではないかと思います。

取材・文:生湯葉しほ
撮影:植本一子
※この記事は、本特集の冊子版であるJIKKEN MAG「well-workingの第一歩」内の企画を掲載したものです。
働くの実験室(仮)by SmartHRについて
本連載を企画している「働くの実験室(仮)」は、これからの人びとの働き方や企業のあり方に焦点をあてた複数の取り組みを束ね、継続的に発信するSmartHRの長期プロジェクトです。
下記ウェブサイトから最新の活動が届くニュースレターにも登録していただけます。