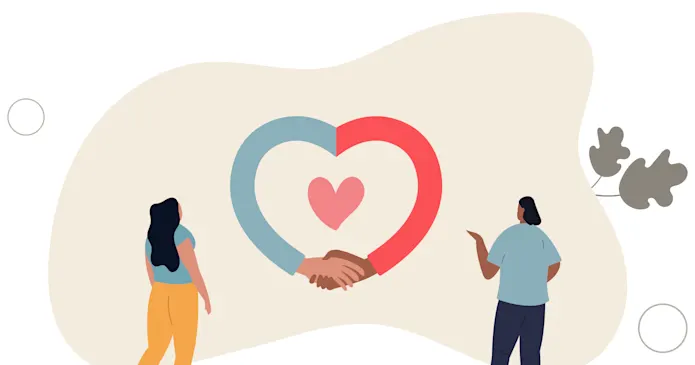「人間関係のすれ違い」はなぜ起きる?理由と対処法を紹介
- 公開日

目次
皆さん、こんにちは。一般社団法人日本心理的安全教育機構 代表理事の小野みかです。
私たちが生きていくうえで「人間関係」は欠かせない要素です。人間関係を構築していくと、仲の良い友人になったり、信頼できる同僚ができたりする一方で、ときにはすれ違いや誤解が生じることもあります。
たとえば日常的にみられる「言った/言わない」の問題は、人間関係のすれ違いの原因の一つではないでしょうか。また、相手の意図を正しく理解できなかったゆえに、摩擦や不快感が生まれるケースも少なくありません。
このようなコミュニケーションのズレを解消するためには、確認の重要性や心理的安全性を理解するとともに、自分自身の心の状態を見つめ直すことが必要です。
そこで本記事では、人間関係のすれ違いが起きる理由と対処法について詳しく解説し、より良いコミュニケーションを築くためのヒントをお届けします。
人間関係のすれ違いとは
学校や職場など、日常生活のさまざまな場面で「人間関係のすれ違い」を感じた経験がある方は多いのではないでしょうか。すれ違いとは、相手との意図や感情が正しく伝わらないことを指します。
すれ違いが原因で誤解や摩擦が生じることも少なくありません。とくに「言った/言わない」の問題は、身近な例の一つといえます。
相手に誤解されるケース
言った/言わないの問題は、コミュニケーションのなかでも頻繁に発生します。
たとえば、友人から何かお誘いを受けた際に「また今度ね」と言ったとします。都合がつかずに気軽に断ったつもりが、相手には「もう遊びたくないんだ……」と受け取られてしまった経験は、多くの方がもっていると思います。
このように、自分が言った意図とはまったく違う意味で相手に受け取られてしまい、誤解を生んでしまうのは、言葉の選び方や伝え方、受け取る側の状況が大きく影響しています。
自分が誤解するケース
日常生活のなかで起きるすれ違いには、自分が誤解してしまう場合もあります。
たとえば、挨拶をしたのに相手から返ってこない場合です。通勤中に友人に「おはよう」と声をかけたのに、相手がイヤホンをしていて気づかれなかった経験をした方も多いのではないでしょうか。
この場合、声をかけた側は「無視された」と感じるかもしれません。ですが、実際には相手がイヤホンで音楽や音声に夢中になって、単に聞こえていなかっただけなのです。または、挨拶を返したけれど、こちらが聞こえていなかった場合も考えられます。
しかし声をかけた側は、挨拶が返ってこなければショックを受けますよね。「私は、嫌われているのかな」「何か嫌なことしちゃったかな……」と気にしてしまう方もいるかもしれません。
このような小さなすれ違いが積み重なると、お互いに誤解が生じてしまい、徐々に関係が悪化してしまう場合があります。
誤解が生じる背景
相手と自分との間に誤解が生じる背景には、複数の要因が絡んでいます。

言葉のニュアンス、トーンを間違うと誤解の元に
まず、言葉の選び方です。友人に対して「また今度ね」と軽い気持ちで返した場合でも、相手には冷たく感じられたり、拒絶されたと受け取られ、解釈されることがあります。このように、言葉のニュアンスやトーンは異なる解釈を生む原因となりやすいです。
伝え方も重要。とくにテキストは要注意
次に、伝え方です。LINEやメールで「また今度ね」と送った場合、相手はその言葉だけを受け取り、感情や意図を読み取るのが難しいかもしれません。対面でのコミュニケーションでは、表情や声のトーンが相手に与える影響が大きいですが、テキストメッセージやスタンプなどではそれらが伝わらないため、誤解が生じやすくなります。
相手の状況にも配慮しよう
受け取る側の状況も考慮する必要があります。相手がストレスを抱えていたり、忙しくて心に余裕がない場合には、あなたの言葉をネガティブに解釈する可能性が高まります。相手の心の状態や環境が与える影響は大きく、同じ言葉でも異なる意味をもつことがあるのです。
これらの要因が組み合わさると、より事態が複雑化して、誤解やすれ違いが生まれやすくなります。したがって、コミュニケーションにおいては、相手の受け取り方を意識し、言葉と伝え方を選ぶことが必要です。
一方で、自分が人間関係に過敏になっている、相手のことを余計に気にしている、といった状態だと「自分が勝手に誤解している」「間違った思い込みをしている」場合もあります。そのため、冷静に自分や周りの状況を受け止めることも大切です。
すれ違いを解消する「確認」の重要性
受け取り方のズレを理解し、相手とのコミュニケーションを深めるためには「確認」が不可欠です。誤解が生まれるプロセスを確認し、状況に応じたアプローチをご紹介しましょう。
誤解が生まれるプロセス
人間関係を円滑にするコミュニケーションをしていくためには、誤解が生まれるプロセスを知っておく必要があります。

以下が3つのプロセスです。
- 発信者がメッセージを送信
- 受信者がそのメッセージを受け取り、解釈
- その解釈の反応を見て、発信者も解釈
解釈の段階で、心の状態や周囲の環境が受信者または受信者へ影響を与え、最終的に誤解が生じることになります。
受け取り方のズレ
上記のプロセスからみていくと、受け取り方のズレは、発信者と受信者の意図の違いから生まれます。
集中しているとき、あるいはショックな出来事があった場合などには、相手の反応が鈍くなることがあります。先述したイヤホンの例もこれに当てはまるでしょう。
このような状況では、発信者の意図が正しく伝わらず、誤解が生じる可能性が高まります。とくに、感情が高ぶっているときや体調が悪いとき、他のことに気を取られているときには、相手の言葉を正しく理解するのが難しい場合も少なくありません。
人間関係のずれを解消する「確認」の方法
こうした場合に有効となるのが「確認」です。
もっとも簡単な確認の方法は、もう一度挨拶や声かけをやってみることです。
たとえば、相手があいさつを返さなかった場合には、再度「おはよう、聞こえた?」と軽く声をかけることで、相手の状況を確認できます。
非常に簡単な方法ではありますが、意外とやっていない方も多いのではないでしょうか。些細なプロセスではありますが、意識すれば人間関係のすれ違いをグッと減らせます。
ただし、相手へ確認をする際には、状況に応じたアプローチが求められます。相手の表情や態度をよく観察し、確認のタイミングを見極めるのは重要なポイントです。相手が忙しそうにしている場合は、話を聞いてもらえない場合もあるかもしれません。そんなときは、無理に話しかけるのではなく、状況を見たり、時間を置いたりして確認のプロセスを踏むとよいでしょう。
心理的安全性が確保できているか?
「確認」のプロセスを踏むうえで重要な考え方となるのが心理的安全性です。心理的安全性とは、個人が自分の意見や感情を安心して自由に表現できる環境を指します。この概念は、とくにチームや組織において、メンバーがリスクを恐れずに発言できる状態を指し、オープンなコミュニケーションを促進するものです。
心理的安全性の詳細の内容は以下の記事をご覧ください。
心理的安全性の重要性
職場・学校・地域など、自分が属するコミュニティにおいて心理的安全性が確保されていることは、人間関係のすれ違いを起こしにくくするために非常に重要です。
心理的安全性が確保されている環境では、自由に意見を述べたり、質問をしたりできるため、早期かつ気軽に意思の確認が取りやすく、コミュニケーションが活発化して誤解が生じにくくなります。
反対に、心理的安全性が欠如している場合には、相手に対して自分の気持ちを正直に伝えられません。その結果、誤解が生じやすくなる、すれ違いが起きたまま解消するきっかけがない、といった状況に陥るのです。
心理的安全性を確保する方法
心理的安全性を確保するための方法は複数ありますが、ここではすれ違いの解消に役立つ3つの方法を厳選してご紹介します。

オープンな対話の場をつくる
1つ目は、オープンな対話の促進です。職場や学校といった場では、、メンバーが自由に意見を述べられる環境をつくり、率直なコミュニケーションを促進します。定期的なミーティングやイベント、意見交換の場を設けることで、考えを安心して表現できる土壌を醸成できます。
フィードバックを受け入れる姿勢
2つ目は、フィードバックを受け入れる姿勢です。他者からの意見や批判を受け入れるのは勇気が必要ですが、改善に努める姿勢をもてば、個人だけでなく組織全体の成長にもつながります。フィードバックを恐れずに受け入れることで、自分が普段使っている言葉、態度などを見直すきっかけにもなり、誤解やすれ違いを回避できます。
相手を理解する
3つ目は、共感の姿勢です。相手の気持ちを理解しようとする姿勢は、信頼関係を築くうえでの基盤となります。相手をよく観察して「もしかしたら別のことが気になっているのではないか」「今は話しかけない方がよい」など、その人が置かれている状況や感情に対して理解を示せば、信頼が高まり人間関係も円滑になるでしょう。
こうした方法を実践することで、心理的安全性を確保し、より良いコミュニケーションと協力的な関係を構築できます。
「自己理解の深化」と「相手の状況の理解」が重要
人間関係のすれ違いを解消するためには、自分自身の心の状態を見つめ直すことも必要です。自分の心の状況が、相手に対する反応に影響を与える場合が多く、それを避けるために自己理解の探求が求められます。

自己理解の深化が心の余裕を生む
自分の心の状況が弱っていると、相手の言動に対して過敏に反応してしまうケースも少なくありません。
たとえば、ストレスが溜まっているときや、疲れているときには、普段は気にならないような言葉でも、ネガティブに受け取ってしまうことがあります。友人からの軽い冗談や、何気ない一言が、自分の心の状態によっては、傷つけられたと感じる原因になる場合もあるでしょう。
そのため、円滑な人間関係を目指すためには、まずは自分の心の状態を意識することが大切です。自己理解を深めていけば、相手の言葉を客観的に受け止める余裕ができ、誤解を避けられます。
相手の状況の理解で信頼関係を構築
相手の状況を考慮することも大切です。たとえば、相手が忙しい、疲れている、あるいは何か悩みを抱えている場合、その状況を理解しようとする姿勢が、誤解を減らすきっかけになります。このような配慮があると、相手も自分を理解してくれると感じ、信頼関係が深まります。
人間関係は相互作用によって築かれるものだからこそ、自分自身の心の状態を見つめ直しつつ、相手の状況を理解しようとする姿勢をもちましょう。
人間関係のすれ違いを減らすメリット
人間関係によるすれ違いを減らす最大のメリットは、誤解や断絶を未然に防ぐことで、人間関係における悩みが圧倒的に減る点です。相手の意図や感情を正確に理解すれば、無用なトラブル・心配を避けられます。また、コミュニケーションがスムーズになるため、相互理解が進み、より強固な関係を構築できます。
さらに組織の場合には、コミュニケーションの活発化により、チーム全体の生産性や問題解決能力の向上、人間関係から来るストレスの軽減などにもつながります。
すれ違いを減らすため「確認」を習慣化するには、日常的に意識した行動が欠かせません。会話のなかで常に相手の反応を意識する、相手の立場を考慮した言葉・態度を心がけることで「確認」のプロセスが自然な行動として定着するでしょう。
相手の立場の理解と確認ですれ違いを回避しよう
今回は、人間関係のすれ違いが起きる理由と対処法についてご紹介しました。
人間関係のすれ違いは、私たちの日常生活で避けられないものです。しかし、「相手の立場に対する理解」と「確認のコミュニケーション」を通じて回避できます。また、定期的に自分の心の反応を見つめ直すことで、感情に流されず冷静に対処できるようになります。
人間関係において違和感を覚えたときには、ぜひ今回の対処法を試してみてはいかがでしょうか。
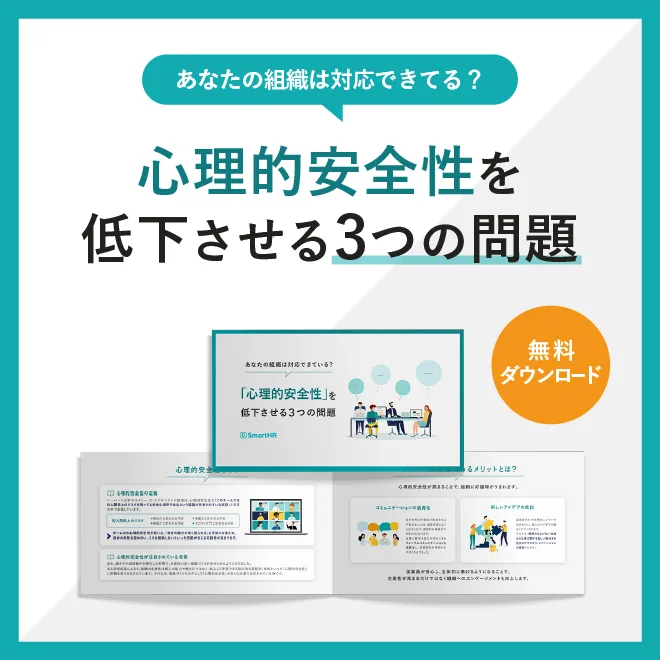
お役立ち資料
あなたの組織は対応できている?「心理的安全性」を低下させる3つの問題
この資料でこんなことがわかります
- 心理的安全性を高めるメリット
- 心理的安全性を低下させる3つの問題
- 心理的安全性をチェックするときに有効なもの