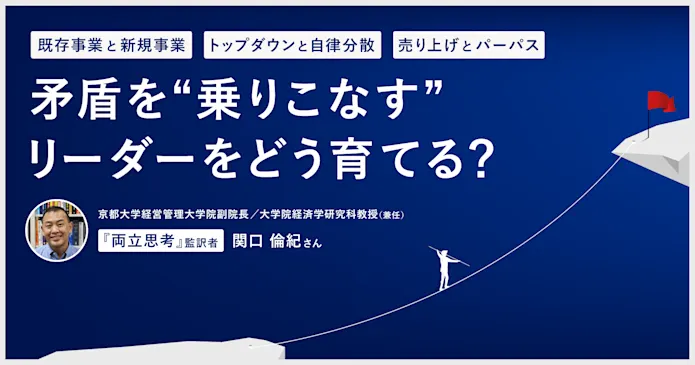多様な人材が活躍する組織をつくる“インクルーシブ・リーダーシップ”とは
- 公開日
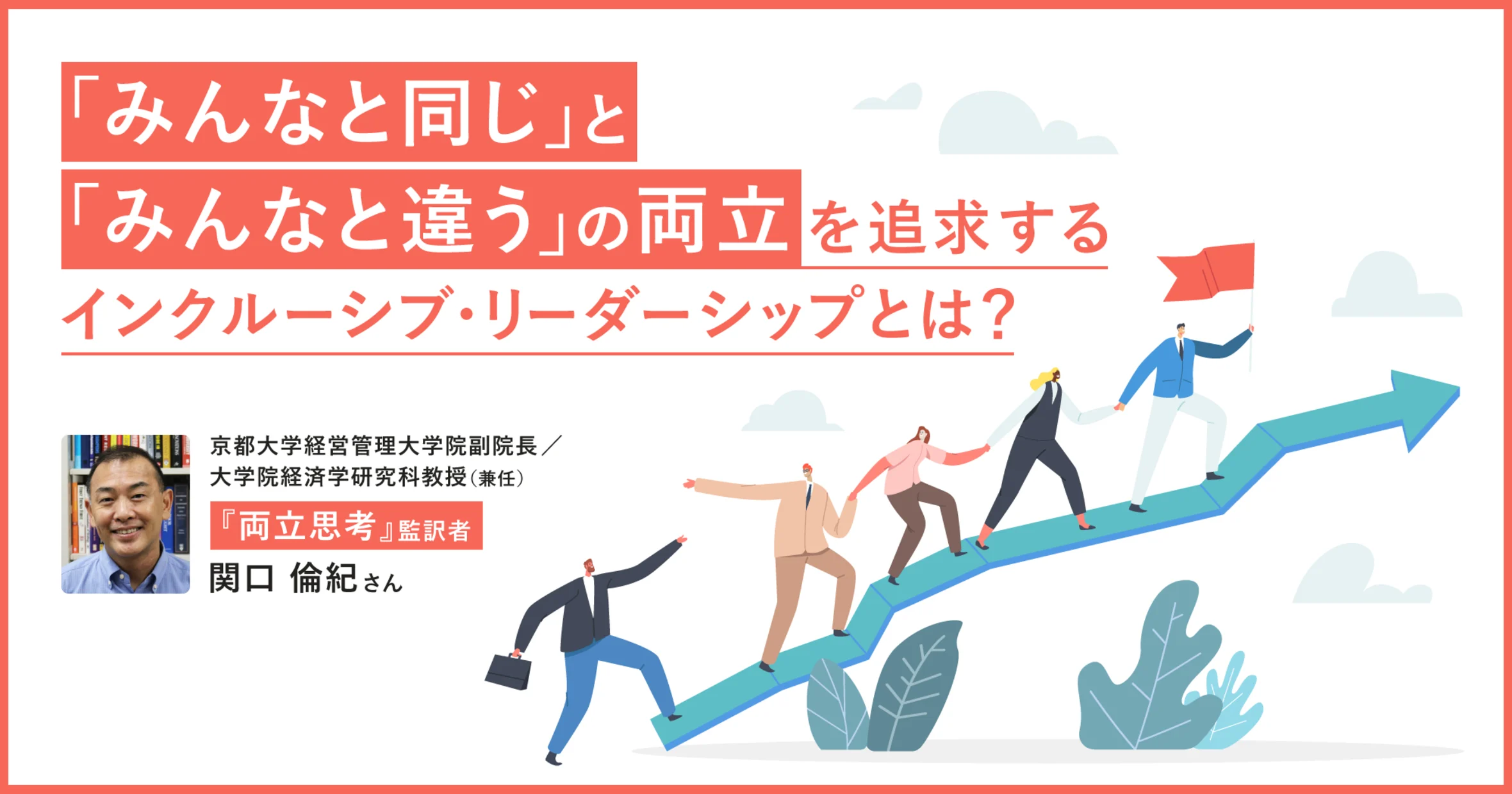
ダイバーシティ推進の重要性が増すなか、企業には多様な従業員が活躍できる組織づくりが一層求められています。その実現を担うリーダーには、多様な個を包摂するインクルーシブ・リーダーシップが必要です。
今回は、リーダーシップや組織マネジメントなどの研究でも知られる京都大学の関口教授に、インクルーシブ・リーダーシップのあり方や実践についてお話を伺いました。

京都大学経営管理大学院副院長、大学院経済学研究科教授(兼任)
大阪大学大学院経済学研究科教授等を経て2016年より現職。専門は組織行動論および人的資源管理論。欧州アジア経営学会(EAMSA)会長、日本ビジネス研究学会(AJBS)会長、国際ビジネス学会(AIB)アジア太平洋支部理事、学術雑誌Applied Psychology: An International Review共同編集長、Asian Business & Management副編集長、European Management Journal副編集長等を歴任。共編著書に『国際人的資源管理』(中央経済社)、共監訳書に『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(日本能率協会マネジメントセンター)がある。
「みんなと同じ」と「みんなと違う」の両立を追求する
はじめに「インクルーシブ・リーダーシップ」とは、どういったリーダーシップなのでしょうか?
関口さん
インクルーシブ・リーダーシップとは、あらゆるタイプの多様なメンバーをすべて組織内に包摂(インクルージョン)することを志向する施策を打っていくリーダーシップです。
インクルージョンには一見すると矛盾している2つの次元があります。
1つは「みんなと同じ」という感覚。自分が会社で排除されておらず、「組織の一員だ」と所属意識を感じられる状態です。
もう1つは「みんなと違う」という感覚。自分には個性があり、違いを活かして実力を発揮できていると感じられる状態です。
たとえば異なる文化的背景をもつ外国籍社員がいたとします。その人が社内でほかのメンバーと同様に扱われているとしても、周囲の社員と同じ働き方を求められ、個性を一切活かせていないとしたらインクルージョンとは言えません。
逆に自分の個性は発揮できているけれど、それゆえに「違う集団」と見られて所属感が薄い場合もあてはまりません。
「みんなと同じ」と「みんなと違う」という矛盾の両立を志向するのがインクルーシブ・リーダーシップの役割です。
インクルーシブ・リーダーシップが必要になる背景を伺えますか?
関口さん
大きく2つあります。1つは社会的な側面です。企業には不平等や差別をなくし、公平性を追求する責任があります。これは企業として当然取り組むべき課題です。
もう1つはビジネスの側面です。人口減少やグローバル化が加速するなか「大卒・男性・正社員中心」という従来型の人材構成では、組織の持続的な成長は望めません。性別や国籍、年齢なども多様な人材の力を活かし、違いを強みに変えられなければ、グローバルの競争における優位性は保てないでしょう。
ダイバーシティの段階に応じたリーダーシップが必要
インクルーシブな組織風土をつくるには、どのような要素が必要なのでしょうか?
関口さん
インクルーシブな組織風土には3つの重要な要素があります。
1つ目はリスペクトです。違いをネガティブに捉えるのではなく「違うからこそ学べることがある」「違いが組織にとってプラスになる」と積極的に受け入れる姿勢です。
2つ目はフェアネスです。すべての人に対して公平な機会を提供することです。
3つ目は意思決定における参加です。意思決定のプロセスから誰も排除されることなく、参加できる環境を整えることです。
これらの要素を実現できるリーダーがインクルーシブ・リーダーと言えます。
私たちの最近の研究では、とくに「組織エンベデッドネス(組織への埋め込まれ感)」という概念に着目して、インクルーシブ・リーダーシップのあり方を整理しました。
そもそも組織は無意識のうちに、特定の人々を排除してしまう力が働きがちです。たとえば、日本企業で外国籍社員の離職率が高いのは、この排除のメカニズムが働いているためです。
このメカニズムを紐解くうえで鍵となるのが「組織エンベデッドネス」という概念です。なぜ人は組織にとどまるのかを捉えるうえで役立ち、以下の3つの次元で構成されています。
・対人的つながり:組織内の人々との関係性や、プロジェクトへの参加度合い
・組織との適合性:組織と個人の価値観の一致度
・リソース:組織を去ることで失いたくないリソース
組織においてマイノリティはエンベデッドネスを築きにくい傾向にあります。そのため人間関係を築けず、実力を発揮できないまま離職してしまうことが少なくありません。そこで私たちの最近の研究では、組織エンベデッドネスの考え方をダイバーシティの文脈に適用したのです。
どのように組織の多様性の段階によって、リーダーの役割が変わってくるのでしょうか?
関口さん
インクルーシブ・リーダーの役割は、組織のダイバーシティの度合いによって3段階で変化します。
【組織のダイバーシティの3段階】
画一型組織 | 大多数が支配的社会集団(マジョリティ集団)に属する従業員から成り立っているために均質的ではあるが、少ないながらも周縁的社会集団(マイノリティ集団)に属する従業員が一定数存在する組織 |
|---|---|
多元型組織 | 支配的社会集団に属する従業員と、主に組織の低階層において複数の周縁的社会集団に属する従業員が共存しているような組織 |
多文化型組織 | 組織のあらゆる階層に様々な社会集団に属する従業員が存在し、それゆえ多様性が高く、インクルーシブな環境を有しているような組織 |
(引用)『インクルーシブ・リーダーシップと組織的エンベッデッドネスを通してダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)を促進する理論モデル』
画一型組織の段階では、マジョリティのマインドセットを変え、マイノリティを取り込む意識を醸成することが最優先です。
多元型組織の段階では、たとえば「アジア人グループ」「ヒスパニックグループ」といったサブグループ間の対立が生じます。この段階ではグループ間の協力関係を促進し、互いの強みを活かしたコラボレーションを生み出すことが重要です。
多文化型組織の段階では、マジョリティ・マイノリティの区別が薄れます。ここでは個々の独自性も大切にしながら、「私はA社の社員です」という組織としての一体感を育むバランス感覚が求められます。
つまりインクルーシブ・リーダーシップとは画一的なものではありません。組織の排除メカニズムを理解したうえで、多様な人材の組織への溶け込みを妨げる障壁を状況に応じて適切に取り除いていく。そうした動的なリーダーシップのあり方なのです。

(引用)『インクルーシブ・リーダーシップと組織的エンベッデッドネスを通してダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)を促進する理論モデル』
ダイバーシティに伴うパラドックスを受け入れ、乗りこなす
最後に、これからダイバーシティ推進に取り組む企業へのアドバイスをお願いします。
関口さん
私たちの研究が示すように、組織のダイバーシティは段階的に発展していきます。そのため、自社が今どういうステージにいるのかを正確に把握する必要があります。また、次のステージに進むにはどうすればいいのかを描くのも重要です。それがなければダイバーシティのない状態にとどまり続けてしまうからです。
ただし、ここで理解しておくべきなのは、基本的にダイバーシティが高まれば高まるほど、組織運営は複雑さや困難さを増すということです。
多くの日本企業が置かれている単一型組織の段階では、マジョリティのマインドセットを変えることが主な課題。解決は簡単ではありませんが、少なくとも構造は明確です。ですが、ダイバーシティが進むにつれてグループ間の対立や価値観の衝突など、課題は複雑さを増していきます。場合によっては、一時的に企業の業績が低下するリスクもあります。
だからこそ、ダイバーシティ推進はいうほど簡単ではないという認識は重要です。表面的な「高めましょう」という言葉では実質的な変化は起きません。困難を理解したうえで、それでもやる覚悟と段階に応じた適切なマネジメントが不可欠です。