人事に活かせる哲学は「無知の知」を認めるところから始めよう!
- 公開日

目次
 品川皓亮(しながわ・こうすけ)さん
品川皓亮(しながわ・こうすけ)さん1987年、東京都生まれ。京都大学法科大学院を修了後、弁護士としてTMI総合法律事務所で勤務。その後、株式会社LiBに転職し、キャリア支援や採用に関する新規事業に携わり、人事部門の責任者も担う。株式会社COTENにも所属し歴史調査に従事するかたわら、自身で『日本一たのしい哲学ラジオ』を発信。ApplePodcastの哲学カテゴリーで1位を獲得する。著書は『日本一やさしい法律の教科書』、『日本一やさしい条文・判例の教科書』(いずれも日本実業出版社)など。2021年より妻と子ども4人と大分市で暮らす。
 坪谷邦生(つぼたに・くにお)さん
坪谷邦生(つぼたに・くにお)さん1976年、福岡県出身。立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業に就職。2001年、人事部門へ異動し、人事マネジャーなどを経験する。2008年、株式会社リクルートマネジメントソリューションズで人事コンサルタントとなり、50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として株式会社壺中天を設立。主な著作は『図解 人材マネジメント入門』、『図解 労務入門』(いずれもディスカヴァー・トゥエンティワン)など。ポメラニアン好き。
「人事・労務の仕事がグッと深まる異分野トーク」は、領域外で活躍する方の経験を通じて、人事・労務の担当者が仕事に活かせる考え方やハウツーを学ぶ連載企画です。
第2回目のテーマは、「人事×哲学」。X(旧Twitter)で『人事のための哲学スペース』を発信し、注目を集めている坪谷邦生さんと品川皓亮さんに、前後編と2回にわたってお話を伺います。
前編では、人事は重大な意思決定をするときほど、哲学に導き出された「持論」をもつべきだというお話が展開されました。続く後編では、「持論」にどう磨きをかけていくのか、坪谷さんと品川さんが語らいます。
「それってあなたの主観ですよね」で問題なし
前編では、人事は哲学をヒントにして、持論をもつことの大切さがわかりました。ちなみに、お二人は具体的にどのようにして持論をもたれたのでしょうか?
坪谷さん
私自身は、ある事柄を「経験」をしてから「概念」に気づくことが多いです。
前編でお話しした大学時代の手品サークルの例ですが、その後、私は師匠からサークルを受け継ぎ、2代目のトップになりました。そこで私は、師匠にならい「今度は300人規模のホールを借りよう」「そこではこんなエンターテイメントショーをやろう」と指し示しました。すると、それが思った以上に成功して、実践値を積み重ねていった結果、「リーダーは指し示すことが大事だ」と、自分なりの持論ができあがっていったんです。
品川さん
僕は、知識と経験のどちらが先に来てもいいと思っています。あらかじめ、本を読んで知り得たことが実際に起き、「本に書いてあるとおりだった」と、持論になる場合もあれば、坪谷さんのように、経験を積み重ねた結果、傾向に気づくケースもあります。
ただ、哲学の本を読んでいるだけだと、難しい内容も多く、なかなか自分ごととしてつながりにくい側面もあるんですよね。でも、人事の視点をもって哲学を学んでみると、見え方が変わってくると思います。たとえば、前編でお話しした「中庸」についても、人事が経営者と現場で板挟みになっているときに読めば、「なるほど、このようなときには中庸をとればいいのか」と腹落ちしやすいでしょう。

人材系のベンチャー企業に勤務するほか、歴史調査や哲学など幅広く活動する品川皓亮さん
ですが、そうして積み上げていった持論自体が間違っていたらと思うと不安です。
坪谷さん
まったく問題ありません。大前提として、持論は「正しい・間違っているを超える」ものです。仮に、ほかの人に持論を言って、「それってあなたの主観ですよね」で退けられるものでいいんです。だって、持論ですから。
いま、客観的なデータはいくらでも集められます。何か調べようと思ったら、AIチャットを使えば、瞬く間にエビデンスをそろえられます。それより、人事担当者であれば「自分が考える人事としての美学、つまり持論に照らして、その考えが納得のいくものかどうか」を問いかけてほしい。なにが正しくて、なにが正しくないのかは一度置いてください。
自分なりの持論を、他者の意見や客観的なデータで磨き上げるイメージです。主観としては納得いかないが、客観的には正しいこと、それは「妥協」です。主観自体を磨き、客観との統合を狙いましょう。そのために、まずは持論を仮説としてぶつけてみましょう。他者の意見や客観的なデータが集めやすくなり、持論にも磨きがかかるはずですよ。
品川さん
非常に興味深い問いをいただいて、僕はワクワクしています。僕にとっても持論は、変更したり訂正したりする可能性があるものです。
たとえば、僕や坪谷さん、そしてほかの学者も、そもそも誰1人としてアリストテレスの「中庸」を100%は理解していないと思うんです。真の意味で理解しているのは、おそらくアリストテレス本人だけではないでしょうか。
思想だけでなく、目の前に置いてあるスマートフォンもそうです。仮に、画面を上にして置かれていたら、僕たちは裏側がどうなっているのかはわからない。つまり、物であっても、概念であっても、すべての観点から「完璧に」捉えるのは不可能です。そうした前提で、「私はここから見ます」「私はこう感じました」でいいと思うんです。
全員にとっての真実を並べて、初めて浮かび上がる世界
なるほど、持論は随時アップデートしていくものなのですね。
品川さん
むしろ、どんどん訂正してほしい。『人事のための哲学スペース』の初回でアリストテレスの中庸について語りましたが、僕が今後さらにアリストテレスについて学び彼に対する見方が変われば、スペースで話したことを訂正する可能性もあると思っています。
坪谷さん
会社組織においても同様で、経営者や責任者が、企業のありとあらゆることを完璧に理解しているわけではありません。自分も相手も「無知である」ということを知っておいたほうがいいですね。では、そうしたなかでどう意思決定をするのかと言うと、やはり主観が必要です。
品川さん
まさに、「哲学の父」とよばれる古代ギリシャの哲学者・ソクラテスが重視する「不知の自覚」ですね。「無知の知」という格言としても有名です。
坪谷さん
まさしくそのとおりです。一度、自分が無知であることを認めたうえで、会社、経営者、現場のことを知ろうとすれば、より多くの知識を吸収できますし、結果として持論も磨き上げられます。
持論をもつことに、勇気が出てきそうです。
品川さん
ちょっとこの辺り、論を重ねちゃっていいですか?
坪谷さん
どうぞ、どうぞ。
品川さん
「群盲(ぐんもう)象を撫(な)でる」というインド発祥の古い寓話があります。目の見えない人たちがゾウに触れ、「あなたが触ったものは何か?」と問われたときに、足に触れた人は「柱のようです」と答え、尾を触った人は「綱のようです」と答えた、という話です。
通常、この寓話は、「物事の一面だけを知っただけで全体像を理解したと誤解する」というような、ネガティブな文脈で使われることが多いと思います。

(画像引用:Wikipedia)
品川さん
しかし、僕はこの話は、とてもポジティブな意味で解釈できると考えています。
人によって感じ方や捉え方が異なるのは、決して悪いことではありません。むしろ「自分はこう感じた」「でも、あなたはそう思ったんだね」という事実をつなぎ合わせていけば、たとえ目が見えなくても、一つの立体的な象のイメージができ上がるかもしれない。さらに言えば、みんなの知見をもち寄って、一つの事象についてズームアップしたり、俯瞰したりしてみると、見える世界はもっと変わってくるかもしれない。僕は、こういった対話を楽しみたいと思っています。
坪谷さん
人事という文脈になぞらえると、まさに「対話型組織開発」そのものですよね。「私が触ったところは硬かったのに、“綱のよう”と言う品川さんはおかしい」というスタンスでは、対話にならない。「あなたはそう感じたのですね」から対話を進め、解としての「象」を浮かび上がらせていく。大切な姿勢ですよね。
品川さん
それに、一度「柱のようだ」と答えた人も、尾を触ったら「やっぱり綱だった」と思うかもしれない。いろんな意見があったとしても、どれも真実なんですよね。
坪谷さん
社会構成主義ですね。「現実は人々の頭のなかでつくられる」という考え方です。人はそれぞれの価値観というメガネを通して現実を認識しているため、必然的に現実の見え方や認識が異なるわけです。

人事・労務担当に向けて、著書の出版や人事塾の主催など多岐にわたり活動する坪谷邦生さん
「私には御社がこのように見えています」が正しい理由
「私はこう思う」。たしかに、理屈としても間違いではないですね。
坪谷さん
実際、私がクライアント企業に提案をする際、「私には御社がこのように見えています」という表現をよく使います
品川さん
わかります!僕も社内のミーティングで、「この課題は、僕からはこう見えています」というようなことをよく言います。
僕から見えた景色が「客観的に正しい」かはわかりませんが、少なくとも、僕からそのように見えていることは、課題を解決するための一つのヒントにはなるはずなので。
坪谷さん
25年にわたって人事の経験をし、数々の企業を見てきた私にとって「御社はこう見えます」というのは、紛れもない事実です。するとお客さまは「なるほど、坪谷さんにはそう見えているんですね」というスタンスで私の提案を聞いてくれます。
ただ、注意点としては、「あなたは、いったい何を言ってるの?」と思われるような主観にもとづく提案なら、ビジネスにはならない。つまり、主観に説得力をもたせるためにも、やはり持論を磨いていかないといけないんです。
『人事のための哲学スペース』をもう一度聴き直したいと思いました。
坪谷さん
ありがたいことに、予想以上の反響がありました。『人事のための哲学スペース』を始める際、品川さんと「一度やると決めたなら、誰も聴いてくれなくても最後まで続けよう」という約束をしていました。でも、いざやってみたら、第1回目でログを聴いてくれた人が600人、第2回目で2,500人とどんどん増えていって。
品川さん
うれしいですよね。私の周りでも、人事の方はもちろん、経営者の方もたくさん聴いてくださっているようです。
坪谷さん
感想のなかで「2人が楽しそうに話しているのがおもしろくて、気がつくと最後まで聴いちゃいました」といったものも多くて。おじさん2人が楽しそうにしゃべっている『人事のための哲学スペース』に、こんなにニーズがあるとは思っていなくて、ちょっとびっくりしています(笑)。
品川さん
僕自身は、坪谷さんと出会う前に始めていたポッドキャスト『日本一たのしい哲学ラジオ』を配信した経験から、「自分たちが本当にいいと思うものを話せば、きっと伝わる」と感じていました。もちろん、初めて哲学に触れる方も多いはずなので、知識量などは調整しています。
とはいえ、たくさんの方が楽しんでくださっていると知って、とても光栄に思っています。

めざすは人文知の総合商社
『人事のための哲学スペース』は全12回分がいったん終了したとのことですが、今後のご予定はいかがでしょうか。
坪谷さん
実は、『人事のための哲学スペース』を始める前に、品川さんと人事と哲学をテーマにした本を書きましょうという話をしていたんです。ですので、次は書籍化に向けて動いていくと思います。
私は「90歳で現役のプロ」というのを目標にしています。その夢に向けて、70歳で1冊、自分にとって理想の本を出せたらいいなと考えています。いままではずっと人事に関する本を執筆してきましたが、この本は人事領域を越え、哲学書になるのではと感じています。
品川さん
個人の活動として、僕は哲学をはじめ、人文知を世の中にもっと広めていきたいと思っています。
先にもお伝えしたように、哲学には解釈が難しいものも多く、解説書を読んでもピンとこないものばかりです。たとえば、ニーチェが説いた「力への意志」の解説で「我がものとし、支配し、より以上のものとなり、より強いものとなろうとする意欲」と書かれていても、「だから何?」としか思えないですよね(笑)
そんな時、僕は現代の社会や自分が人生で経験してきたことに照らして、多くの人が「なるほど、そういうことか!」と納得しやすいように解釈をし直して、ニーチェが本当に伝えたかったことを届けたいと思うんです。自分なりに魂を込めた哲学の意義を伝えて、哲学のおもしろさを世に広めていきたいですね。
たしかに、『人事のための哲学スペース』をきっかけに哲学に興味をもった人も多いと思います。
品川さん
人文知を社会の実践知に変換する役割を担うため、僕は今後、「人文知の総合商社」のような動きをしていくのかな、と思っています。
イメージとして、豊かな人文知の油田が、砂漠の果てにあるとします。普通の人は容易にそこへはアクセスできないので、代わりに僕がその油田に赴き、原油を日本にもち帰る。そして、それらをガソリンにしたり、灯油にしたりと使いやすい形に加工し、パッケージ化していく。今回の『人事のための哲学スペース』はまさにそうです。
実はいま、自宅兼“哲学図書館”の立ち上げを進めています。大分市で建設を進めていて、完成すれば人文知にどっぷり浸れる空間ができるのでは、と考えています。
坪谷さん
「人事のための哲学スペース」を行えたことで、哲学が人事には必要だという実感がさらに強くなりました。いま、品川さんと一緒に「人事の基礎五教科」という講座を構想中です。中庸・縁起・弁証法などの人事の皆さんに絶対に知って欲しい5つを、人事の実践として学べる講座です。
人事のあなたが自分の道を指し示そう
今日のお話を受けて、なんだか悩みが晴れ、ぱっと道が開けたような気がします。
坪谷さん
そう思われたならぜひ、『人事のための哲学スペース』の第4回の禅(十牛図=じゅうぎゅうず)を聴いていただきたいですね。

聴いてみます! 最後に、人事職として働く人たちにメッセージをお願いします。
坪谷さん
「人を生かして事をなす」のが人事の仕事です。この「人」のなかには自分も含まれているのですが、人事はついほかの人を生かすことばかりを考えてしまいがちです。まずは、あなた自身を生かしてほしい。あなたを満たしてほしいのです。そのために、大切なのは持論です。主観を磨こう、自分の道を自分で指し示しましょう。それが、私からのメッセージです。
品川さん
ときどき、哲学って何だろうって考えます。そこで出た一つのキーワードは、「自由」です。東洋西洋問わず、人間の「自由になりたい」という心の叫びが哲学に結びついていると僕は感じています。
では、自由を得るためにはどうすればいいか。やはり、考え、問い続けることです。そうした試行錯誤を続けた結果、自分のなかに答えが導き出されて、実行する勇気がわいてくると思うんです。僕は、そんな勇気こそ、哲学を学んで得られる最大の果実だと感じています。
(取材・文/土橋水菜子、POWER NEWS編集部、写真/横関一浩)
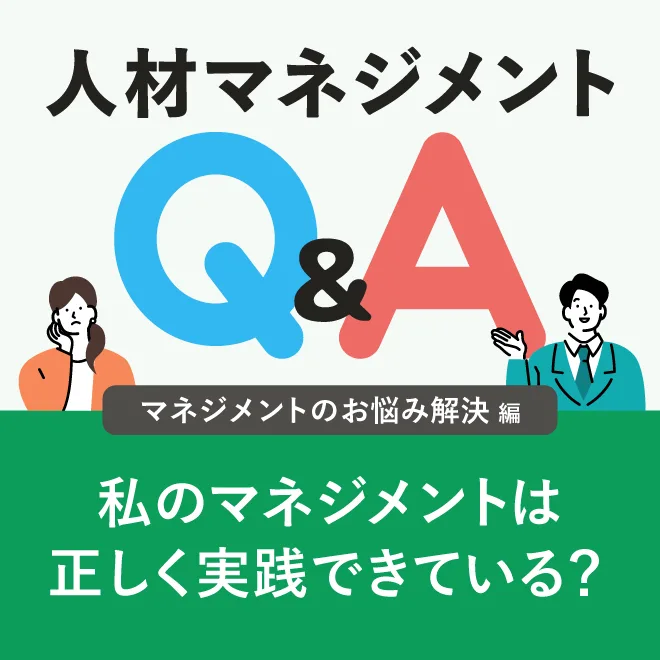
お役立ち資料
人材マネジメントQ&A マネジメントのお悩み解決
この資料でこんなことがわかります
- ネガティブフィードバックのやり方は?
- 1on1で部下の本音を引き出すには?
- パワハラとの線引きはどこ?
- 目標達成に向けて動いてもらうには?



























