哲学的な思考が役に立つ。人事担当者がもつべき「持論」のすすめ
- 公開日

 品川皓亮(しながわ・こうすけ)さん
品川皓亮(しながわ・こうすけ)さん1987年、東京都生まれ。京都大学法科大学院を修了後、弁護士としてTMI総合法律事務所で勤務。その後、株式会社LiBに転職し、キャリア支援や採用に関する新規事業に携わり、人事部門の責任者も担う。株式会社COTENにも所属し歴史調査を担うかたわら、自身で『日本一たのしい哲学ラジオ』を発信。ApplePodcastの哲学カテゴリーで1位を獲得する。著書は『日本一やさしい法律の教科書』、『日本一やさしい条文・判例の教科書』(いずれも日本実業出版社)など。2021年より妻と子ども4人と大分市で暮らす。
 坪谷邦生(つぼたに・くにお)さん
坪谷邦生(つぼたに・くにお)さん1976年、福岡県出身。立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業に就職。2001年、人事部門へ異動し、人事マネジャーなどを経験する。2008年、株式会社リクルートマネジメントソリューションズで人事コンサルタントとなり、50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として株式会社壺中天を設立。主な著作は『図解 人材マネジメント入門』、『図解 労務入門』(いずれもディスカヴァー・トゥエンティワン)など。ポメラニアン好き。
「人事・労務の仕事がグッと深まる異分野トーク」は、領域外で活躍する方の経験を通じて、人事・労務の担当者が仕事に活かせる考え方やハウツーを学ぶ連載企画です。
第2回目のテーマは、「人事×哲学」。今回お招きしたのは、人気コンテンツ『日本一たのしい哲学ラジオ』を運営する品川皓亮さんと、『日本の人事部 HRアワード2020 書籍部門』に入賞した『図解人材マネジメント入門』の著者、坪谷邦生さんです。お二人は「人と事、現場と経営、短期と長期…葛藤の多い人事に、いま必要なのは哲学だ!」をコンセプトに、人事と哲学を絡めたポッドキャスト『人事のための哲学スペース』を発信して注目を集めました。
品川さんと坪谷さんは人事の責任者を担ったり、書籍を出版したりとまさに人事のプロフェッショナル。そんなお二人はなぜ哲学に興味をもったのか。どうして、人事に哲学が必要なのか……。これらについて、前後編に分けてたっぷりお届けします。
人事のプロ2人が届ける音声メディア
まずは、品川さんのご経歴やお仕事についてお聞かせください。
品川さん
いま、僕が取り組んでいることは大きく分けて3つあります。1つ目は、株式会社LiBというベンチャー企業でキャリア支援や採用に関する事業に携わっています。2つ目は、世界史データベースの研究・開発をしている株式会社COTENの歴史調査チームに所属しています。
そして3つ目は、今回のテーマ、哲学です。僕は哲学が大好きで、哲学を社会にどう実装できるかを探求しつつ、2年ほど前から、Aqua TimezというロックバンドのドラマーであるTASSHIさんと一緒に、ポッドキャスト『日本一たのしい哲学ラジオ』を発信しています。2024年10月からは、今日ご一緒している坪谷さんと『人事のための哲学スペース』もスタートしました。
常日頃から、哲学について誰かに話したくて話したくて……今日は呼んでいただき、ありがとうございます。僕は大分市在住なのですが、うれしくて飛行機で飛んで参りました。

人材系のベンチャー企業に勤務するほか、歴史調査や哲学など幅広く活動する品川皓亮さん
お越しいただきありがとうございます! ぜひ今日は哲学について存分に語ってください。つづいて坪谷さんのご経歴とお仕事についてお聞かせください。
品川さん
ありがとうございます! しゃべりつづけてしまいそうなので、坪谷さんにバトンを渡します。
坪谷さん
伝えたいことが多すぎて、“蛇口”の調整が難しいですよね……。コンパクトにまとめます。
私は大学卒業後、エンジニアとしてキャリアをスタートしました。当時勤めていた会社でマネジメント不全を感じ、人事部門の立ち上げも経験しています。以来、エンジニア職から人事職に転身し、25年間ずっと人事畑を歩んできました。その後、転職したリクルートマネジメントソリューションズでは8年間コンサルタントを務め、50社以上の企業を支援しました。
現在は、株式会社壺中天を立ち上げ、企業の顧問やアドバイザーなどを行っています。同時に「壺中人事塾」を運営し、卒業生も100名以上になりました。

人事・労務担当に向けて、著書の出版や人事塾の主催など多岐にわたり活動する坪谷邦生さん
つづいて、ポッドキャスト『人事のための哲学スペース』について教えてください。
品川さん
『人事のための哲学スペース』はX(旧Twitter)のスペースで隔週火曜日の1時間、毎回人事と哲学を絡めてテーマを1つ設定し、話し合ったものです。ニーチェの「超人」、ヘーゲルの「弁証法」、龍樹の「縁起」など、西洋・東洋のさまざまな思想を扱いました。現在は、用意した全12回分が一通り終了し、Spotifyでまとめて公開しているので、ご興味があればぜひ聴いてみてください。
哲学に着目したきっかけは対人関係の悩み
哲学に目覚めたのは、どういった経緯がありましたか。
坪谷さん
いったん小学生のころまで遡りまして。幼少期、私は自分が考えていることが相手になかなか伝わらないという悩みをもっていました。そうしたなか、出会ったのが心理学者のユングの性格(タイプ)論です。現代では性格検査「MBTI」が有名になりましたね。本で自分のタイプを初めて知って、「だから、自分の声はほかの人に届きにくいんだ」と気づいたんです。
小学生がユングの本を手に取った理由が気になります。
坪谷さん
私の母は図書館で勤めていたこともあり、ものすごく本を読む人だったんです。その影響で、家にはたくさんの本がありました。私にとって、本はとても身近な存在だったので、ユングをはじめ、さまざまな書籍を手に取っては「学校の友達より、アリストテレスのほうが気が合うなあ」と感じていました。
アリストテレスのほうが気が合いそう……おもしろいですね(笑)。
品川さん
僕も、初めて哲学に触れたのは小学生のころです。当時、思想家のヴォルテールが言ったとされている「あなたの意見に賛成できるところはないが、あなたがそれを発言する権利だけは、私は命をかけても護るつもりです」という言葉に深く感銘を受けたのを覚えています。
これまた、小学生がヴォルテールに出会い、感銘を受けたのですね。
品川さん
僕の場合は、名言集のようなものを読んだのかもしれません。何を読んだのかまでは忘れてしまったのですが、その言葉をメモにとって、ヴォルテールの顔のイラストを描いて、トイレに飾ったことは鮮明に覚えています(笑)。
すごい、飾ってまで。
品川さん
坪谷さんとはタイプが異なるかもしれませんが、男ばかりの4兄弟の末っ子で、兄たちとは年の差もあり、僕もずっと言いたいことを言えない幼少期を過ごしていました。「僕のほうが絶対正しいのに」「でも、言えない」みたいな。だから、ヴォルテールの言葉がとても胸に響いたんです。実際に、この言葉をヴォルテールが言ったかどうかは、諸説があるのですが。
僕は仏教などの東洋哲学にもとても興味があります。母が鍼灸マッサージ師で東洋医学に詳しかったため、西洋の科学的な考え方とは異なる思想にも触れる機会があったからだと思います。けがをしたとき「手を当てておけば治るんだよ」と教わったのが印象的で、東洋の思想に興味をもつきっかけだったのかもしれません。
坪谷さん
まさに賃金にも関係する「手当」ですね(笑)。

坪谷邦生さんがお勧めする哲学関連の著書。とくに野中 郁次郎、紺野 登(2007年)『美徳の経営』(エヌティティ出版)はアリストテレスの考えを人事に生かすヒントが詰まっているという
哲学は人事の「ど真ん中」
お二人の意気投合っぷりをひしひしと感じているのですが、知り合ったきっかけは何でしたか。
坪谷さん
たしか、1年前くらいでした。共通の知人から「絶対に気が合う人がいるから、会ってみて」と紹介され、リモートで初めて品川さんとお話ししたんです。
初対面にもかかわらず、とても話が盛り上がったのを覚えています。
その後どういった経緯で「人事と哲学」というテーマで対話を始めたのでしょうか。
品川さん
繰り返しになりますが、哲学ってすごくおもしろいんです。だけど、哲学をどう社会に生かしていくのかまでは、正直わからないことも多くて。僕は、社会の役に立つから哲学を勉強しているわけではなく、純粋に哲学が好きだから学んでいます。一方で、せっかく勉強しているなら何らかの形で社会に還元できたらうれしいという思いもありました。
そこで坪谷さんに「哲学を人事に生かすことができないか」と相談したところ「むしろ、哲学は人事のど真ん中じゃないですか?」と言ってくれたんです。
坪谷さん
そうそう、私からすると、品川さんの問い自体が不思議だったんです。「人事と哲学は直結してますよね。反対にどこで切れているのでしょう?」という気持ちでした。その場で「人事×哲学」で何かをやろうという話になりました。
品川さん
その後、2024年の春に直接お会いしました。たしか、17時くらいに坪谷さんのオフィスに伺って、夕食を一緒に食べようって言ってたんですよね。でも話が盛り上がりすぎちゃって……。
坪谷さん
結局、21時くらいまでオフィスで話していました。
品川さん
「お腹すいたな〜」っていう記憶が鮮明に残っています(笑)。でも、それくらい盛り上がったんですよね。僕は「ここで話した内容は、そのままコンテンツになる」という手応えを感じていました。それからは、どんな切り口で話すかなどのコンセプト決めには半年ほど要しましたが、『人事のための哲学スペース』のスタートまで、スムーズに進みました。

品川皓亮さんがお勧めする書籍は、梶谷真司(2018年)『考えるとはどういうことか』(幻冬舎 )。哲学の本質である「考え、問いつづける」ことの大切さを教えてくれるという
「人事のプロフェッショナル」の条件
人事にとって、哲学が有意義な理由を教えてください。
坪谷さん
人事は、「人と事」「現場と経営」「短期と長期」……と間に立たされる局面が多い仕事です。ロジックや知識だけでは解決しない問題に直面したとき、自分は何をもとにして判断するのかという基準、つまり“持論”が必要になります。
私は自分のなかにこの基準をもっている人を「人事のプロフェッショナル」とよんでいます。とはいえ、そもそも持論をもつこと自体が難しい。そこで、その持論をもつために役に立つのが哲学だと私は考えています。
品川さん
僕も坪谷さんの「持論をもつべき」というメッセージにはとても共感しています。僕自身、LiBという会社で人事の責任者を担っていましたが、ときに人事の立場から経営者や社員に「NO」を言わなければならない局面がありました。
それって、一介の平社員である人事担当者にとってはすごく勇気がいることです。そんなときに自分の信念はもちろん、いろんな思想家たちの考えから導き出された持論をもっていれば、勇気のある決断ができるんです。
持論とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
坪谷さん
たとえば、私の持論のひとつに「指し示す」ことがあります。人事やリーダーは自分のなかで基準をもって、「こっちだよ」と方向を示すことが大切だと考えています。
初めてそれに気がついたのは、大学生のときでした。のちに私の師匠となる、ある先輩が立ち上げた手品のサークルに所属していたのですが、彼がサークルの運営や組織づくり、めざすべき方向性をまさに指し示してくれました。それは彼の主観、強い想いから出てくるものだったのです。その主観に乗って一緒にマジックショーを創っていくのですが、それが本当におもしろかった。
ちょうど同じころ、大学のあった京都の若王子(にゃくおうじ)橋と銀閣寺橋の間を結ぶ『哲学の道』を歩いていると、日本で初めての哲学者であると言われる西田幾多郎の石碑を目にしました。そこに「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」と書いてあったんです。まさに指し示すことだと、ハッとしましたね。他者がどうであるかは関係ない。自分で決めて、自分の道を進むべきだ、と受け止めたのです。
以来、私の根幹となる持論は「指し示す」となり、写真を撮るときも必ず指を1本立てるポーズをとるようにしています。

持論を「指し示す」、いつものポーズをとってくださる坪谷さん
まずは思想家たちの考え方を知る
人事が持論をもつためには、どうすればいいのでしょうか。
坪谷さん
先ほど、品川さんが「いろんな思想家たちの考えから導き出された持論をもっていれば、勇気のある決断ができる」とおっしゃっていたように、まずは思想家たちの考え方を知っておくのも一つの解だと思います。
品川さん
そういった意味でも、『人事のための哲学スペース』の第1回目でお話しした、古代ギリシャの哲学者・アリストテレスが説いた「中庸(ちゅうよう)」はすぐに応用できますよね。
坪谷さん
中庸の教えは、たとえば「経営者はこう言っている」「現場はこう言っている」と、人事が経営者と現場の間に立たされたとします。その際、「経営者の言うとおりにやりましょう」でもダメだし、「現場に寄り添いましょう」だけでも人事としては足りません。
そのようなときに、「片側に寄らず、両者の真ん中をとる」「でも、その真ん中は決して足して2で割った平均ではなく、その時々にちょうどいい1点(=中庸)をとる」という考え方です。
品川さん
アリストテレスがすごいのが、思想だけではなく「How」についてまでも言及している点です。著作のなかで「中庸を定める際、自分はどちらに偏る傾向があるのかをまず知りなさい」「自分の偏りを認識したうえで、その反対側に少し寄せたくらいがちょうどいい」といった具体的なところまで言及してくれているんですよね。

坪谷さん
おっしゃるとおりです。もっと例を出せば、会社として事業成果をとるのか、個人の成長をとるのかといった場面があったとします。成果だけを狙うと、個人はやる気をなくしますし、反対に個人成長だけをとると、事業がうまくいかなくなる恐れがあります。そのとき、普段から事業成果ばかりを意識している会社なら、少し個人成長に寄せる。同様に、個人の成長に重きを置きがちな会社なら、ちょっとだけ事業側に寄せる。
そして、一度定めたからといって、そこで終わりではありません。実践はそこから始まっていて、常にインジゲーターを変えつづけるのがポイントです。都度、意思決定することで、リーダーシップが磨かれていくんです。
哲学、おもしろいですね。興味がわいてきました。
品川さん
古代ギリシャの時代、アリストテレスはポリスをはじめ、周囲の独裁国家など、さまざまな政治形態を観察していたと思います。そうして導き出された「中庸」という概念が、2千年以上後の現代に役に立つ。彼らの人生と、いまを生きる私たちが一本の線でつながるような気がして、やっぱり哲学を学ぶのは楽しいなと思います。
坪谷さん
概念と自分の経験を照らすと、「これまで考えてきたことは、カントの言う“自律”で説明がつく」とわかったりしますしね。同時に、自分の思考が及ばなかったことまで、やっぱり昔の哲学者は考えていることもあります。そうした発見をした瞬間、「よし、自分の持論をさらに磨けるな。しめしめ」なんて思っています。
記事の後編はこちら
(取材・文/土橋水菜子、POWER NEWS編集部、写真/横関一浩)
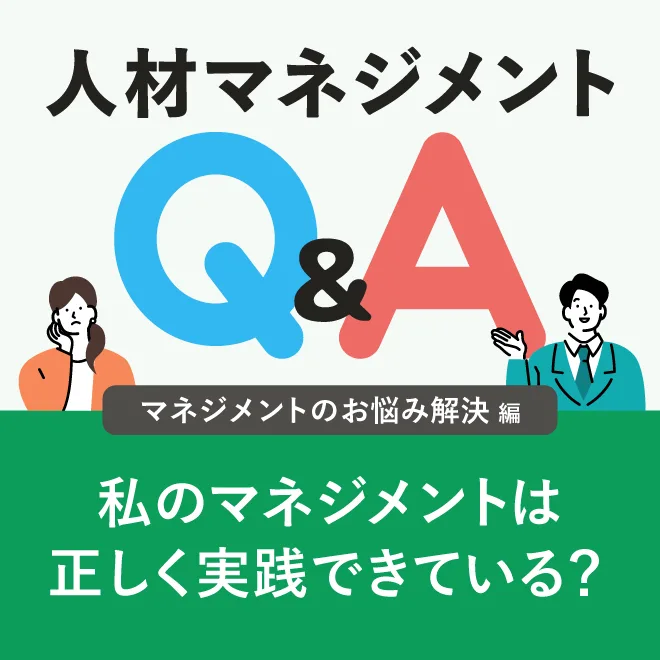
お役立ち資料
人材マネジメントQ&A マネジメントのお悩み解決
この資料でこんなことがわかります
- ネガティブフィードバックのやり方は?
- 1on1で部下の本音を引き出すには?
- パワハラとの線引きはどこ?
- 目標達成に向けて動いてもらうには?



























