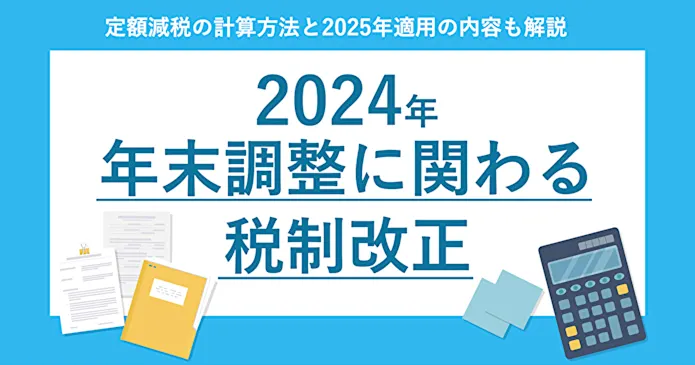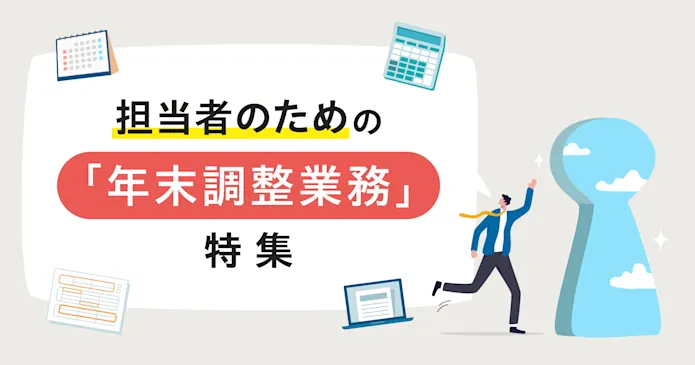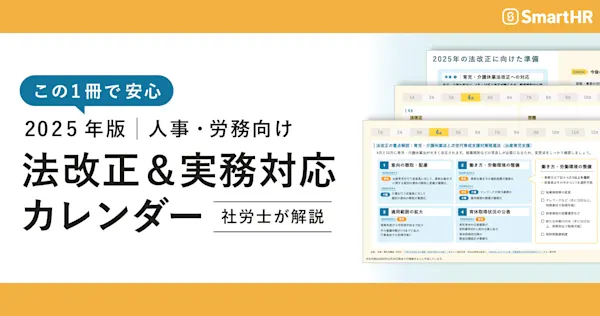年末調整「還付金」計算方法。仕組みや金額、貰える時期を解説
- 更新日
- 公開日

目次
こんにちは。特定社会保険労務士の山本 純次です。
今年も年末調整の準備は進んでいるでしょうか? 人事・労務の担当者にとって年末の一大イベントといえばやはり「年末調整」であり、毎年最大の繁忙期を迎えます。
従業員の方は、難しいながらもどうにかこうにか各種申告書を書き上げて提出し、税金が戻ってくるという楽しみを心待ちにされていることかと思います。今では情報をウェブで入力し作成できるシステムもあり便利になりました。
この年末調整時に発生する「還付金」は、どういった仕組みで、どのような人が受け取れるのでしょうか?
年末調整とは
年末調整とは、その年の1年の給与収入(転職があった場合、前職の収入を合算、賞与などの臨時の支給も含める)とそれまでに支払った所得税、社会保険料の合計を集計し、年末時点での扶養状況に応じて、扶養控除を再計算します。
加えて、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除など、法定で定められている控除を計算し、当年度の所得税を確定させます。
年末調整前まで1年間に支払った所得税が、調整後の金額より多かった場合、税金が戻ってくることとなり、これを「還付金」と呼んでいます。
還付金を受け取ること自体は嬉しいですし、人によってはちょっとしたお得感を覚えるかもしれませんが、実際に得をしているワケではないのでご注意ください。
「還付金」が発生するのはどういう人?
毎月の給与から控除される所得税は、年間の課税分より少し多く徴収されるよう設計されています。そのため、年末調整では多くの方が還付金が出るような仕組みになっています。
そのなかで、年末調整で控除として申請できる「生命保険料控除」や「住宅ローン控除」は毎月の給与での所得税計算では想定されていないので、申告をすると還付金が戻るケースが多いです。
また、年度途中に扶養対象者が増えた方について、年末調整では年末での扶養の基準で1年分の税金を計算しますので、還付が出るケースが多いです。
年末調整で「還付金」が発生する仕組み
月々の給与から源泉徴収している所得税は、課税対象となる支給額(基本給、残業代、インセンティブなど)から社会保険料を控除した額に対して、一定の控除額と、その月の扶養の人数に応じて税額表に該当する金額を控除しています。この金額は残業代や扶養の変更によって変動になりますが、年末調整では年間の支給額をもとに年間の税額を再計算するため、月ごとの計算との差額が発生します。
算出された所得税とそれまで徴収していた所得税の間に差が生まれ、年間の所得税のほうが低いときに還付金が発生する仕組みです。
還付金と年末調整の関係はさまざまです。たとえば、年度途中で結婚をして配偶者控除の対象となると38万円分の控除が受けられます。年末調整では、年末時点での扶養状況で1年分の控除が受けられるので、その結果、課税所得が減少するため、還付金が発生するのです。
また、生命保険や地震保険に加入していても、支払った保険料に応じて一定の金額が年末調整で控除されます。その場合、対象者は毎年10月前後に送付される保険料控除証明書の添付が必要となるので、事前に準備しておきましょう。
なお、年末調整で申告できる控除は決まっており、最近多くの方が利用されている「ふるさと納税」は、所得税ではなく住民税を振り分ける仕組みとなるため、年末調整では申告できません。
そのほかには住宅ローンを組まれている場合、年末のローン残高に応じて控除が受けられますので、11月頃には金融機関などから送付される書類を手元に準備し、申請に備えてください。
年末調整の「還付金」計算方法
還付金の計算方法を見ていきましょう。
(1) 給与と源泉徴収額を集計
まず、「給与と源泉徴収額の集計」を求めます。年間を通して受け取った給与、社会保険料、源泉徴収額の総計を明らかにします。給与額の集計のポイントとして通勤交通費や立替経費などは非課税の支給になるので含めないことになります。
また、賞与も含まれますが、副業など業務委託報酬で得たものは、年末調整では申告できません。その年の途中に転職した場合、前職から退職までの給与額などを集計した源泉徴収票が発行されるので、その金額も合計します。ここまでは、過去の給与明細などを照会すれば比較的簡単に算出可能です。
(2)給与所得控除後の給与を計算
次に、「給与所得控除後の給与の計算」を行います。給与等の支給額などの総計額に応じて、控除額を確定させていく作業です。社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)は、集計した金額がそのまま控除されます。また、年末時点での扶養者に応じて控除を受けたり、生命保険料、地震保険料、個人型確定拠出年金保険料などの控除を受けられます。
控除をしたうえでの金額が課税対象所得額となり、その金額に税率を乗じたものが年間の所得税額になります。この税率は所得が多くなるにつれて税率が上がるので、累進課税とも呼ばれます。
(3)算出した年税額から住宅借入金等特別控除額を差し引く
そして、算出年税額から住宅借入金等特別控除額を差し引くと、「年調年税額」がわかります。
後は、年調年税額と実際に支払われた税額を比べ、差があるときの調整額が還付金もしくは徴収金となります。
多くの方の場合、毎月の計算では控除対象にしていない生命保険料控除などの申告があるため、還付金が発生する仕組みとなっています。
このように還付金の算出には多くの工数が必要となります。確実にミスなく還付金を算出するためには、このタイミングで人事・労務領域で効率化するべき業務を整理してみてはいかがでしょうか。

人事・労務領域 効率化すべき業務チェックリスト
年末調整の「還付金」の具体的な算出方法
年間の給与所得が500万円の方を例に、具体的な数字で見ていきましょう。
「年間給与所得500万円」の場合の還付金は?
- 年間給与額:4,000,000円
- 年間賞与額:1,000,000円
- 年間社会保険料:730,000円
- 年間源泉所得税額:125,000円(D)
- 生命保険料控除:50,000円
- 扶養配偶者1名
(1)年間給与額計または給与所得控除額を計算し課税所得額を算出
課税所得額を求めます。年間給与額計か給与所得控除額を計算します。
- 50,000,000 – 1,440,000=3,560,000円(A:給与所得控除後の金額)
(2)各種控除を集計
- 社会保険料控除:730,000円
- 生命保険料控除:50,000円
- 扶養控除:380,000円
- 基礎控除:480,000円
- 控除計:1,640,000円(B)
(3)税額を計算
給与所得控除額の金額から控除額の合計を差し引き、税額を計算します。
- 3,560,000(A) – 1,640,000(B)×税率(5%)=96,000円
- 96,000円×102.1%=98,000円(C)※100円未満は切り捨て
(4)還付額を計算
年間源泉所得税額から税額を差し引いた金額が還付額となります。
- 125,000(D) – 98,000(C)=27,000円
- 結果:27,000円の還付
「還付金」はいつ貰えるの?
一般的には、年内最後の給与である12月の給与支払い時に、還付が実施されます。
また会社によっては、年内の収入が確定したうえで年末調整を実施し、その場合は1月に還付を実施されるケースもあります。
還付金とは逆に、追加で税金を支払うケースも
還付金があると思っていても、反対に追加で税金を支払わなければならないケースもあります。その例としては、年度途中に扶養者が外れたケースや、月額の給与額に比べて賞与の支給額が大きかった場合は、賞与の税率が低く抑えられ、年末時に不足が発生するケースもあります。
また、年度途中の転職で大きく収入が変動した場合に、追徴となるケースもあります。ただし、「還付金」が得をしているわけでなければ、こちらの追徴も損をしているわけではありません。あくまで毎月の控除で計算したものと、年間の正しい税額との差額を調整しているものになります。
「年末調整」というのは言葉のとおり、年末に当年度の所得税額を再計算し、調整する作業なのです。
年末調整Q&A
Q. 年末調整還付金何が戻ってくる?
年末調整前まで1年間に支払った所得税が、調整後の金額より多かった場合、税金が戻ってくることとなり、これを「還付金」と呼んでいます。
Q. 源泉徴収税額とは戻ってくる金額ですか?
毎月の給与から控除される所得税は、年間の課税分より少し多く徴収されるよう設計されています。そのため、年末調整では多くの方が還付金が出るような仕組みになっています。人によってはちょっとしたお得感を覚えるかもしれませんが、実際に得をしているワケではないのでご注意ください。

お役立ち資料
担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整
年々複雑化する年末調整に関するマニュアルのアップデートや、従業員からの質疑応答に大幅に時間を取られるなど、大量の書類管理に追われ残業が増えてしまう人事・労務担当の方も多いのではないでしょうか。
わかりやすくて使いやすいと好評のSmartHRのペーパーレス年末調整についてご紹介します。
【こんなことがわかります】
- SmartHRの年末調整はココが違う!
- 年末調整システム導入時の注意点

メールマガジン「週刊SmartHR Mag.」
社会保険労務士や弁護士など、人事・労務の専門家による実務に活かせる生の情報を発信していきます。メールマガジンでしか読めない専門家のこぼれ話なども掲載中です!