契約書に「暴力団排除条項」や「反社会的勢力の排除」が必要な理由とは?
- 更新日
- 公開日

2017年夏、各地の“お祭り”において「暴力団排除」に向けた動きが強化されました。
「暴力団排除」といえばお祭りだけではなく、皆さんも仕事や家を借りる時などに契約書で「暴力団排除条項」や「反社会的勢力の排除」といった文字を目にする機会も多いことでしょう。
今回は、契約書に「暴力団排除条項」や「反社会的勢力の排除」が必要な理由について解説します。
「暴力団排除条項」「暴力団排除条例」とは?
そもそも「暴力団排除条項」とはどのようなものなのでしょうか?
法務省の指針によると「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが記載されており、これを受けて、契約に「暴力団排除条項」(以下、「暴排条項」といいます。)を定める努力義務を規定した、「暴力団排除条例」が全国で施行されるに至っています。
では、暴力団排除条例で課せられているのはあくまで「努力義務」である中で、契約書に暴排条項を定めなかった場合の問題点はあるのでしょうか?
暴排条項がないと「レピュテーション・リスク」に繋がりかねない
暴排条項の定めがなくとも、「反社会的勢力による不当要求」を受けた場合は警察に相談する等の方法による対処は可能です。
しかし、反社会的勢力は民事法・刑事法上違法にならないように巧みに行動しますから、取引相手に反社会的勢力が含まれていることが後に発覚した場合、暴排条項によらずに債務不履行等に基づく契約解除は困難になります。
契約解除ができず、反社会的勢力との関係を継続していることは、企業の「レピュテーション・リスク(企業の信用やブランド価値低下のリスク)」となります。
また、会社の役員等の「善管注意義務違反」ともなり得ますので、取引相手が反社会的勢力である場合に、直ちに契約解除を可能とする暴排条項の定めは置くに越したことがありません。
「適切な暴排条項」の定め方とは?
契約に暴排条項を定めたとしても、相手方が反社会的勢力に該当することは「解除する側」が立証しなければなりません。そのため、そもそも暴排条項に基づく契約を解除をするには、実務経験とスピードが必要になります。
その上、暴排条項の定め方が適切でないと「解除の効力」も争われてしまうことがありますので、さらに反社会的勢力との関係遮断が困難になってしまいます。
「適切な暴排条項」定めるには、下記の要素が重要です。
- 「反社会的勢力」の定義が明確であること
- 当事者が反社会的勢力ではないことの表明・確約条項が入っていること
- 暴排条項に基づく解除は無催告で行えること、また、解除した側において損害賠償義務を負わないこと
なお暴排条項や表明保証・確約書の定め方については、以下のリンク先が参考になります。
上記の公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターのリンク先「暴力団対応ガイド総合版」は、反社会的勢力に対する具体的対応等についても記載がありますので、企業の法務担当部署の方は一読するとよいでしょう。
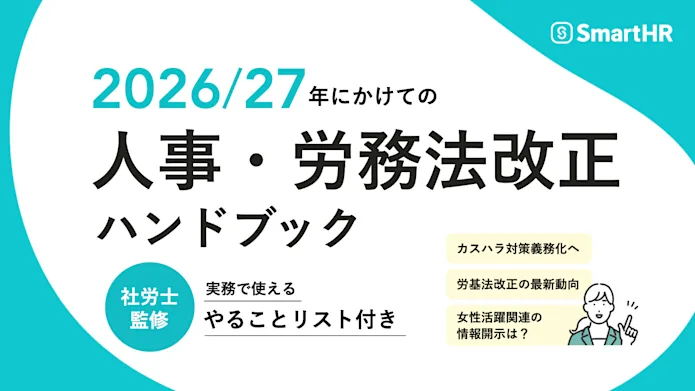
お役立ち資料
2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック
この資料でこんなことが分かります
- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正
- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正
- 人事・労務担当者 やることリスト


























