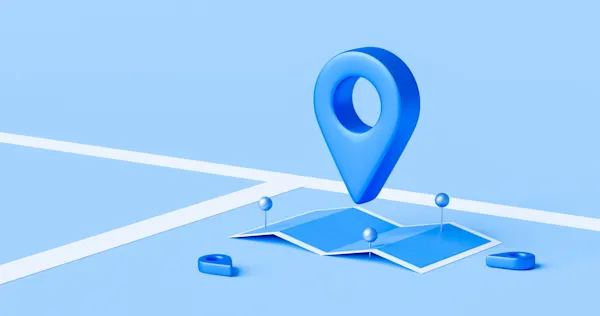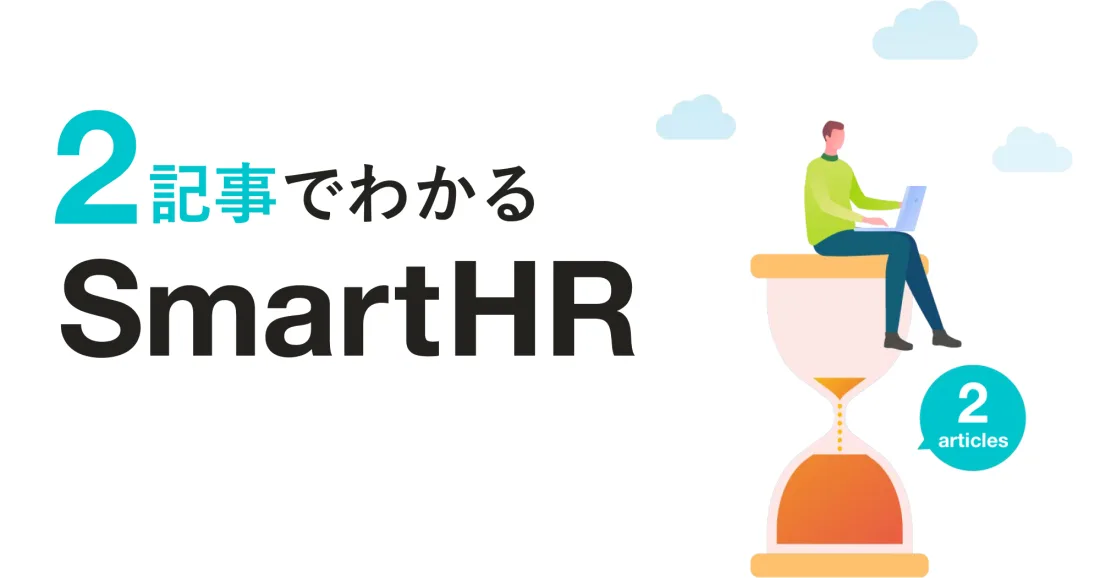人事評価において正確性はどの程度重要か?〜公正研究の見地から〜人事評価の現在地 #05
- 公開日
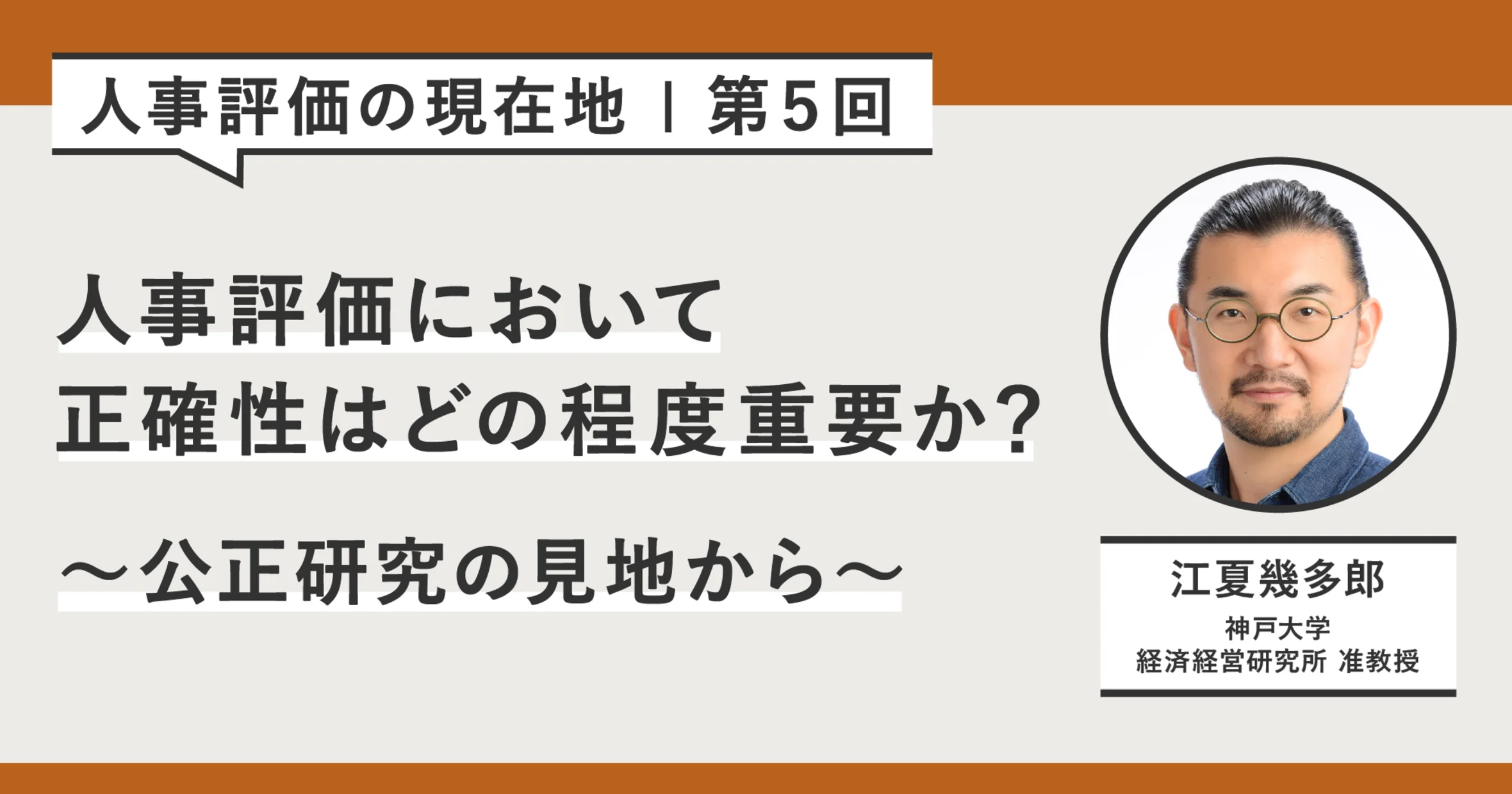
目次
「人事評価制度がうまく運用できていない」「現場の評価への不満が収まらない」。人事評価制度の課題は、多くの企業で抱えているのではないでしょうか。
この連載では、人材マネジメントを研究している神戸大学 経済経営研究所・江夏幾多郎准教授が、人事評価についてのさまざまな考え方をご紹介。人事評価制度を導入する企業、評価者、被評価者である従業員のそれぞれが、人事評価のポテンシャルをどのように開拓し、有益な方法としていけばよいか、その道筋を考察します。
第5回目は「人事評価制度における正確性の重要度」について紹介します。
はじめに:人事評価のジレンマ克服は「組織的公正論」にヒントがある
正確な人事評価を通じて、従業員の満足感や納得感を確保するために制度を整備することで、評価者の負担感が強まりかねない。そうなると、十分な正確性を確保できず、従業員の不満や不納得が生まれかねない。前回の連載で示した「人事評価のジレンマ」を、どのように克服すればよいのだろうか。
「組織的公正論」と呼ばれる研究領域の知見が、ジレンマ克服のヒントを与えてくれる。組織的公正論では、人事評価の正確性は部分的にしか推奨されない。従業員の満足感も部分的にしか追及されない。組織からの扱いを人々が受容=納得することに関して、多くの知的成果を出してきた。
人事評価における「測定」以外の側面
人事評価や報酬への従業員の満足感は、自分の能力や貢献を踏まえて、「もらいたい」と考える水準に、実際の水準が近づくときに高まる。しかし、従業員が知覚する「もらいたい」水準と、評価者が知覚する「与えたい」水準はしばしば一致しない。これらの水準を極力そろえることが、人事評価のコミュニケーションでは求められる。
水準をそろえる手がかりになりうるのが、正確な人事評価であり、評価者と被評価者が、従業員の能力や貢献についての明確な事実を共有することである。しかし、このアプローチの貫徹は、これまでの連載で述べたように困難である。
評価者は正確だと判断しても、被評価者はそのように思わない。評価者自身も正確な評価ができていないと自覚する。そのような人事評価の結果が頻繁に現れる。人件費の制約などにより「与えられる」水準が、評価者の「与えたい」水準を下回るとき、従業員の満足度を満たす困難さがさらに顕著になり、従業員の不満が生じやすくなる。
このとき、企業や評価者にとっては、個人的な「もらいたい」に過度に引きずられずに、従業員が実際の人事評価について定義してくれることが望ましい。たとえば、「従業員の事情やニーズと、企業や評価者の事情やニーズがバランスよく満たされた評価や報酬の水準である」という観点からの定義である。
「比較他者」で評価への不満を抑止できる可能性が生まれる
人事評価の妥当性について、自分自身の価値基準だけではなく、自分とほかの人事評価の関係者との関わり合いという目線からも、従業員に判断してもらう。これにより、従業員の満足感は実現できないかもしれないが、不満は抑えられ、納得は得られる可能性がある。
この点について最初に明確な理論を示したのが、ジョン・アダムズの1965年の研究である(Adams, 1965)。アダムズ以前の研究では、個人において、報酬とそれを得る労力が釣り合うことが、よしとされてきた。しかしアダムズは、個人の「報酬/労力」が比較他者(ひかくたしゃ)のそれと釣り合う、公平性の意義を主張した。比較他者には、同僚のほかにも、自分に報酬を提供する企業や評価者も含まれる。企業経営や職場運営が厳しい(報酬)なかでも、従業員に報いるために最大限の努力(労力)をしていると知った従業員は、報酬水準そのものに満足できなくても、企業や評価者による評価を受け入れることもあるだろう。
従業員が比較他者の状況を知る主たる手段は、彼らとの関わり合いである。ロバート・フォルジャーらは、「人事評価は従業員の貢献についての測定ではなく、論争である」とした(Folger, et al., 1992)。彼らは、「論争における適切な過程」を以下の3つから成るとした。
- 十分な周知
- 公正な聴取
- 証拠にもとづく判断
これらは、一見すると正確な人事評価に向けた測定に関するものである。こうした人事評価により、従業員の能力や貢献についての自己評価と、他者評価が一致することもあるだろう。被評価者の許容範囲が、自己評価から見た「もらいたい」水準を一定程度下がる範囲まで拡張することもあろう。
だが論争の過程とは、究極的には評価者と被評価者との人間同士の関わり合いであり、それ自体が被評価者にとっての報酬にすらなりうる。このとき、論争を通じて評価者や企業への理解が進むことで、被評価者の「もらいたい」を下回る、評価者の「与えたい」「与えられる」が被評価者により許容されることもある。
人事評価における「満足感」「納得感」「公正感」の違い
人事評価への満足感と納得感は異なる。従業員の満足感は、能力や貢献についての自己評価から見た「もらいたい」を満たす評価や報酬に対して抱かれる。反面、納得感は、そのような条件がなくても、ほかのさまざまな状況次第で抱かれる。企業や評価者が従業員に提供できる報酬が限られるとき、「満足はできないが納得できる」と従業員が感じられる手がかりを増やさなければならない。
人事評価に対する従業員の満足感に、正確性が寄与できる部分は大きい。しかし、人事評価制度の運用の難しさ、人事管理に投入できる企業の経済的資源の制約を踏まえると、すべての従業員に正確な人事評価を行い、満足してもらうことは不可能だ。それにもかかわらず、従業員が、自分自身への人事評価を取り巻く状況を勘案することで、「満足しきれない人事評価を納得的に受け入れる」ことはある。
従業員の「事実への合理的な理解」が納得の手がかり
人事評価に従業員が納得する手がかりとなるのが、実際に起きていることへの合理的な理解である。企業とは、従業員、経営者、株主や顧客などの組織外のステークホルダーが、便益や費用を分かち合う場である。分かち合いのあり方が、十分に正確ではないにせよ、そうならざるを得ないという意味で理にかなっている(すなわち公正である)場合もある。その場合、たとえ自らに配分される評価や報酬に十分に満足できなくとも、従業員はそれを受け入れやすいだろう。公正感にもとづく納得感が、満足感にもとづく納得感を代替するのである。
組織的公正論は、公正な扱いを受けたいという人々の根源的欲求に立脚した理論構築を進めてきた。公正な扱いを人々が望むのは、それが、長期的な便益への期待、社会的欲求の充足、自らの道徳基準に周りが沿っているという感覚、を与えてくれるからである。
評価への納得感を生む「4つの公正」
先行研究では、M&A、ダウンサイジング(リストラ)、組織変革など、従業員にとっての想定外の状況も、内容や進め方が公正であると知覚されれば、従業員は受容できることが実証されてきた。日本でも、成果主義的な評価・報酬制度が従業員に受容される条件として、公正性の意義が度々指摘されてきた(e.g. 江夏, 2010; 守島, 1997)。
先行研究では、公正であるといえる客観的状況について、以下の4つの次元で把握することが多い(Colquitt, 2001)。フォルジャーらが示した3つの次元とも重複するが、評価者には、人事評価の実態について従業員に誤魔化さない努力が求められ、人事部門には制度設計上の工夫が求められる。こうした取り組みは、人事評価の正確性を少なからず高めるし、従業員による正確性とは別の次元での人事評価への理解も高めうる。
(1)分配的公正
公平性、平等性、必要性など、人々が公正と見なす報酬分配原理には、さまざまな要素がある。自らが重視する原理を企業や評価者が採用し、その原理が人事評価や報酬に反映されることを従業員は期待する。
(2)手続き的公正
人事評価や報酬配分を適切に実施するため、企業には従業員の貢献を評価しやすい基準や尺度の整備が求められる。そして評価者は、必要な情報収集や情報処理を率先して実行しなければならない。
(3)対人的公正
従業員についての情報収集や情報処理の際には、彼らの人間性への尊重や配慮を十分に行うことが、評価者には求められる。従業員への配慮を欠いた人事評価の正確性や入念な手続きは、彼らの心証をかえって害しかねない。
(4)情報的公正
「企業や評価者から十分に配慮してもらった」という従業員の感覚は、彼らへの嘘偽りのうえで成り立つべきではない。評価の水準や決定過程について、評価者から被評価者への十分な情報提供が必要となる。
さいごに:正確性を追求する努力が人事評価の納得感を生む
人事評価を正確に実施する重要性は言うまでもないが、その実現は難しく、すべての従業員を満足させるのは不可能である。しかし、できるだけ正確であろうという企業や評価者の努力の姿勢が、たとえ彼らの目標が十分に達成されないとしても、多くの従業員の納得感につながることは十分に期待できる。こうした納得感の背景にあるのは、実際に提供された評価や報酬のみならず、提供の過程における評価者や企業との関わり合い、そして双方の内実を知り、尊重するに至ることである。
もっとも、ここで示した公正性のさまざまな原則すら、人事評価の現場では、しばしば実現困難なものである。そうしたなかでも、評価者は従業員に人事評価に納得してもらい、かつ職場や企業全体の業績につながる貢献をしてもらう必要がある。そのために必要なことについて、次回と次々回で検討したい。
- 参考文献
- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol.2 (pp. 267-299), Academic Press.
- Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
- 江夏幾多郎 (2010).「処遇に対する公正感の背景―不透明な処遇を従業員はいかに受容するか」『経営行動科学』23(1), 53-66.
- Folger, R., Konovsky, M. A., & Cropanzano, R. (1992). A due process metaphor for performance appraisal. In B. M. Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior, Vol.14 (pp.129-177). JAI Press.
- 守島基博 (1997).「新しい雇用関係と過程の公平性」『組織科学』31(2), 12-19.
- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol.2 (pp. 267-299), Academic Press.

お役立ち資料
経営の未来をつくるカギは人事評価にある
人事評価が「従業員の能力や業績を評価して、待遇・賃金を検討するための仕組み」であることは言うまでもありません。しかし、人事評価が影響する範囲は大きく、自社の経営の未来をつくる存在でもあります。
本資料では、見落とされがちな経営戦略と人事戦略を連動させる重要性について解説しています。