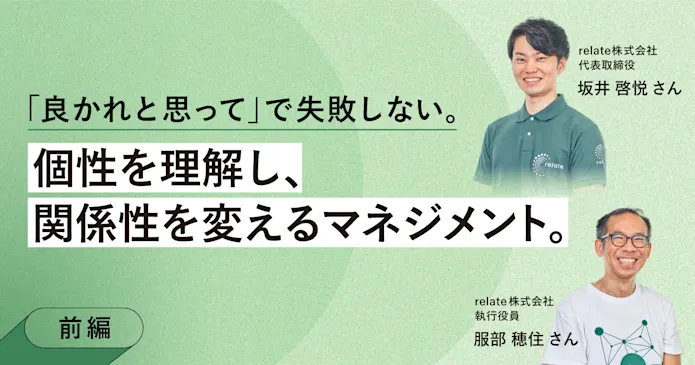「個」を活かす組織のつくり方。ミクロとマクロで動かす組織変革
- 公開日

目次
 坂井啓悦
坂井啓悦relate株式会社 代表取締役
神戸大学経営学部卒業後、株式会社シグマクシスに入社。通信業界における事業基盤整備、航空業界における新規事業立上げ/BDD/事業計画策定、総合商社業界での投資先バリューアップ計画策定/物流アルゴリズム開発PMO、商業施設不動産業界における他社との協業スキーム設計、B2Bアプリ開発PMO等、様々な領域での戦略・業務コンサルティングの経験を有する。2023年よりrelateを創業。
 服部穂住
服部穂住relate株式会社 執行役員
早稲田大学法学部を卒業後、2005年株式会社リクルートHRマーケティング東海(現株式会社リクルートジョブズ)に入社し、求人広告の企画営業及び組織マネジメントに従事。2012年グリー株式会社に人事として入社し評価・育成・福利厚生・社内活性化の責任者を務める。2015年株式会社マネーフォワードに入社し、人事領域の責任者として5年で組織が7倍となる急成長に関わる。2020年より事業部門に異動し、セールス・サクセス組織の管掌及び新規事業の責任者を務める。2024年relate株式会社に参画し事業全般を管掌。
多くの企業がサーベイを「実施しただけ」にとどまっており、現場は“サーベイ疲れ”を起こしている現状。肝心の課題解決には結びついていません。
従業員エンゲージメント向上の重要性が叫ばれる一方で、このようなジレンマをどのように解決していけばよいのでしょうか。
前編では、サーベイによる可視化にとどまらない具体的なネクストアクションとして、従業員の「個性」と関わり方に着目したERM(Enployee Relationship Management)にもとづいたアプローチ方法をご紹介しました。
後編では、現場の取り組みを組織全体の力へとつなげる、マクロの組織戦略について、引き続きrelate株式会社 代表取締役の坂井啓悦さんと、執行役員の服部穂住さんにお話を伺いました。
やりっぱなしではなく、行動変容につなげるためのミクロとマクロの取り組み
多くの企業で、人事施策が「やりっぱなし」で終わってしまうという課題があるかと思います。原因はどこにあるのでしょうか。
坂井さん
組織編成や異動、サクセッションプランなどの取り組みは、人事のテーマとして非常に大きなものです。そのため役割を切り分けることになりますが、過度な細分化は、役割自体を目的化してしまいます。
たとえば、人事担当者は「ツールを導入して可視化すること」が目的になり、人事部長は「経営会議で承認を得ること」が目的になる。その結果、本来の目的であるはずの「効果創出」へコミットする責任者が誰もいない、という構造が生まれます。
だからこそ、人事施策はミクロでのアプローチと、マクロでのアプローチを両輪で進めるべきなのではないかと考えています。
「ミクロ」なアプローチでは、前編で述べたようなマネージャーと部下の関係改善や、メンバーの自己理解、相互理解を促進し、組織の細部まで「血肉」を通わせます。
「マクロ」なアプローチでは、経営戦略にもとづき、各組織のミッションに合った人材ポートフォリオを設計し、中長期的な視点で組織構造を変えていくことで、組織の「骨格」を形づくります。
骨格だけでも、血肉だけでも、組織という大きな体は動かせません。両方がそろってはじめて、人事施策を「やりっぱなし」ではなく、実際の行動変容へとつなげられると考えています。

「異質」を活かす組織のつくり方
前編でお話しいただいたミクロの取り組みと比べて、マクロの取り組みはハードルが高いと感じます。どのように進めていくべきでしょうか。
服部さん
まず、経営層が明確なメッセージを発信することが不可欠です。
組織の文化とは、「○○な人が多い会社」であり、従業員一人ひとりの口癖や習慣に現れるものだと思います。だとすれば、組織的なマクロの取り組みの第一歩は、従業員に共通する「組織の口癖と習慣」です。
つまり、経営層が「異質性の尊重」や「個性の活用」を積極的に発信することが重要なのです。それがやがて従業員の口癖になっていき、自分と個性の異なる人を尊重する行動や習慣へと変わっていくのです。このようにして組織的な文化が醸成され、マクロの取り組みも進んでいくのではないでしょうか。
私たちが考える理想的な推進体制は、経営層(上)と従業員(下)で、管理職(中)を挟み込む「サンドイッチ構造」です。
まず、経営層が大義名分と目的を明確に示し、全社的な取り組みであることを宣言することで、方向性がぶれないようにします。一貫した経営方針の表明は、行動変容の推進役である管理職を守る「盾」となります。
次に、現場で働く従業員が診断などを通じて自分と周囲の「個性」を把握し、互いを生かし合うことの価値を理解する必要があります。これは、管理職を下から支えます。
最後に、経営層の方針表明と従業員の理解に挟まれる形で、管理職が現場の行動変容を推進します。この体制により、人事施策が形骸化することなく、エンゲージメント向上の具体的なアクションと成果へつなげられると考えています。

エンゲージメント向上を「絵に描いた餅」で終わらせないために
効果測定については、どのような指標を置くべきでしょうか。
服部さん
まずはマイナスをゼロにする指標を追うことをおすすめします。具体的には、「離職率の低下」「若手の早期退職の防止」「管理職の負荷軽減」などが挙げられます。FFS理論(開発者:小林 惠智博士)はストレス理論がベースであり、人間関係の改善に直結するため、マイナス要因を解消する取り組みで比較的、成果が現れやすいのです。
「プラスを証明する」のではなく、「マイナスを減らす」ことから始める、と。
服部さん
一見すると「守り」に偏った施策に聞こえるかもしれませんが、これらの指標は効果を測定しやすく、人材獲得や再教育にかかるコストの削減につながるため、経済合理性を説明しやすいのです。
坂井さん
ただし、離職率のような指標も成果として現れるまでに最低でも1年以上かかるため、中間指標を置いて、最終的な成果が出るまでの過程を可視化することも欠かせません。
具体的には、施策導入から3か月後、6か月後といったタイミングで、アンケートなどを通じて現場の意識や行動の変化を捉えます。
マネージャーへの設問は「部下一人ひとりに合わせたコミュニケーションが取れている実感はありますか」などを設定します。メンバーへは「上司に報告する際に工夫ができるようになったか」「自分のメンタルが落ち込んでいることを自己認知し、対処できるようになったか」といった設問を用意します。
設問の設計には工夫が必要ですが、中間指標の改善を可視化できれば、施策の継続が最終成果につながることを社内に説得力をもって説明できます。
人的資本ROIや従業員エンゲージメントなどの大きな最終成果だけに注目するのではなく、プロセスを可視化する指標を設計し、足もとの地道な効果測定を続けていくことが重要です。その結果として、従業員エンゲージメントの向上や人的資本経営の実現へとつながるのではないでしょうか。
一人ひとりの「個性」が「強み」に変わる組織へ
最後に、読者である人事担当者や経営層の方々へ、メッセージをお願いします。
坂井さん
大切なのは、施策の実施自体を目的とするのではなく、現場に変化を起こすことを最優先に考える視点だと思います。
近年、HRBPやCHROといった役職を置く企業が増え、人事から組織を変革していくという気運は高まっています。しかし実態は、そうした役職の人たちが日々の労務作業に追われており、本来の役割と実態がかけ離れている状況が生まれています。これでは、ご本人たちも辛いはずです。
社内向けの説明や承認プロセスのためではなく、事業の成長に貢献するための人事施策を実施できるよう、変わっていくべきです。
そのためには、経営陣や外部の専門家を巻き込むことが重要です。FFS理論の文脈でいうなら、変革を担うのに適した「個性」をもつ人材を配置するイメージです。異なる立場や専門性をもつ人材が一体となって取り組むことこそが、変革の成功につながるのです。
私たちは、人事の皆さんが組織変革の中核的な担い手として、自らの仕事に誇りと自信をもてる未来をともに創っていきたいと考えています。

服部さん
人事の仕事に絶対的な「正解」はありません。だからこそ、「意志」が何よりも重要です。
世の潮流に合わせて多様性や心理的安全性の重要性を唱えるだけでなく、自社独自の個性を活かす組織ビジョンを明確に立てることが、人事担当者の役割だと思っています。
そして、実際に行動に移すときには、一人ひとりの「個性」の違いを単に相互理解で終わらせず、自分と個性が異なる人を尊重する言動へとつなげていく。この積み重ねこそが我々relateが目指すERM(Enployee Relationship Management)の形であり、従業員エンゲージメントを向上させ、誰もが自分らしく輝ける組織の土台となるはずです。
執筆:藤森 融和
撮影:矢野 拓実
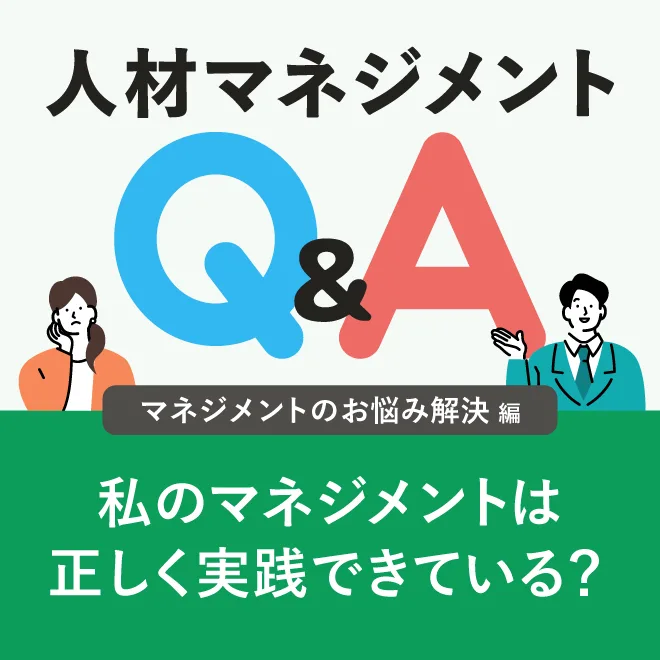
お役立ち資料
人材マネジメントQ&A マネジメントのお悩み解決
この資料でこんなことがわかります
- ネガティブフィードバックのやり方は?
- 1on1で部下の本音を引き出すには?
- パワハラとの線引きはどこ?
- 目標達成に向けて動いてもらうには?