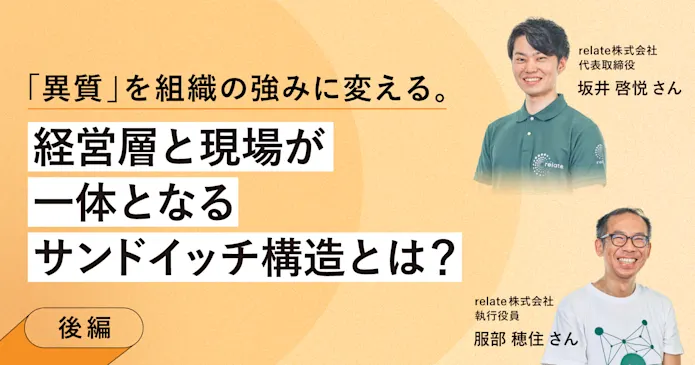「個性」を活かして人を動かす。マネージャーの“ラストワンマイル”を埋める科学的マネジメントとは
- 公開日

目次
 坂井啓悦
坂井啓悦relate株式会社 代表取締役
神戸大学経営学部卒業後、株式会社シグマクシスに入社。通信業界における事業基盤整備、航空業界における新規事業立上げ/BDD/事業計画策定、総合商社業界での投資先バリューアップ計画策定/物流アルゴリズム開発PMO、商業施設不動産業界における他社との協業スキーム設計、B2Bアプリ開発PMO等、様々な領域での戦略・業務コンサルティングの経験を有する。2023年よりrelateを創業。
 服部穂住
服部穂住relate株式会社 執行役員
早稲田大学法学部を卒業後、2005年株式会社リクルートHRマーケティング東海(現株式会社リクルートジョブズ)に入社し、求人広告の企画営業及び組織マネジメントに従事。2012年グリー株式会社に人事として入社し評価・育成・福利厚生・社内活性化の責任者を務める。2015年株式会社マネーフォワードに入社し、人事領域の責任者として5年で組織が7倍となる急成長に関わる。2020年より事業部門に異動し、セールス・サクセス組織の管掌及び新規事業の責任者を務める。2024年relate株式会社に参画し事業全般を管掌。
労働人口の減少、低い生産性、従業員の定着率の低迷――。
多くの日本企業がこれらの経営課題に直面するなか、解決策の1つとして「従業員エンゲージメント」の向上に注目が集まっています。
しかし、多くの取り組みはエンゲージメントサーベイによる「可視化」にとどまり、改善に向けた具体的な打ち手につながっていないケースは少なくありません。
そこで、本記事ではエンゲージメントと強い相関関係にあるとされる自己効力感に着目しました。従業員の自己効力感を高めるための「個性と強みの開放」をテーマに、エンゲージメントの向上へつながる具体的な打ち手について、relate株式会社代表取締役の坂井啓悦さんと、執行役員の服部穂住さんにお話を伺いました。
前編では「ミクロ編」として、マネージャーが現場で取り組める具体的なアクションに焦点を当てます。そして、後編では「マクロ編」として、企業風土や制度設計など組織開発の観点から解説します。
なぜエンゲージメント施策は「やりっぱなし」で終わるのか
いくつかの調査によると、エンゲージメントサーベイに関するサービスの市場は伸びている一方で、従業員エンゲージメント自体は横ばいであることが示唆されています。多くの企業で、エンゲージメント向上施策がうまく機能していないのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
服部さん
私たちもそのように感じています。企業が取り組むべきは、サーベイにより問題を可視化し、その原因に対する施策を講じることのはずです。しかし、多くのエンゲージメントサーベイでは、スコアは算出できても「なぜそのスコアになったのか」という根本的な原因まではわかりません。
たとえば、「仕事へのモチベーション」のスコアが低いと認知できても、原因までは特定できません。そのため、対策は「どうにかスコアを上げてください」と現場任せになったり、「とりあえずキャリア面談を実施しましょう」とあいまいなものになりがちです。
その結果、現場は「解決策もなしにデータだけを出されても」とストレスを感じ、サーベイ疲れのような状況に陥ってしまいます。
坂井さん
サーベイのような「可視化」は初手として着手しやすい施策です。人的資本経営の流れを受け、この領域に予算を割く企業が増えていますが、可視化で満足してしまい、具体的なアクションに活かせないまま終わるという課題が深刻化しているように感じています。

「個性の違い」を理解し、そこから行動変容へとつなげる
サーベイによって可視化したあとは、どのようなアクションを取ればよいのでしょうか。
服部さん
1つの方法は、スコアが低いチームの「個性」を分析してみることです。私たちは、マネージャーとメンバーの間で起こる「個性」の衝突が、エンゲージメントに影響する要素の1つだと考えています。
皆さんも子どものころ、親や先生から「自分がされて嫌なことは他人にしてはいけないよ」「自分がされてうれしかったことは他人にもしてあげよう」と教わった経験がないでしょうか。
これは意外にも私たちのなかに深く根付いています。仕事においても、マネージャーの多くは過去の自身の経験をもとに「こうすることが相手にとってもよいことだろう」と考えて部下を指導しています。
しかし、良かれと思ってしたことが相手の「個性」に合わないとき、部下にとってはむしろストレスがかかる状態になってしまいます。
たとえば、「自由な発想で物事を進めたい」という個性の上司が、「着実に進めたい」という個性の部下に対して、「とりあえず思うようにやってみて」と背中を押したとします。上司にまったく悪気はなく、むしろ善意からそうしたのに、個性の違いによって部下は「なんて適当な人だ」と強いストレスを感じてしまいます。
逆に「着実に進めたい」という個性の上司が、「自由な発想で物事を進めたい」という部下の行動進捗を良かれと思って管理したとすると、部下は「マイクロマネジメントだ」と不満を抱いてしまいます。
つまり「個性」や「多様性」への理解が必要ということでしょうか。
服部さん
理解することは大前提ですが、それだけでは不十分です。重要なのは個性の違いを理解したうえで、どのように関わり方を変えるかです。
relateが重要だと考える「ERM(Employee Relationship Management)」は、まさにこの「個性の理解」と「関わり方」に着目し、より良い関係性をデザインすることで従業員一人ひとりが相互に強みを引き出し合える環境を実現することを目指しています。

マネジメントの引き出しを増やし、「個性」を「強み」に変えるアプローチへ
個性の「理解」を「行動変容」へとつなげるために、具体的にはどのような方法があるのでしょうか。
服部さん
私たちが提唱しているのは、FFS理論を用いて「個性」と「強み」を理解し、適切なアプローチを試みることです。
FFSとは「Five Factors & Stress」の略で、生理学をベースにしたストレス理論です。FFS理論(開発者:小林 惠智博士)では「個性」を5つの因子の組み合わせで捉えます。

適切なストレス環境下では、個性が「強み」として発揮される。しかし、過度なストレス環境では、強みが過剰に現れ、裏返って「弱み」になってしまう。FFS理論ではこのように考えます。
たとえば、5つの因子のうち「保全性」の数値が高い人は、計画を立てて着実にものごとを進めることが強みです。しかし、「保全性」のストレッサーである先が見えない状況や急な変更といった刺激が加わると、計画どおりに進めようとする個性が過剰に表出します。その結果、「私は私のやり方でやります」「新しいことは受け入れません」などの言動をとってしまい、周囲からは保守的、拒絶的に見える場合があります。
「強みを伸ばし、弱みを補う」という考え方とは異なるということでしょうか?
服部さん
はい。「数値の高い因子が強みで、低い因子は弱み」といった発想ではありません。その人特有の5つの因子が示す数値の組み合わせこそが「個性」であり、「個性」が強みとして表出するように「アプローチの仕方を変える」という考え方が、FFS理論と一般的な診断ツールとの大きな違いです。
マネージャーが一人ひとりの個性に合わせてアプローチ方法を変えるのは、現実的に難しいのではないでしょうか。
坂井さん
ご指摘のとおり、100人に対して100通りの対応をするのは現実的に不可能です。
しかし、FFS理論の「型」を使えば、個性をある程度パターン化できます。各パターンに応じた対応方法の引き出しをもつことで対応がしやすくなります。
まずは自分のやり方で指導して、うまくいくならよし。しかし、「どうもこの人には響かないな」という人が現れたときに、FFS理論という引き出しを開けて、考え方のヒントを得るのです。
重要なのは、現場で引き出しやすいシンプルさです。診断ツールのなかには、数十個にもわたる項目で結果を示すものもあります。詳細に分析できる利点はありますが、引き出しの数が多くなりすぎて、忙しい現場のマネージャーにとっては使いづらくなってしまいます。
FFS理論の場合、因子が5つのみとシンプルです。さらに、自分と相手で共通する因子がいくつか存在するため、理解しやすく覚えやすい仕組みになっています。

坂井さんご自身も、マネジメントにおける「引き出し」の重要性を感じた経験があるそうですね。
坂井さん
前職で上司が特定の価値観にもとづいて動機付けをしてくれたことがあったのですが、正直、私には響きませんでした。頭では理解できるのですが、私を行動変容させるモチベーションにはならなかったのです。
もし、上司が私の個性を理解したうえで、別の“引き出し”を使ってアプローチしてくれていたら、私のリアクションは違うものになっていただろうと思います。
現場の行動変容に必要なのは「具体的なアプローチ方法」と「小さな成功体験」
“引き出し”とはつまり、現場で使える具体的なアプローチ方法ということですね。
服部さん
はい。座学で学ぶ「多様性理解」と、現場で起こる「上司部下のコミュニケーション問題」を効果的に結びつけるマネジメントのラストワンマイルとして、FFS理論という“引き出し”が活用できると考えています。
「報連相をしない部下」への対応方法として、どのようなアプローチが考えられるのでしょうか。
服部さん
FFS理論を使うことで「なぜ報連相をしないのか」という疑問に対しての仮説を立てられます。
たとえば、相手のために行動したい「受容性」の数値が高い部下は、上司が忙しそうだと遠慮して報連相を控えている可能性があります。この場合は、「いつでも声をかけていいんだよ」と伝えることが有効でしょう。
完璧を求める「保全性」の数値が高い部下なら、準備がしっかり整ってから報告しようとしているのかもしれません。その場合は、「完璧でなくていい。1日1回話す機会をつくろうか」と、報告のハードルを下げるアプローチが効果的です。

仮説を立てられるようになれば、闇雲に試行錯誤するのではなく、打ち手の方向性が明確になりますね。
坂井さん
一人ひとりの個性にもとづいたアプローチは、一見すると、マネージャーのコストが大きいように思われるかもしれません。
しかし、コストをかけたことによってアプローチ方法が明確になり、必要以上の労力を省けるため、投下したコスト分は必ず回収できます。実際に私たちのクライアントからも「マネジメントの負荷が軽減された」という声が数多く寄せられています。
服部さん
FFS理論は現場で引き出しやすいので、短期間で小さな成功体験を積み重ねられます。一度でも成功体験を得ると、1対1のコミュニケーションの場はもちろん、チーム全体の雰囲気も前向きに変化します。
困ったときに開ける“引き出し”があるという安心感と、それを使えばうまくいくという成功体験。この2つをそろえることが、現場での自発的な行動変容には欠かせないと考えています。
執筆:藤森 融和
撮影:矢野 拓実
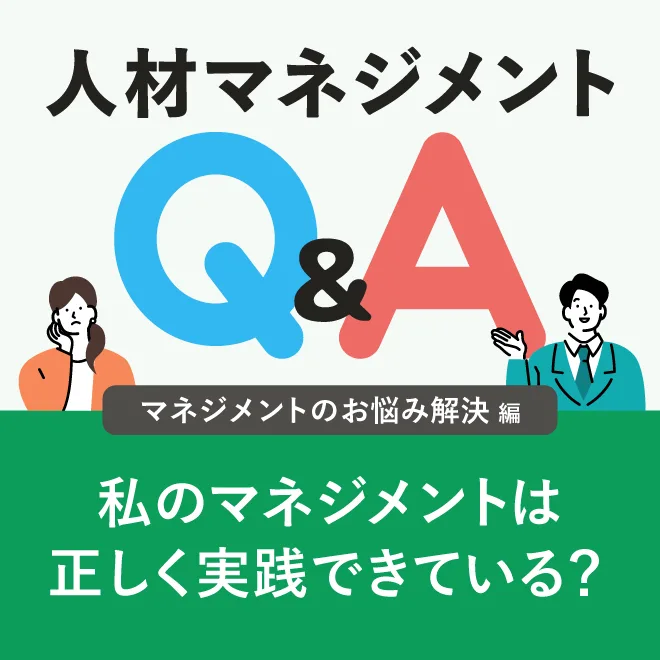
お役立ち資料
人材マネジメントQ&A マネジメントのお悩み解決
この資料でこんなことがわかります
- ネガティブフィードバックのやり方は?
- 1on1で部下の本音を引き出すには?
- パワハラとの線引きはどこ?
- 目標達成に向けて動いてもらうには?