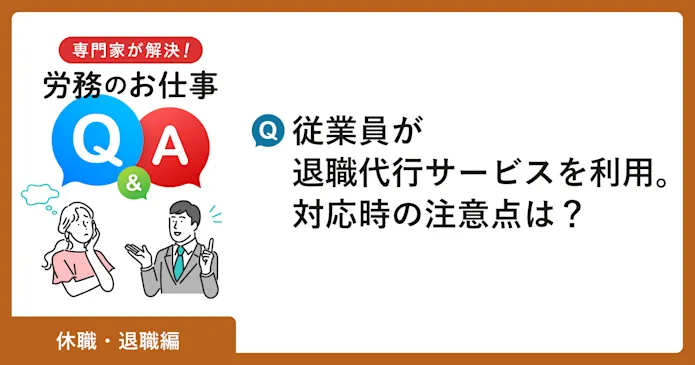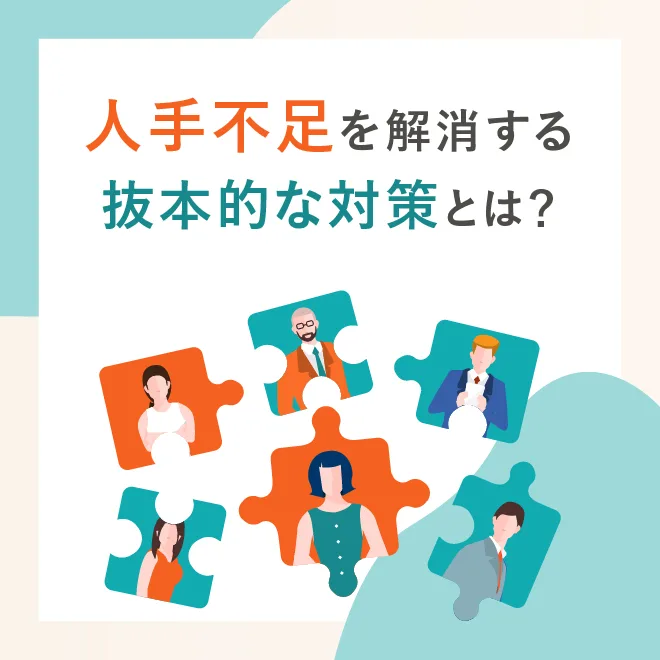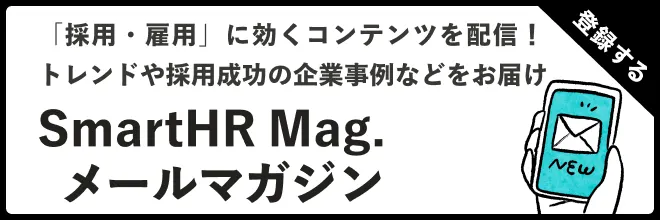「辞めたい」が言えない日本の職場。退職代行から読み解く組織課題と人事の役割
- 公開日
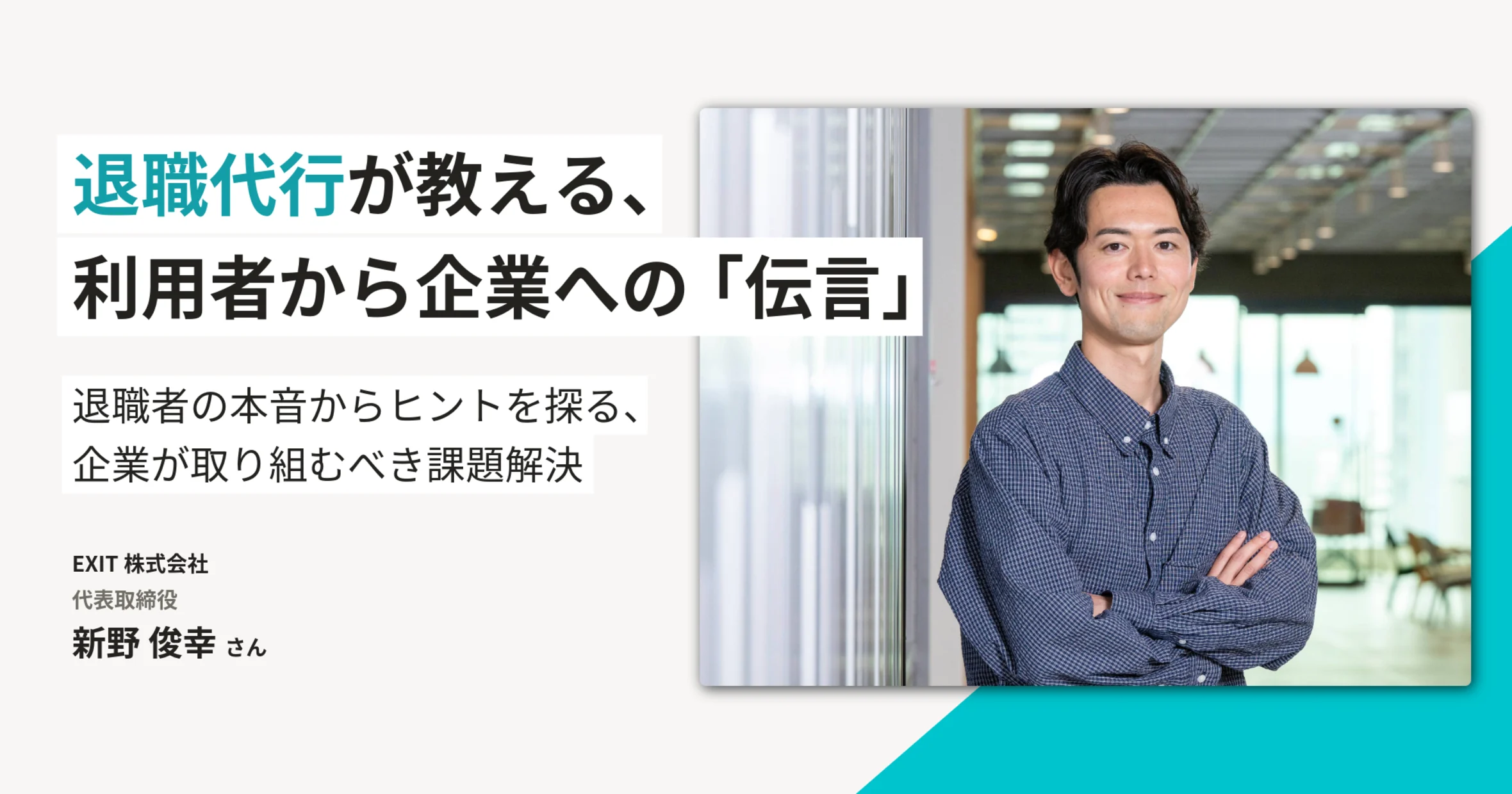
1989年神奈川県鎌倉市生まれ。青山学院大学文学部英米文学科を卒業後、大手企業など3社で勤務し、その間、ニートやフリーターも経験している。自身の退職経験をもとに「退職代行」という新たなコンセプトを考案し、2017年に退職代行EXITを創業。退職代行サービスの先駆者として注目を集める。
利用者が急増する退職代行サービス。その広がりの背景には、引き留めやハラスメントに悩む従業員の切実な現実があります。
本来、組織との対話を通じて進むはずの「退職」というプロセスが、なぜ第三者によって代行されるのか。退職代行サービスの生みの親であるEXIT株式会社の代表取締役・新野俊幸さんに話を聞き、業務のなかで寄せられる“退職者の本音”から、企業が人材流出を防ぐために取り組むべき組織の課題と、改善のヒントを探ります。
自身の苦い経験から生み出されたサービス
退職代行サービスの利用者は年々増加し、マイナビリサーチ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」によると、直近1年間に転職した人のうち16.6%が退職代行を利用したという報告もあります。あらためて退職代行とはどのようなサービスなのか教えていただけますか?
新野さん
退職代行は、「会社を辞めたい」という意思を、本人に代わって企業に伝えるサービスです。また、離職票や雇用保険被保険者証といった退職後に必要な書類について、その種類や用途を説明したり、場合によっては企業に発行を依頼したりして、それらの書類が利用者の手元に届くまでサポートもします。
ただし、弁護士法人ではないので、未払い賃金など退職条件に関する交渉はしません。あくまで、利用者の意思を企業に連絡する“伝書鳩”のような立ち位置です。

世界的に見ても珍しいユニークなサービスですが、アイデアはどのような経緯で思いつきましたか?
新野さん
私自身、これまでに3回退職を経験しましたが、いずれも非常に辞めづらく、強いストレスを感じるものでした。そうした個人的な経験が、このサービスを立ち上げる原点になっています。
そもそも日本の職場には、「辞める」と言い出せない独特の雰囲気があるように思います。せっかく採用してもらって、上司にいろいろ教えてもらったのに、みんな忙しいなかで自分だけ抜けるなんて申し訳ない……。“辞める=裏切り”に近い感覚をもつ方もいる。これは、日本社会特有の価値観かもしれません。
以前、アメリカの記者から取材を受けたとき、「アメリカではみんなスパッと辞めてしまうから、このビジネスは成り立たない」と言われました。そもそもアメリカでは“辞める=裏切り”という概念がないんでしょうね。
新野さん自身も、退職時に同じような空気を感じたのですね。
新野さん
ある会社では、退職を決意してから伝えるまでに3か月もかかりました。ようやく言えたと思ったら、課長、部長、統括部長、本部長と次々に面談が続き、最後には人事から「甘い」と怒られる始末です。決意は固まっていたのに、多くの時間とエネルギーを消耗することになりました。
ほかの2社でも同じように強く引き留められ、スムーズに辞められませんでした。さらに周囲を見ても、「辞めたいけど言えない」と悩む仲間たちが多くいました。こうした経験を通じて、退職代行には確実にニーズがあると確信するようになりました。
利用者の7割が20代で、職種・業界はさまざま
まさにその予想が的中したわけですね。
新野さん
とはいえ、創業当時は依頼件数も月1件や2件とスズメの涙ほどでした。「退職代行」という概念自体が浸透していなかったので、完全に怪しい業者としか見られていませんでした。実際に、退職の連絡を入れた相手企業から「そもそも御社はどういう会社なんですか」と突っぱねられたり、よく怒られたりしていました。
そんな状況が一変したのは、SNSで私たちのサービスが、ある匿名インフルエンサーに取り上げられたことでした。その投稿が数万規模で拡散されたのをきっかけに一気に広まり、突然、驚くほどの数の依頼が舞い込むようになりました。
比較的新しいサービスなので、利用者はやはり若い方が中心ですか?
新野さん
利用者の約7割が20代です。ただ、最近では30〜40代の利用も着実に増え、さらに50〜60代といった上の世代からも依頼されるようになってきました。
その理由は、もともと退職を自分で言い出せずに悩んでいた人は一定数存在していたものの、解決する手段がなかったからではないでしょうか。そこに、退職代行というサービスの存在が広く知られるようになり、「他者に頼ってもよい」と思える人が増え、利用ハードルの低下や、実際に利用する年代層の拡大につながっていると考えています。

職種や企業規模によって利用に偏りはありますか?
新野さん
飲食、医療・介護、建設業などでやや利用が多い傾向はありますが、全体としては職種・業界ともじつにさまざまで、大企業から数名規模の会社まで企業の大きさも関係ありません。なかには、大手コンサルティングファームや商社といった人気企業に勤めていた方からの相談も寄せられました。
主な理由は引き留めやハラスメント
退職代行は、連絡を受ける企業にとっては驚きや抵抗もあるかもしれませんが、実際にはどのような状況で利用されているのでしょうか。
新野さん
大きく2つに分かれます。退職の意思を伝えたのに、うやむやにされていつまで経っても辞められないケースが約3割。残りの7割は「辞める」と言い出せないまま、ひとりで悩んでいるケースです。この割合はどの年代にもいえることです。
前者は、まさに私自身の経験とも重なります。上司に退職の意思を伝えたものの、「責任者にも伝えておくから、少し時間がほしい」と言われ、そのまま1か月ほど進展がありませんでした。あらためて確認すると、「もう少しだけ待ってほしい」とさらに引き延ばされてしまう。このような対応はじつはよくあるケースで、「上司が辞めること自体を許してくれない」といった相談も少なくありません。
この背景には、構造的な問題もあると考えています。たとえば、新卒社員が早期に離職すると、上司の人事評価に影響する仕組みがある企業では、なんとか退職を引き留めようとする力が働きやすい。加えて、退職届を出せば原則2週間後には退職できるという民法の基本的なルールを知らない上司が多いのも、問題を複雑にしている要因の一つです。
「辞める」と言い出せないケースには、どのような事例がありますか?
新野さん
退職を伝えられないケースとしては、過度に成績を求められ精神的に追い詰められてしまったなどのパワハラが挙げられます。ほかにも「食のハラスメント」で吐くまで食べさせられたとか、社長からお金を借りていて返済のために辞められないというような特殊な事例。さらに深刻なのは、部長からセクハラを受け、社長に相談したところ社長からもセクハラを受けた、というようなひどいケースもありました。
そのようにさまざまな理由で追い詰められた結果、出勤できなくなったり、職場を思い浮かべるだけで呼吸が苦しくなるほどの精神状態になったりして、最終的に私たちに依頼が届くという流れです。なかには、電話で泣きながら現状を訴え、相談してくる方もいます。
実際に御社のサービスを利用するなかで、退職者から企業への伝言にはどのような内容が多いのでしょうか。
新野さん
もっとも多いのは「メールを含め、今後一切連絡しないでください」という伝言で、「会社のこの制度に問題がある」など、改善を求める声が伝えられることもあります。
伝言を受け取った企業の反応はいかがでしょう?
新野さん
「社会人として許されない」と怒りをあらわにする企業もあります。しかし、その反応については、私自身、退職代行は家事代行などと同じく、ただ退職手続きを外部に委託しているにすぎず、過剰に反応することではないと思っています。
ほかにはどのような反応がありますか?
新野さん
本当にさまざまですが、「仕方ない」とあっさり受け入れる企業もあれば、「社員の苦悩に気づけず申し訳なかった」と謝罪されることや、感謝の言葉をいただくこともあります。

感謝されることもあるのは、意外でした。
新野さん
たとえば、利用者がなんらかのハラスメントを受けていた場合、本人は「もめたくない」「事情を聴かれるのが嫌だ」「面談が怖い」といった理由から、何も言わずに会社を去ろうとするケースがほとんどです。でも、退職代行という第三者が間に入ることで、本人の許可が得られれば、私たちから企業に事実をありのままに伝えられます。
そうした情報を通じて、「だからこの部署は離職率が高かったのか」といったように、企業や人事部がはじめて問題に気づける可能性もあります。結果として、組織改善へとつながっていくこともあるんです。
人材流出を防ぐために真摯な姿勢と対話を
退職代行を通じた利用者からの伝言が、組織改善のきっかけになりうるのですね。
新野さん
そのとおりです。ただ、退職代行が使われると、企業の窓口担当者以外は本人と直接対話をする機会や、その方の退職を防ぐための改善策を講じるリカバリーのチャンスを失ってしまいます。
だからこそ、私自身も一経営者として、日ごろから「辞めたいという思いがある」と従業員が気軽に相談できるような仕組み、つまり、従業員が本音で話せる環境を整えるのが重要だと考えています。たとえば、上司と腹を割って話せる1on1を定期的に実施するなど、「対話の場」をつくる工夫が必要です。
対話が何よりも重要なのですね。
新野さん
最近では、「上司を尊敬できない」「将来のキャリアが見えない」といった理由で辞める人も増えています。もししっかりと対話できれば、上司の意外な魅力や、キャリアビジョンにおける発見があるかもしれません。また、人事部としてもキャリアプランを積極的に提示したり、悩みをもつ方にコーチングしたりすることで、従業員が将来に希望がもてるようになる可能性もあります。
そうすれば、仕事自体には不満がないのに、人間関係や将来への不安から退職してしまう——そんな、本来であれば辞める必要のなかった人材の流出を防げるはずです。
辞める必要のなかった人材の流出を防ぐために、人事にはほかにどういったことができると思いますか。これまで数多くの退職相談を受けてきたなかで、“退職者の本音”に触れてきたと思うので、それを踏まえてご意見をお聞かせください。
新野さん
その職場でまだやり直せる可能性がある従業員に対しては、これまで以上に本気で向き合うとよいと思います。たとえば、入社3か月で退職を訴えてくる新入社員に対して、「そういう時期を乗り越えて、みんながんばっている」などと対応してしまう人事担当者も、少なからずいるのではないでしょうか。
もちろん、そのアドバイスは必ずしも間違っているわけではありません。でも、そのような姿勢では、本人はますます追い詰められ、結果的に退職代行を利用する選択にいたってしまう可能性があります。
それを防ぐためには、具体的にどうすればよいでしょうか?
新野さん
「なぜ、新入社員がたった3か月で辞めたいと思ったのか?」という視点をもつことが重要だと思います。辞めたい理由を本人の甘えや一時の迷いと捉えるのではなく、組織側の課題として丁寧に掘り下げていく。その問題にしっかり時間をかけ、改善に本気で取り組む姿勢を見せるだけでも、従業員の気持ちは大きく変わるはずです。
もちろん、具体的な改善ができれば理想的ですが、仮にそれが難しい場合でも、人事の態度やコミュニケーションの取り方を見直すだけでもきっと状況は変わります。同じ目線で真摯に耳を傾け、親身になって対話する。そうすれば、「もう少しこの会社でがんばってみようかな」と思う人も出てくるかもしれません。

ハラスメントへの対策についてはいかがでしょうか?
新野さん
ハラスメントが原因で退職を考える人がいる以上、社内にしっかりとした相談体制を整えることは不可欠です。そこでも、企業側がまず被害者の声に直接耳を傾ける姿勢をもつのが大前提だと思います。
ただし、パワハラの訴えがあっても、加害者に注意するだけで、その加害者が「たいしたことではない」と受け流すような対応では逆効果で、被害がさらに悪化する恐れもあります。
簡単なことではありませんが、ハラスメント含め、本気で組織課題の改善に取り組む企業が増えれば、人材流出の根本的な防止にも必ず結びついていくと思います。
(取材・文/POWER NEWS編集部、写真/横関一浩)
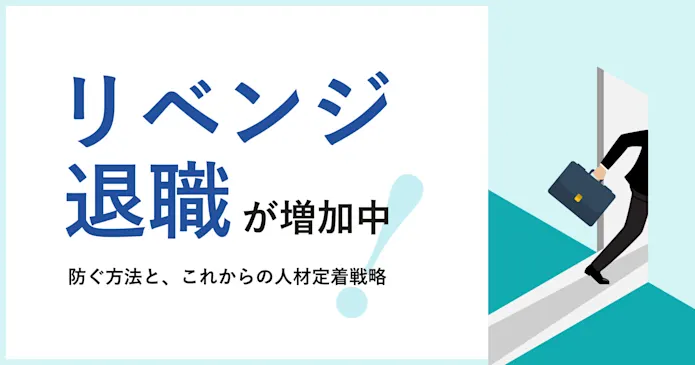
お役立ち資料
リベンジ退職が増加中 防ぐ方法と、これからの人財定着戦略
この資料でこんなことが分かります
- アメリカで急増中の「リベンジ退職」が、なぜ日本でも増える?
- リベンジ退職を引き起こす4つの不満
- 防止する4つのアプローチ、キーワードは「マイナスの払拭」と「やる気をプラス」

お役立ち資料
知らぬ間に拡大する「静かな退職」は早めに対策を!
この資料でこんなことが分かります
- 「静かな退職」とは?
- 「静かな退職」を放置することの問題点
- 「静かな退職」を生み出さないために
- 従業員の声を収集する「従業員サーベイ」のポイント