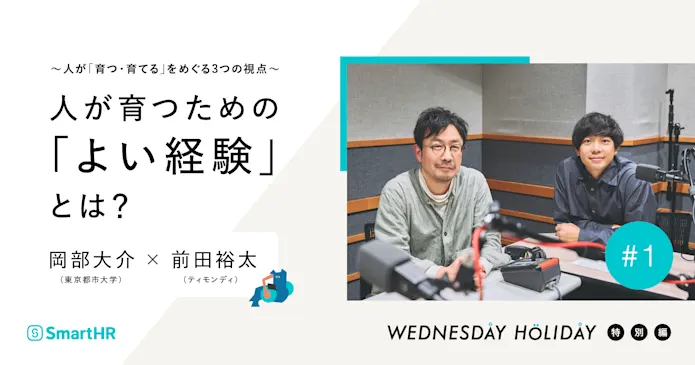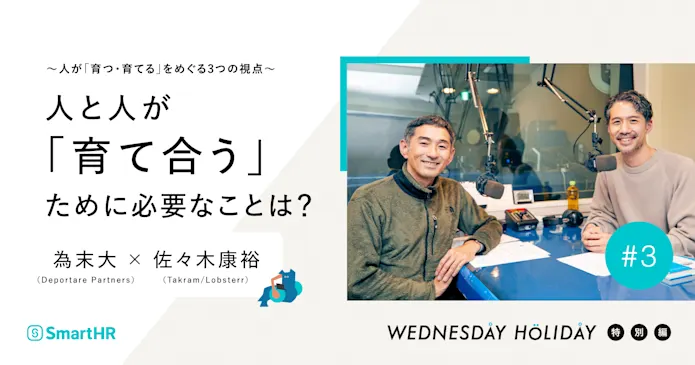マネージャー育成の新しい形とは? AIと組織マネジメントの未来を語る
- 公開日
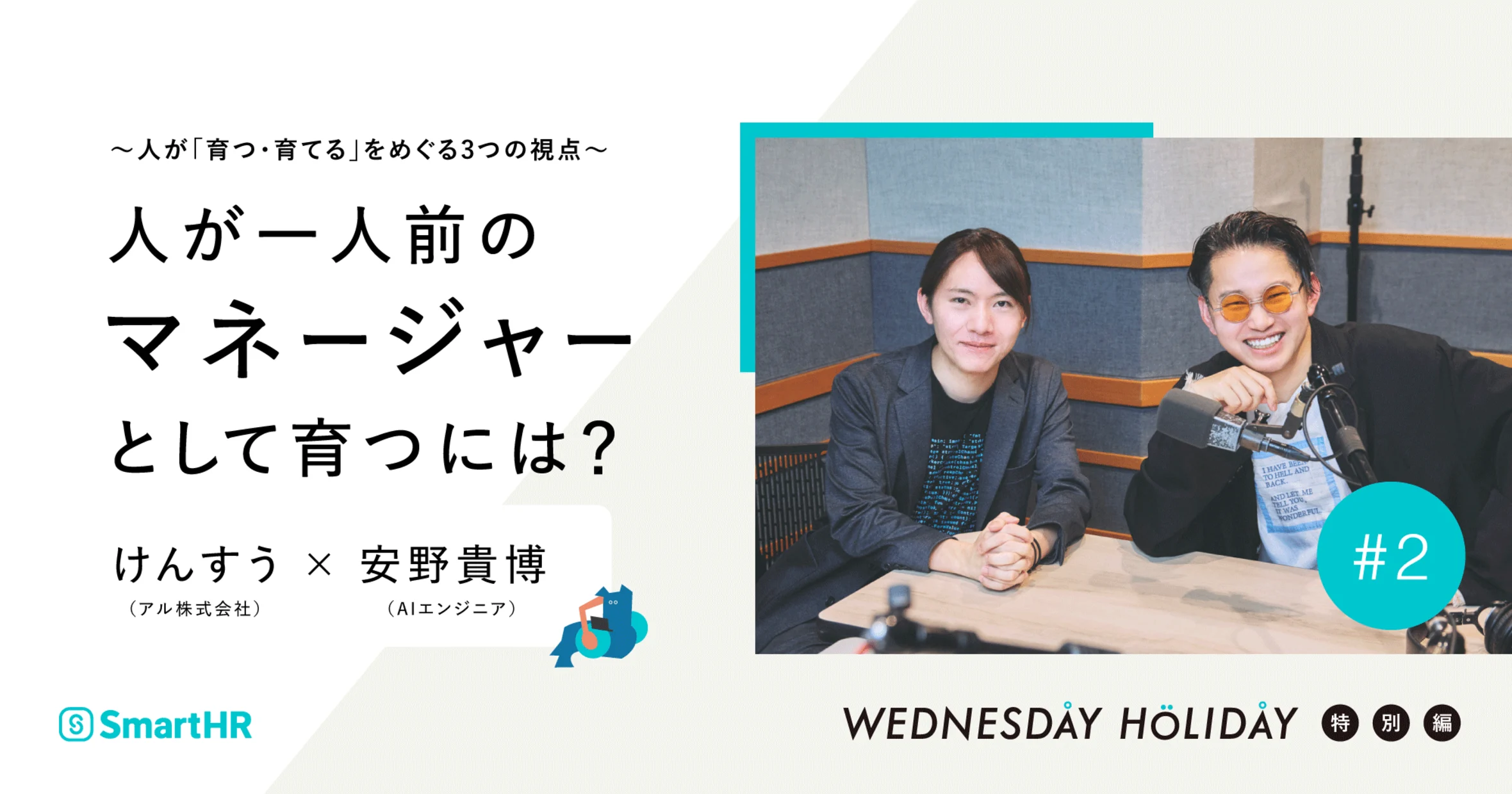
SmartHRが「“働く”を語る水曜日の夜」をコンセプトに配信するポッドキャスト番組『WEDNESDAY HOLIDAY(ウェンズデイ・ホリデイ)』。2022年6月の番組スタートから2年が過ぎ、先日配信100回を迎えました。そこで今回は、100回を記念して配信された全3回の特別編「WEDNESDAY HOLIDAY 特別編 〜人が『育つ・育てる』をめぐる3つの視点〜」のレポートをお届けします。
第2回のパーソナリティを務めたのは、アル株式会社・けんすうさんとAIエンジニアの安野貴博さんです。番組では、「人が一人前のマネージャーとして育つには?」をテーマにお二人の経験も交えながら対話が進みました。
- けんすう(古川健介)
アル株式会社 代表取締役
学生時代からインターネットサービスに携わり、2006年株式会社リクルートに入社。新規事業担当を経て、2009年に株式会社ロケットスタート(のちの株式会社nanapi)を創業。2014年にKDDIグループにジョインし、Supership株式会社取締役に就任。2018年から現職。会員制ビジネスメディア「アル開発室」において、ほぼ毎日記事を投稿中。
- 安野貴博
AIエンジニア 起業家 SF作家
開成高校を卒業後、東京大学へ進学。内閣府「AI戦略会議」で座長を務める松尾豊の研究室を卒業。外資系コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループを経て、AIチャットボットの株式会社BEDORE(現PKSHA Communication)、リーガルテックのMNTSQ株式会社を創業(後者は共同創業)し、デジタルを通じた社会システム変革に携わる。未踏スーパークリエータ。デジタル庁デジタル法制ワーキンググループ構成員。日本SF作家クラブ会員。 2024年、東京都知事選に出馬、デジタル民主主義の実現などを掲げ、AIを活用した双方向型の選挙戦を実践。
変化するマネージャーに求められる役割
「プレーヤーとマネージャー(の働き方)に大きい断絶があるし、中間管理職のなかでもレイヤーによってやることが違ってきたりする」と切り出す安野さん。そこから、ご自身の経験を交えながら、お二人が考える多岐にわたるマネージャーのあり方について盛り上がります。
けんすうさん
管理職になったばかりのころって、管理職のなかでは一番下っ端になるので、その大変さもある。とはいえ部下からしてみたら、偉い人みたいに見られる。それがつらいという話をよく聞きます。
安野さん
たしかに。マネージャーになった瞬間、いきなり周りからの接し方が変わってびっくりすることってありますよね
けんすうさん
突然部下からは「何でもやってくれる人」みたいに扱われるし、上からはお前がやれ、みたいな感じになってつらいんですよね。
安野さん
しかもプレイヤーのときって、自分がめっちゃ頑張って手を動かして何か成果を出すことは歓迎されますが、マネージャーになってくると、自分でやるタイプの人もいますけど、果たして本当にそれがよいのかという課題もあります。
安野さんは続けて自身が新卒で入社したコンサルティング会社で経験した複数のマネージャー像について語ります。
安野さん
私が新卒で入社したコンサルティング会社では、3か月ごとにプロジェクトが変わり、同時に上司も変わりました。
なので、さまざまなマネジメントスタイルを経験できました。「なぜこれをやるのか」を説明したうえで、成果の出し方、方法については「自分でいろいろ試しながらやりなさい」と裁量をもたせてくれるスタイルが個人的には合っていました。
逆にマイクロマネジメントをされる方もいました。それが心地よいと感じるタイプもいると思います。
一言に「マネージャー」といっても、組織から求められている役割と、マネージャー個人のスタイルには多様性があります。同時に、マネージャーのあり方に唯一の正解はなく、組織が目指すビジョンや、協働するメンバーとの関係性によって最適を模索することが求められそうです。
メンバーに自律的な行動を促す「自己組織化」
ここで安野さんは、都知事出馬で経験したボランティアスタッフの「自己組織化」とその仕組について語り始めます。
安野さん
都知事選では、ポスター貼りや街頭演説などを手伝ってくれるスタッフをボランティアとして募集し、金銭関係を発生させない形で進めました。
けんすうさん
どのような仕組みで、ボランティアスタッフを導くのでしょうか?
安野さん
通常、ポスター貼りは業者に依頼すると、1,000万円を超えるコストがかかります。そんな資金もなければ、ボランティアスタッフにポスターを貼り付けてもらう場所を適切に指示する余裕もありませんでした。
そこで私が作ったのは、「ポスターがどこの掲示板に貼られているのか・いないのかをリアルタイムに確認できるシステム」です。そして、「自分の周りで貼られていない箇所があれば貼ってください」と声をかけ、自己組織化を促しました。
その結果、全体の90%までは、積極的に自分の周辺にポスターを貼ってくれるという動きでカバーできました。残り10%になると、貼られていない箇所は都内に点在しはじめます。ここからは、皆さんがLINEなどで「私はここを担当しますから、あなたはここを担当してください」と情報を交換し、めでたくすべての箇所にポスターを貼ることができました。自己組織化が進んでいく様を目の当たりにすることができましたね。

「自己組織化」というキーワードから、人が自律的に動く仕組みと、おせっかいなマネジメントの弊害について議論が進みます。
けんすうさん
昔からの友人で、「2ちゃんねる」創設者、ひろゆきさんもボランティアにいかに自律的に動いてもらうかをシステム的につくるのがめちゃくちゃ上手です。自身のYouTubeの切り抜きに関してもユーザーに開放し、結果ものすごい再生数を稼ぐ仕組みをつくるなど、すごく面白いなと思います。企業もこうした動きを取り入れていく必要があるんじゃないかと思います。
「真面目にマネージャーが頑張って部下をマネジメントしようとすると、潰れちゃうんですよね」と自律的行動を促す「自己組織化」とは対象的なマネジメントの弊害を示すけんすうさん。
けんすうさん
マネージャーになるとみんな部下を子供のように扱ってしまいます。「これできなさそうだからちゃんと指示してあげよう」、「マニュアルを作ろう」、「働きやすいようにオフィスに◯◯を導入しよう」など、結果として部下が本当に子供のようになってしまう。要は、そのようなマネジメントは部下とかメンバーのためにならないことが多いのです。

AIがもたらすマネジメントの可能性
「組織マネジメントにAIを活かせるだろうか」と話す安野さん。そこからマネジメントとAIの関係について議論が展開します。
安野さん
組織マネジメントにAIをどのように活かせるか、ぜひけんすうさんに聞いてみたいです。
けんすうさん
うちの会社では「アプトプットの提出の前に一度AIを通してください」と促した結果、人間関係がめっちゃ良くなったんですよ。
たとえば資料の「ちょっとした言い回しのミス」や、「この観点が抜けてんじゃないか」とか マネージャーが言わなきゃいけないけど、あまり言いたくないことってあるじゃないですか。
それらがAIに通すことで全部なくなり、結果ポジティブな話しかしなくなるんです。 要は、30分使ってミスの指摘をしていたのが5分で終わる。すると25分間を人間関係の構築に使えるし、本当にお客さまにとって嬉しいこととは?という本質的な話ができるのですごくいい点だと思います。
さらにAIによるコーチングなど「未来のマネジメント」に視点を移し、マネジメントの進化の可能性を示します。
けんすうさん
たとえばマネージャーが1on1を週に1時間、7人分の場合7時間を使うのは難しい。さらに、人の悩みは5時間ぐらい喋らないと本音がでてこないこともあります。 その時間をマネージャーが捻出するのは不可能です。
そこで、5時間分はAIに吐き出してもらい、そのサマリーをマネージャーが見て、最後の30分だけサポートするなどが実現するとよいでしょうね。安野さんはAIを使ったマネジメントついてアイデアはありますか?
安野さん
来年(2025年)くらいから、コミュニケーションをAIが強化するようになるだろうと考えています。私は勝手にAIオーグメンテッド・コミュニケーションと呼んでいるんですけど、たとえば1対1でLINEをしていて、言葉足らずで喧嘩になってしまうことってありますよね。でも、AIが文脈を補完してくれることで、そのような齟齬は起きなくなるかもしれない。
会社のコミュニケーションツールでも実現ができれば、組織内のコミュニケーションの円滑化に貢献できそうです。
対談の終盤で、安野さんはこれからのマネージャーに必要な要素を示します。
安野さん
私は大事なことが2つあると思います。
1つは言語化能力です。 自分がこうした方がいいんじゃないか、ここを目指すべきなんじゃないかという考えをしっかりと言葉にして伝えること。これは人間に対しても、AIに対しても必要だと感じます。
2つ目は、「こっちの方向を目指そう」という自分の意思をもつこと。自分がどうしたいのかわからないとそもそもAIも使えないし、部下もマネジメントできないと思います。まずは「自分の意志をもつ」ことがすごく大事です。
「意思をもち、言語化する」。ビジネスパーソンがマネージャーになるうえでは、これができていればいいんじゃないかな、と思います。
けんすうさんと安野さんの対談を通じて、マネジメントの形が組織の性質や目的によって大きく変わり、マネージャーに求められる役割も変化することがわかりました。そしてマネジメントにおいて、AI活用は効率化だけでなく、本質的な組織貢献に寄与できる可能性が示唆されました。対談のなかで示された「マネージャー自らの意思もち、その言語化が求められている」というひとつの解は、これから生まれる新しいマネージャーの要諦と言えるかもしれません。

「人が一人前のマネージャーとして“育つ”には?」(アル株式会社・けんすう、AIエンジニア・安野貴博)全編の再生はこちらから
音声版では、今回の記事で取り上げた内容以外にも「よい経験」をめぐるさまざまな話を展開しています。お時間のある時に、こちらもぜひお聴きください。
ポッドキャスト番組「WEDNESDAY HOLIDAY」 について
フリーアナウンサーの堀井 美香さんをパーソナリティに迎え、ビジネス・アカデミック・文化芸能などさまざまな世界で活躍するゲストとともに、個人の働き方や、組織やチームのあり方、仕事を通じた社会との関わり方などをゆるやかに語るトークプログラム。毎週水曜日の夕方5時頃に、最新エピソードを配信しています。配信中のエピソードは、各種音声プラットフォームにて、無料でお聴きいただけます。
撮影:関口佳代