管理職の心理的安全性は誰が守る? 孤立するリーダーに必要な支え
- 公開日

人材の多様化、業務の肥大化、成果へのプレッシャー。「管理職は罰ゲーム」と揶揄されることがあるほど、その役割は重く複雑になっています。最前線で組織を支える管理職の負担を軽くし、重圧をやりがいへと変えるにはどうすればよいのか。管理職自身が取るべきアクションと、企業が講じるべき具体的対策について、法政大学キャリアデザイン学部教授の坂爪洋美さんにお話をうかがいました。
法政大学キャリアデザイン学部教授
人材ビジネス業に従事後、和光大学現代人間学部を経て、2015年4月より現職。2001年慶應義塾大学大学院経営管理研究科単位取得退学、博士(経営学)。専門は産業・組織心理学、人材マネジメント論。ダイバーシティの中でも、とくに女性のキャリア形成ならびにワーク・ライフ・バランス推進における管理職の役割について研究を進める。
「罰ゲーム」化する管理職
プレイングマネージャー(現場の業務も行いつつ、チームの管理や育成も行う)としての管理職が定着し、管理職の仕事量や負担は増加の一途を辿っています。長年管理職を対象とした研究を続けてこられた坂爪先生が見る、管理職の現状について教えてください。
坂爪さん
管理職の基本的な役割は、自分の部門に任された仕事を、メンバーに割り振ってきちんと遂行し、業績を上げていくことです。そのためには、部下に力を発揮してもらわないといけない。ですから、部下の能力を育成したり、部下の意欲を高めたり、仕事の進捗をサポートしていくことも求められます。

この基本的な役割は、昔から変わっていないのですが、部下を動かす手間が大きくなっていたり、他の仕事も請け負うようになっているために、管理職の負担が増しているのです。
新しく増えた手間や他の仕事とは、具体的にどういうものですか?
坂爪さん
手間の要因はいくつもありますが、まず挙げられるのは「人材の多様化」ですね。昔は、部下といえば「年下」の自分と同じ「男性」ばかりでした。だから「背中を見て覚えろ」「俺と同じようにやれ」が通用しやすかったんです。
でも今は、企業で働く人の性別や出自、価値観もより多様化していますし、子育てや介護をしながら働く人なども増えています。転職が一般化して人材の流動性が高まったことや定年後再雇用が広がったことで、年上の部下をもつこともめずらしくなくなりました。
しかも、昔は昇進スピードも年次管理による横並びでしたが、今は「個別管理」が当たり前になっています。一人ひとりを評価し、個人の志向も考慮しながら、バラバラのキャリアを提示していく流れがある。

つまり、今は多様な部下に合わせて、マネジメントスタイルを変えていく必要が高くなったわけです。比較的画一的な部下を相手に、シンプルなスタイルでいられた昔に比べて、チームメンバーをモチベートしていく難易度は、段違いに高くなっていると思います。
また、管理職にとって新たに“当たり前”になった仕事として、部下に対する「キャリア形成支援」や「人事施策の運用」などが挙げられます。定期的な1on1やキャリア面談は、多くの会社で管理職に任されていますよね。配置や育成、育休制度など、人事施策を、部下に適切に運用し浸透させる役割に苦心している管理職も多いはずです。
なるほど。どうしてここまで管理職の負担が増えてしまったのでしょうか?
坂爪さん
大きな要因として、「どんなによい人事制度をつくったとしても、人事制度だけでは社員のモチベーションや行動を管理できなくなったこと」があります。企業も成長し、給与も右肩あがりの環境があって、働き手も潤沢でした。「嫌なら辞めてもいい」「“獅子の子落とし”よろしく、這い上がってきた人材が育てば会社としてはなんとかなる」といった空気があったんですね。
でも今は、そういうわけにはいきません。働き手は不足する一方だし、転職もずいぶん当たり前になりました。入社前から転職サイトに登録して、比較検討する人もたくさんいます。それに、ダブルインカム(1つの世帯に2つ以上の収入源がある状態)も一般的になっていますから、給与を上げることだけに躍起にならない人も増えました。働くことへの価値観も変化していて、「言われたことだけやればいい」と考えながら働く人も一定数います。

つまり、今は人事制度だけでなく、その運用を工夫したり、管理職のリーダーシップや職場の風土といった部分で、社員をつなぎとめ、モチベートし、仕事で成果をあげるべく頑張ってもらえるようなモチベーションを用意する必要があるわけです。
そうなると、多くの企業は「最前線にいる管理職が頑張ることが重要だ。彼らがよいマネジメントを発揮すれば問題は解決するのではないか」と考えているんですよね。その結果、管理職の肩には、人事や経営層からのそういうフワッとした期待が一挙にのしかかっているんです。
たしかに、部下が去っていくのは管理職に責任がある、と考える人は多そうです。
坂爪さん
そうですよね。さらに言えば、上層部からは「俺たちはうまくやっていたじゃないか、なんで君たちはやれないの?」というプレッシャーがあります。けれど、今の管理職世代が受けたマネジメント方法を踏襲すれば、大反発をくらうでしょう。部下から「ハラスメントですよね?」と告発される可能性だって大いにある時代です。上の世代と下の世代、その間に挟まって、どちらからも理解してもらいにくいのが今の管理職の特徴かもしれません。

プレイヤーとして、管理職として、こなさなくてはならない大量の仕事に加えて、精神的なプレッシャーやストレスも大きい。そんな大変な状況を思うと、「管理職は罰ゲーム」と称されるのも、うなずける気がしてしまいます。
今、必要な「管理職への投資」
ある企業の調査によると、一般社員のうち「管理職にはなりたくない」と感じている人は、7割を超えていると言います(日本能率協会マネジメントセンター、2023年)。そうした「管理職のネガティブなイメージ」を払拭するには、どうしたらいいのでしょうか?
坂爪さん
若手は上司の大変そうな姿を見て「なりたくない」と思うわけですから、現在の管理職がいきいきと働く姿を見せるのが一番大切ですよね。そのためには、「部下マネジメントの見直し」と「管理職の孤立対策」が必要だと思っています。
まず、これまでお話ししてきたような「部下マネジメントの面倒さ」をどうにかしなくてはいけません。今って「部下マネジメントをしなさい」と言われすぎていて、管理職全体の視線が下、すなわち部下にばかり向きやすくなっているんですよね。本来の「部下育成」の外側にある部分まで拾うような、かなり手厚いサポートが標準的になっている気がします。

そもそも本来、管理職の役割としては「担当職場で業績を上げる」という目的が先にあって、その後ろ、というかそれを実現するためのステップにあるのが「部下の育成」であるはずです。それなのに、今は「部下のキャリア形成を支援する」ことがフワッと独立して管理職の“目的”と化している。これはちょっとおかしな構図ではないでしょうか。
管理職はそれらの“目的”をつなぎ合わせ、「成果を上げる」という本来の目的に目線を保つ必要があります。現状を俯瞰して、次の打ち手を考える。どうしたら自分が少しでも楽になって目的が達成できるかを考える。一人ひとりが管理職としてのロードマップを描き、そこに育成を落とし込むといった俯瞰図を描くことが大事だと思いますね。忙しすぎてそれどころではないと思いますが、目の前の仕事に対処していたら1年経ってたという方も多いと思うので、目線を上げてマネジメントの絵を描くことはやってほしいと思います。
また、企業側がしっかり管理職の役割を切り分けることも大切です。人事領域における流行りに乗って、「これもやっといたほうが良さそうだね」と、あれこれ管理職に役目を丸投げしている企業はとても多いです。そうではなく、会社側が「こういう目的で、ここまで管理職にお願いしたい」「ここは社員一人ひとりに任せる」というように、施策の目的や各人の業務の境界を明確にするメッセージを出すことも重要だと思います。
具体的に、部下マネジメントの負担を軽減できるような制度や仕組みなどはないのでしょうか?
坂爪さん
もちろん、会社側が行う制度づくりとして、取り組めることはたくさんあります。たとえば、管理職一人ひとりが見る部下の人数を減らしたり、補佐役を置いたり、業務量に対して適切な人材を配置することなどは、直接的に負担を減らせる策でしょう。
あるいは、管理職の裁量を増やすこともよい改善策です。たとえば、部下とのキャリア面談は、今や管理職にとって不可避であり、部下マネジメントの負担を増す要因になっているタスクですよね。
ここで、部下から「今は営業職だけど、将来は財務部で働きたい」と相談があったとして、有効なストロークが返せる管理職はどれほどいるでしょうか。日本の課長クラスは、他国に比べて権限がすごく狭いと言われていて、ほとんどが人事異動に関する裁量権をもっていません。
部下はそのうち、「どうせこの人に話しても意味がないし……」と面談を面倒に思うようになるでしょう。これは、上司部下の関係構築において、かなりの悪影響です。

キャリア面談で実効性のあるコミュニケーションを行うためには、管理職にもっと裁量権を与えるか、あるいは異動の権限をもつ上位の管理職も入れて行うなど、会社側がしっかりと策を講じなければいけません。これは、社員のキャリア形成の面でも、部下マネジメントの観点でも重要だと思います。
それから、部下のキャリア形成支援についての先進的な取り組みとして、「社内OB訪問」のようなサイトを導入している企業があります。
「〇〇の仕事の経験があります」「育児中」「介護経験あり」「大学に通っている」など、社員たちが、自分の話せることを登録しておくサイトです。誰かが「〇〇がしたいけど、どうしたらいいだろうか」と今後のキャリアに悩んだときに、そのサイト経由で、経験者を探し、直接話を聴くことができる仕組みになっていました。
これがあれば、社員は手軽に有益なアドバイスが受けられるだけでなく、管理職側にとっても、面談時に「この人に話を聴いてみたら?」などと有効な提案ができるメリットが生まれますよね。仕組みをつくることで、社員も管理職もサポートできている好例だなと感じました。
そんなふうに独自の仕組みづくりを進めている企業もあるんですね。他に、部下マネジメントを楽にする手段として、「タレントマネジメント」などのデジタルツールを導入するのはどうでしょうか?
坂爪さん
たしかに、そうしたツールを使って、現場の管理職が部下のタレント(能力)を把握できることはすごく良いことだと思います。一方で、ツールに集まるデータを使いこなせない人もいるでしょう。

なので、「こうやってデータを使うと、こんなふうに部下が育っていくんだよ」というモデルケースまで具体的に示せるといいと思います。そういう具体的で取り入れやすいメッセージを通して、「このツールを使わないとマズい」くらいのムードがつくれたら、より広範囲で実践的な活用につながるのではないでしょうか。
もう一つの問題点として、「管理職の孤立」も挙げられていました。こちらはどういった問題意識からでしょうか?
坂爪さん
今の管理職って、かなり追い詰められているんですよね。自由にできることは少ないのに、どんどん仕事が降ってきて、上にも下にも意見される板挟みの状態。以前、管理職の方に「職場の心理的安全性を管理しましょう」という話をしたら、「じゃあ僕の心理的安全性は誰が確保してくれるんですか?」と真顔で聞かれたこともあります。追い込まれて、「頑張ったところで何も変わらない」と諦めている人も大勢います。
そういう方に「他の管理職の方も苦労している」と話すと、「自分だけじゃないんだ」と安心されるんですよね。つまり、管理職同士の横のつながりが薄く、悩みや解決策をシェアする環境が整っていないのでしょう。忙しさや競争意識など、理由はさまざまですが、「部下にこう言われたらどう答える?」と気軽に相談できない空気があるんだと思います。
それが、管理職の大変さ、ひいてはネガティブイメージを生んでいる問題点なのですね。どうすれば、そんな孤立無援の状態を改善できるのでしょうか?
坂爪さん
これも、会社側が仕組みでサポートできると思います。
たとえば、「男性部下から『3か月の育休を取りたい』と言われたときにどんな対応をしたか」など、具体的なやりとり事例をまとめたサイトをオープンするとか。あるいはAIを取り入れて、「こんな場面ではどう答えるのが適切だろうか?」と気軽に壁打ちができるようにするのもよいですよね。

「サポートなんかしなくても、“管理職”だったらできるよね」という丸投げの姿勢が、管理職の苦しさを生んでいる要因の一つ。会社は、きちんと管理職への投資も行っていくべきだと思います。
「手札」と「ビジョン」を磨け
過酷な管理職という役目に就いていても、部下と良好な関係を築き、成果を上げている人もいると思います。坂爪先生から見て、そうした「できる管理職」に、なにか共通点はありますか?
坂爪さん
一つは“手札”がいっぱいあることですね。
どんな管理職でも、部下との相性がよいときは、うまく部下を動かすことができるんですよ。でも、今は部下が多様化しているから、ハマらない確率も上がっています。一方、相手を動かす“手札”をたくさんもっている人は、どんな部下がチームに来ても、うまく関係を築き、しっかり育成していくことができるんです。

“手札”というのは、言うなれば、コミュニケーションを取る際の言葉のバリエーションや、伝え方の組み合わせです。たとえば、Aさんにはこの順番で話す、Bさんには逆のほうが納得してもらいやすい。Cさんはこの話から入ると嫌な話にも耳を傾けてくれる。そんなふうに個別に関わり方を変えていくんです。
それが自然とできているのが、今の「できる管理職」の特徴の一つだと思います。
もう一つは、自分の意志を語れることです。「こんな職場をつくりたいんだよね」「この仕事ってこういう意義があると思うんだよね」など、チームで共有できるような“ビジョン”を語れること。発信力があることと言い換えても構いません。
今は誰もが「なんでこの場にいるんだろう」「このままで大丈夫かな」と自問自答する時代です。とくに若手はキャリアに不安を抱えている人が多い。だからこそ転職も活発になっているわけですよね。逆に言えば、ほっとくと簡単に人が離れていってしまう時代なんです。

そんな時代で、「ここにいたほうがいいよ!」「ここで、こういう未来を一緒につくっていこう!」と魅力的な未来予想図を見せられるかどうか。それは、最後までAIには代替できない、マネージャーに不可欠な力なんじゃないかなと思っています。
もちろん、「あなたに言われたって……」と思われるような仕事への向き合い方や関係性じゃいけない、という前提がありますけどね(笑)。
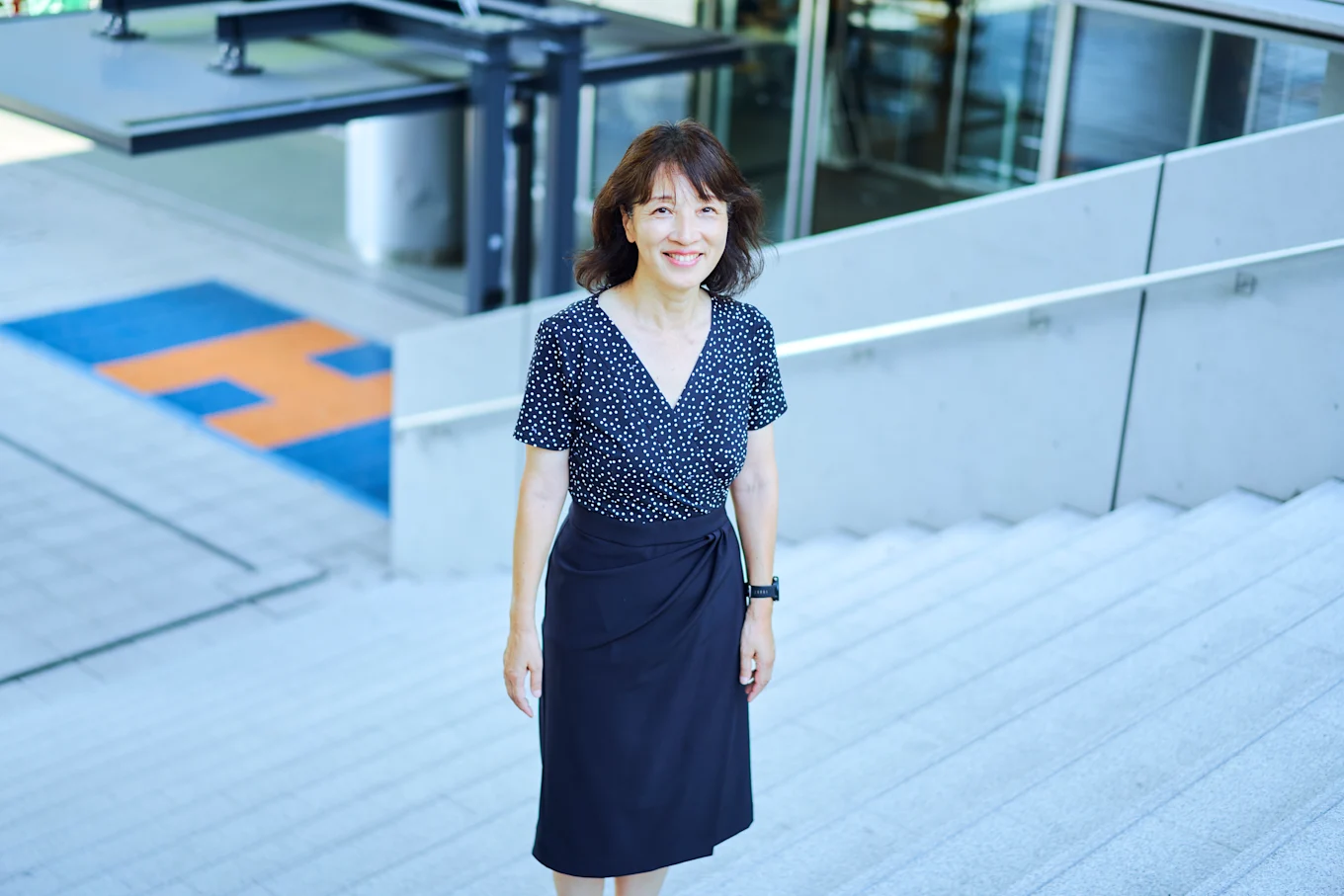
これから、AI導入などによる大きな変化も予測され、ますます企業の働き方は多様化し、産業も複雑化していくと考えられます。管理職の仕事はどう変わっていくでしょうか?
坂爪さん
AI導入が進むと管理職の仕事は変わってくるかもしれません。負担が減る可能性もありますし、管理職の機能が一部代替されることで「管理職ってなんで偉いんだっけ」といった疑問が部下から出てくる可能性もあります。部下との関係性が変化すると、これまでの部下マネジメントが通じなくなるかもしれません。「やることは変わらないけどやり方がかわる」「やることが知らず知らずに積み重なる」という現象は続きそうです。その中でも「こうしよう」「こうなろう」という未来を描き示すことの重要性は高まると考えます。そもそも、「管理職が大変」というより、企業全体が大変になっていくんですよね。より良い人材を採ろうと思ったら、働き手に選ばれる会社でなければいけませんから。会社として、どうありたいのか、人的資本の確保のためにどんな取り組みをしているか。そのメッセージが必要不可欠になるでしょう。
残業時間や育休取得率といった、いわゆる「働きやすさの指標」を改善していくことも当然必要ですが、会社としての業績や将来的なビジョンも大切です。「この船に乗ってみたい!」と思わせられる、会社としての魅力が必要だと思います。
そのために、経営層がしっかりと人事の仕組みづくりを行い、良い組織風土を築いていかなくてはならないと思います。形だけの取り組みを管理職に丸投げするのではなく、自社の社員に本当に必要な取り組みはなんなのか。管理職に、若手に、どんな投資をしていくべきなのか。管理職が人材マネジメントに不可欠な存在であるなら、管理職にもっと投資をする必要があります。人材マネジメントというと制度作りに焦点があたりがちですが、運用面を重視した人材マネジメントにより向き合うときが来ているのではないでしょうか。

サービス10周年を記念した、特設サイトを公開中
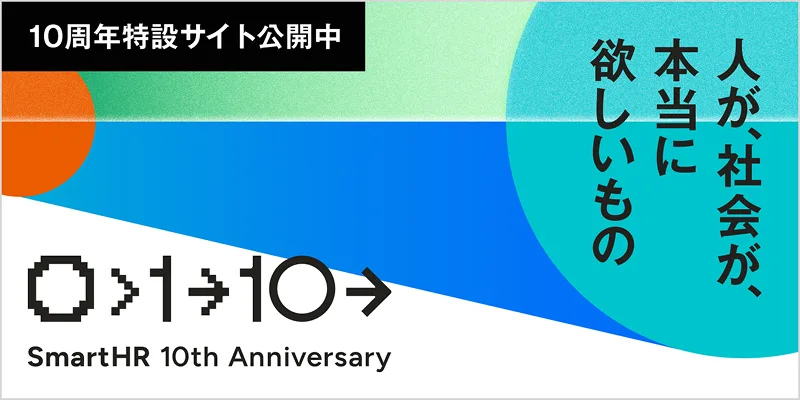
2025年、SmartHRはサービス提供開始10周年を迎えることができました。特設サイトでは、ユーザーのみなさまとSmartHRが10年のなかでともに変化してきた歩みをたどった対談記事、サービス成長の軌跡、これからの“働く“を考えるヒントを探す有識者インタビュー、SmartHR代表の芹澤雅人による次の10年に向けたメッセージなど、さまざまなコンテンツを掲載しています。
取材・執筆:水沢環
写真:岡田健
編集:野路学(株式会社ツドイ)


























