全員が社長になる未来? 「AIネイティブ」時代の企業アップデート
- 公開日

AIが仕事を奪う——かつて予測のひとつにすぎなかったこの言葉は、すでに現実となりはじめました。“AIと共存する世界”が急速に形づくられている今、企業や働く人々にはAIを使いこなすための思考や、生き残るための組織改革が迫られています。5年後、10年後、人々の働き方や企業の姿はどのように変わっているのでしょうか。生成AI研究の最前線に立つ今井翔太さんに、人間の役割の未来と、変化の波を乗りこなすヒントをうかがいます。
株式会社GenesisAI代表取締役社長/CEO 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)客員教授
東京大学大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻 松尾研究室にてAIの研究を行い、2024年同専攻博士課程を修了し博士(工学)を取得。人工知能分野における強化学習の研究、とくにマルチエージェント強化学習の研究に従事。ChatGPT登場以降は、大規模言語モデルなどの生成AIにおける強化学習の活用の研究を行う。2024年7月に株式会社GenesisAIを創業し、同社代表取締役社長/CEO。2025年より北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)客員教授。著書に、生成AIのベストセラー『生成AIで世界はこう変わる』(SBクリエイティブ)など。
AIに仕事を奪われる時代、人間の強みはどこに?
多くの人が生成AIを日常的に使うようになり、仕事への影響も大きくなってきています。AI研究の第一人者である今井さんは、現在の生成AIやその影響をどう捉えていらっしゃいますか?
今井さん
我々研究者の予想よりも早く、“人間の役割が見直される時代”になったなと思っています。

もともと、僕たちは2010年代からずっと「生産性に関わる仕事はなくなる」と言っていたんですね。なぜなら、汎用人工知能(AGI)と呼ばれる、「特定の生成タスクだけでなく、人間と同じように汎用的な知能処理ができる人工知能」は確実につくれるはずだから。
ただ、そんなAGIができるのは、2050年〜60年くらいの話だと思っていたんです。でも、生成AIの急激な進化によって、2020年代〜2030年ごろにはAGIが実現されそうな流れになっていますよね。
すでに、自分の仕事をAIに浸食されている人たちも出てきています。なかでもプログラマーやイラストレーター、ライターなどは、その実感があるんじゃないでしょうか。
日本は規制が厳しいのであまり見かけないですが、アメリカでは雇用もどんどん切られています。とくにプログラマーの雇用統計を見ると、2022年を境にガクンと減っている。GAFAやマイクロソフトなんかに勤めていた優秀なエンジニアが、自分たちが開発したAIによって首を切られているわけですから、とんでもない事態ですよね。
我々研究者にとっても予想外のスピードで人間の役割が変わりはじめています。これからその波がますます多くの職業へ広がっていくでしょう。
そんな状況を聞くと、「自分もAIに仕事を奪われるのでは」と恐怖を感じる人も多いかもしれません。AIには奪われない、人間にしかできない役割とはなにか。ぜひ今井さんの考えをうかがいたいです。
今井さん
いわゆる“仕事”とはちょっと違うんですが、機械にはできない人間の役割を挙げるとすれば、2つ思い浮かびます。ひとつは競技性のあること。
たとえば、囲碁や将棋って、どう考えても今は機械のほうが強いですよね。将棋ソフトを使えば、そのへんの小学生だって99.9%藤井聡太名人に勝てる。陸上とかもそうで、「早く移動する」だけだったら、ウサイン・ボルトも役立たずです。でも、どれも人間がやることに意味がある。なぜなら「競技」という形で、現実世界の生産性や単純な勝ち負けとは切り離されているからです。
競技性があることは、これからも人間にしかできない役割だと思います。

もうひとつは、人間らしい価値判断です。人間の強みって、「人間社会にとてもよく馴染んでいる」点にあると思うんです。人間の身体で、何十年も人間社会を生きてきているわけですから。
これからもデジタル環境を使ったシミュレーション技術なんかは発展していくと思いますけど、それでも、人間が住んでいる物理環境や人間の身体をデジタルで完全に再現できるわけではない。であれば、人間社会に合った価値判断というのは、人間の方がうまくできると思うんです。
たとえば、きちんとした指標ではなく、長年業界に精通している人の価値判断に従う方が成功率が高かったり。AIマーケティングによる広告施策より、経験則に基づいたデザインの広告の方が閲覧率が高い。そういった事例は変わらず残っていくだろうと思いますね。
なるほど。そんなふうに人間の役割を見極めることと同時に、AIを上手く使っていくことも重要だと思います。どうすれば、AIを使いこなせる人間になれるのでしょうか?
今井さん
一番大切なのは、真っ当な基礎知識や教養を身につけることです。極端な話ですけど、今は小学生でもスマホでAIを使えますから、アクセスできる(もっている)知識量としては、僕と変わらないんですよね。でも、たとえば「AI研究」で勝負をしたら、小学生が百万人束になっても、僕が圧勝するでしょう。
なぜかと言うと、僕は「AIになにを聞けばいいのか」がわかるから。AI研究に関する基礎知識があるからです。膨大な知識をもっているAIから、いかにして適切な知識を切り出すか。誰もがAIを使えるからこそ、その人自身にインストールされた知識の量が差を生むことになるんです。

とは言っても、「すべてを知る」必要はありません。今の世界って、情報が多すぎるんですよね。それこそAIを使えば無限に手に入ってしまう。そのせいで、あれもこれもと際限がなくなったり、「これを全部知らなきゃいけないなんて……」と絶望してしまいがちです。
だけど、知識は“ある程度”で十分です。AIがあるんですから。
情報過多のこの世界では、「自分はどこまで知るべきで、なにを知らなくていいのか」を見極める必要がある。基礎的な知識があれば、その線引きの感覚もおのずとつかめるはずです。

AIネイティブな会社が、既存企業を駆逐する
生成AIがものすごいスピードで発展している一方で、日本企業での導入率はわずか17.3%にとどまっています(帝国データバンク『生成AIの活用状況調査』2024年)。普及を妨げているのには、どんな要因があると考えられますか?
今井さん
まずひとつは、純粋に今のAIの性能不足ですね。すごく賢くなっているのはたしかですが、所詮文字を出力できるだけ。今のAIにできることには限界があるのだろうとは思います。
これはやや研究に込み入った話になりますけど、我々研究者が今悩んでいるのが、AIの賢さを測る手段がもうなくなっていることなんです。
東大の入試問題も、Googleの入社試験の問題も、フィールズ賞を受賞した数学者がつくるまったく新しい数学問題も、AIは全部解いてしまった。じゃあ、すでに汎用人工知能(AGI)になっているかと言うと、まったくそんなことはないんですよね。

どれだけ難しい問題をクリアできても、なぜかAGIはできない。これ以上、なにをもってAIの賢さを測っていけば、AGIが実現するんだろう。そんな壁にぶつかっているのが今なんです。
さらに言えば、そもそも「仕事ができる人間」の能力を測る方法ってあったんだっけ?って疑問も噴出していて。たとえば、入社試験で主席だった人が、入社後に必ずしも「一番仕事ができる人」になるとは限らないですよね。その視点はAIにも当てはまります。どれだけ難しい問題を解けるAIでも、会社で「仕事ができる」とは言い切れないわけです。
つまり、我々はここ数か月くらいで「人間らしい本当の知能」を測る方法がない、という問題に気づき始めたところなんですね。この辺りの問いがクリアにならないと、AIが普通の会社で導入できる性能になるのは難しいのかもしれません。
なるほど。「難しい問いを解ける」以外の、新しいAIの知能のモノサシが必要なんですね。
今井さん
はい。そしてもうひとつ、企業内の業務フローやデジタルツールが完全に「人間向け」になっている点も、AI導入が進まない要因だと考えられます。
一旦物理空間でたとえますけど、会社のなかには階段や椅子がありますよね。ロボットって、車輪でスルスルスルッと移動できるから、人間よりも速くて効率的なはず。なのに、現実はそうはいかない。ロボットには階段を上れないからです。同様に、人間にとっては当たり前の「椅子に座る」動作もロボットにはできません。
要するに、今の世界って、人間の身体がないと使えないものばかりなんです。今まで、この世界で仕事をするための存在、つまり労働力は、人間しかいなかったから当然なんですけどね。

これと同じようなことが、デジタル空間でも、業務フローのなかにもいっぱいあるんですよ。たとえば、みなさんがよく読むPDFはAIにとっては読み取りづらいし、印刷したり、ハンコをもらったりするフローはまさに「人向け」でしょう。つまり、今の世界や社内は人間向けに整えられすぎていて、AIが活躍できる環境にはなっていないわけです。
実際に企業のなかでAIがうまく働けるようになるためには、いろんな環境を「AI向け」に整備していかないと難しいんじゃないかと思います。
新しい労働力としてAIを受け入れる準備ができていない、と。性能不足と準備不足、2つの問題点は今後クリアされていくのでしょうか?
今井さん
性能不足の問題は、クリアされるだろうと期待したいです。少なくとも、AI自体の発展としては、性能が上がっていくしかない。とはいえ、我々研究者が人間の知能を測る基準の不在をうまく解決できるかですね。
一方、環境整備についてはかなり難しいかもしれません。
だって、人間に合わせてつくられている諸々を丸ごと全部ぶっ壊して、新たに構築するって、なかなかできないですよね。デジタル空間についてはまだ可能性があるかもしれませんが……、それでも社内の業務フローの完全改革は、よほど勇気のある企業じゃないと難しいと思います。とくに大企業であればあるほどそうでしょう。
場合によっては、新しく設立された、完全にAIネイティブな会社のほうが強いのでは、と思いますね。業務スピードも、成長スピードも段違いに速いでしょうから。そういう企業が増えていったら、既存の企業がごっそり駆逐される可能性もあると僕は思っています。
AIネイティブの会社、というのは?
今井さん
最初からAI向けに業務を構築している会社、というイメージです。

たとえば僕の会社は、最初から人間は僕ひとりで、業務は全部AIにやらせています。これは別に人間を排除したいと思っているわけではなくて。どれだけAIが働いてくれても、必ずどこかで人間が必要な場面が出てくるんですよ。だから僕は、「AIに極限までやらせてみて、AIができなかったところに人間を雇い入れていこう」って発想なんです。
つまり、これまでの企業のように「人間が働く前提」でAIを入れる、という発想自体を逆転させて、「AI前提」に刷新した企業がAIネイティブの会社です。今後は、そんな企業が台頭していくのではないでしょうか。
AIと労働が混ざり合った未来で
AI導入をためらう企業の声を聞くと、「外部に流出しては困る機密情報を多く取り扱っているため、AIを導入するのは難しい」という意見も多いです。SmartHRが重点を置く人事領域はとくにそうした懸念が強いのですが、今後のAIの発展とともに、そんな危惧もなくなっていくのでしょうか?
今井さん
おっしゃる通り、そこは難しい問題だと思います。
少なくとも、人事領域には地雷が埋まりすぎている。たとえば、採用時にAIで評価を下すのはもはや古典的な炎上ネタですよね。人事領域におけるAI導入に関しては、技術的、生産性的な問題というよりも、倫理や価値観の観点で、慎重にならざるをえない部分だと思います。

採用領域でのAI導入に関しては、僕個人的には「選ぶ側(企業)より選ばれる側(働き手)が有利になる使い方」ならいいんじゃないかと思っています。
たとえば、普通の入社試験で、受験者のすべてを完璧に知り尽くすことはできないじゃないですか。わずかな面接時間で人生の蓄積全部を語るなんて無理だし、だからといって事前に100万字のエッセイを書くのも不可能。そもそも人事が読む時間もありませんよね。
でも、AIだったらできる。受験者の情報をいくらでも読み込むことができるし、それを整理して資料化するのだって一瞬です。
つまり、AIを使えば、受験者が「これを伝えられたら受かったかもしれないのに」と後悔するのを防げるんです。もちろん、企業側の「これを知っていたら採用したかった」という心残りもなくせるでしょう。
たとえば採用の場面で、最終判断をするためではなく、判断材料を増やし、受験者の本質を汲み取るためにAIを使う。そんなふうに、企業にだけ都合がよいのではなく、「働き手」にとって有利になる使い方ならば、人事領域でもAI活用の可能性は大いにある気がします。
たしかに、それはお互いにとってメリットの大きいAIの活用法ですね。
今井さん
それから、機密情報に関しては、今後AIのサイズが小さくなっていけばクリアできるかもしれません。ここでいうサイズとは、AIの「パラメータ」と呼ばれるものの数のこと。パラメータは、AIの頭脳をつくる小さなネジのようなもので、この数が多いほど複雑で賢い振る舞いができますが、そのぶん巨大なコンピュータが必要になります。
今みなさんが使っているChatGPTやGemini、Claudeなどの生成AIは、実は我々がもっているスマートフォンやPCのなかで直接動いているわけではありません。端末の処理能力ではまったく足りないため、実際にはOpenAIやマイクロソフト、Googleといった企業がもつ大規模なサーバー上で動いています。
もちろん各企業は、機密情報保護のために国際的なセキュリティ認証を取得したり、データを高度に暗号化するなどの対策を講じていますが、極論外部のサーバーを経由しているから、機密情報が流出するのではないかという懸念が生まれるわけですよね。

でも、最近では、AIのサイズがどんどん小さくなっていっているんです。例を挙げると、2023年3月14日に登場したGPT-4は、約1.8兆のパラメータを持つ巨大なモデルだったのですが、今は、約90億パラメータのモデルでも、GPT-4に近しい性能を発揮できるようになっています。実に200分の1になりました。
「1.8兆が90億に」という数字の変化だけでも小型化のスピード感は伝わると思いますが、最近の研究論文では、「3ヶ月ごとに必要なサイズが半分になる」とも報告されています。
この傾向を考えれば、いずれは、すごく性能の高いAIも、自分たちのPCのなかだけで処理が完結できるようになると思います。なので、究極的には機密情報の問題も、おそらく時間経過による技術進展によって、クリアできるだろうと思いますね。
そんなふうにAIが順調に発展し、企業への導入も進んでいくとすれば、私たちの働き方はどうなっていくでしょうか?
今井さん
難しい問題ですが、大きく変わっていくことは間違いないですよね。
たとえば「全員が社長になる」みたいなことも起こっていく。みんなが組織上の決定権をもつわけじゃないですけども、「AIに指示する存在としての社長」みたいな人がいっぱい出てくると思いますね。
最近は、会社に属さず、生成AIでプロダクトを生み出してお金を稼いでいる「LLM(大規模言語モデル)無職」と呼ばれる人たちも増えています。そんなふうに、職に就かない人も増えていくでしょうし、「組織」自体、正直どうなるかわかりません。

ただ、僕としては「それでもみんなで集まる」方向をやや信じていますね。
なぜなら、人間、ホモサピエンスは、誕生してから30万年もの間、社会的な動物として生きてきた生物だから。社会的じゃないと生き残れなかったと言ってもいいです。そう考えると、生物学的な本能の部分で「人と集まらない」ことを拒否するのかも、と思うんです。
なるほど。おっしゃるように、誰にも正確な未来予想図が見えないなかで、私たちはどんな心構えをもつべきなのでしょうか?
今井さん
これから求められるのは、自分自身が変化し続けて、社会全体の変化の波に対応していくことだと思います。たとえば、続々と登場する新しいAIを積極的に使うことも、「自分自身の変化」のひとつでしょう。
周りを見ていると、新しいツールをバンバン取り入れている人って、「仕事を仕事とだけ捉えず、遊びのように取り組める人」だと思います。研究者はまさにそんな人が多いですけども、日常と仕事が同化していて、休日なんて関係なく、本来「仕事」であるはずのことを遊ぶようにやっているんですね。
それはなぜかと言うと、「相手より上にいきたい」という競争意識が強かったり、自分を高められること自体を幸せだと思っているからだったりする。そういう向上心があるから、いろんなものを学び取っていくんだと思うんです。
反対に、なかなか新しいツールに手を出さない人は、仕事と人生を完全に切り分けているんだと思います。だから、取り入れる動機があまりないんですね。
そうした考えももちろんありだと思いますが、AI時代の変化に対応していくという意味では、あまりそぐわない可能性もあります。そう思うと、根本的な向上心みたいなものは、これからのAI時代を乗りこなしていくうえでひとつ、カギになるのかもしれません。

サービス10周年を記念した、特設サイトを公開中
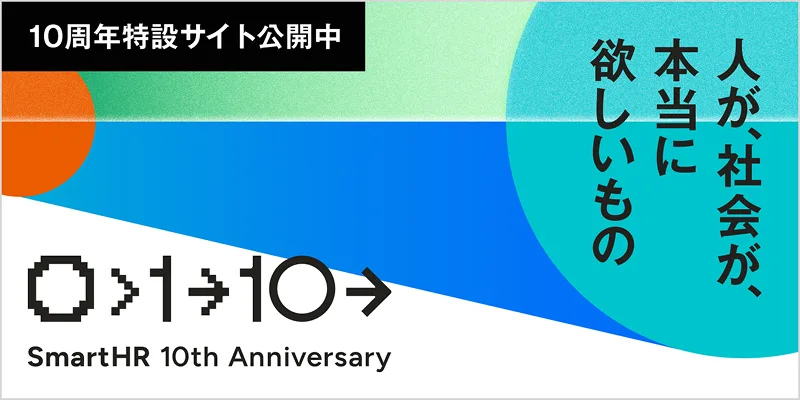
2025年、SmartHRはサービス提供開始10周年を迎えることができました。特設サイトでは、ユーザーのみなさまとSmartHRが10年のなかでともに変化してきた歩みをたどった対談記事、サービス成長の軌跡、これからの“働く“を考えるヒントを探す有識者インタビュー、SmartHR代表の芹澤雅人による次の10年に向けたメッセージなど、さまざまなコンテンツを掲載しています。
※2025年7月末に取材しています。
取材・執筆:水沢環
写真:小池大介
編集:野路学(株式会社ツドイ)


























