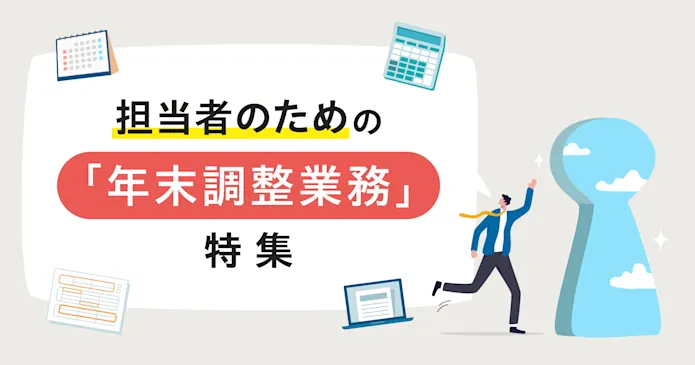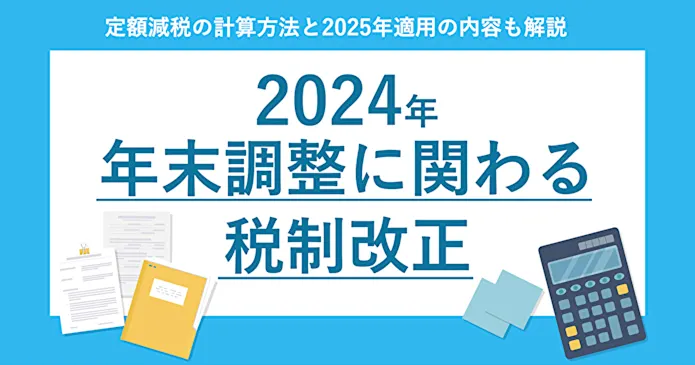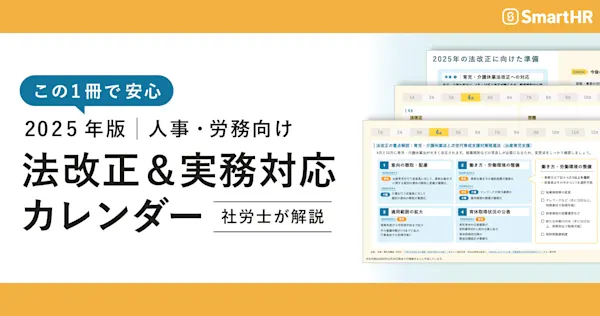年末調整で知っておくべき「扶養控除」「配偶者控除」の対象範囲や注意点
- 更新日
- 公開日

扶養控除は、年末調整を受ける給与所得者にとって、所得税や住民税の金額に関係する重要な仕組みです。また、健康保険上の扶養に関するルールもあり、世帯全体の保険料負担がどうなるのか気にしなければならない場合もあるでしょう。さらに、今年に関しては定額控除にも影響が考えられます。
今回は、「どのような家族・親族が扶養控除の対象になるのか」「年末調整に必要な扶養控除申告書の作成時に、どのような点に注意すべきか」などについて、解説していきます。
「源泉控除対象配偶者」の要件
2018年から配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みや控除できる年収の上限金額などが大きく変わりました。この改正に伴い、年末調整のときに使用する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式も変更され、これまで「控除対象配偶者」とされていた欄が「源泉控除対象配偶者」となりました。
また、配偶者控除を適用できる納税者の条件や、配偶者の年収の上限も変更されたので、世帯の状況によっては働き方を考えてみる必要があるでしょう。従来は配偶者控除を適用できる納税者本人の年収額に制限はありませんでしたが、年間の所得見積額900万円超え(給与年収1,120万円超え)の方は適用できなくなりました。
一方、所得金額が900万円以下の方は、配偶者の所得金額が48万円以下であれば配偶者控除、49万円超95万円以下(給与年収150万円以下)であれば満額の配偶者特別控除が適用されます。
これまでの税金に配慮して労働時間を調整するパート勤務の方などは、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も考慮する必要があります。
ただし、納税者が個人事業主であって、「青色事業専従者」や「白色事業専従者」として納税者から給与の支払いを受けている配偶者の場合は適用されない点には注意してください。
「控除対象扶養親族」の4つの種類
配偶者以外にも扶養している親族がいる場合、年齢別に4つの種類の控除が適用されます。
「一般の控除対象扶養親族」に該当するのは、16~18歳・23~69歳の親族で控除額は38万円です。
大学生などの教育費の負担が大きいとされる19~22歳の親族は「特定扶養親族」に該当し、税負担を軽減する目的で控除額は63万円に設定されています。
アルバイトをしている大学生など、扶養されている親族の年収が103万円を超えると控除の対象から外れてしまいますので、働きすぎに注意したほうがよいでしょう。
70歳以上の親族は「老人扶養親族」で、同居の場合は58万円・その他の場合は48万円が控除されます。親族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判断する決まりです。
「扶養」で押さえておきたい2つのルール
扶養に関する決まりには「税法上の扶養」のほかに「社会保険上の扶養」もあります。扶養対象にするための親族の収入限度額などが異なっているので、きちんと理解しておきましょう。
親族を「税法上の扶養」の対象にしたい場合には、その親族の給与年収が103万円以下であることが必要です。いわゆる「103万円の壁」というやつですね。控除対象になれば、納税する本人の収入から控除され、所得税や住民税の一部が免除されます。
「社会保険上の扶養」は、健康保険料や年金保険料の負担をすることなく社会保険に加入できることを意味しています。
具体的には、子どもやパート勤務の主婦などが夫の勤務先の社会保険に加入している例が挙げられるでしょう。給与年収が130万円を超える見込みになったときには、扶養対象から外れて自分で社会保険料を負担する決まりです。
扶養から外れた親族は、年間で20万~30万円程度の保険料を負担して国民健康保険・国民年金に加入、または勤務先の社会保険に加入します。
「配偶者控除額が変更になったからもっと働きたい、でも社会保険料を自己負担したくない」というパート勤務の配偶者などがいる場合には、「いくらまでの年収範囲で働くか」を考えたほうがよいでしょう。
「年少扶養親族」は控除の対象とならない
「児童手当」支給の対象となる16歳未満の年少扶養親族は、所得税上では扶養控除の対象になりません。
年少扶養親族と生活しているにもかかわらず、収入の関係で児童手当を受給していないという場合でも扶養控除の対象にすることはできない決まりです。
ただし、住民税については「非課税限度額」という特別な制度があり、16歳未満の子供の有無もその判定に関わってきます。今年に関しては、16歳未満であっても定額控除額の計算対象にもなります。
そのため、扶養控除等申告書の年少扶養親族に関する事項には記入が必要ですので、注意しましょう。
告知資料の配布などで確実な申告書回収を!
結婚・出産、子どもの進学・独立など家族構成やライフスタイルの変化によって、扶養控除の対象者も変わっていきます。
その変化を正確に年末調整の結果に反映させるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員から提出してもらうことが必要です。
申告書の提出がないと年末調整ができないにもかかわらず、提出が遅れがちな従業員がいると労務管理担当者は困ってしまいます。
年末調整を年内に確実に完了させたい場合には、申告書記載方法のポイントや提出期日を明記した文書を早めに従業員に配布し回収するなどの工夫をしましょう。

お役立ち資料
担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整
年々複雑化する年末調整に関するマニュアルのアップデートや、従業員からの質疑応答に大幅に時間を取られるなど、大量の書類管理に追われ残業が増えてしまう人事・労務担当の方も多いのではないでしょうか。
わかりやすくて使いやすいと好評のSmartHRのペーパーレス年末調整についてご紹介します。
【こんなことがわかります】
- SmartHRの年末調整はココが違う!
- 年末調整システム導入時の注意点

メールマガジン「週刊SmartHR Mag.」
社会保険労務士や弁護士など、人事・労務の専門家による実務に活かせる生の情報を発信していきます。メールマガジンでしか読めない専門家のこぼれ話なども掲載中です!