マイカー通勤手当「非課税限度額改正」タスクと注意点
- 公開日

目次
こんにちは! 開業社会保険労務士の岸本です。自動車やバイク、自転車などで通勤する従業員が受け取る通勤手当について、非課税限度額の引き上げが令和7年(2025年)11月20日に施行されました。
改正のポイントは、改正後の非課税限度額が令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当にもさかのぼって適用されることになり、本年の年末調整で精算が必要となる点です。
本記事では、今年度の年末調整業務における実務上の注意点をご紹介します。
非課税限度額が改正された経緯
令和7年の8月7日に令和7年人事院勧告が行なわれ、令和7年4月1日以降の措置内容として勧告された「自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当額の引き上げ」が、今回の改正のきっかけとなっています。

主な対象は自動車通勤などの通勤手当
これは「自動車などを使用して通勤する国家公務員に対して、通勤手当の金額が引き上げられた」ものです。そして、金額変更に伴って一般企業で給与として支給されている「通勤手当の所得税法上における非課税限度額」についても、同じタイミングで改正がなされました。
今回の改正は「令和7年4月1日以降」に遡及適用されます。これは、国家公務員に対する制度が年度単位で整理されている側面もあり、同様に年度初めの4月1日を基準とした改正内容になったものと考えられます。
自動車などを利用する通勤者の
通勤手当における改正後の非課税限度額
給与所得者に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税です。自動車などで通勤する人に支給する場合、1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。
令和7年11月20日に所得税法施行令の一部を改正する政令が施行され、通勤のために自動車やバイク、自転車などを使用する人に対して支給する通勤手当の非課税限度額が、以下の表のとおりに引き上げられました。
区分 | 課税されない金額 | ||
改正後 (令和7年4月1日以後適用) | 改正前 | ||
①交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) | 同左 | |
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上である場合 | 38,700円 | 31,600円 |
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 32,300円 | 28,000円 | |
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 25,900円 | 24,400円 | |
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 19,700円 | 18,700円 | |
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 13,500円 | 12,900円 | |
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 | 7,300円 | 7,100円 | |
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 | 同左 | |
通勤距離が片道2km未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) | 同左 | |
④交通機関または有料道路を利与するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額 (最高限度 150,000円) | 同左 | |
要対応の「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは
改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、以下については、改正後の非課税限度額は適用されませんのでご注意ください。
- 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
- 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
- 「1.」または「2.」の通勤手当の差額として追加支給されるもの
改正後の非課税限度額を適用後に過納となる税額がある場合には、本年の年末調整で精算となります。すでに支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下であれば、精算の手続きは不要です。
また本年の中途に退職した従業員など、年末調整で精算する機会がない場合は、確定申告により精算となります。
人事・労務担当者が実施する年末調整での精算手続き
年末調整での具体的な精算手続きは、次のとおりです。
- 改正前の非課税限度額で課税された通勤手当のうち、改正後の非課税限度額により新たに非課税となる金額を計算します。
- 「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の余白に「非課税となる通勤手当」と記載し、計算根拠と今回の改正により新たに非課税となった金額を記入します(ただし、正しく年調年税額が算出されているのであれば記載は省略可能)。

- また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額から新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。

- 改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれます。その差引後の給与総額をもとにして年末調整を実施します。
記入の具体例(例:片道50kmの自動車通勤の場合)
以下の例をもとに、具体的な計算方法と記入例をご紹介します。
- 片道50kmを自動車で通勤
- 毎月300,000円の給与と30,000円の通勤手当を支給
- 令和7年1月~10月までは改正前の限度額28,000円を適用して源泉徴収を実施
(1)改正前と改正後の非課税限度額を確認
通勤距離が片道45km以上55km未満の区分に該当するため、非課税限度額の改正前は「28,000円」、改正後は「32,300円」となっていることを確認します。
(2)令和7年4月1日以降に支給した通勤手当のうち、
課税支給として支給済みの金額を算出
毎月30,000円の通勤手当に対して、改正前の非課税限度額28,000円を超えて課税されていた金額(2,000円)を算出します。
(3)改正後の非課税限度額に照らして、
新たに非課税対象となる通勤手当の金額を確認
毎月の通勤手当が30,000円なので、全額が改正後の非課税限度額「32,300円」以内となり、(2)で計算したひと月あたり「2,000円」が新たに非課税対象となることを確認します。
(4)非課税対象となる通勤手当の算出根拠と合計額を整理
4月から10月までの7か月が対象となるので、「2,000円」×「7か月」=「14,000円」が非課税対象となります。
(5)源泉徴収簿の余白に記載する内容と
「給料・手当等の①欄」から差し引くための金額を反映
余白には「非課税となる通勤手当14,000円(2,000円×7か月)」と記載し、「給料・手当等の①欄」から「14,000円」を差し引いた金額に反映します。

「実務者目線」6つのチェックポイント
以下の6点が注意点です。源泉徴収簿へ記入する前に確認しましょう。
(1)自動車などを利用した通勤者と手当支給の確認
まずは、自動車などを利用して通勤している従業員の有無と、該当者への通勤手当支給状況を確認しましょう。
(2)就業規則・賃金規程などの確認
もし、就業規則や賃金規程などに「所得税法上の非課税限度額を通勤手当として支給する」といった記載がある場合、通勤手当の追加支給が必要となる可能性もあるため要注意です。
※差額支給する通勤手当も非課税対象です。
(3)11/20以降に支払う給与への反映
11月20日以降に支払われる給与には、改正後の非課税限度額を適用することになっています。しかし、11月給与はすでに給与計算作業が終わっている場合も多いため、別途対応が必要です。
(4)給与・年末調整関連システムの確認
利用している給与計算システムや年末調整関連システムに、今回の改正内容がどのようにアップデートされるのか、いつされるのかを早めに確認しましょう。
(5)今年の退職者へ発行済みの源泉徴収票について
再発行が必要かどうかを早急に確認
年の中途に退職した人などに対して、すでに給与所得の源泉徴収票を交付している場合は要注意です。「支払金額」 欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付が必要です。
(6)年の途中で年末調整を実施した対象者の確認
年の途中に年末調整をした人(海外赴任者や死亡退職者など)で、対象となる通勤手当がないか確認します。
※対象となる場合には年末調整の再計算が必要です。
参考:通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A - 国税庁
焦らず確実な年末調整業務を!
今年の年末調整は、通勤手当の非課税限度額改正だけでなく、所得税の非課税ラインの引き上げなど、大きな変更があります。人事・労務担当者にとって例年よりも負担は大きくなりますが、焦らず確実な作業を心がけましょう。
対応する側は非常に大変な内容でもありますが、従業員にとってはメリットのあるものばかりとなっているので、このピンチをチャンスと捉えてポジティブ思考で進めていきたいところです。
また、正確かつ速やかに適切な対応を進めていければ、会社および人事・労務担当者に対する従業員の信頼度も必ず向上するはずなので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう!
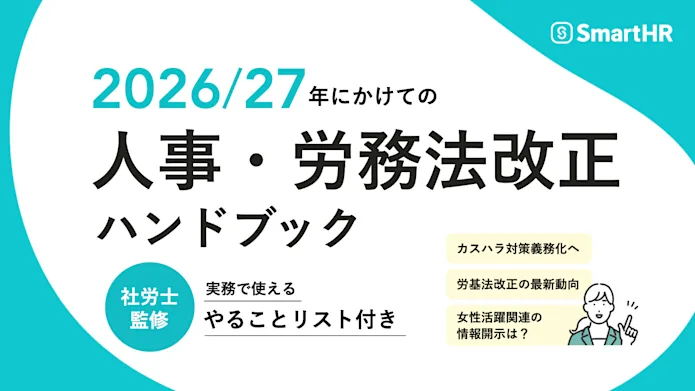
お役立ち資料
2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック
この資料でこんなことが分かります
- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正
- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正
- 人事・労務担当者 やることリスト


























