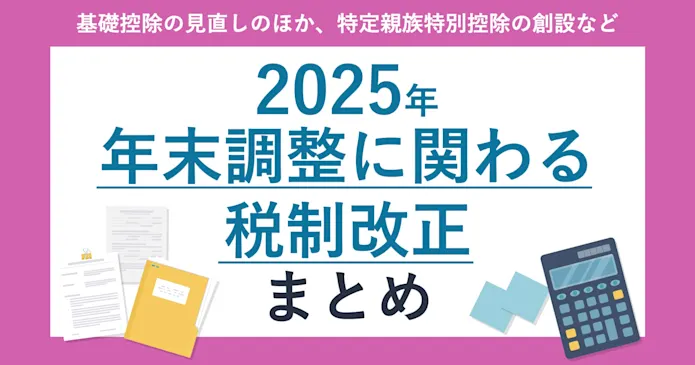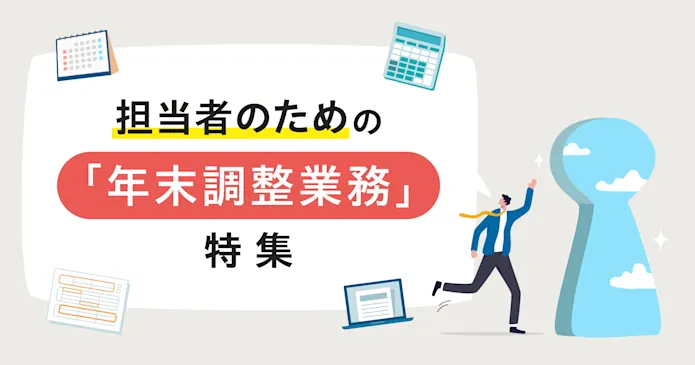所得金額調整控除申告書の書き方や計算方法を税理士がわかりやすく解説
- 更新日
- 公開日

目次
こんにちは。税理士の高橋です。
今年も早いもので、年末調整について考えなければならない時期がやってきました。
本稿では「所得金額調整控除申告書」の書き方や計算方法について解説します。こちらは令和2年の年末調整書類から登場してはいますが、まだまだ認知度が低く、多くの方にとって馴染みのない制度となっています。
まずは「所得金額調整控除」とは何かをあらためて確認したうえで、計算方法や申告書の記載方法を確認していきましょう。年収850万円を超える高所得者の方で、子供や特別障害者がいる世帯などが対象となる制度です。最大15万円の控除が受けられる可能性がありますので、該当する方はぜひ活用してください。
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、子供や介護者がいる世帯や年金を受給しているなど、一定条件に当てはまる世帯を対象に税負担を軽減する制度です。基礎控除や配偶者控除などといった所得控除の仲間ではなく、給与所得の金額を計算するうえでのいち項目という位置づけです。
令和2年からの所得税法の改正により、給与所得控除額に関して10万円の減額と上限金額の引き下げが行なわれました。10万円の減額は基礎控除の増額とセットで行なわれていますので、単純な増税とはなりませんが、上限金額の引き下げは対象となる方の税負担増に直結します。
「年収850万円を超える高所得者だから仕方ないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、負担が増えてしまう方のなかにも、養育すべき子供や特別障害者がいるといった事情を抱えている方もいます。そのような方の税負担を調整するために創設されたのが所得金額調整控除です。
所得金額調整控除の対象者
所得金額調整控除には以下の2種類があります。
- 子供・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
- 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
このうち年末調整で適用があるのは1のみですので、今回は1についてのみご紹介します。対象者は以下のとおりです。
所得金額調整控除の適用を受けるためには、まず「給与等の収入金額が850万円を超える」という要件を満たす必要があります。そのうえで、以下のいずれかに該当する場合に控除の対象となります。
納税者本人が特別障害者である場合:身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳の1級、重度の知的障害者などに該当する方が対象です。
同一生計配偶者が特別障害者である場合:配偶者が上記の特別障害者に該当し、かつ年間の合計所得金額が48万円以下である場合に適用されます。
扶養親族が特別障害者である場合:扶養親族のうち誰かが特別障害者に該当する場合が対象となります。
23歳未満の扶養親族がいる場合:その年の12月31日現在で年齢が23歳未満の扶養親族がいる場合に適用されます。子供の年齢や学生かどうかは問いません。
これらの要件に該当しない場合は、申告書の記載自体が不要です。
所得金額調整控除の計算方法
所得金額調整控除の具体的計算は以下のとおりです。
<給与等の収入金額が950万円の場合>
・所得金額調整控除:(950万円−850万円)×10%=10万円
計算自体は簡単ですが、1つだけ注意点があります。
所得金額調整控除の計算上、給与等の収入金額が1,000万円超の場合には1,000万円をベースとされます。
ですから、所得金額調整控除は(1,000万円-850万円)×10%の15万円が上限額となる点をおさえておきましょう。
給与所得の計算方法
所得金額調整控除ができる前は、給与所得の金額の計算は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算してきましたが、所得金額調整控除の対象者はも差し引くことになります(そのほかにも「特定支出控除額」というものもありますが、全国的にもあまり利用者の多くない制度でもありますのでここでは割愛します)。
給与所得の計算方法:給与等の収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除
給与所得控除額とは「サラリーマンの必要経費相当額」として設けられている控除で、給与等の額面を以下のような速算表に当てはめて計算します。

※実際に収入金額が660万円までの場合には、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得の金額を計算しますので、上記の計算とは若干異なる場合があります。
給与等の額面が950万円であれば、給与所得控除額は、以下の計算式となります。
給与所得の金額:950万円-195万円-10万円=745万円
所得金額調整控除申告書の書き方
だいぶ前置きが長くなってしまいましたが、この所得金額調整控除を年末調整で受けようとする場合には、今回の本題である「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。もちろん年末調整で織り込み忘れても、確定申告でフォローはできますが、会社が手続きをすることですべてが完結するのであればその方が従業員は楽です。
それでは、所得金額調整控除申告書の書き方を解説します。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
同じ用紙でありながら、「所得金額調整控除申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の特定親族特別控除申告書」との間には大きな違いがあります。
ほかの3つは申告書の中で控除額まで記載するのに対し、所得金額調整控除申告書に記載するのは「どの要件に該当するのか」という点、つまり事実関係を記載するだけです。
給与所得の収入金額や控除額は会社側で把握できているので、あえて申告書に記載する必要はないわけです。
(1)「要件」欄
まずは1つめの「要件」欄です。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
こちらでは「どういった要件に該当するために所得金額調整控除を受けるのか」を選択します。
どこに印をつけるかによって右側の☆欄、★欄に記載が必要かどうか決まります。その点も書類に明記してくれていますので、指示に従いましょう。
なお、今年から「注2「特別障害者」、「同一生計配偶者」及び「扶養親族」に該当するかは、裏面の4-1の(4)をご確認ください」とあるので、確認するようにしましょう。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
(2)「☆扶養親族等」欄
2つめは「☆扶養親族等」欄です。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
こちらには「要件」欄の「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が年齢23歳未満」、つまり親族の状況を要件として所得金額調整控除の適用を受ける場合に、その親族の状況を記載することになります。
記載内容は、氏名、フリガナ、個人番号、生年月日、別居している場合の住所、続柄はとくに問題ないかと思います。
少し面倒なのはその方の合計所得金額ですが、こちらはこの用紙でこれまでも登場しているのでもう大丈夫かと思います。
合計所得金額の計算方法については、以下の記事をチェックしてください。
(3)「★特別障害者」欄
最後に3つめの「★特別障害者」欄です。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
こちらには「要件」欄で「あなた自身が特別障害者」「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」に印をつけた方がその特別障害者の状況などについて記載します。
なお、所得税法上の特別障害者とは、障害者のうち特に重度の障害のある方をいい、たとえば以下のような方が対象となります。
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
申告書にはこのような要件に該当するかどうかを具体的に記載しなければなりませんので、この欄には障害の状態、交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の等級などを記載することとなります。
なお、特別障害者に該当する人が「扶養控除等申告書」に記載している特別障害者と同一である場合には、特別障害者に該当する事実の記載に代えて「扶養控除等申告書のとおり」と記載して差し支えありません。
所得金額調整控除を行う際の注意点
年間の給与所得が850万円を超えるかわからない場合
年末調整の申告書を提出する時点で、正確な給与収入が確定していないケースがよくあります。このような場合でも、年収が850万円を超える可能性があるなら、所得金額調整控除申告書は提出しておくことをおすすめします。
実際の年収が850万円以下だった場合、所得金額調整控除は適用されませんが、申告書を提出したことによる不利益はありません。一方で、申告書を提出せずに年収が850万円を超えても、年末調整では控除を受けられず、確定申告が必要になってしまいます。
複数の会社から給与所得があり合計で850万円を超える場合
副業などで複数の会社から給与収入がある場合、それぞれの会社での給与は850万円以下でも、合計すると850万円を超えることがあります。
この場合、所得金額調整控除は主たる給与の支払者(通常は本業の会社)でのみ適用できます。年末調整では一つの会社でしか処理できないため、複数の給与がある場合は最終的に確定申告で正しい金額に調整することになります。
1円未満の計算処理方法
所得金額調整控除の計算では、1円未満の端数が生じる場合があります。税務上の計算では、1円未満の端数は切り上げて処理します。
ただし、実際の計算では円単位での端数処理が発生する可能性がありますので、給与計算システムや税務ソフトの処理方法に従ってください。
夫婦がともに850万円を超える給与所得がある場合
夫婦それぞれが年収850万円を超える場合、要件に該当すればそれぞれが所得金額調整控除を適用することができます。
とくに注意が必要なのは、23歳未満の扶養親族(子供)がいる場合です。この場合、夫婦のどちらか一方が扶養親族として申告することになりますが、所得金額調整控除は、扶養親族を申告した方のみが適用を受けることができます。
たとえば、夫が子供を扶養親族として申告している場合、妻は年収が850万円を超えていても、子供を理由とする所得金額調整控除は適用できません。ただし、妻自身が特別障害者である場合や、配偶者が特別障害者である場合などの要件に該当すれば、それぞれが控除を受けることは可能です。
夫婦で所得金額調整控除を受けるには、扶養親族の申告をどちらで行うかを事前に検討しておくことが重要です。
年末調整はコツコツ進めましょう
所得金額調整控除申告書は馴染みのないものですから、なんとなく「よくわからないもの」と考えてしまいがちですが、記載する内容は決して難しいものではありません。
最大15万円とはいえ、逃してはもったいない控除になりますので、今のうちに書類への記載方法を身につけてしまいましょう。

お役立ち資料
担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整
年々複雑化する年末調整に関するマニュアルのアップデートや、従業員からの質疑応答に大幅に時間を取られるなど、大量の書類管理に追われ残業が増えてしまう人事・労務担当の方も多いのではないでしょうか。
わかりやすくて使いやすいと好評のSmartHRのペーパーレス年末調整についてご紹介します。
【こんなことがわかります】
- SmartHRの年末調整はココが違う!
- 年末調整システム導入時の注意点

メールマガジン「週刊SmartHR Mag.」
社会保険労務士や弁護士など、人事・労務の専門家による実務に活かせる生の情報を発信していきます。メールマガジンでしか読めない専門家のこぼれ話なども掲載中です!