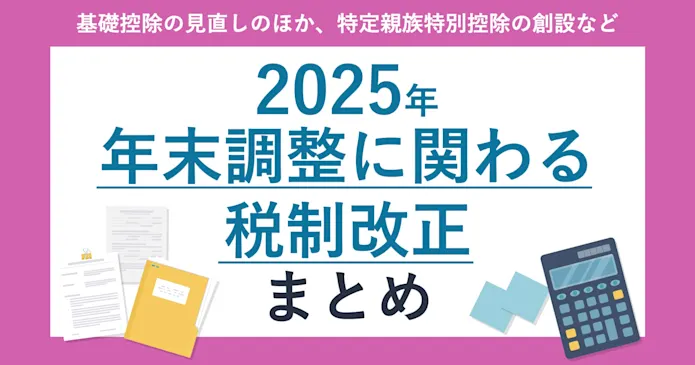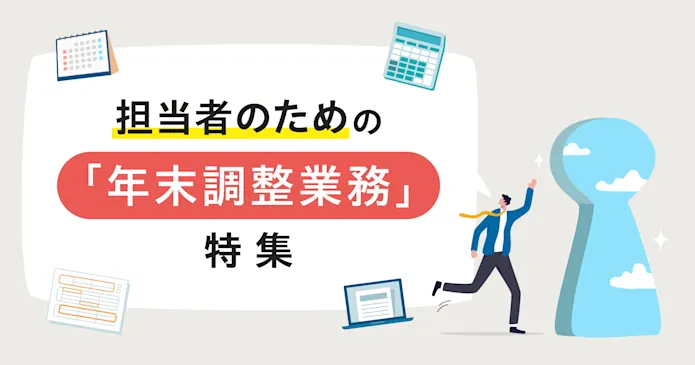年末調整「給与所得者の基礎控除申告書」の書き方。合計所得金額の計算方法も解説
- 更新日
- 公開日

目次
こんにちは。税理士の高橋 創です。
今年も早いもので、年末調整について考えなければならない時期がやってきました。
従業員からしてみると、年末調整は何枚かの書類に毎年同じような内容を記載して会社に提出するだけ、といったイメージを持っているかもしれません。今回もその作業自体は変わりませんが、昨年はあった「定額減税」がなくなったり、「103万円の壁」問題の影響もあったりで、様式や記載内容の変更があります。
大枠は変わっていないとはいえ、年に一度の作業ですのであらためて記載方法をしっかりおさらいするのは大切です。まずは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の内容を確認していきましょう。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とは
この書類は、4つの申告書が一体となったもので、昨年の「年末調整に係る定額減税のための申告書」にかわり「給与所得者の特定親族特別控除申告書」というものが加わっています。また新たな申告書が出現したわけですが、大学生世代のお子さんをもつ方にとっては税負担の軽減につながる可能性があるものですので、内容を理解したうえできっちりと記載できるようにしておきたいところです。
そこで、これから3回にわたり、それぞれの控除の内容や4つの申告書の記載方法を具体的に解説しますが、今回はまず「給与所得者の基礎控除申告書」の書き方について解説します。
なお、今年より新設された特定親族特別控除については、以下の記事もご覧ください。
控除の基準となる「合計所得金額」
早速本題に、と言いたいところではありますが、まずは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」全体に関する基礎知識のご紹介です。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は4つのパートに分けられます。
この4つすべてのパートに記載する欄が設けられているのが「合計所得金額」です。
すなわち、この用紙に必要事項を記入する際にはまずこの「合計所得金額」とはなにかを知る必要があります。
「合計所得金額」は、その名のとおり「その年に稼いだ利益(所得金額)の合計額」です。そこだけ聞くと簡単なようにも思えますが、この計算は一筋縄ではいきません。
所得税では稼いだ収入を10種類に区分し、それぞれの方法により利益を計算するため、収入の種類に応じて計算の仕方を変えなければならないためです。
本題からは離れてしまいますのでここでは深く触れませんが、計算方法を簡単にご紹介いたします。これを見るだけで、なかなか大変な作業が発生するのが伝わるのではないでしょうか。
- 利子所得:収入金額
- 配当所得:収入金額-元本取得に要した負債の利子
- 不動産所得:総収入金額-必要経費
- 事業所得:総収入金額-必要経費
- 給与所得:収入金額-給与所得控除額
- 退職所得:(収入金額-退職所得控除額)×1/2
- 山林所得:総収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)
- 譲渡所得:総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)
- 一時所得:総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
- 雑所得 公的年金等:収入金額-公的年金等控除額
- 雑所得 公的年金等以外:総収入金額-必要経費
そしてややこしい分類によって計算した所得金額を以下の方法で合算したものが合計所得金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
- 退職所得金額
- 山林所得金額
合計所得金額は、上記の1〜4を合算することで算出できます。
申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額の合計額を加算した金額です。この際、長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額で合計する必要があります。
この金額を算出するためには収入や経費を集計する必要がありますので、「プチ確定申告」とでもいうべきかなり大変な作業です。そもそも現段階で12月末までの正しい所得の計算などできない方が普通なような気もします。
この計算を間違えて控除の金額が異なるような場合、のちのち税務署から突然修正の連絡が入ることもありますが、裏を返せば「間違えていたら修正すればよい」というものでもあります(もちろん、ミスなくできるのがベストです)。
求められているものはあくまで「合計所得金額の見積額」ですので、あまり思い詰めずに「今現在はこれが正しいと思う!」くらいの気持ちで取り組んでみてください。
国税庁のページも、参考にしながら進めていきましょう。
給与所得者の基礎控除申告書とは
基礎控除は、納税者の本人の最低限度の生活を維持するため、生活に必要な部分には税金を課さないようにするために設けられたものです。
令和元年分以前の基礎控除の金額は一律38万円だったのですが、その後のさまざまな改正を経て、現在ではかなり複雑になってしまっています。現在の金額も令和7年と8年限定のものです。
その複雑になってしまった基礎控除について、年末調整においての適用の有無や、控除額を計算するために設けられているのが「給与所得者の基礎控除申告書」です。制度の複雑さに不安を感じる方もいらっしゃると思いますが、この申告書に必要事項を埋めていけば基礎控除額にたどり着けますので、ご心配なく。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える方は基礎控除を受けられないため、「給与所得者の基礎控除申告書」を記載する必要はありません。
給与所得者の基礎控除申告書の書き方
さて、それでは本題となる給与所得者の基礎控除申告書の書き方をご紹介します。

(出典)令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄
こちらには先ほどご紹介した合計所得金額の見積額を「(1)給与所得」と「(2)給与所得以外の所得の合計額」に分けて記載します。
ここで一番悩ましいのが、「収入金額」と「所得金額」の違いです。計算方法は合計所得金額のところで紹介したとおりなのですが、「収入金額=売上総額」「所得金額=利益」というようなイメージをもっておいていただければと思います。
また、給与所得だけが特別扱いされているのは、そもそも年末調整自体が給与所得者を対象としたものであるためです。
(1)給与所得
まずは上段(1)の給与所得。
こちらに関しては給与の額面金額である「収入金額」と給与に関する利益である「所得金額」を記載します。
「額面は会社が把握しているんだから勝手に計算してくれないものか……」と思われる従業員の方もいらっしゃるかもしれませんが、この申告書はあくまでも自ら申告するもの。がんばって集計しましょう。
「収入金額」が集計できたら次は所得金額の計算ですが、所得金額は、「収入金額」以下の表を基に計算した「給与所得控除額」を差し引いた金額となります。昨年は用紙の裏面に「早見表」のようなものがあったのですが、今年はなくなってしまいましたね。

たとえば、年間の給与収入が350万円である場合、該当する行の右側の算式に金額を当てはめると、
給与所得控除額 350万円×30%+8万円=113万円
所得金額 350万円-113万円=237万円
となります。
この金額が給与所得の「所得金額」です。なお、複数の会社などから給与をもらっている方については、その給与の合計額をもとに計算する点には注意が必要です。
(2)給与所得以外の所得の合計
給与所得が終わったら次は「(2)給与所得以外の所得の合計額」です。
こちらには給与所得以外の所得を合計所得金額の項目でご紹介したとおりに集計し、所得金額の合計額のみを記載します。
そして、(1)(2)の「所得金額」に記載された金額の合計額が「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」となります。
「○控除額の計算」欄
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の計算に応じた区分の□にチェックをつけ、その右側にある控除額を「基礎控除の額」欄に転記します。
基礎控除の計算はこれで終わりです。
「給与所得者の配偶者控除」で使用するため、合計所得金額の見積額が1,000万円以下の場合には(A)(B)(C)のいずれかを「区分Ⅰ」に記載するのをお忘れなく。
「完璧すぎ」を目指さず気楽に計算する気持ちで
合計所得金額さえわかってしまえば基礎控除自体は難しいものではありません。
しかし、その「合計所得金額の見積額の計算」は難関です。実質的に確定申告と同様の作業をこの申告書の提出期限までに完璧に計算するのは簡単なことではありません。
もちろんベストを尽くす必要はあるかと思いますが、完璧を期するあまり思い詰めてしまうとイヤになってしまいますので、個人的にはある程度、気楽に計算してもいいように思います。

お役立ち資料
担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整
年々複雑化する年末調整に関するマニュアルのアップデートや、従業員からの質疑応答に大幅に時間を取られるなど、大量の書類管理に追われ残業が増えてしまう人事・労務担当の方も多いのではないでしょうか。
わかりやすくて使いやすいと好評のSmartHRのペーパーレス年末調整についてご紹介します。
【こんなことがわかります】
- SmartHRの年末調整はココが違う!
- 年末調整システム導入時の注意点
年末調整に関する主なQ&A
Q. 年末調整で何を書けばいい?
対象者によりますが、年末調整で記載する書類は「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」などの申告書になります。申告書の内容によって各種控除額等を確認し、その労働者が1年間に支払うべき所得税額を確定させます。
Q. 基礎控除48万円って何?
基礎控除とは、納税者の本人の最低限度の生活を維持するため、生活に必要な部分には税金を課さないようにするために設けられたものです。控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて異なります。
Q. 年末調整ではいくら返ってくる?
年末調整では、算出された所得税とそれまで徴収していた所得税の間に差が生まれ、年間の所得税のほうが低いときに還付金が発生します。

メールマガジン「週刊SmartHR Mag.」
社会保険労務士や弁護士など、人事・労務の専門家による実務に活かせる生の情報を発信していきます。メールマガジンでしか読めない専門家のこぼれ話なども掲載中です!