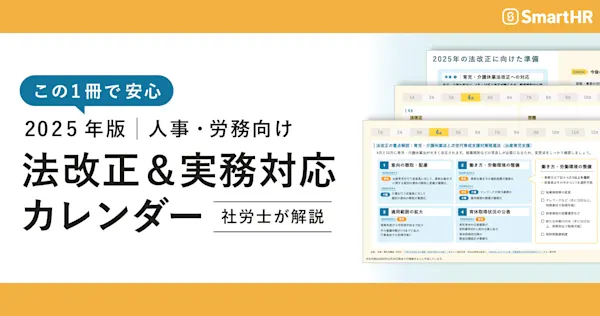2025年の年末調整業務、令和7年度税制改正をふまえた影響について
- 公開日
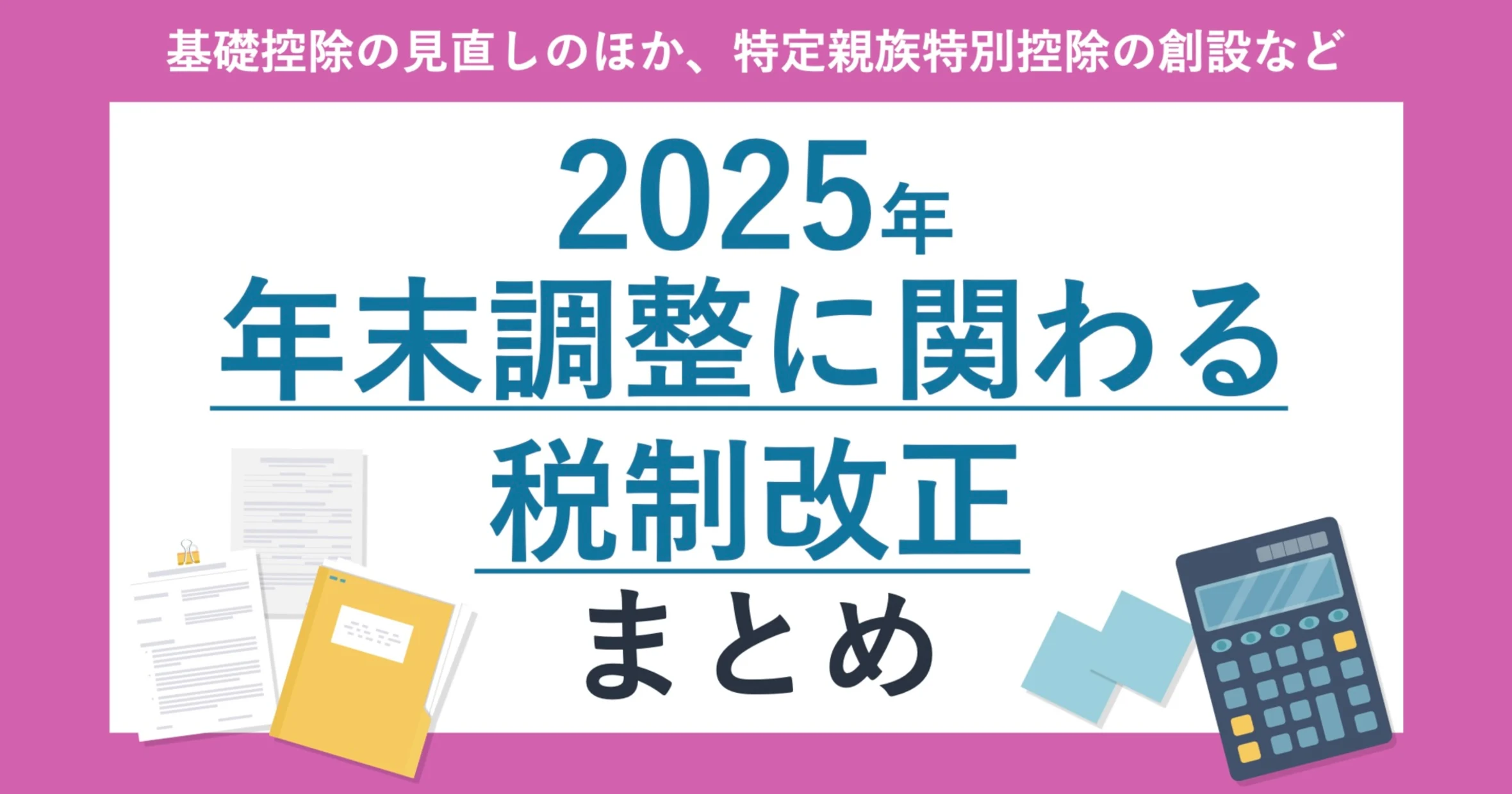
この記事でわかること
令和7年度の年末調整に関するトピックを中心に、以下について紹介します。
- 令和7年分の年末調整に影響する改正点
- 基礎控除額の引き上げや、給与所得控除の最低保証額引き上げなど
- 基礎控除額の引き上げや、給与所得控除の最低保証額引き上げなど
- 令和8年分の年末調整に影響する改正点
- 扶養控除等申告書の記載事項の変更や、子育て世代等に対する生命保険料控除の拡充など
詳しくは、以下の目次をご覧ください。
目次
こんにちは。SmartHRドメインエキスパートの中島です。クラウド型人事労務システム「SmartHR」の年末調整機能の開発に携わっています。
2025年4月に、国税庁から 「令和7年 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。令和7年度税制改正は「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」を基本方針とし、とくに「103万円の壁」の引き上げや子育て世代への支援強化に重点を置いています。
本記事では、令和7年および令和8年の年末調整に影響する主要な改正点と、その実務対応について解説します。
※本記事は2025年5月時点で明らかになっている情報をもとに作成しました。年末調整に関する最新の情報や書類の様式などは、今後アップデートされる可能性があります。あらかじめご注意ください
はじめに
今年の税制改正は、物価上昇による生活負担の軽減や就業意欲の高い子育て世代への支援強化を目的としています。とくに「103万円の壁」の見直しは、多くの家庭にとって大きな影響を与える改正であり、年末調整にも大きな変化をもたらします。
103万円の壁とは
まずは、「103万円の壁」について整理をしましょう。
103万円超で自分の所得税が課税される
年間の給与収入が103万円を超えると、所得税の基礎控除額48万円と給与所得控除額55万円の合計額を超えるため、超過した金額に対して所得税が課税されるようになります。
103万円超で学生などの親の税金が増える
扶養親族(学生や収入の少ない家族など)の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である場合に、納税者本人が扶養控除を受けられます。
そのため、扶養されている家族の収入が103万円を超えると、親の所得税の計算において扶養控除が適用されなくなり、税負担が増える場合があります。
配偶者は103万円超でも扶養控除の影響はない
配偶者の扶養控除は、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインになりました。
配偶者にとっての103万円の壁は、自身の年収に対する所得税の課税ラインを指しています。そのため、税制上の扶養においては配偶者の103万円の壁は直接的には関係ありません。
そのほかの「年収の壁」
年収の壁問題は主に103万円の壁(所得税) だけにフォーカスされがちですが、ほかにもさまざまな壁があります。
壁の名称 | 内容 | 主な影響 |
|---|---|---|
106万円の壁 | 社会保険(被用者保険の加入義務) | 「従業員51人以上」の企業の場合、条件を満たすと健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生 |
130万円の壁 | 社会保険(扶養外) | 106万円の壁に該当しなかった人でも、自らの勤務先の社会保険に入るか、国民年金・国民健康保険に入る必要あり |
150万円の壁 | 所得税(配偶者特別控除の減額) | 配偶者特別控除が満額受けられなくなる |
201万円の壁 | 所得税(配偶者特別控除の終了) | 配偶者特別控除が受けられなくなる |
「103万円の壁」が見直されたからといって、単純に多く働けるというメリットだけがあるわけではありません。社会保険の加入や配偶者控除の適用など、いくつかの観点を理解したうえで自分のライフプランにあった働き方を選択する必要があります。
令和7年分の年末調整に影響する改正点
それでは、2025年(令和7年分)に関する年末調整に影響を及ぼす税制改正について解説します。
1. 基礎控除の見直し
改正の背景
基礎控除は納税者の最低限の生活を守るために設けられた制度で、すべての納税者が所得に対して一定額を控除できる仕組みです。令和元年以前の基礎控除額は一律38万円でしたが、令和2年から10万円引き上げられ、控除額は48万円となりました。
改正内容
今回、以下のように令和7年以降の恒久的措置と、令和7〜8年の2年間の時限立法措置の組み合わせで、以下のように控除額が見直されました。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P2より
年末調整への影響
年末調整で基礎控除の適用を受ける場合、基礎控除申告書の提出が必要です。令和7年以降、より細かい所得区分に応じた申告が求められるため注意が必要です。

出典:国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」内の年末調整関係書類より
2. 給与所得控除の見直し
改正の背景
給与所得控除は、給与収入から経費相当分を控除する仕組みで、給与所得者の生活コストを考慮するためのものです。
これまでの控除額は、本人の給与収入額をもとに以下のとおり算出されていました。

参考:国税庁のウェブサイトの情報をもとに弊社で作成
改正内容
今回、給与所得の最低保証額がこれまでの55万円から65万円に引き上げられます。これにより、基礎控除と合わせた所得税非課税ラインは160万円(95万円+65万円)となり、従来の103万円の壁が大幅に引き上げられます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P2より
また、「160万円の壁」について私が解説している動画コンテンツもございますので、もしお時間があればご覧ください。
年末調整への影響
「1.基礎控除の見直し」と同じく、年末調整で基礎控除の適用を受けるにあたって申告書の(1) 給与所得欄の「所得金額」を記入する際に、正しい金額が記載されているか注意して確認しましょう。

出典:国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」内の年末調整関係書類より
3. 特定親族特別控除の創設
改正の背景
特定扶養親族(※1)がいる場合、63万円の控除が受けられます。しかし、親族の収入が103万円(所得48万円)を超えると控除適用できません。そこで若年層の就業支援を強化する目的で、新たに「特定親族特別控除」が設けられました。
※1 控除対象扶養親族(合計所得金額が58万円以下) のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人
改正内容
扶養家族に特定親族がいる場合、その特定親族ひとりにつき合計所得金額に応じて控除する「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。
今回、創設された特定親族の特別控除額は、以下のとおりとなっています。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P3をもとに弊社で作成

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P3より
年末調整への影響
年末調整で特定親族特別控除の適用を受けようとする場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。

出典:国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」内の年末調整関係書類より
4. そのほかの所得金額要件の引き上げ
基礎控除の見直しにともない、扶養対象扶養親族などの所得要件が以下のとおり変更されます。
改正内容
- 控除対象扶養親族
- 所得要件が48万円(収入103万円) 以下から、58万円(収入123万円) 以下に変更
- ひとり親の生計を一にする子
- 所得要件が48万円(収入103万円) 以下から、58万円(収入123万円) 以下に変更
- 配偶者
- 同一生計配偶者
- 所得要件が48万円(収入103万円) 以下から、58万円(収入123万円) 以下に変更
- 配偶者特別控除対象配偶者
- 所得要件が48万円(収入103万円) 超〜133万円(201.6万円) 以下から、58万円(収入123万円) 超〜133万円(201.6万円) 以下に変更
- 上限額は133万円から変更なし
- 同一生計配偶者
- 勤労学生控除
- 所得要件が75万円(収入130万円) 以下から85万円(収入150万円) 以下に変更
- 従来
- 所得75万円=給与収入130万円ー給与所得控除55万円
- 令和7年以降
- 所得85万円=給与収入150万円ー給与所得控除65万円
- 従来
- 所得要件が75万円(収入130万円) 以下から85万円(収入150万円) 以下に変更
5. 住宅ローン控除の拡充措置継続
令和6年に決定していた控除の拡充措置が、令和7年についても以下のように適用されます。
改正内容
(1)特例対象個人(※2) が認定住宅等の取得をして令和7年1月1日〜12月31日までに入居した場合にも、控除対象借入限度額が以下のように引き続き適用
認定住宅:4,500万円→5,000万円
ZEH水準省エネ住宅:3,500万円→4,500万円
省エネ基準適用住宅:3,000万円→4,000万円
※2 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯または19歳未満の扶養親族を有する世帯
(2)新築住宅の床面積40平方メートル以上の住宅の要件緩和措置(合計所得金額1,000万円以下の場合) が、令和7年12月31日までに建築確認を受けた住宅の取得にも適用

参考:国税庁のウェブサイトの情報をもとに弊社で作成
※ 2024(令和6)年1月1日以後に建築確認を受けた場合も、登録簿上の建築日付が2024(令和6)年6月30日以前であれば適用の対象になる
令和8年分の年末調整に影響する改正点
続いて令和8年分の年末調整における変更点や、影響がある税制改正について解説します。
1. 扶養控除等申告書の記載事項の変更
令和7年分までの扶養控除等申告書B欄に記載されている「控除対象扶養親族」が、令和8年から「源泉控除対象親族」に変更されました。
【令和7年分】

出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
【令和8年分】

出典:国税庁「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
なお、源泉控除対象親族のうち、特定扶養親族や特定親族がいる場合は、上図の右側にある項目にチェックをつけなければなりません。
2. 源泉控除対象親族とは
前項で触れた「源泉控除対象親族」は、以下のいずれかに該当する人を指します。
(1)控除対象扶養親族(従来どおり)
(2)居住者と生計を一にする親族のうち、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人
令和7年までは「控除対象扶養親族」のみでしたが、令和8年からは「控除対象扶養親族」に「特定親族(の一部)」を加えて、「源泉控除対象親族」と枠組みが変更されました。名称変更にともない、申告書に記載すべき親族の範囲も変わります。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P7より
年末調整への影響
令和8年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、令和8年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出しなければいけません。一般的には前年の年末調整時に同時に提出するため、本内容は令和8年からの適用ですが、実際は令和7年の年末調整の実務にも影響します。

出典:国税庁「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
3. 子育て世代等に対する生命保険料控除の拡充
子育て世帯の支援強化を目指して、 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます(下図参照)。また、旧生命保険料控除及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行の12万円から変更ありません。

参考:「令和7年度税制改正の大綱」(P10)をもとに弊社で作成
こちらは令和8年分からの変更で、2025年5月時点で書類の様式などは公開されていません。ただし、書類上で子供(23歳未満の扶養親族)に関する情報を確認する必要があるため、様式の変更が予想されます。
令和7年は基礎控除の見直しを中心に、情報のキャッチアップを進めましょう
令和7年度の税制改正は、「物価上昇への対応」と「就業調整の解消」が主な目的です。とくに103万円の壁が160万円の壁に引き上げられる点と、19歳~23歳の若年層の就労促進や子育て世帯への支援強化がポイントになります。
年末調整実務では、令和7年分から基礎控除・給与所得控除の引き上げや、特定親族特別控除が新たに適用され、令和8年分からは源泉控除対象の特定親族の確認や、子育て世代向け生命保険料控除拡充なども本格適用されます。
昨年の定額減税の対応に続き、今年も複雑な制度変更により書類の様式変更が予定されています。年末調整の時期に向けて、早めに変更内容を理解し、着実に準備を進めていきましょう。

お役立ち資料
担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整
年々複雑化する年末調整に関するマニュアルのアップデートや、従業員からの質疑応答に大幅に時間を取られるなど、大量の書類管理に追われ残業が増えてしまう人事・労務担当の方も多いのではないでしょうか。
わかりやすくて使いやすいと好評のSmartHRのペーパーレス年末調整についてご紹介します。
【こんなことがわかります】
- SmartHRの年末調整はココが違う!
- 年末調整システム導入時の注意点