人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年10月振り返りと11月のポイント
- 公開日

目次
こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。ほんの先日まで記録的猛暑の夏だったと記憶していますが、11月に入ってからは朝晩を中心に冷え込む日が増えてきました。気候のよい時期は本当に短いものですね。インフルエンザの流行も始まっているようです。人事・労務担当者はこれから繁忙期に入っていきますので、あらためて健康には注意しましょう。
10月1日から新しい最低賃金の発効が始まっていますが、今年度は発効日が11月以降の県も多くあります。よって今月はまずこの話題から取り上げていきます。
10月のトピックを振り返る
トピック1 最低賃金対応
先月の当ニュースでも「最低賃金引き上げに対応した業務改善助成金の拡充」について取り上げましたが、今年度は過去最大の最低賃金引き上げとなっています(※)。そのため、発効日まで十分な準備期間をとる自治体が多くなり、今年度は下図のとおり27府県で11月1日以降の発効という異例の対応となりました。各種助成金を活用し、最低賃金上昇分をカバーしながら、生産性向上を進めていきましょう。

トピック2 厚労省が来春施行の「年金制度改革」ショート動画を公開
今年5月に年金制度改正法が成立し、来年(2026年)4月から段階的に施行が始まります。今回の改正内容は多岐にわたり、個人や企業に影響のある改正が多く含まれています。
そこで厚生労働省は、国民・企業の理解を促進するために、わかりやすい説明資料や、改正点ごとに簡単にまとめた20秒~40秒程度のショート動画をYouTubeで公開しています。今後の施行点を理解するのに役立つ動画ですので、ぜひご覧ください。
「年金制度改革」ショート動画シリーズ
トピック3 年次有給休暇取得促進期間
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。
働き方改革以降、多くの企業で年休の取得率は上昇し、下図のとおり令和5年の年休の取得率は65.3%と過去最高となっています。令和10年までに70%という政府目標の達成もいよいよ視界に入ってきたと言えるでしょう。

しかし、まだまだ年休が取得しにくい職場が少なからず存在することは事実です。これから冬休み期間に入りますので、人材の定着を促進するためにも、従業員が年休を取得しやすい環境づくりを継続していきましょう。
11月のポイント
いよいよ年末が近づいてきました。今月の実務としては冬季賞与および年末調整の準備が最も大きなテーマとなるでしょう。冬季賞与準備については先月お伝えしていますので、今回はその他のトピックを取り上げます。
11月のHRトピックについては、動画でも取り上げていますので、ぜひご覧ください。
トピック1 年末調整
今年も年末調整の季節がやってきました。今年の年末調整は、特定親族特別控除の創設など税制改正により、例年以上に従業員とのコミュニケーションが重要となります。最新情報を確認し、提出書類や記載内容に不備がないよう入念にチェックするようにしましょう。
なお、今年の年末調整の詳細は、SmartHR Mag.の特集をご参照ください。
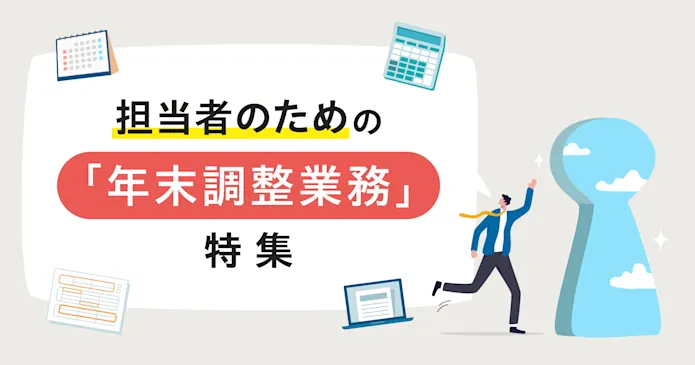
“人事・労務担当者のため”の「年末調整」|今年度の変更点と業務上の注意点を解説
人事・労務担当者にとって、年末調整は1年でもっとも重要な業務の1つです。年末調整の仕組みは年々複雑化しています。今年度の変更点などの最新動向から作業上の注意点まで、年末調整業務で知っておきたい情報をまとめました。
トピック2 協会けんぽの被扶養者資格再確認
協会けんぽでは、被扶養者資格の再確認を毎年度実施しています。これは、健康保険の被扶養者が、現在も扶養対象であるかを確認し、保険給付を適正化する取り組みです。
今年は、10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が事業主に送付されています。以下、ポイントを確認していきましょう。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
再確認の対象となる被扶養者
扶養解除の可能性の高い対象者に絞って確認業務を実施しましょう。
- 健康保険の資格が重複している可能性が高い人
- 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い人
- 令和6年中の課税収入額が130万円(※)の金額を超過している人(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
確認のポイント
確認の際には以下のポイントを確実に押さえておきましょう。
- 他の健康保険に加入していないか
- 同居が必要な続柄の者が別居していないか【図参照】
- 被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
- 同居の場合:被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の年収の半分未満か
- 別居の場合:被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少なくなっているか
- 被扶養者の年収が130万円※を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか
※被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。また、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります(被保険者の配偶者を除く)。
【図】同居が必要な続柄の者の範囲
下図の〇の続柄の方は、被保険者と同居していることが、被扶養者認定要件となります。

(出典) 「事業主・加入者のみなさまへ 令和7年度被扶養者資格再確認について」- 協会けんぽ
会社としては、従業員に被扶養者となっている家族の収入を確認し、年収が130万円以上の場合は、一時的な増収であることの証明を提出してもらう必要があります。これは被扶養者の勤務先が発行する書類のため、時間を要する場合があります。できるだけ早めに案内できるとよいでしょう。
社会保険における年収の壁については、以下の動画でくわしく解説しています。
繁忙期こそ、事前準備の徹底で早めの対応を
担当者にとって11月は、冬季賞与の支給準備や年末調整を進めながら、細かい対応が求められる多忙な時期となります。いずれも事前準備がきわめて重要な業務になりますので、早めに対応を進めましょう。



























