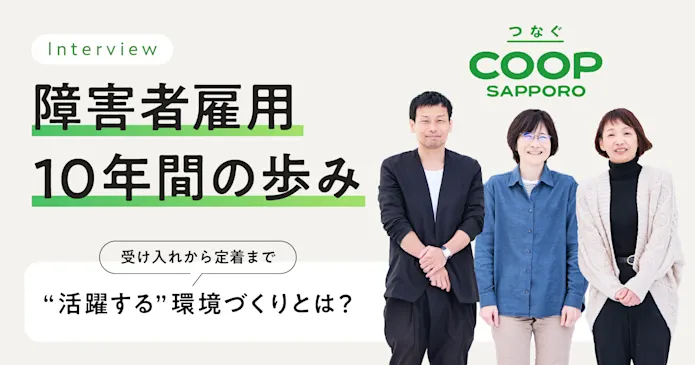人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年4月振り返りと5月のポイント
- 公開日

目次
こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。
5月は新入社員の受け入れ、そして賃上げの対応も終わり、少しホッとしている頃ではないでしょうか。しかし、初夏に向け、さまざまな実務の準備が必要になる時期でもあります。まずは4月のトピックの振り返りから確認していきましょう。
4月のトピックを振り返る
4月に受け入れた新入社員への研修が終了し、現場配属を完了された企業が多いのではないでしょうか。そして5月は、その配属に伴うさまざまな問題が表面化してくる時期でもあります。今月は新入社員の定着に向けた取り組みからみていきましょう。
トピック1:“五月病”の時期、新入社員ケアと職場定着支援を
多くの企業で入社式が行われた4月1日の翌日には、早くも退職代行会社を利用して退職した新入社員のニュースがマスコミでも取り上げられ、話題となりました。みなさんの会社の新入社員の状況はいかがでしょうか?
入社直後の退職は極端な例ですが、新入社員は就職によって生活環境が大きく変化するため、ストレスが溜まりやすい状況にあります。「気分が落ち込む」「眠れない」「気力が湧かない」など、いわゆる“五月病”の症状が現れることが少なくありません。
医師監修メディア「HIT the Knee」※1が昨年のゴールデンウィーク明けに実施した「男女384名に聞いた!五月病に関するアンケート」によれば、27.6%が「五月病だと思う」と答えています。この結果から、この時期に多くの従業員のメンタルが不安定になっていることがわかります。就職により大きな環境変化があった新入社員は、既存社員よりも高い割合で五月病の症状が表れやすいと考えるのが妥当でしょう。
※1:さまざまなジャンルの専門医と共に健康に関するヒントや学びを提供する医師監修メディア「HIT the Knee」

五月病の対策には、十分な睡眠確保、バランスの取れた食生活、周囲とのコミュニケーションの維持などがポイントです。新入社員を中心に社員の様子に注意を払い、変化がみられた場合には必要に応じて声がけをしていきましょう。人事・労務部門としては、各職場にこれらの注意を促すとともに、セルフケアとラインケアの重要性を改めて全社に周知し、メンタルヘルスケアの強化を図ることが望ましいでしょう。
トピック2:試用期間の運用見直しを
多くの企業では、従業員の新規採用時に試用期間を設けています。試用期間とは、従業員の能力や適性、勤務態度などを確認し、本採用を行うかを見極める期間です。一般的には3か月〜6か月程度の期間が設定されています。
しかし実態としては、試用期間が設定されているだけで、実質的な評価管理が行われず、気づいたときには試用期間が終了しているケースが少なくありません。これでは制度の意味がありません。対策として、たとえば、配属から1か月後に、上司から人事部門へ新入社員の勤務状況を報告する。問題がみられる場合には、速やかに面談を実施するといった体制整備が重要です。
何事も最初が肝心です。新入社員の円滑な受け入れと雇用リスク低減の観点から、試用期間の運用のルールを定め、徹底していきましょう。
トピック3:歴史的な賃上げを記録。賃金制度改定は必要?
今春も歴史的な賃上げとなり、多くの企業でベースアップが行われました。近年のベースアップは、初任給や最低賃金の引き上げを受け、20代から30代前半など若手社員の賃金を重点的に引き上げる傾向が顕著です。この結果、賃金のフラット化が進んでいます。これにより30代・40代の中堅社員の不満が高まり、転職市場の活況も相まって、これらの年齢層の離職が増加しているケースが少なくありません。
30年間ほとんど変化のなかった賃金水準がここ数年で急速に上昇しており、従来の賃金カーブに綻びが生じている企業が増えています。この新たな環境に応じた賃金制度をいかに再構築するかは、人材確保と安定的な事業運営において欠かせない事項です。
内閣官房は、「三位一体の労働市場改革」の方針をもとづき、昨年8月に「ジョブ型人事指針」を公表しました。この公表では20社の人事制度改革の事例が具体的に紹介されています。人事担当者の皆さまはこうした資料も活用しながら、自社の人事制度の見直しを進めることをおすすめします。たとえば以下は、株式会社日立製作所の「管理職の報酬を職務給に一本化」を説明する図です。

出典:p.25内閣官房・経済産業省・厚生労働省「ジョブ型人事指針」
トピック4:4月1日施行の「カスタマーハラスメント防止条例」への対応
令和6年4月1日に東京都・北海道・群馬県においてカスタマーハラスメント防止条例が施行されました。今後、労働施策総合推進法の改正により、「カスハラ」による就業環境の悪化を防ぐための、相談窓口の設置や対応マニュアルの策定などがすべての企業に義務づけられる見通しです。
法整備が進む背景には、すでに多くの職場でカスハラ問題が発生している実態があります。東京都産業労働局の調査によれば、約6割の方が「カスタマーハラスメントの被害にあった」または「見聞きしたことがある」と回答しています。

カスハラ防止対策については、厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」などを公開しています。これらを活用し、対策を進めましょう。

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
5月のポイント
これから初夏にかけて、労働保険年度更新をはじめとするさまざまな手続き業務が発生します。5月はその準備を計画的に進めておきましょう。
トピック1:労働保険年度更新、期限内に申告手続きを
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます。算定方法は、この期間に支払われた賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を掛けます。
保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末の賃金総額確定後に精算する手続き(年度更新)が求められますが、今年は6月2日(月)から7月10日(木)の間に申告しなければなりません。期限内に必ず手続きを完了させましょう。
具体的な手続きとしては、昨年4月1日から今年3月31日までの賃金を集計し、5月末に届く申告書に必要事項を記入します。
すでに3月までの賃金は確定しているはずのため、申告書が届く前に賃金の集計作業を済ませておくと、その後の申告手続きもスムースに進むでしょう。賃金の集計方法および申告書の書き方については、以下のリンク先にある資料をご確認ください。

トピック2:夏季賞与支給の準備を効率的に
多くの企業では6月下旬から7月にかけて夏季賞与の支給が行われます。各シンクタンクの予測によれば今期の支給額は前年比+1.9~3.0%※2となる見込みです。
人事担当者の皆さまは、賞与支給に向けた実務としては、夏季賞与に関わる人事評価や面談の手配、その後の賞与支給額の算定が必要です。
人事評価および面談を効果的に実施するために、クラウド型人事サービスの活用も検討しましょう。
※2:以下のレポートをもとに記載
トピック3:障害者雇用納付金の申請・納付手続きを忘れずに
障害者雇用促進法では、障害者の職業安定を目的として法定雇用率を設定しています。現在、民間企業の法定雇用率は2.5%(令和8年7月以降は2.7%に引き上げ予定)です。
実際に障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理など経済的負担が伴うため、障害者雇用納付金制度が設けられています。これは、法定雇用人数を満たしていない事業主と、法定雇用人数を満たしている事業主の間の経済的負担の調整を図ることを目的としています。
常用労働者数が100人を超え、かつ障害者法定雇用率を満たしていない事業主から、不足1人あたり月額5万円の納付金が徴収されます。この納付金を財源として、「障害者雇用調整金」や「報奨金」などが支給されます。
そのため、常用雇用労働者数が100人を超える事業主は、令和7年4月1日から5月15日までの間に申告申請が必要です。忘れないように申請しましょう。また法定雇用率を満たしていない事業主は、早めに障害者雇用の採用活動などを進めましょう。

トピック4:職場の熱中症対策「労働安全衛生規則」により義務化
近年、企業の熱中症対策が進められていますが、猛暑が続くなか、熱中症による災害発生件数は増加しています。2024年の職場における熱中症による死傷者数は1,195人にのぼり、死亡者数も30名と深刻な状況が続いています。

熱中症対策の重要性が高まるなか、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。この改正により、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務づけられます。
その内容は以下のとおりです。

日本気象協会によれば、今年の夏は観測史上1位の高温直近2年の夏には及ばないものの、気温は平年よりかなり高く、猛暑となるようです。厚生労働省のパンフレットも参考にしながら、万全な熱中症対策をしましょう。
5月は新入社員フォローと各種届出の準備を計画的に
5月は、新入社員の定着フォローアップと、各種届出の準備が中心となります。本記事では、実務に必要な情報へのリンクも記載していますので、資料も確認しながら、対応漏れがないように進めていきましょう。
編集:佐々木 四史