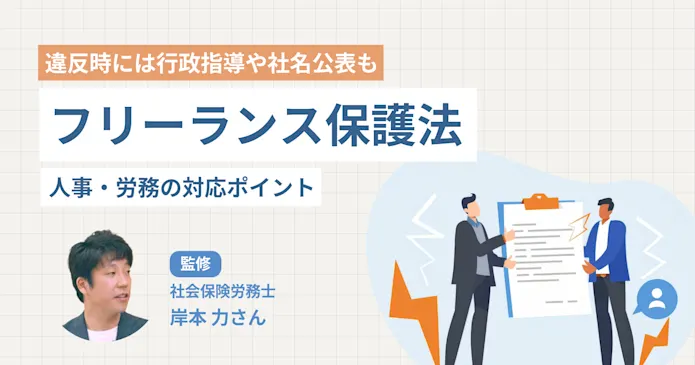【チェックリスト付き】業務委託の管理で会社を強くする「守りのDX」
- 公開日

目次
人手不足が深刻化するなか、多くの企業が即戦力として期待するのがフリーランスや業務委託パートナーです。しかし、2024年11月に施行されたフリーランス保護法をはじめ、業務委託を取り巻く法規制は年々厳しくなり、違反すれば行政指導や社名公表といったリスクもあります。
「法令遵守」と聞くと、制約と捉える方が多いかもしれませんが、ルールを適切に守り、実行することで業務委託パートナーとの信頼関係を強化し、結果的に事業の安定成長へとつながります。本記事では、社会保険労務士監修のもと、業務委託管理における「守りのDX」の重要性をお伝えするとともに、今すぐ確認できるチェックリストも用意しました。
さぁ、業務委託管理を盤石にして、守りのDXを実現しましょう!
知らないでは済まされない!業務委託管理のトレンド
相次ぐ法改正で高まる企業の責任
ここ数年、業務委託に関する法整備が急ピッチで進んでいます。とくに注目すべきは以下の法律です。
フリーランス保護法(2024年11月施行)
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が一定の資本金規模の企業間取引を対象としていたのに対し、この法律はすべてのフリーランス個人が対象となります※。適用範囲が格段に広がり、これまで下請法の対象外だった企業も、新たに法令遵守の義務を負うことになりました。
※事業者間(BtoB)における委託取引が対象であり、消費者との取引(BtoC)などは対象外となります。
改正下請法(2026年1月施行予定)
下請法が「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として大幅に改正されます。これにより、業務委託取引の透明性確保や公正な取引慣行の確立がさらに求められます。詳しくは、公正取引委員会のウェブサイトをご確認ください。
改正電子帳簿保存法・インボイス制度
契約書や請求書といった重要書類の電子保存要件や、適格請求書の発行・保存義務など、バックオフィス業務における対応も必須となっています。
対応を怠ると発生する具体的なリスク
上記の法令に違反した場合、企業が被るリスクは深刻です。
- 行政指導:公正取引委員会や中小企業庁による調査対象となり、改善を求められます
- 社名の公表:悪質なケースでは企業名が公表されます。実際に2025年6月には出版業界の大手2社の企業名が公表※され、大きなニュースとなりました
- 罰金・過料:法令によって罰金や過料が科され、フリーランス保護法では50万円以下の罰金・20万円以下の過料が定められています
- 取引関係の悪化:不適切な対応により、違反行為を外部窓口などへ通報される恐れがあります。結果として優秀な業務委託パートナーとの信頼関係が崩れ、今後の発注に影響を及ぼすリスクがあります
- 採用への悪影響:企業イメージや評判が悪化すれば、採用活動にも支障をきたすおそれがあります
※参考:公正取引委員会「(令和7年6月17日)株式会社小学館に対する勧告について」「(令和7年6月17日)株式会社光文社に対する勧告について」

DXには「攻め」と「守り」がある
一般的に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」というと、新規事業の創出や売上拡大といった「攻めのDX」をイメージする方が多いでしょう。実際、多くの企業がデジタル技術を活用して顧客体験の向上や新たな収益源の創出に取り組んでいます。
しかし、DXにはもう1つ重要な側面があります。それが「守りのDX」です。
守りのDXとは、業務プロセスの効率化や自動化を通じて、コンプライアンスリスクを軽減、業務品質を担保して、結果的にコスト削減や意思決定の迅速化を実現する取り組みです。とくに業務委託管理においては、契約から請求まで一連のプロセスのデジタル化により法令違反のリスクを未然に防ぎ、管理工数を大幅に削減できます。
攻めのDXが「売上を伸ばす」ためのものなら、守りのDXは「会社を守りながら強くする」ためのものと考えてください。
社労士監修、あなたの会社は大丈夫?業務委託に関するチェックリスト
以下のチェックリストは、社会保険労務士の監修のもと、実務で見落としがちなポイントをまとめています。守りのDXを実践するにあたって、あなたの会社の業務委託管理が適切に行なわれているか、段落末にあるチェックリストを活用して診断結果を確認しましょう。
【基本編】契約内容の適切な把握・管理
□01. 業務委託契約をきちんと締結していますか?
業務委託契約とは、請負契約や委任契約、準委任契約といった契約種類を問わず、委託をする側とされる側の業種や規模に関係なく、業務委託に該当するすべての契約が対象となります。まずは現在、自社がどのような業務委託契約を締結しているのか、全体像の把握からはじめましょう。
□02. 締結済みの業務委託契約を把握・管理できていますか?
業務委託契約は雇用契約とは異なり、メインで担当する部署や人が明確に決まっていないケースがよくあります。その結果、契約書がバラバラに保管されていたり、誰がどのパートナーと契約しているのか把握できていなかったりする状況が生まれます。会社として把握すべき情報を一元的に管理できているか、今一度確認しておきましょう。
【法令遵守編】フリーランス保護法への対応
□03. フリーランス保護法を遵守できていますか?
一定の資本金規模の事業者に対する取引が対象となっている下請法とは異なり、フリーランス保護法はすべてのフリーランス個人が対象となります。適用範囲が非常に広く、直近では違反企業に対する行政指導や社名公表も大きなニュースとなりました。自社の対応状況について、必ず確認が必要です。
□04. 業務委託の際、書面などで取引条件を明示していますか?
下請法では「3条書面」の交付が義務付けられていますが※、フリーランス保護法でも業務委託をする際には取引条件の明示が義務となっています。口頭での連絡だけで済ませていないか、書面や電子メールなどでも取引条件を明示できているか確認しましょう。
※参考:公正取引委員会「親事業者の義務」
□05. 取引条件の明示に必要な項目が揃っていますか?
明示が求められている項目には、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「検査完了日」「報酬の支払方法」があります。自社で使用している契約書や発注書の内容と照らしあわせて、不足している項目がないかチェックしてみましょう。
【運用編】日常業務で遵守すべき項目
□06. 報酬支払期日の設定と期日内の支払いは適切ですか?
発注した物品等を受け取った日から、60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが義務付けられています。しかし、そもそも期日の設定方法が適切でないケースもよく見られます。「60日以内」の起算日が正しいか、実際の支払いが期日を過ぎたり、万一支払い漏れが発生していないかなど、あらためて確認しましょう。
□07. 契約期間の管理と更新を漏れなく対応できていますか?
とくに毎月同じ業務の遂行を目的とする準委任契約の場合は、すでに終了している契約期間に気づかないまま業務を継続してしまっているケースがよく見られます。契約更新の時期を見逃していないか、更新手続きが適切に行なわれているか、確認しておきましょう。
□08. 禁止行為が契約書などに盛り込まれていませんか?
フリーランス保護法では、「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」が禁止されています。実際の取引で一連の行為がないかはもちろん、契約書の文言に意図せずこうした内容が含まれていないかも確認が必要です。
【体制編】継続的な対応のための仕組みづくり
□09. ハラスメント相談窓口などの体制整備と周知ができていますか?
フリーランスに対するハラスメント行為については、一定の措置を講じることが義務付けられています。育児・介護休業法などで設置が義務付けられている、従業員向けの「ハラスメント相談窓口」の管理・運用方法も含めて、体制の整備状況を確認しましょう。また、発注書や契約書にその窓口・連絡先を明記するなど、パートナーへも忘れずに周知する必要があります。
□10. 法改正などの最新情報をキャッチアップできていますか?
2024年11月施行のフリーランス保護法に続き、2026年1月には下請法が取適法に変更して施行されるなど、近年、業務委託契約に関する法改正が頻繁に行なわれています。会社として把握すべき最新情報やトレンドを常にキャッチアップし、早めの準備・対応を進められる体制の構築が、今後ますます重要になっていきます。
チェックリストまとめ

診断結果
- 10個:まったく問題なし
- 6個以上:まだ大丈夫ですが、予防策として記事の続きをどうぞ
- 3〜5個:改善の余地あり、次の見出しの内容をお読みください
- 1〜2個:要改善!業務委託管理クラウドLansmart サービス紹介資料を無料ダウンロードください
次の段落では、これらの課題を解決するための「守りのDX」の具体的なアプローチを解説します。

社会保険労務士
CEwin労務コンサルティングオフィス 代表社会保険労務士(元SmartHR社員)。会社と従業員の双方をWin-Winの関係にすることを信条とし、法令と実態の乖離調整を得意とする。これまでは、大手BPO、大手企業人事、総合法律事務所の社労士法人立ち上げなど、500社を超える企業人事に関わり、人事労務を内側と外側から携わってきた実経験が1番の強み。現在は主にスタートアップ向けの労務DDや社内体制構築、コンプラ対応に従事。
リスクを回避するための「守りのDX」3つのポイント
チェックリストで浮き彫りになった課題を解決するには、デジタル技術を活用した仕組みづくりが不可欠です。ここでは、業務委託管理における「守りのDX」を実現するための3つのポイントを紹介します。
ポイント(1)業務委託の管理を一元化する
最も重要なのは、契約・発注・稼働管理・請求といった一連のプロセスを1つのシステムで管理することです。情報が分散していると、契約期間の把握漏れや支払い遅延といったミスが発生しやすくなります。一元管理により、「誰が」「どのパートナーと」「いつまで」「どのような条件で」契約しているのかが可視化され、リスクを大幅に軽減できます。
ポイント(2)契約書・発注書を常に最新の法令に対応させる
法改正のたびに契約書や発注書のひな型を手作業で更新するのは、現実的ではありません。法令に準拠したテンプレートを備えたシステムを活用すれば、必要項目の記載漏れを防ぎ、常に最新の法令に対応した書類を作成できます。また、過去の契約書の管理も容易になり、監査対応などもスムーズになります。
ポイント(3)法令は「意識」ではなく「仕組み」で遵守する
業務委託管理では、発注は各部署の担当者ごとに行なわれ、横断的に管理しにくい特性があります。発注時に明示する取引条件も、要件が多く複雑かつ「一度だけ」ではなく、継続的・網羅的に守る体制が求められるため、実行するのは容易ではありません。結果として、気づかないうちに“うっかり違反”が起きやすいため、意識ではなく仕組みで予防することが求められます。
「守りのDX」を実現するLansmart by SmartHRの活用
「守りのDX」を実現するために、Lansmart by SmartHRがどのように役立つのか、課題に応じた代表的な機能を紹介します。
(1)法令で義務化された項目を網羅した発注書作成が負担
Lansmartでは、フリーランス保護法で義務化されている取引条件の明示項目(業務内容、報酬額、支払期日など)をすべて網羅したフォーム入力で、カンタンに発注書を作成できます。過去の発注書を複製する機能もあるため、定期的な業務委託の場合はとくに効率的です。法令対応の漏れを防ぎながら、作成工数を大幅に削減できます。
(2)60日以内の支払い期日を守れているか不安
Lansmartには、当月中に支払期日が60日を超えそうな案件を自動で一覧化し、通知する機能があります。経理担当者が個別に計算する必要がなくなり、うっかり期日を過ぎてしまうリスクをゼロにできます。承認済みの請求書データを全銀形式のCSVでダウンロードすれば、振り込み作業もスムーズに実施できます。
(3)契約更新のタイミングを見逃してしまう
契約期間が6か月以上の業務委託契約について、発注事業者が契約を解除・更新しない場合、30日前までにフリーランスや業務委託パートナーへ予告する義務があります。
Lansmartのアラート機能を使えば、契約更新時期が近づいたタイミングで自動通知されるため、予告義務違反を防げます。また、契約ステータスが自動更新されるため、現在どの契約が有効なのかが一目で把握できます。
これらの機能により、法令遵守の負担を最小限に抑えながら、貴社の業務委託管理の質を高められます。
守りのDXで会社を強くする
業務委託を活用する企業にとって、フリーランス保護法をはじめとする法令への対応は避けて通れない経営課題です。しかし、これを単に「やらなければいけない」として捉えるのではなく、「守りのDX」として積極的に取り組むことで、パートナーとの信頼関係が強化され、結果的に事業の安定成長につながります。
まずは本記事のチェックリストで自社の現状を確認し、課題が見つかったらツールを活用した仕組みづくりに着手しましょう。守りのDXは、攻めのDXと並んで企業の成長を支える重要な要素です。Lansmart by SmartHRのようなツールを活用しながら、安心して業務委託を拡大できる体制を整えていきましょう。