ストレスチェックで離職は防げる? ストレスの多様性から考える離職防止策
- 公開日
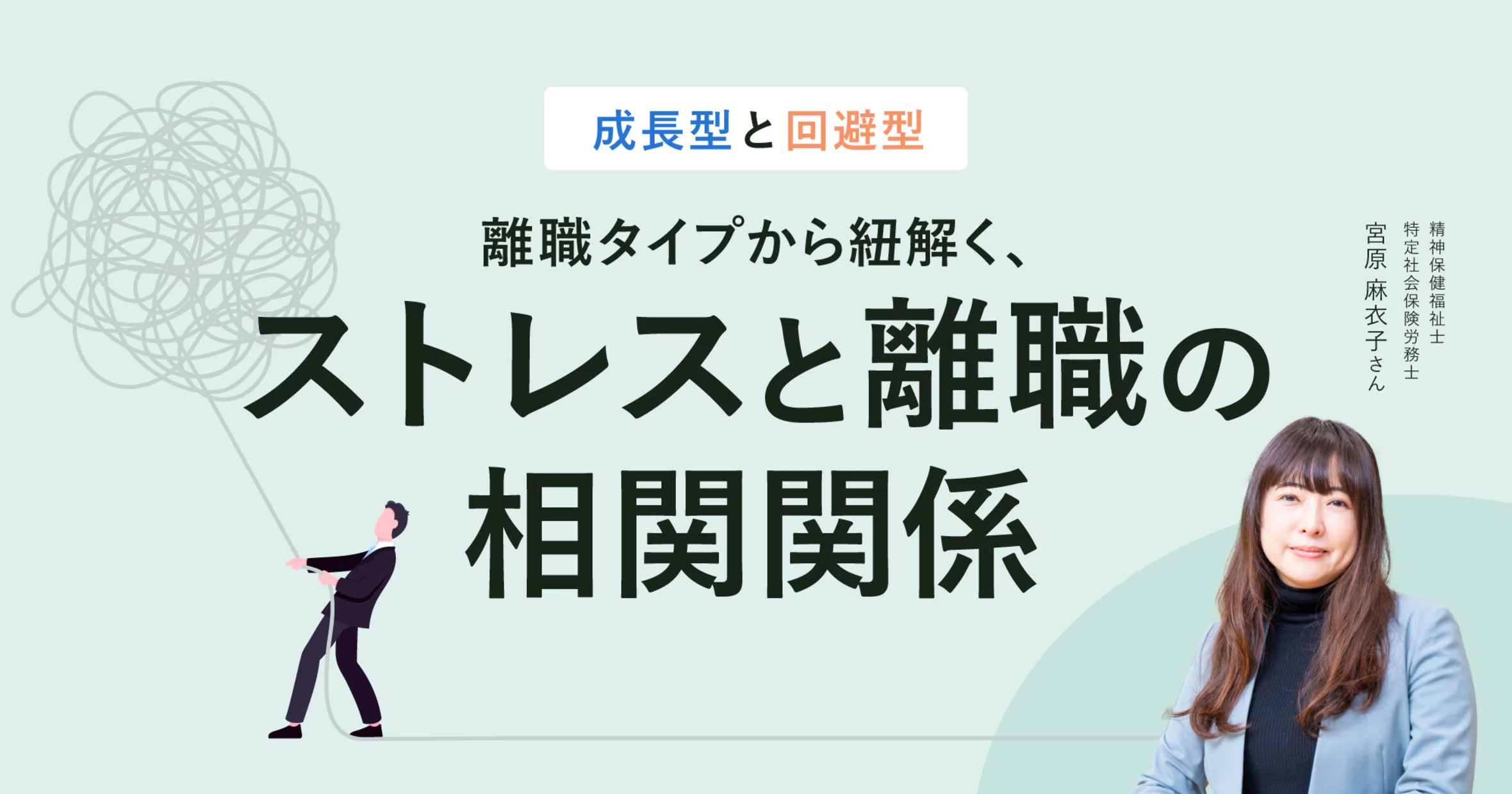
目次
人的資本経営が重視される昨今、多くの企業が離職防止対策に取り組んでいます。離職の理由はさまざまですが、職場のストレスによる退職経験がある方も多いのではないでしょうか。
そうしたなかで、2025年3月14日にすべての企業にストレスチェックを義務づける、労働安全衛生法の改正案が閣議決定されました。これまで除外されていた従業員50人未満の事業所にも対象を広げる改正です。
はたしてストレスチェックで離職を防止できるのでしょうか? 約10年間の制度運用から浮き彫りになった課題と、企業に求められる本質的な対応とは? 今回は産業メンタルヘルスの専門家である宮原麻衣子先生にお話を伺い、離職の本質と効果的な人材定着策について考えます。
ストレスチェック義務化から約10年、見えてきた課題

2015年12月1日にストレスチェックが義務化されてから今年で約10年が経過しました。「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)- 厚生労働省」によると、50人以上の事業所におけるストレスチェック実施率は81.7%と高く推移しています。

※ 赤い囲み部分
- 総合健康リスク:110以上を赤色、100以上を黄色に色分け
- 高ストレス者(A判定)割合:15%以上を赤色、10%以上を黄色に色分け
また、ストレスチェックマガジンが発表した「ストレスチェック業界平均値レポート2024」によると、総合健康リスクの基準値100以上を記録する業界が減少しており、改善傾向です。
「受検率も高いことから、従業員の方が自身のストレスの状態に気づけるきっかけとなり、メンタルヘルスケアにおける一次予防の観点で一定の効果があると言えるでしょう」と宮原先生はストレスチェックの良好点をあげます。
しかし、その一方でいくつかの課題も顕在化していると宮原先生は指摘します。
「精神障害の労災補償件数が増加傾向にあり、メンタルヘルス不調による休職や離職も多いという現状があります。調査対象全体における総合健康リスクの数値の改善をふまえると、高ストレス状態が続いている方と改善されている方の差が開いている可能性があります。また、毎年同じ質問を繰り返すことで、回答の形骸化や意図的な低ストレス回答などを生み、従業員の本質的なストレス状況を把握しづらくしているのかもしれません」(宮原先生)

「加えて、高ストレス判定された人は、任意で医師による面接指導を受けることが可能ですが、実施率が低いといった課題もあります。医師の面接指導を希望してストレスチェックの結果が会社に開示されることに抵抗感を抱く人や、医師の面接指導自体にメリットを感じられていない人が多いのかもしれません」(宮原先生)
職場ストレスと離職に相関関係はある?

職場とストレスの関係を探るために、SmartHR Mag.編集部は2024年12月にメールマガジン登録者向けにアンケートを実施し、「職場のストレスが要因で退職したことがある」と回答した人は50.9%でした。一方で、令和5年の労働安全衛生調査によると、仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスを抱えている人の割合は82.7%です。この2つの数字から、ストレスを抱えながらも離職を選択しない人も一定数いることが考えられると宮原先生は指摘します。
「日本の労働者のワークエンゲージメントは低いにもかかわらず、離職に踏み出す人は少ない傾向にあると言われています。会社を辞めずに最低限の業務をこなし、それ以上の努力や貢献を意図的に控える『静かな退職』という言葉がありますが、そうした状態の方が82.7%のなかに含まれているのかもしれません」(宮原先生)
また、SmartHR Mag.編集部のアンケートで「ストレスがない状態でも転職経験がある」と回答した人も約半数いたことについて宮原先生は次のように説明します。
「人によって何をストレスに感じるかはさまざまです。たとえば、待遇面への不満や個人的な事情はもちろん、キャリアアップが見込めない、自分のスキルを活かしきれない、会社や自身の未来像が見えない、企業の文化と自分が合わないなど。これらの理由を、必ずしもストレスとして認識するとは限りません」(宮原先生)
さらに宮原先生は、最近の傾向として、過重労働やハラスメント防止に意識が向きすぎるあまり、人材育成に積極的に取り組めない企業が増えていると指摘します。そうした「ゆるブラック企業」や「パープル企業」と呼ばれる職場は、一見ストレスが少なく働きやすそうに見えますが、成長の機会を得られない、キャリアアップできないといった点でストレスを感じて辞める人もいるようです。
このことから、ストレスチェックで測定されるストレスレベルと実際の離職行動には、必ずしも単純な相関関係があるとは言えないことがわかります。

お役立ち資料
知らぬ間に拡大する「静かな退職」は早めに対策を!
この資料でこんなことが分かります
- 「静かな退職」とは?
- 「静かな退職」を放置することの問題点
- 「静かな退職」を生み出さないために
- 従業員の声を収集する「従業員サーベイ」のポイント

成長型離職と回避型離職、2つの離職タイプ
離職のタイプをわかりやすく分類すると、「成長型離職」と「回避型離職」の2つあります。成長型離職は、キャリアアップや自分のスキルをより発揮できる場所への転職といった、能動的な離職です。一方、回避型離職は緊急回避の意味合いが強く、過剰なストレスや将来への悲観的な見通しから回避するための離職です。そのうえで、宮原先生は成長型離職であっても必ずしも前向きな選択とは限らないと指摘します。
「企業側は成長型離職を個人のキャリア選択として見過ごすのではなく、その背景にある組織的な課題を見極める必要があると思います。たとえば『ここではもう成長できないな』と思って離職する場合、成長できないストレスから回避しているとも言えます」(宮原先生)
また、企業としては、成長型離職をする人材はつなぎとめたいと考えるのが一般的です。キャリア志向が強く、より自分の能力を発揮できる場を求める人材には、社内で成長の機会を提供したいところです。
「一方で、雇用の流動性が高まっているということは、他社で成長型離職した人材を受け入れるチャンスとも捉えられます。自社の成長志向の人材をつなぎとめながら、他社の優秀な人材に選ばれる組織づくりを進めれば、多様な経験や視点が交わり、イノベーションが生まれ、結果として事業成長へとつながる好循環を生み出せるのではないでしょうか」(宮原先生)
「退職理由を把握できていない」が46.3%

離職防止において鍵となるのが、退職理由の適切な把握です。先述のSmartHR Mag.によるアンケートでは、人事担当者の46.3%と約半数が「退職理由を把握していない」と回答しています。
人事は従業員が退職を申し出た際に、その原因や経緯を十分に検証する時間を確保できないケースも多くあります。一方で、従業員も約半数が「退職の本当の理由を伝えていない」という回答も。
「おそらく、離職者は円満退職したいという気持ちが強いのでしょう。本当のことを言えばなんらかの圧力を受けるかもしれない、あるいは他の人に迷惑をかけたくない、関係性を悪化させたくないという気持ちから、本当の退職理由を伝えられないのだと思います。また、日ごろから現場と人事のコミュニケーションが十分でない環境では、従業員はさらに本音を話しづらくなってしまう可能性もあります」と宮原先生は、現場と人事の日常的なコミュニケーションの重要性を強調しました。
離職タイプ別アプローチと長期的な人材育成のポイント
宮原先生が提案する離職タイプ別の防止策は以下のとおりです。
回避型離職の防止策
- 労働環境やワークライフバランスの状況を適切に把握・管理する
- ストレスチェックの結果を実際の職場改善に結びつける
- 病気や家族の介護など個人的事情と仕事の両立支援体制を整える
成長型離職の防止策
- 社内で自律的なキャリア形成ができる仕組みを構築する
- 明確なキャリアパスを示し、成長の道筋を可視化する
- スキルアップのための具体的な支援制度を設ける

お役立ち資料
自律型人材が育つ組織へアップデートするには?
どちらの離職タイプにおいても、コミュニケーションを通して、従業員の状況をしっかりと把握することが重要です。状況把握における、ストレスチェックや従業員サーベイの活用について、宮原先生は以下のとおり強調します。
「ストレスチェックや従業員サーベイなどの結果を表面的に捉えるのではなく、なぜそうした結果が出たのか考察を深め、対策を講じることが重要です。企業側も実施に労力をかけ、従業員の方も時間を使って回答している、お互いがリソースを割いているからこそ、結果から得られる気づきを確実に職場改善に活かしましょう。やりっぱなしにしていると、『意見を出しても何も変わらない』という不信感が生じかねません」(宮原先生)
続けて宮原先生は、「オンボーディング」という概念の重要性についても言及します。
「オンボーディングとは、会社と従業員が同じ船に乗り、共に成長していくという考え方です。単に入社した人材が自然と成長することを期待するのではなく、長期的な視点で5年、10年先を見据え、キャリア開発やスキルアップ、エンゲージメント向上のための計画的な人材育成プログラムの構築が重要です」(宮原先生)
さらに、一度離職した人を「アルムナイ」として再雇用する動きも増えていることから、「辞める方の負担にならない程度でつながりをもち続けること」の重要性も指摘しました。

従業員理解が生み出す好循環
お伝えしてきたとおり、職場ストレスと離職の問題には、単一の解決策はありません。回避型と成長型どちらのタイプにも、コミュニケーションと従業員理解という共通基盤が求められます。宮原先生は、これらの取り組みの根底にあるべき姿勢について、次のように述べます。
「まずは、従業員一人ひとりに関心をもつことが大切です。従業員は企業にとっての戦力である以前に、それぞれに人生観や夢、希望、達成したい目標をもつ個人です。そうした側面に関心を寄せ、真摯に向き合うことから、信頼関係は構築されていきます。企業と従業員が共に歩んでいこうとする姿勢があれば、人材育成も進展します。人材育成によって従業員の成長意欲を高めることで、ストレス耐性も向上し、回避型離職・成長型離職ともに最小限に抑えられます」(宮原先生)
ストレスチェック義務化などの制度だけでは解決できないストレスと離職の課題。企業は、本質的な離職理由を理解し、適切に対応していくことが求められています。そのためには、一人ひとりの従業員と向き合い、彼らの成長と幸福に関心をもつ企業文化の醸成が不可欠なのです。

お役立ち資料
従業員エンゲージメントを向上させるサーベイ運用ノウハウ
この資料でこんなことが分かります
- エンゲージメントが重要な理由
- 従業員サーベイの考え方や手順
- エンゲージメントを向上させる効果的な取り組み
撮影:曳野 若菜



























