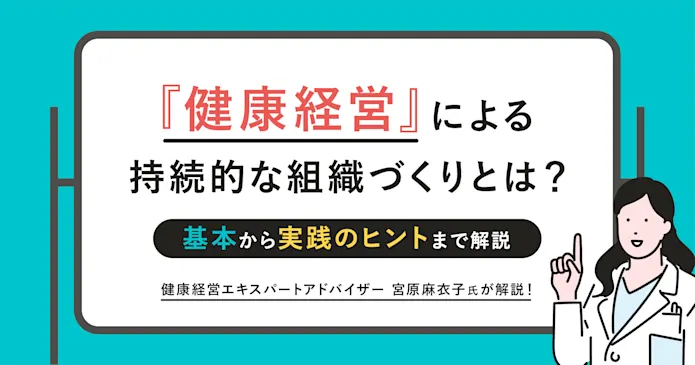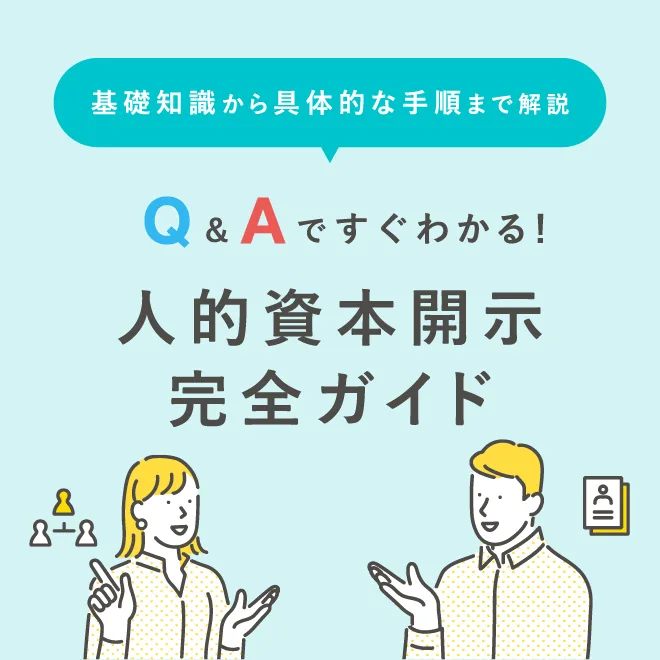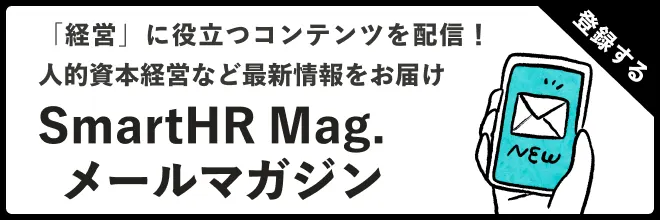「健康経営×成果定義」で組織を育てる。いい生活CFO兼人事部長の実践
- 公開日

目次
株式会社いい生活は、事業成長を続けながらも従業員の健康を重視し、6年連続で「健康経営優良法人」に認定されています。ハードワークが求められる場面と従業員の健康維持をどのようにバランスを取るべきか、持続可能な組織づくりについてCFOと人事部長を兼任する塩川さんにお話しいただきました。

株式会社いい生活 代表取締役副社長 CFO
早稲田大学政治経済学部卒。1991年住友銀行入行後、リーマン・ブラザーズ証券で日本企業の海外M&Aに従事。1994年ゴールドマン・サックス証券入社、株式資本市場部で企業のIPOや資金調達を担当。2000年にGSの同僚と「不動産市場のIT化」を目指し株式会社いい生活を創業し、2006年東証マザーズに上場、代表取締役CFO就任。「不動産市場に、テクノロジーを」「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」というミッションの実現に向け活動中。
近年、多くの企業が健康経営やウェルビーイングを掲げていますが、事業成長との両立には依然として課題を抱えています。「不動産×IT」という新領域に挑戦する株式会社いい生活は、創業以来の成長を続ける一方で、従業員の健康を重要な経営課題と位置づけてさまざまな施策に取り組み、「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に2020年から6年連続で認定されています。
名だたる企業でハードワークを経験してきた経営陣たちは、なぜ事業の成長フェーズのまっただなかでも健康経営を重視し、推進してきたのでしょうか。
本稿では、株式会社いい生活CFOと人事部長を兼任する塩川さんに、時にハードワークが求められる場面と従業員の健康維持のバランスや、目標管理の仕組みと健康経営を組み合わせた持続可能な組織づくりについて伺いました。
経営×人事の視点で捉える、組織の持続可能性
はじめに、塩川さんの現在の役割について教えてください。
塩川さん
株式会社いい生活の創業メンバーの一人として、代表取締役副社長兼CFOを務めています。また、人事部長とコーポレート本部長、総務部長も兼任しています。幅広く開発とマーケティング、セールス以外、IRやコンプライアンス関連なども守備範囲というポジションですね。
CFOと人事部長を兼任しているのは、かなり珍しいケースかと感じます。
塩川さん
よく「領域が違うのに大変じゃないか」とは言われますね。ただ、CFOは「事業計画を通じて企業価値を設計し、価値を実現していく仕事」で、人事部長は「その価値創造と提供に必要な人財を見つけ、活躍してもらう仕事」と捉えています。私のなかではこの2つの役割は、つながっており、そこまで矛盾なく受け入れられているんです。
私たちは人財を「人的資源」ではなく、「人的資本」と位置づけています。人は会社にとって単なるリソースではなく、投資によって成長させられる存在です。「会社の価値や競争力の源泉は人財である」という認識のもと、弊社では採用や育成のための研修に注力しています。
直近ではどのような人事課題に直面していますか?
塩川さん
常に人財は不足気味ですね。弊社が求めているのは「IT」と「不動産」の両方の分野にある程度精通している人なのですが、日本のキャリア採用の市場にはあまりいないタイプなんです。こうした人財をいかに見つけるか。いないのであれば、いかに育てていくかを、日々真剣に考えています。

塩川さん
一方で、「人が足りないなりに、どうやりくりしていくか」という思考も大事にしています。会社として本当に求めたい成果を定義しながら、そこに確実につながる業務にフォーカスしていく。成果に集中するためには何が必要で、何が不必要かを模索しながら、社内の仕組みづくりに向き合っています。
ミッション実現に向けた健康経営の位置づけ
健康経営に取り組み始めた背景について教えてください。
塩川さん
もともと創業メンバーは健康意識が比較的高く「プロフェッショナルなビジネスパーソンとして健康であることはデフォルト」くらいに考えていました。「仕事で成果を出すために、健康を大切に」という文化を会社にどのように浸透させていこうかと検討しているなかで、健康経営優良法人認定制度の存在を知りました。
どうせ取り組むなら、こうした認定をもらえたほうが、採用やリテンションにも生かしていけそうだと思ったんです。
弊社は市場規模約60兆円とされる巨大な不動産マーケットにおいて、「情報テクノロジー×不動産」という新しい領域を開拓し、市場全体のDXを推進していく……という壮大なミッションを掲げています。短期間で達成できる目標ではないからこそ、持続可能な働き方が不可欠です。健康経営の認定を目指しながら社内での取り組みを整理していくことで、社員の健康をマネジメントするシステムを整えていきました。
塩川さんご自身は、健康と仕事、会社の関係について、どのように捉えていらっしゃいますか?
塩川さん
かくいう私も20代の頃に、朝早くから夜遅くまで会社で働き詰めだった時期がありました。ある日、朝起きて伸びをしたら胸のあたりから「ピキッ」って音がして痛み出したんです。病院で診察を受けると肋軟骨の剥離骨折だと診断されたうえで、医者から「ビタミンDが不足しているので、ちゃんと日光を浴びてください」と言われました(笑)。
そういった経験もあるので、つくづく健康は大事だと痛感しています。ハードワークと健康管理は、決してトレードオフの関係ではありません。むしろ、ハードワークで常に実力を発揮するためには、健康でなければいけない。私は立場上「人が力を発揮する環境や仕組みはどういうものなのか?」と常に試行錯誤していますが、その答えのひとつが健康経営だといえますね。

健康経営のためにも「成果をきちんと定義する」
健康経営に向けて、具体的にはどのような施策を実施したのですか?
塩川さん
健康経営の取り組みを進めるうえで、「人的資本拡大の基本方針」「労働安全衛生基本方針」を成文化しました。これらでウェルビーイングに注力していくことを宣言し、労働災害というマイナスを生み出さない土台を整えたうえで、プラスを生み出すために乗せる要素として、健康経営を位置づけました。
具体的な取り組みとしては、はじめに「健康経営宣言」をリリースして取り組みを周知したうえで、認定制度の要件に沿ってストレスチェックの徹底や過重労働対策などの施策を、一つずつ整えていきました。
その後、健康経営の向かうべきところを整理しつつ、各取り組みによって得られる効果を可視化するために「健康経営戦略マップ」を作成しました。現在はこのマップをマイルストーンとしながら、施策の精度向上に努めています。
浸透のポイントはどこにあるのでしょうか。
塩川さん
個別の細かい施策を挙げると、マッサージルームの設置と鍼灸師の常駐や、ウォーターサーバーの導入などが挙げられます。しかし、そうした「How」の部分よりも、大元の「Why」の部分、すなわち健康経営の意義をいかに社内に浸透させていくかが最も重要なポイントだと感じています。

先ほど「ハードワークと健康管理はトレードオフではない」とおっしゃっていましたが、事業の成長フェーズにおいて、ついつい無理して働いてしまう社員は少なくないと思います。会社として「ハードワークと健康」のバランスを最適化するために、塩川さんはどのような配慮をされていますか?
塩川さん
大前提として、労働関連のルールは絶対に遵守しなければいけません。スポーツで言うならば、野球で点が取れないからといって「もう1イニング追加で」なんて変更は認められませんよね。ビジネスも同じです。働く時間をいたずらに増やすのではなく、決められたルールのなかで最大の成果を出す方法を考える必要があります。
そのためにも、人事部長として注力しているのは、成果をきちんと定義することです。具体的にはOKRとKGI、KPIを使い分けています。OKRは事業をドライブさせるためのツールとして位置づけ、かなりストレッチさせた目標を設定します。
ただ、実際の人事評価はOKRではなく、そこから派生する形で現実的に設定したKGI及びKPIを参照するんです。チャレンジングな目標と現実的な目標のバランスを取ることで、持続的な成長と着実な成果の両立を試みています。
社員が「自分のために健康でいよう」と思える働きかけを
健康経営の取り組みを本格化させて、社内にどのような変化がありましたか?
塩川さん
最もうれしい変化は、少しずつですが「ハードワーク=長時間労働」という固定観念が抜けて、「時間は有限である」という意識が確実に浸透してきていることですね。先ほどお話したOKRなどの目標設定の整理の効果もあると思いますが、「ルールで定められた時間内で、より高い成果を上げるにはどう動けばよいか」と考えるマインドが根づきつつあります。
ただし、まだまだ道半ばという実感もあります。時折「健康経営は対外的にアピールするため、人事部のための取り組みですよね?」といった声が上がったりします。そういうときは必ず「健康経営の受益者はあなたとあなたのご家族ですよ」と伝えていますね。そして「会社には社員を健康な状態で家に帰す義務がある」とも言っています。
社員の方々の行動を促すためのポイントはどこにあるのでしょうか。
塩川さん
現場の反応を見ながら、あらためて細かい施策については、個々の行動に過度に介入しすぎないのも重要と感じています。
たとえば禁煙の推進にしても、背中を押すことはできても、最終的な判断は個人に委ねる必要がある。そこには、タバコを吸うことやジャンクフードを食べることによってこそ保たれる心の健康があるのかもしれません。押し付けにならない程度のバランスを保ちつつ、社員が自律的に「自分のために健康でいよう」と思えるよう、より効果的なアプローチを模索していきたいですね。
成果志向の醸成、組織課題の把握にも効く健康経営
健康経営については「やりたいけれども、本業における費用対効果が見えにくい」と、なかなか踏み出せていない企業も多いように感じています。健康経営に対する投資の効果測定について、どのように考えていますか?
塩川さん
健康経営に限らず、人事施策の全般は「これをやったからこれだけの利益がでました」という因果関係を示すのが難しいものです。現在、私たちが健康投資の効果測定の指標として注目しているのは、一人当たりの付加価値額です。さまざまな取り組みの総合的な反映先として、これをキャッチアップすることで、数値上の成果を確認しています。

塩川さん
また、健康経営の直接的な効果とは言い難い部分もありますが、取り組みを始めてから求人の応募者数は増加、離職率は低下傾向にあります。たとえば採用の場面で「ここは健康経営に取り組んでいる」という事実が、最終的な意思決定の後押しになることはあるのではないかと思います。
これから健康経営に注力していこうと考えている企業の経営者や人事領域のリーダーの方々に向けて、アドバイスをいただけたら幸いです。
塩川さん
やるべきことに迷ったら、まずは「健康経営優良法人の認定を取得する」という目標から始めてみるのがよいでしょう。運営母体からスコアや順位といったフィードバックも得られるので、外部のアドバイザーを雇わなくても、自分たちでPDCAを回しながら取り組みを整えていけるはずです。
また、こうした取り組みを通じて、より成果志向の組織マインドが醸成されたり、組織課題の把握と解決につながったりと、さまざまな副次的な効果も期待できます。ぜひ「一粒で何度もおいしい人財マネジメントツール」として、健康経営をうまく活用していってください。
※編集部註:2025年1月取材時の情報であり、現在の同社の取り組みとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
執筆:西山 武志、撮影:矢野 拓実
編集後記
取材のなかで印象的だったのは、ゴールドマン・サックスなど名だたる企業でのハードワークを経験してこられた塩川さんが、「ハードワークと健康管理はトレードオフではない」と明言されたこと。若い頃に過度の仕事で体を壊した経験から、「ハードワークで常に実力を発揮するためには、健康でなければいけない」という確信にいたる過程には説得力がありました。
また、健康経営を推進するうえで単に「働き過ぎないように」と言うだけでは不十分で、「成果をきちんと定義する」ことが欠かせないという指摘も重要でしょう。いい生活さまではOKRとKGI/KPIを使い分けることで、チャレンジングな目標設定と現実的な評価のバランスをとっていました。
健康経営の取り組みによって「時間は有限である」という意識が浸透し、「限られた時間でより高い成果を上げるにはどう動けばよいか」というマインドが根づきつつあるという変化は、まさに健康経営と事業成長の好循環を示していると感じました。
今後もSmartHR Mag.では、いい生活さまのように人材と事業の持続的な成長を同時に実現するための組織づくりについて、さまざまな視点から情報を発信していきたいと思います。