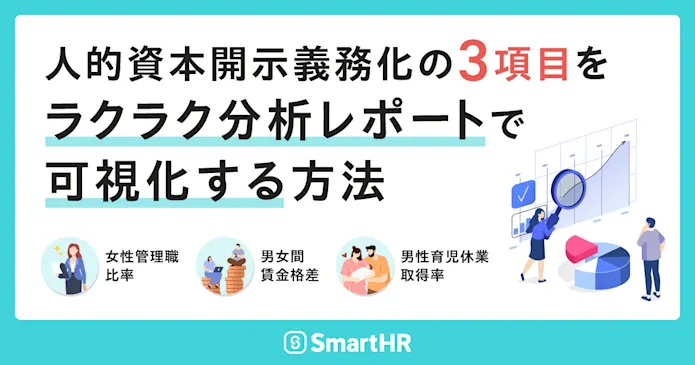どの情報を開示すべき?企業規模別・情報公表義務まとめ
- 公開日
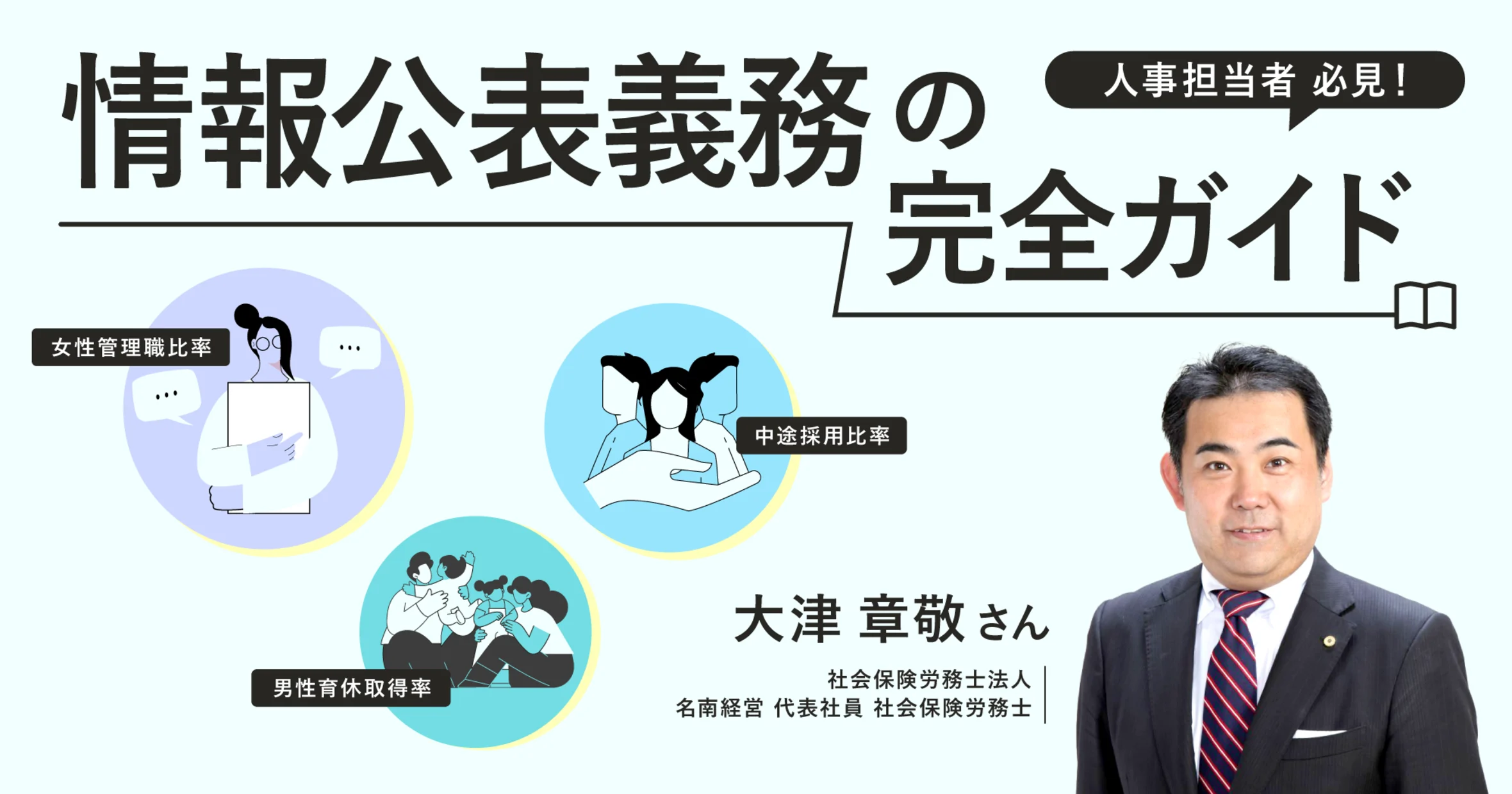
目次
こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。
2025年4月に従業員数301人以上の企業に男性の育児休業等取得率の公表義務が課せられるなど、近年、企業には従業員の働き方に関するさまざまな情報開示が法律で義務付けられるようになりました。それぞれ対象企業や開示内容、公表方法が異なるため、「自社は何をどこまで開示すべきなのか」と戸惑う人事担当者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、企業に求められている情報公表の義務を横断的に解説します。これさえ読めば、自社がどの情報を開示すべきかがすぐにわかります。ぜひ最後までご覧ください。
【101人以上】女性活躍に関する情報
まずは女性活躍推進法による情報公表です。厚生労働省の調査(令和5年度 雇用均等基本調査結果)によれば、全国の企業で課長級以上の管理職に占める女性の割合は12.7%と国際的に見ても低い水準にあり、男女による賃金の格差も存在しています。
こうした状況を改善するため、女性活躍推進法にもとづき、企業は以下のとおり情報を公表する必要があります。
- 常時雇用する従業員数301人以上の事業主
- 表1の①の区分から「男女の賃金の差異」を含めた2項目以上
- ②の区分から1項目以上を選択して、合計3項目以上
- 常時雇用する従業員数101人以上300人以下の事業主
①と②の全項目から1項目以上
表1
「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」(厚生労働省)P.20より引用
※「常時雇用する従業員」とは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員なども含み、具体的な対象者は以下のとおりです。週所定労働時間が短いパートタイマーなども、下記条件に当てはまれば人数にカウントします。
(1)期間の定めなく雇用されている人
(2)過去1年以上続けて雇用されている人
(3)採用時点で1年以上雇用される見込みがある人
今後、常時雇用する従業員数101人以上300人以下の事業主においても「男女の賃金の差異」および「管理職に占める女性労働者の割合」の公表を義務化する法改正が予定されています。
算出・公表方法
男女の賃金の差異の算出方法
- 直近の事業年度の賃金台帳、源泉徴収簿などをもとに、正規雇用・非正規雇用・全労働者ごとに男女別の賃金総額を計算する。
- それぞれ人数で割り、正規雇用・非正規雇用・全労働者ごとの男女別の平均年間賃金を算出
- で女性の平均年間賃金が男性の平均年間賃金の何パーセントに当たるかを、正規雇用者・非正規雇用者・全労働者の3つの区分ごとで算出する。
※数値は、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までのものとする
例:正規雇用労働者における女性の平均年間賃金が350万円、男性が400万円の場合
350万円 ÷ 400万円 × 100 = 87.5%
「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」(厚生労働省)
管理職に占める女性労働者の割合の算出方法
「管理職に占める女性労働者の割合」の算出方法は、「女性の管理職数÷管理職数×100(%)」とされています。ここでいう管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計を指します。
公表方法
情報公表の内容については、おおむね年1回以上更新し、いつの情報なのかがわかるよう更新時点を明記することが求められています。公表先は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページなど、学生をはじめとした求職者が閲覧できるようにする必要があります。
【301人以上】中途採用比率
2021年4月1日から常時雇用する従業員数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されています。
人生100年時代を迎え、職業生活がより長期化することを背景に、労働者が自律的にキャリアを形成し、必要に応じて転職できる環境が重要です。そこで企業の中途採用環境整備を促進するために、この情報公表制度が設けられました。
「中途採用」とは、新卒採用者以外のすべての採用を指します。
- 「中途採用」=「新卒採用」以外のすべての採用
- 「新卒採用」=次の人を対象とした採用
- 大学・高校・専門学校などを卒業したばかりの人
- 職業訓練校などを修了したばかりの人
算出方法
中途採用比率の具体的な計算方法および公表形式は以下のとおりとされています。
「令和3年4月1日から 常時雇用する労働者数が301人以上の企業において 正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます」(厚生労働省)
なお、実務においてはFAQ「中途採用比率の公表における解釈事項等について」を参考にするとよいでしょう。
公表方法
おおむね1年に1回以上、公表日を明らかにしたうえで、直近の3事業年度の情報を、自社のホームページや、厚生労働省が開設している「職場情報総合サイト しょくばらぼ」などに掲載し、求職者が閲覧できるようにする必要があります。
【1,001人以上→301人以上】男性労働者の育児休業取得率
2023年4月に改正施行された育児・介護休業法では、常時雇用する従業員数が1,001人以上の企業に男性労働者の育児休業等の取得状況の公表が義務付けられました。2025年4月からは301人以上の企業も義務化の対象となります。
公表内容と算出方法は以下のとおりです。公表日の直前の事業年度における表2の①または②のいずれかの割合とされています。
表2
「両立支援のひろば」(厚生労働省)
また、表3は経団連の会員企業おいて、2023年4月の法改正時の育児休業取得率の調査結果です。2022年度の男性の育児休業取得率は大きく上昇しており、この結果から、法改正による情報公開の義務化が男性の育児休業取得を促進したことが推測できます。「男性の育児休業取得率100%」という企業の事例をよく耳にするようになったのもこのころだったのではないでしょうか。
表3
「「男性の家事・育児」に関するアンケ―ト調査結果 」(一般社団法人日本経済団体連合会)
公表方法
公表時期は公表前事業年度終了後、約3か月以内とされており、自社のホームページや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表が推奨されています。
【上場企業】人的資本の情報開示
近年、企業価値における「人的資本」の重要性が高まっています。これは従業員を単なるコストではなく、教育や業務経験を通じて能力や意欲を高め、企業の付加価値を創造する重要な「資本」と捉える考え方です。
このような人的資本への注目の高まりを受けて、2023年3月期から有価証券報告書で人的資本に関する情報開示が義務化されました。義務化の対象は、有価証券報告書を発行している企業約4,000社とされています。2022年8月に内閣官房は「人的資本可視化指針」を公表し、以下の7分野の情報開示を求めています。
- 人材育成に関連する開示事項
- 従業員エンゲージメントに関連する開示事項
- 流動性分野
- ダイバーシティ分野
- コンプライアンス
- 労働慣行分野
- 健康・安全分野
具体的な開示にあたっては、上記の「人的資本可視化指針」のP20以降で開示事項(例)も示されていますので、それらを参考にするとよいでしょう。
情報公表が求められる背景と今後の動向
企業に求められる情報公表は今後も拡大していく見込みです。現在も、労働基準法改正の議論の中では、企業の時間外・休日労働の実態について情報公表を義務化する案が検討されており、2027年度にも法制化される可能性があります。
情報公表が求められる理由
政府が情報公表義務化を進める背景には、社会課題を解決するための方法論の変化があります。具体的には次の2つのアプローチがあります。
- ハードロー型アプローチ:罰則付きの強制的な法規制
- ソフトロー型アプローチ:情報公開などを通じた企業の自主的改善促進
ハードロー型アプローチは強制力がある一方で、柔軟性に乏しく、監督指導など執行コストも大きくなります。そこで注目されているのがソフトロー型アプローチです。
情報公表義務化により、企業は数値改善に向けて積極的に取り組むことが予想されます。また求職者にとっても、企業の実態が透明化されることで適切な就職先選択ができ、入社後のミスマッチを防止できるメリットがあります。
戦略的な情報公表の活用
こうした情報公表は法的義務への対応という側面だけでなく、自社の魅力を求職者に訴求する機会としても活用できます。義務化されている数値だけでなく、自社の強みを示すデータも積極的に開示することで、企業のブランディングにも寄与するでしょう。
そのためには、各種データを簡単に集計できるような仕組みを導入し、自社のホームページなどで計画的かつ戦略的に情報開示していくことが重要です。

お役立ち資料
採用力強化になぜつながる?人事データベースを活用した情報開示が大切な理由
情報開示を、採用力強化にうまく繋げている企業の共通点は何か。SmartHRでできること、情報開示による採用力強化の事例について解説しています。
SmartHRで情報公表作業を効率化
情報公表義務化に対応する際、データ集計の手間が課題となりますが、SmartHRの「分析レポート」機能を活用することで効率的に対応できます。従業員マスターデータを常に最新の状態で管理でき、さまざまな切り口でデータを集計できます。
詳しい活用方法については、以下の記事をご参照ください。