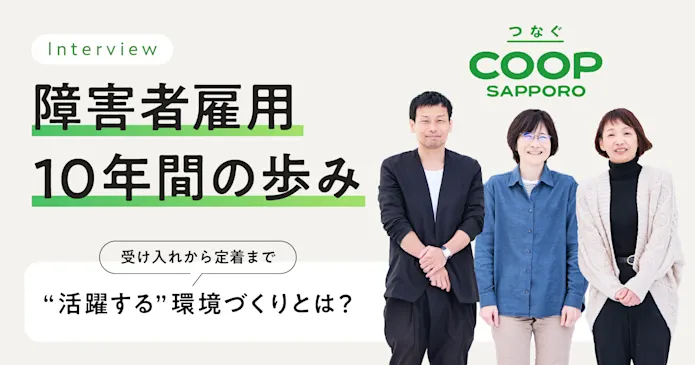人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年3月振り返りと4月のポイント
- 公開日
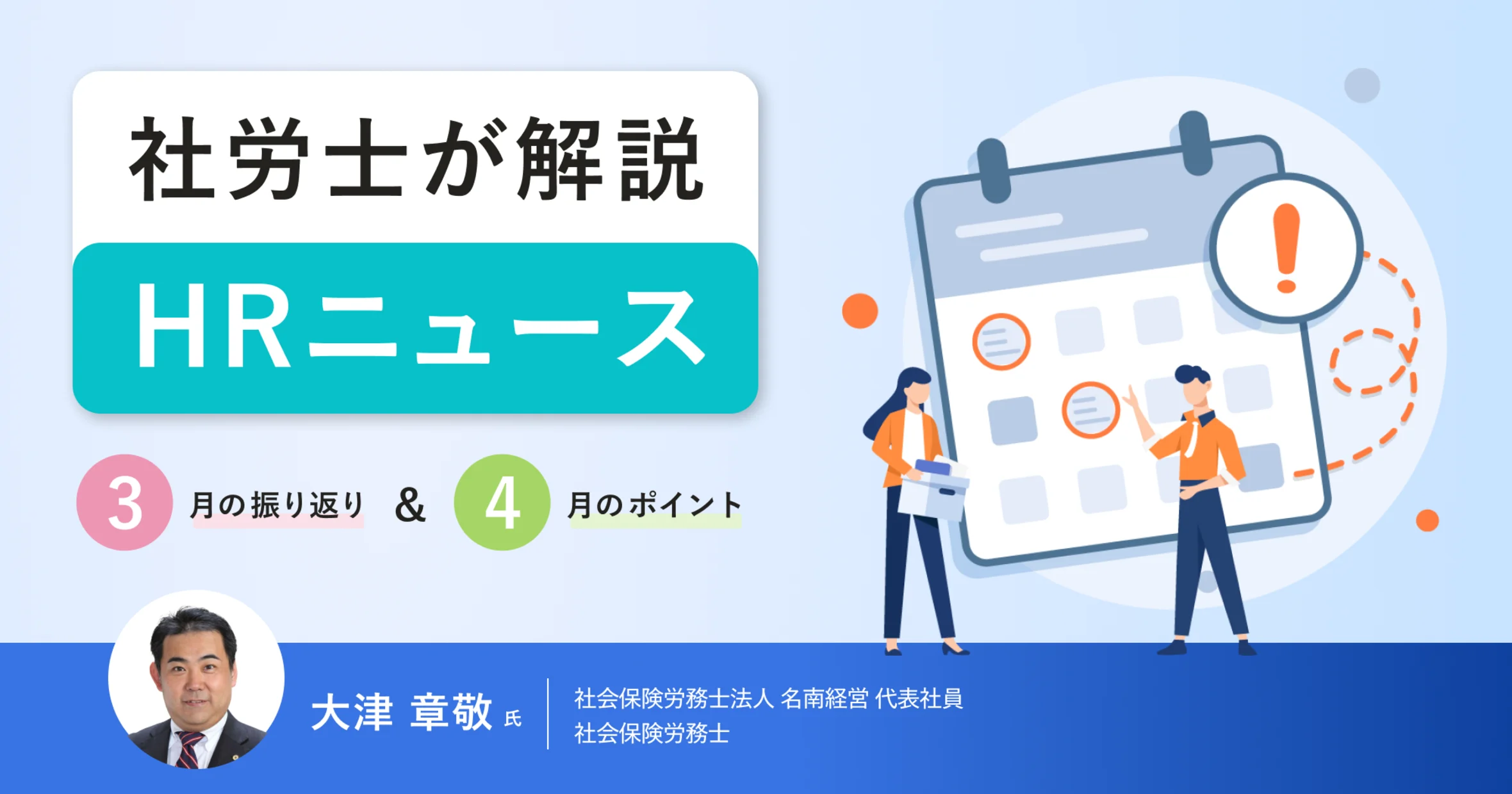
目次
こんにちは。社会保険労務士法人名南経営の大津です。今月からHRニュースを担当することになりました。皆さまのご業務に役立つ人事・労務の最新情報をお届けして参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
4月は新入社員の受け入れもあり、人事のみなさんは繁忙期ではないかと思いますが、新入社員の入社は先輩社員にとっても大きな刺激になります。新入社員の受け入れを通じて組織全体をリフレッシュさせ、また1年間、頑張っていくきっかけにしたいものです。
今月は複数の法改正があり、その対応が求められますが、まずは3月のトピックの振り返りから確認していきましょう。
3月のトピックを振り返る
3月12日に2025年の春闘の集中回答日がありましたが、満額回答連発で、あらためて賃金の上昇を実感することとなりました。その他にも注意が必要なトピックがありますので、対応漏れがないかチェックしてみてください。
トピック1 昨年を上回る賃上げ
バブル崩壊以降、30年間ほとんど引き上げられなかった我が国の賃金ですが、物価高騰や深刻な採用難などの状況を受けて、上昇を開始しました。昨年は歴史的な賃上げの春になりましたが、連合の賃上げ集計(2025春季生活闘争 第2回回答集計結果(2025年3月21日現在))を見ると、昨年実績の5.25%を上回る5.40%となっています。
個別企業の回答状況を見ると、大手企業では15,000円前後のベースアップを行う企業が多く、上昇を続ける初任給の見直しを含め、ベースアップへの対応が求められています。ベースアップに関しては、ここ数年、原資が限られるなか、若手社員中心にベースアップした結果、中堅以上の社員の不満が高まっているケースが増加しています。今後も賃上げ基調が続くと考えられるため、賃金制度全体の見直し議論も進めていく必要があるでしょう。

トピック2 高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了
高年齢者雇用安定法により、60歳から65歳までの雇用確保措置が企業に義務づけられていますが、このうち継続雇用制度については、経過措置として、平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていました。この経過措置が3月31日をもって終了しました。
これにより4月1日以降は、解雇事由・退職事由に該当する場合を除き、希望者全員の継続雇用の実施が必要となります。
また最近は人手不足の対応もあり、定年年齢を引き上げる企業も増加しています。その際には60歳以降の職務設計(役職定年の設定を含む)や処遇の見直し、退職金制度の改定などがポイントとなります。

トピック3 36協定の締結
36協定(時間外・休日労働に関する協定)は労務管理におけるもっとも基本的な手続きであり、時間外労働・休日労働を命じる際には確実に締結し、労働基準監督署への届出が求められます。年度に合わせて締結している企業が多いため、4月から新年度という企業においては、締結漏れがないように注意しましょう。

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
4月のポイント
4月は何といっても育児・介護休業法の改正対応が最重要となりますが、その他の関連事項も含め、トピックを確認していきましょう。
トピック1 改正育児・介護休業法への対応
改正育児・介護休業法は今年4月と10月の2回に分け、施行されます。
4月施行分の改正内容は以下の9点となります。
1 子の看護休暇の見直し
- 対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大
- 取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が追加
- 継続雇用期間6か月未満の者の労使協定での適用除外の見直し
- 子の看護等休暇への名称の変更
2 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 小学校就学前の子まで対象範囲を拡大
3 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加
4 育児のためのテレワーク導入
- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置の努力義務化
5 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務の対象が従業員300名超の企業に拡大
6 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 継続雇用期間6か月未満の者の労使協定での適用除外の見直し
7 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにする措置の義務化
8 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務化
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供の義務化
9 介護のためのテレワーク導入
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できる措置の努力義務化
具体的な対応としては、まずは育児・介護休業規程の見直し、そして労使協定の再締結が必要となります。厚生労働省では規程サンプルの提供も含め、さまざまな情報発信を行っていますので、以下の資料を参考にしながら対応を進めましょう。
資料名 | 概要 | 資料URL |
|---|---|---|
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 | 今回の法改正の内容が簡潔にまとまった資料。全体像を把握するには最適な内容で、法改正対応のチェックリストとしても活用できる。 | |
育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説 | 今回の法改正の詳細が解説された資料。法改正対応を進めるにあたっては確実に押さえておきたい。 | |
育児・介護休業等に関する規則の規定例 | 今回の法改正に対応した育児・介護休業規程のサンプル。Word版もダウンロード可能。 | |
育児・介護休業法のあらまし | 今回の法改正だけでなく、育児・介護休業法の全体を解説した資料。 |

3分でわかる!「4月施行の育介休業法対応」5つのポイント
「育児・介護休業法」対応のポイントを、3分でチェックできる動画コンテンツにまとめました。
休憩時間や通勤時間に視聴して、実務対応の確認にお役立てください。
トピック2 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設
育児休業を取得した際には、育児休業給付金・出生時育児休業給付金の受給ができますが、4月からはさらに以下の2つの給付金が創設されます。
1 出生後休業支援給付金
- 子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間支給されるもの。
- 実務を行うにあたってはパンフレット「育児休業給付の内容と支給申請手続」を確認するとよいでしょう。
2 育児時短就業給付金
- 2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下するなど一定の要件を満たす場合に支給されるもの。
- 実務を行うにあたってはパンフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」を確認するとよいでしょう。
各給付金の対象範囲は以下のようになっています。制度の全体像を把握したうえで、申請漏れがないように確実に管理していきましょう。

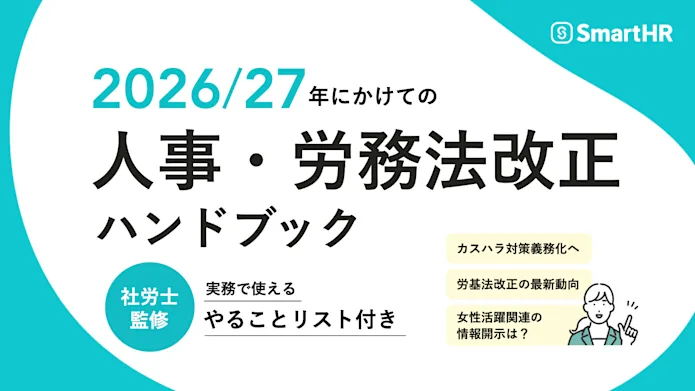
2026/27年にかけての人事・労務法改正ハンドブック
この資料でこんなことが分かります
- 2026年の人事・労務業務に影響する法改正
- 2027年以降の人事・労務業務に影響する法改正
- 人事・労務担当者 やることリスト
トピック3 障害者雇用における除外率の見直し
障害者雇用促進法では、障害者の職業安定のため、法定雇用率を設定しており、2025年4月現在では、民間企業においては2.5%(令和8年4月以降は2.7%に引き上げ)とされています。
その際、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度が設けられていました(除外率制度)。
この制度は平成16年4月に廃止されましたが、現在は経過措置として、段階的に縮小されています。4月からは下表のようにそれぞれ10ポイント引き下げられています(従来、除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となりました)。
引き下げの対象となった業種については従来よりも多くの障害者を雇用する必要がありますので、自社の雇用障害者数が法定雇用人数を満たしているかを確認し、不足する場合には追加での採用を進めましょう。
トピック4 高年齢雇用継続給付の見直し

高年齢雇用継続給付は、高年齢者が意欲をもって働き続けられるよう、65歳までの雇用継続を促す制度です。具体的には、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合に、各月に支払われた賃金の最大15%が支給される仕組みです。
この給付の仕組みが4月から改正され、支給率が引き下げられています。
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない者はその期間が5年を満たすこととなった日)が2025年4月1日以降の者については、以下のように各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

従来と比較すると支給率が引き下げられていますので、対象となる従業員に説明しましょう。なお、これを契機として高齢者の雇用・賃金の仕組みの見直しを検討する企業も増加していますので、必要があれば対応を進めましょう。
トピック5 一般事業主行動計画の見直し
一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援し、働きやすい環境を整えるために策定する計画です。この計画は「次世代育成支援対策推進法」に基づき、一定の期間内で達成すべき目標を設定し、その目標を実現するための具体的な対策と実施時期を定めます。また、子育て中の従業員だけでなく、すべての従業員が働きやすい職場環境をつくることも目的の一つです。
従業員数100人超の企業が、2025年4月1日以降に行動計画を策定または変更する場合は、以下の事項の対応が義務づけられます(従業員数100人以下の企業は努力義務)。
- 計画策定時の育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)把握等(PDCAサイクルの実施)
- 育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
※1 男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」
※2 フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間等の労働時間
(参考)「一般事業主行動計画の策定・届出等について」- 厚生労働省
また、これに伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等も4月1日から改正されています。改正後の認定基準等の詳細は、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
法改正が相次ぐ4月、対応漏れに注意を
このように4月は法改正など、対応すべき事項が数多くあります。実務を行う上で必要な情報への資料も記載しておきましたので、そうした資料も確認しながら、対応漏れがないように実務を進めていきましょう。
最新情報を見逃さないように、人事・労務担当者の方はぜひ以下よりメールマガジンにご登録ください!

登録者5,000名突破!メールマガジン
人事・労務の業務で“すぐに使える”情報を週に1回発信しています。
- 読者の76%が「メルマガの内容を自身やチームの実務に取り入れている」と回答
- 限定コンテンツの閲覧や、有識者・同業者の方との交流イベントへの参加も
あなたの「気づき」につながる情報を、厳選してお届けします!