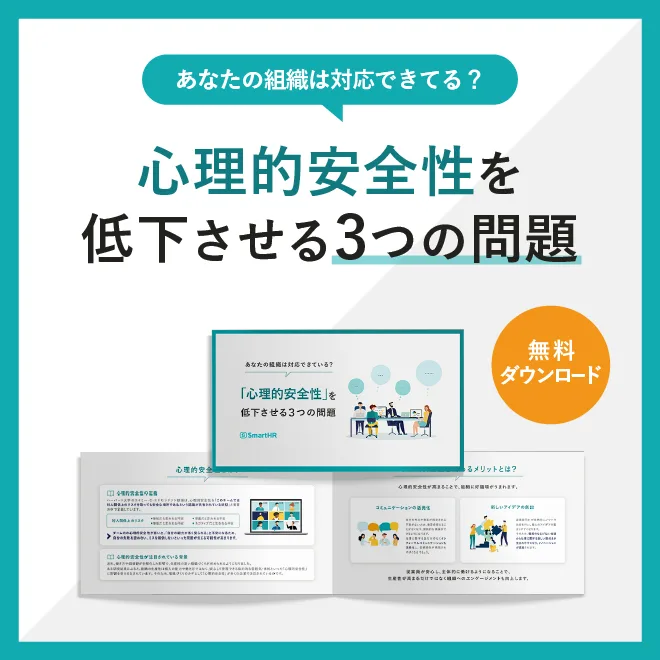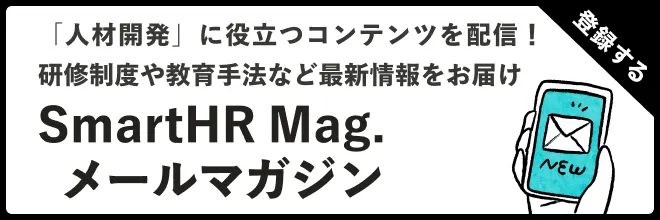なぜ今、人材育成が重要なのか?古代から現代まで、育成の歴史と本質
- 公開日
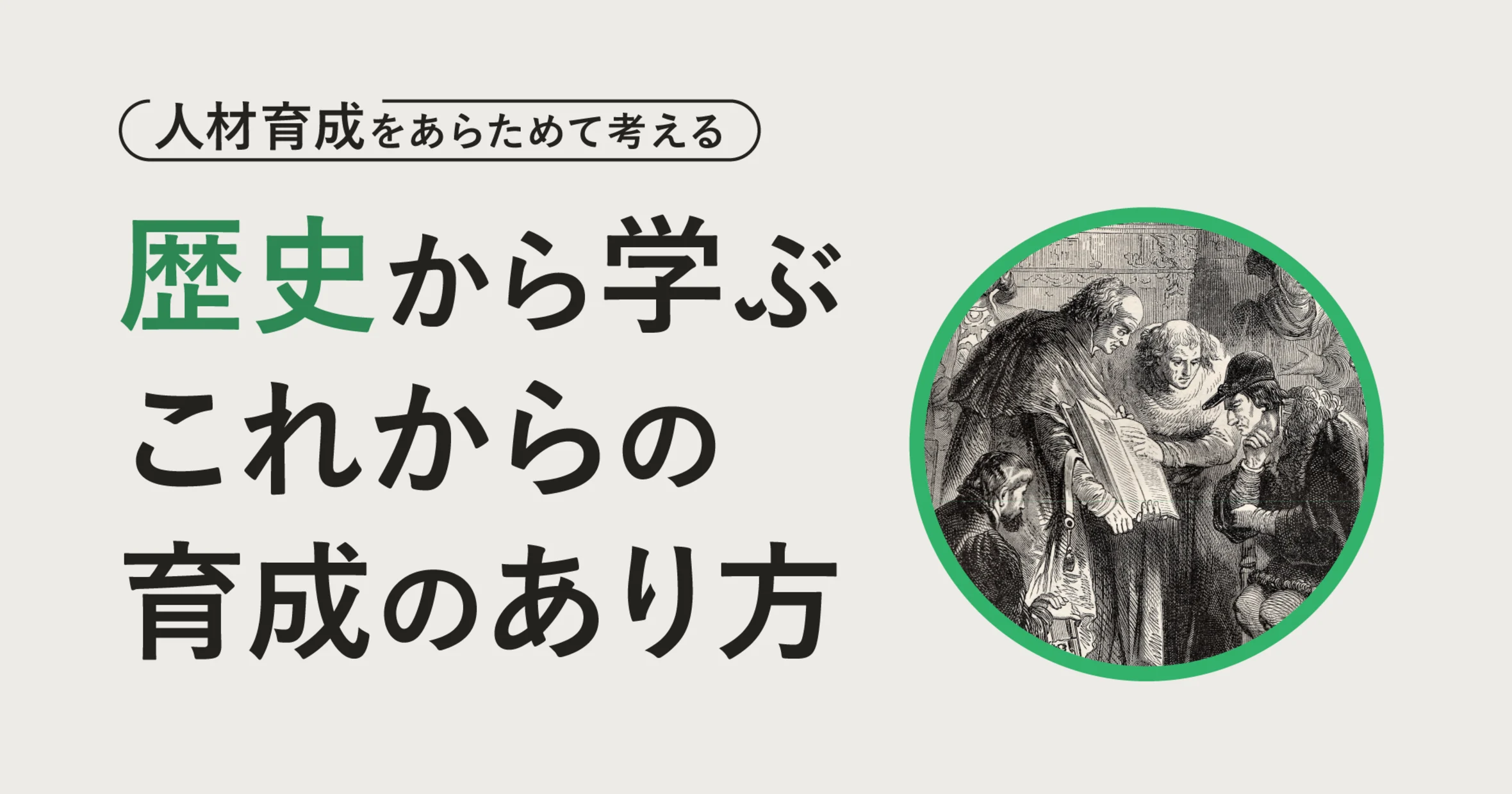
目次
こんにちは!人事職の経験を活かして、SmartHRで人事・労務業務に関する最新情報を社内外へ発信している穴原です。
現代のビジネスシーンでは、「人材育成」が重要なテーマとして取り上げられる機会が増えています。なぜこれほどまでに人材育成が注目されているのでしょうか。
本記事では、その答えを探るため、時代とともに変化してきた「働き方」と「育成の在り方」をひも解き、現代の人材育成の意義やこれからの時代に求められる視点を考察していきます。
労働の歴史と人材育成の進化
(1) 古代〜中世:職人文化と徒弟制度
古代エジプトや古代ギリシャ、中世ヨーロッパにおいて、労働は主に農業や工芸といった実務的なスキルが必要でした。こうした技術は、親から子、または熟練者から弟子へと直接的に継承されていました。また、中世のギルドでは徒弟制度が確立され、職人としての技術だけでなく、倫理観や社会的役割もふくめ、総合的に育成されました。
目的: 社会の安定に不可欠な技術や知識を次世代に継承すること

中世ヨーロッパの木製ターナー
(2) 産業革命:工場労働者の育成
18世紀後半に始まった産業革命は、労働の形を劇的に変えました。工場での大量生産が主流となり、従業員には作業の効率化が求められるようになったのです。この時代の人材育成は、作業の標準化と効率性向上に焦点を当てた短期間の訓練が中心でした。
目的:効率的な生産性向上と作業の均一化

(3) 20世紀前半:科学的管理法とフォーマルトレーニング
フレデリック・テイラーが提唱した科学的管理法は、労働の効率性を追求し、人材育成においても体系的なトレーニングの必要性を強調しました。また、第二次世界大戦中には、兵士や技術者を短期間で育成するプログラムが発展し、その後の企業研修にも影響を与えました。
目的: 組織全体の生産性向上を目的とした標準化された教育の導入

フレデリック・テイラー(画像引用:Wikipedia)
(4) 20世紀後半:個人の成長と能力開発
戦後の経済成長期には、個人の能力開発が重視されるようになりました。とくに日本では、終身雇用を前提とした企業内教育が普及し、新入社員研修や階層別研修が盛んに実施されました。また、アメリカではピーター・ドラッカーが提唱したマネジメント教育が広まり、リーダーシップや経営スキルの育成が注目されました。
目的:個人の成長を通じた組織全体の競争力向上
(5) 21世紀:デジタル化とリスキリングの時代
21世紀に入り、技術革新のスピードが加速し、AIやデータサイエンスといった新たなスキルの需要が急増しています。オンライン学習やマイクロラーニングなどの新しい学びの形が普及し、柔軟かつ個別化された育成が可能となりました。政府や企業も積極的にリスキリング(新たなスキル習得)やアップスキリング(既存スキルの向上)を推進しています。
目的:技術革新と市場変化に対応する柔軟な人材育成

今、なぜ人材育成が重要なのか
歴史を振り返ると、人材育成はその時代ごとの社会や経済のニーズに応じて進化してきたことがわかります。現代において人材育成の重要性が高まっている背景には、以下の4つの要因があげられます。
(1)少子高齢化による人材不足
少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少していくなかで、昨今では人手不足を理由とした倒産も発生しています。既存の労働力を最大化させるには、スキルを高めることが喫緊の課題となっています。



(2)技術革新
技術革新にともない、AIやデータ分析能力など新たなスキルの習得が求められています。しかし、この人材不足時代にスキルをもちあわせた人材を採用するのも限界があるため、企業は社内人材の育成にも力を入れていることが「デジタル時代のスキル変革等に関する調査(2023年度)」から読みとれます。

(3)キャリア自律
キャリア自律とは、「自身のキャリアを自らの意思で設計し、成長の道筋を描くこと」を指します。これは、変化の激しい時代において重要なスキルであり、人材育成の要とも言えます。しかし、「『リスキリング/アンラーニングを起点とする人材育成と組織開発』に関する共同調査」によると、「従業員のキャリア自律意識を高められていない」と回答した企業は約5割にのぼり、多くの企業が課題を抱えていることがわかります。

「リスキリング/アンラーニングを起点とする人材育成と組織開発」に関する共同調査 - マンパワーグループ株式会社/HR総研
(4)グローバル化
経営のグローバル化は国内市場の縮小などを背景に、日本経済の持続的な成長と競争力を維持するために不可欠と言えます。グローバル人材の需要は増加の一途を辿る一方で、「第12回 日系企業における経営のグローバル化に関するアンケート」から「グローバル人材の確保と育成」がグローバル経営を阻む最大の課題となっていることがわかります。

歴史から学ぶ人材育成の本質
労働の歴史をひも解くと、人材育成の本質は「スキルの継承」と「未来への適応」の両立にあることがわかります。どの時代においても、社会の変化に対応するための育成が不可欠でした。
現代では、テクノロジーの進化がとくに速いため、企業や個人が「学び続ける仕組み」を構築することが重要です。歴史をふまえれば、今求められているのは、柔軟性と持続可能性を備えた人材育成のアプローチです。
未来の人材育成に必要な視点
現代の人材育成は社会的・経済的課題の解決に直結することがわかりました。では、未来の人材育成では、どのような視点が重要になるでしょうか。
(1)変化への対応力
AIなどの技術革新は、既存の仕事や生活様式を大きく変える可能性があります。変化を恐れず、新しい技術を学び、活用できれば、変化の波を乗り越えて新たなチャンスを掴めるでしょう。
(2)問題解決能力の強化
現代社会は、地球温暖化、貧困、格差など、複雑で解決が難しい問題に直面しています。これらの問題を解決するためには、論理的思考力、批判的思考力、そして創造性を駆使して、多角的な視点から解決策を探求する必要があります。
(3)生涯学習の促進
知識や情報は常に更新されています。社会人になってからも、常に新しい情報や技術を学び続けることで、自身の市場価値を高め、キャリアアップにつなげることが求められます。
(4)デジタルリテラシーの向上
デジタル技術は、あらゆる産業や分野で活用されています。デジタルリテラシーを高めることで、仕事の効率化、新たなビジネスの創出、そして社会貢献につながるでしょう。
(5)多様性の尊重
グローバル化が加速する現代において、異なる文化や価値観をもつ人々と共存し、協力していくことはますます重要になっています。多様性を尊重することで、よりよい人間関係を築き、より豊かな社会を創造できます。
さいごに
企業、政府、そして個人がそれぞれの役割を認識し、協力して人材育成に取り組むことで、私たちは変化の激しい時代を乗り越えられるでしょう。
とくに、個人は「学ぶ」という行為を、単に知識を詰め込むのではなく、自己成長と社会貢献の手段として捉える必要があります。自ら学び、考え、行動することで、変化に主体的に対応し、未来を創造できるのではないでしょうか。

お役立ち資料