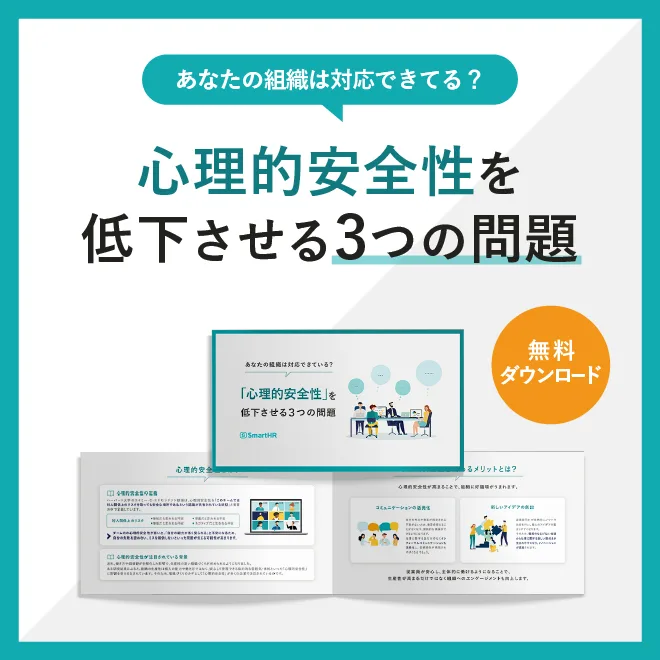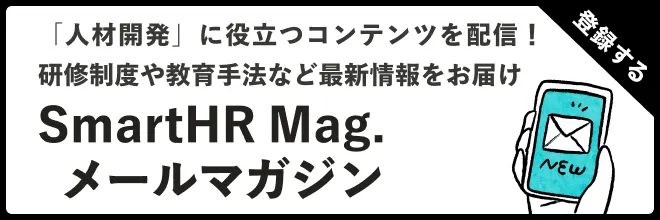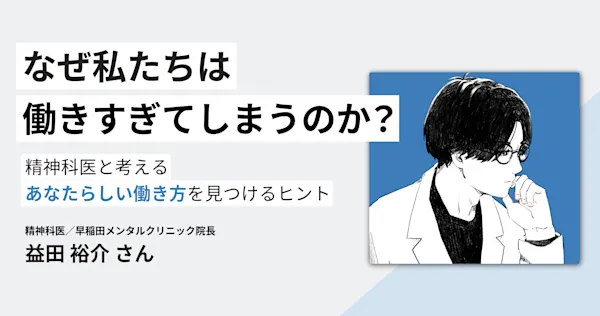優秀人材の「特別扱い」と「周囲の納得」を両立させるには?ー神戸大学 服部教授と解く、これからの人事課題
- 公開日
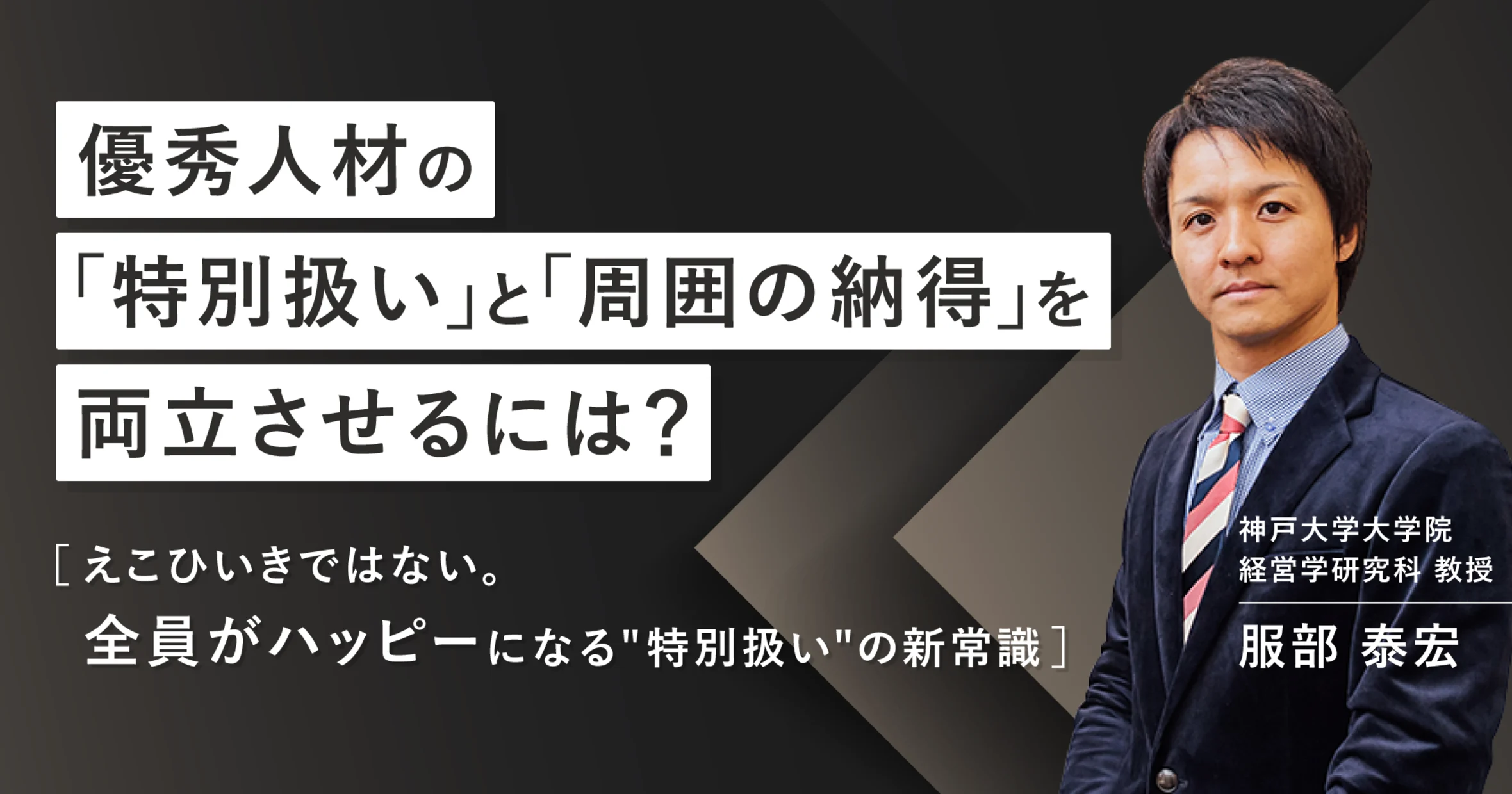
目次
成果を挙げる優秀な人材を正当に評価し、組織で活躍してもらう──それは組織の成長に欠かせません。しかし、優秀人材に対する評価や処遇が、時に「不公平感」や「分断」を生んでしまうこともあります。
優秀人材を適切に評価・育成しながらも、組織全体の納得感を得ていくには、どのようなアプローチが求められるのでしょうか。
今回は、神戸大学大学院経営学研究科にて、組織開発および人材の採用・評価・育成に関する研究をされている服部泰宏教授にお話を伺いました。
「優秀人材をどう見極め、どう育てるか」「“特別扱い”と納得感をどう両立させるか」これからの人事が向き合うべき問いを掘り下げていきます。
※SmartHRでは経営層のみなさまを対象に、ゲストスピーカーを招いた少人数制のオフライン交流会を定期的に開催しています。本記事はPeople Trees合同会社と共催した講演の内容をもとに制作しております。

神戸大学大学院経営学研究科 教授
滋賀大学専任講師,同准教授,横浜国立大学准教授、国立大学法人神戸大学准教授を経て、 2023年4月より現職。日本企業における組織と個人の関わりあいをコアテーマに、経営学的な知識の普及の研究、日本、アメリカ、ドイツ企業の人材採用に関する研究などに従事。2018年以降は、企業内で圧倒的な成果を挙げる「スター社員」に関する研究も行っている。 2010年に第26回組織学会高宮賞、 2014年に人材育成学会論文賞、 2016年に日本の人事部「HRアワード」書籍部門最優秀賞受賞、 2019年に日本の人事部「HRアワード」書籍部門入賞、2020年に労務学会賞(学術賞)および、労務学会賞(奨励賞)を受賞。
「客観的な成果=評価」とは限らない
日本企業の「平等」がもたらすリスク
日本企業は「スター社員」と呼ばれるような優秀人材とそうでない人材の間に、大きな格差をつけない傾向があります。それでは優秀な人材に納得してもらえません。「成果を正当に評価しない会社だ」という評判から採用に悪影響が出たり、「がんばってもがんばらなくても評価は同じだ」と従業員のモチベーションを低下させ、人材の流出を招きます。この問題をどのように解決すべきかが、私の問題意識です。

『成功の科学』に見る評価の本質
優秀人材は「成功者」と言い換えることもできます。それでは成功者とはどのような人を指すのでしょうか。理論物理学者のアルバート=ラズロ・バラバシは著書『THE Formula』のなかで、スポーツ・アート・サイエンスなどの世界で圧倒的な成功を収めた人たちのデータを分析し、「成功に普遍的な法則はあるのか?」という問いを科学的に解明しました。
スポーツ界のように成果が定量化できる世界では、そうした成果と、収入や評価は相関します。しかし、世の中のほとんどの仕事は客観的なパフォーマンスが測定できない世界です。そこで重要になるのが活動する場所、人とのつながりといった客観的なパフォーマンス以外の要素だと、バラバシ氏は分析しています。それらが、チャンスの巡り合わせや知的刺激をもたらし、人的資本以上の価値をもたらすからです。
また、客観的なパフォーマンスには上限があります。突出して優秀な人材といっても、定量成果だけ見るとほかの人材と大差はありません。それなのに、収入や評判にはとてつもない差が出る。社会では、客観的なパフォーマンス以外の要素によって、成功度合いが大きく左右されることがわかります。
こうした話をすると「すごい人はすごいから、それに見合う高い評価・高い報酬をもらうのは当然だ」というリバタリアン的な考えに聞こえるかもしれません。私の考えはむしろ逆で、「だからこそ組織は本当に価値ある人材を正しく見極め、評価する必要がある」という点にあります。現在、高い評価、高い報酬を得ている人は、本当にふさわしい人でしょうか?
人事評価と評判はどこまで一致するのか?
それでは、優秀人材とはどのように決まるのでしょうか。ひとつの指標となるのが「人事評価」と「評判」です。次の図は、横軸を「上司による人事評価」、縦軸を「評判」として、ある日本企業の従業員をプロットしたものです。

服部泰宏教授作成 イベント登壇資料をもとに弊社作成
評判については、同期入社の従業員のリストを配り、次の3つの観点それぞれについて会社に貢献していると思う人を最大6名まで指名してもらい、上位から順にランク付けしました。その際、「人事評価とは関係なくあなたの感覚で指名してください」とお願いしています。
- とくに高い仕事成果を挙げている人物
- 仕事成果に直結しないが、周囲のメンバーによい影響を与えている人物
- 人格的に尊敬できる人物
右下の緑の象限は「人事評価は高いが評判は低い」人たち、左上の黄色い象限は「評判が高いが人事評価は低い」人たちです。上司による人事評価と周囲の評判との間にギャップがあることがわかります。両者の相関係数も0.187で、それほど高くはありません。人事評価と評判とは無関係ではないものの独立性が高く、誰がどうジャッジするかで結果が変わってきそうです。
そこで気になるのが、「人事評価」と「評判」に影響を与える要因です。先ほどとは別の日本企業で同様の調査をしたところ、上司による「人事評価」は関係の良さとの相関が高く、直近のがんばりに引っ張られる傾向がありました。一方で「評判」は、「いいプロジェクトにアサインされている」「偏差値の高い大学を出ている」といった要素に弱いことがわかっています。
人事評価と評判とは必ずしも一致せず、双方に限界があり、どちらの指標がすぐれているとも言い切れない。そのような結果が、2つの調査結果から浮かび上がってきました。だからといって、人事評価や評判に意味がないわけではありません。重要なのは、こうした限界を認識したうえで自社の評価のあり方を見直し、どのような評価が適切かをフラットに考えることだと思います。
優秀人材を優秀人材たらしめる要素とは
優秀人材のキャリアには「共通する経験」があった
優秀人材は客観的な成果をコンスタントに挙げるだけでなく、その成果を増幅させる要素をもっているのではないでしょうか(公式 A)。
スターの形成=複数の顕著な成果 × 成果の増幅(公式A)
私はそのような仮説から、優秀人材に対して「これまでどのような経験をしてきたのか」を調査してみました。その結果、共通していたのは次のような経験でした。

服部泰宏教授作成イベント登壇資料をもとに弊社作成
修羅場やタフな経験が共通項です。だとすれば、「人事として何ができるだろうか、育成問題にどう向き合うべきか」という問いが浮かびます。
優秀人材は「経験から学ぶ力」が高い

「優秀人材」へと成長していくためには、先ほど挙げたような経験をすることが重要です。ここで注意したいのが、経験から学ぶ能力には個人差があります。こうした考え方からできたのが公式Bです。
複数の顕著な成果=適切な経験 × 経験から学ぶ力 + 学習支援(公式B)
同じ経験をしても、そこから学習して成長していける人もいれば、そうならない人もいる。自らPDCAを回して学習していく。この力が強い方であればレバレッジが効いて成長していきます。
学習支援、組織としてできる支援としては、内省支援や1on1などを通じて経験を言語化していく手助けが考えられます。
「尖った人材」を見逃さず発見・育成するには
これまでいくつかの企業を見てきて、優秀人材をすばやく発見して光を当てる取り組みの重要性を実感しました。こうした経験からできたのが、公式Cです。
成果の増幅=成果の発見 × 成果の流布 × リソース配分 × 脱線へのフォロー(公式C)

服部泰宏教授作成 イベント登壇資料をもとに弊社作成
ここで大事なのが、成果の発見=優秀人材を発見する基準を複数もっておくことです。人事評価ではその人の業務上の成果だけでなく、チームワークや管理能力などさまざまな側面から評価をする。人事評価だけではなく評判も参考にするなど、基準を複数もっておくことで、こうした人材を見逃さず発見できます。
「成果の流布」とは、特定の部署や事業で挙げた成果を全体に周知することです。成果を上げた人に対してより多くの挑戦機会を提供することにつながります。
また「リソースの配分」とは、評価されたことを活かせる場をつくることです。昇進はもちろんひとつの手段ですが、その人が生き生きと働けるプロジェクトにアサインするなども効果的な手段です。
「脱線へのフォロー」は、優秀人材を優秀であるがゆえに陥りがちな罠から守ることです。早くから活躍して注目されると「自分は特別なんだ」と傲慢になったり、謙虚さを失って過去のやり方に固執したり、当初問題ではなかった弱みが顕在化したりするリスクが高まります。こうした脱線を防ぎ、優秀人材がさらに成長していけるようフォローすることが大切です。
優秀人材の「特別扱い」と「周囲の納得感」を両立させるには
人事は「トライアド」に挑まなければならない
優秀人材を適切に評価することは、特別扱いをすることでもあります。そこで出てくるのが、特別扱いされない周囲の人たちをどう納得させるのかという問題です。この問題を解決するヒントになるのが、カーネギー・メロン大学のデニス・ルソー教授が提唱した「I-deals(個別配慮)」という概念です。
I-dealsとは「特異的な扱い(idiosyncratic)」と「従業員、雇用者双方にとって理想的(ideal)」を合わせた造語で、「特定の社員に対して、他の社員に対しては認めていないような条件を、個別交渉を通じて認めること」だと言います。
「えこひいき」とは、私情や好き嫌いにもとづく不公平な扱いを指しますが、I-dealsはそうではありません。「I-deals(個別配慮)」は、本人にとっても、組織にとってもよい結果をもたらす——つまり、関係者全員がハッピーになるための“特別扱い”なのです。

I-dealsをうまく機能させる鍵となるのが「トライアド(三者)」の考え方です。これからの人事は、従来の「組織」と「従業員」という二者の関係ではなく、「組織」と「特別扱い(I-deals)を与える従業員」、「その他の従業員」の三者の関係で考えなければならない、とルソー氏は言いました。
優秀人材を“特別扱い”することを避けられない。そしてその“特別扱い”を周囲に納得してもらうことにも、向き合っていかなければならない。トライアドの考え方は、組織にそう突きつけているのです。
周囲へのネガティブな影響を弱める要因と強める要因
それでは、周囲の従業員はどうすれば優秀人材の特別扱いを受け入れてくれるのでしょうか。Gachayevaらの研究(2024)によると、ネガティブな影響を弱める要因には次のようなものがあります。
- 特別扱いの導入について意見を言えること
- 将来、自分にも提供される可能性があること
- スターの高い成果を実際に観察すること
反対に、ネガティブな影響を強める要因には、次のようなものがあります。こうした要因がシニシズム(冷笑主義)の増加や悪い嫉妬の感情、仲間への支援的行動の低下などにつながります。
- 強い個人主義的価値観
- 秘密で行なわれ、それが顕在化すること
優秀人材の“特別扱い”と周囲の納得感を両立させる3つの方法
特別扱いがもたらすネガティブな影響を弱め、優秀人材の特別扱いと周囲の納得を両立するには、どうすればいいのでしょうか。この問いに対して、私は3つの仮説をもっています。

服部泰宏教授作成 イベント登壇資料をもとに弊社作成
1つ目は、特別扱いの条件やルール、手続きをクリアにしていくこと(手続き的公正)です。多面的な評価の実施や、評価基準の透明性なども含まれるでしょう。「なぜ特別扱いされているか」が明確なら、自分もそれを満たせば特別扱いが受けられるという納得感につながるのです。
2つ目は、上司と本人とのコミュニケーションで、他者との比較を解除していくことです。優秀人材に対しては「社外にはもっとすごい人がいるから謙虚になろう」、周囲に対しては「人を羨むばかりではなく、もっと視野を広げよう」と伝え、お互いに対する不信感の払拭をしましょう。
3つ目は、価値観を丁寧に浸透させていくこと(倫理 / 関係性レンズの提供)です。「仕事は1人ではできない」と頭ではわかっていても、本当に理解するのは難しいものです。そこで上司や人事担当者が中心となってこうした価値観を浸透させましょう。「あの人に勝たなきゃだめだよ」「同僚に負けている」など競争や勝敗、比較を連想させる言葉自体を日頃から使わないようにするのも効果的です。

組織ごとに紡ぐ最適解
優秀な人材をきちんと評価し、しかるべき機会を提供することは、組織の未来を創るうえで欠かせません。同時に、それが周囲に与える影響に目を向け、納得感をどう築くかという問いにも真正面から向き合う必要があります。
自社にとって最適な評価とは何か。これらは唯一の正解がある問いではなく、組織ごとに異なる答えを紡いでいくものです。人的資本経営が注目される今だからこそ、誰のどのような成長を後押しするのか、組織としてどのような未来を描きたいのかーーこうした根本的な問いに向き合うことが、納得と成長を両立させる第一歩ではないでしょうか。
執筆:株式会社Tokyo Edit
撮影:其田 有輝也