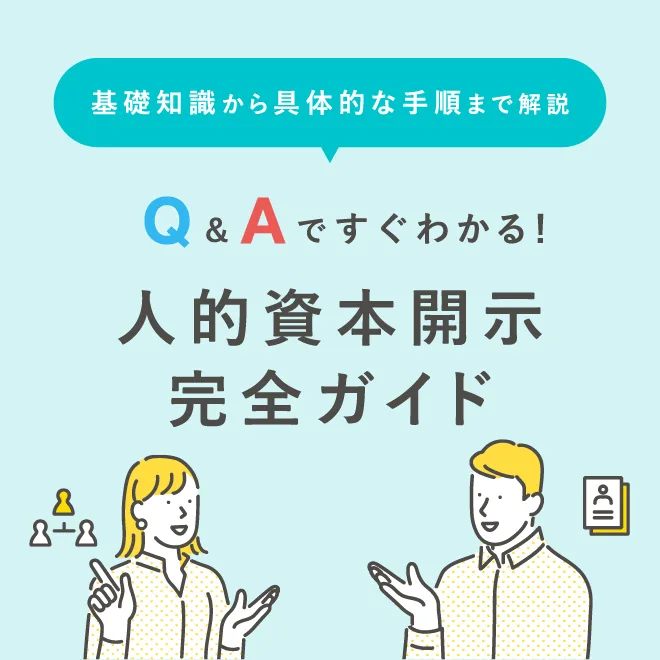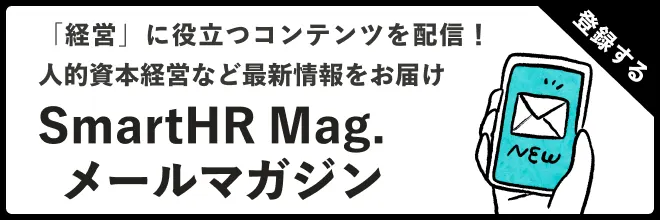鍵は柔軟なシステムと制度。研究が示す、人事投資と生産性の相関
- 公開日
ビジネス環境の変化が加速する昨今、柔軟に人材を活かす力は企業の成長を大きく左右します。HRテクノロジー研究の第一人者・岩本隆氏は、人事評価制度のデジタル化や定期的な見直しが生産性・売上向上につながるといった研究に携わるとともに、データ活用で個を活かす「プロスポーツ型人事」を提唱してきました。個の力を最大化する新たな人材マネジメントの姿と実現を阻む壁、打開のためのヒントを聞きました。

東京大学工学部金属工学科卒業。米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院応用理工学研究科マテリアル応用理工学専攻にて博士号(Ph.D.)取得。日本モトローラ株式会社、日本ルーセント・テクノロジー株式会社、ノキア・ジャパン株式会社、株式会社ドリームインキュベータを経て、2012年から慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授、同大学院政策・メディア研究科特任教授を歴任。2023年から慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、山形大学客員教授を務める。
人事投資は効果が見えにくい?研究が示す生産性・売上への貢献
岩本先生は、各種メディアや講演を通じて「人事こそテクノロジーの最前線に」と提言されてきました。人事領域への投資は定量的な効果測定が難しいとされるなか、過去の研究では、人事評価のデジタル化が生産性向上につながることもデータで示されていますね。
岩本さん
はい。2016年から17年にかけて、IT導入補助金を活用して人事評価制度を整備した47社を対象に、生産性の変化を分析しました。具体的には、導入前と導入後の従業員数、年間平均労働時間、付加価値額といったデータをもとに、人事評価制度と生産性の相関を算出しました。
その結果、全体として生産性が向上する傾向が確認されました。つまり、IT(=HRテクノロジー)による評価制度の整備が、労働生産性の向上に寄与する可能性が示唆されたのです。(参照:人事評価制度を活用した人材確保と賃金向上)
人事評価制度は従業員の活躍や成長を支援する基盤でもあるので、制度を整えることで業績が上がるのは、考えてみれば当然のことです。実際、大企業ではこうした取り組みが「基本のキ」になっていますが、中小企業ではまだ十分に浸透していないのが現状です。
この論文が発表された2019年以降、そのことは知られつつあるのでしょうか。
岩本さん
論文を執筆した当時は事例も限られていました。しかし、その後、中小企業庁が政策として取り上げ大規模な調査を実施しました。そこから得られたエビデンスも発信もされ、認知が広まりつつあります。
中小企業庁は、帝国データバンクに委託して、2021年11~12月に、従業員5人以上の中小企業2万社を対象にアンケート調査を実施(回収4,341社、回収率21.7%)し、その結果を『2022年版 中小企業白書』で公表しました。
その結果、人事評価制度を導入している企業ほど売上高の増加率が高いことが明らかになりました。さらに制度を定期的に見直している企業ではその効果が顕著です。反対に、10年以上見直していない企業では増加率がとくに低いことが判明しました。
中小企業庁の調査から、人事評価制度の硬直化が企業の成長に与える影響や経営層が認識すべきリスクなど、読み取れることはあるでしょうか。
岩本さん
10年以上見直していない企業の売上が伸び悩むのは、人事評価のモノサシが古く、これから事業に必要な行動や挑戦を正しく評価できていないからです。“人事評価制度の硬直化”は、企業の人材ポートフォリオの変革を阻害し、売上停滞を招いています。
経営層が「ウチには人事評価制度があるから大丈夫」と“安心”してしまうこと自体がリスクです。従業員が「人事評価が事業の実態に合わない」と感じた瞬間、人事評価制度は“不満の源泉”と化し、優秀な人材の流出につながりかねません。
また、この「見直し」を妨げる要因の一つとして、データの管理方法があります。人事評価基準や項目が表計算ソフトや紙に分散していては、見直すこと自体が一大プロジェクトになります。データを一元管理し、柔軟な変更に対応できる“システム(HRテクノロジー)”の有無が、見直しの頻度と質を左右することになります。

金太郎飴型から「プロスポーツ型人事」へのシフト
岩本先生は「プロスポーツ型人事」へのシフトを提言されていますね。その理由は?
岩本さん
プロスポーツ型人事とは、データにもとづく評価と役割の明確化により、従業員それぞれをプロとして活躍させるチーム運営です。メジャーリーグなどを想像してもらえるとわかりやすいでしょう。一人ひとりのポテンシャルを引き出して能力を最大限に発揮できるようにし、活躍した分に報いる。また、一人ひとりの成長も同時にサポートすることで、企業の持続的成長につなげていく。
トップダウンで全員が同じ方向に動く“金太郎飴型”の組織では、業績も成長も頭打ちになってしまう。これからは、現場からアイデアや行動が生まれるボトムアップの力が不可欠です。そのためにも「プロスポーツ型人事」への転換が求められると考えています。
これを実現するためには、人事領域におけるデジタル基盤の整備が欠かせません。
デジタル基盤の整備とは、具体的にどのようなものでしょうか。
岩本さん
まずは、勤怠管理や給与計算など日々の労務業務を支える基幹システムを整備し、人事部門の業務効率を高めることが出発点となります。
そのうえで人事評価制度をデジタル化・データ化し、個々人のパフォーマンスや成長を継続的に把握しながら、能力開発、さらに人材配置の最適化に活かしていくべきです。
システムで目標の進捗や成果を日常的に記録・更新すれば、評価のタイミングだけではなく、日々の業務のなかで「いまどの段階にいるのか」「どんなサポートが必要か」を継続的に対話しやすくなります。
こうした仕組みを整えることで、上司が普段から社員一人ひとりの「プロ」としての活躍と成長を支援でき、個人の強みを起点とした新たな価値創出が生まれ、組織全体の業績向上につながります。
人事・労務データ統合で実現する「最適な人材配置」
先生の提唱する「プロスポーツ型人事」について、いざ導入・実現するとなると、そこにはどのような「難しさ」や「課題」があるとお考えですか。
岩本さん
やはり大きな課題は、人事・労務データの統合にあると思います。
プロスポーツ型の人事で肝心なのは、人材配置です。しかし「このポジションは重要だ」と判断しても、適性、実績、ポテンシャルといった多面的なデータがなければ、適切な人材は選べません。
小さな企業であれば経営者が個々を直接把握できているかもしれませんが、数百人、数千人規模になると、データによる可視化なしに経営層が適切に人材をマネジメントすることはほぼ不可能です。
現状は、人事・労務データが部門ごとの表計算ソフトのファイルなどに分散し、統合的に管理されていない企業も少なくありません。こうした古い人事基幹システムでは、採用、育成、評価、異動などの人事データに加え、従業員の働き方や生産性を示す勤怠や給与といった労務データなど人材に関するデータすべてを俯瞰できず、現場の実態を踏まえた意思決定が難しくなります。
ある大手企業のCHROは「多くの企業ではCEOの周辺にいる役員は、体系的な人材登用のプロセスを経て選ばれているわけではなく、CEOに近しい人たちで固められている」と指摘していました。実力や客観的な評価ではなく、“誰の側にいるか”によって次期社長や副社長といったポジションが決まってしまう。
これは、データによる人材マネジメントを実施していないからで、このような構造はいまだ日本企業の一部に根強く残っているのです。
データ統合を進めるには、何が必要だとお考えですか?
岩本さん
本来であれば、評価、勤怠、給与、スキル、配置履歴など、人材に関するすべてのデータをクラウド上のアプリケーションに一元化するのが理想です。実際に人事・労務データを統合しようとする動きも広がりつつあります。しかし現実には、とくに大企業では部門ごとに異なるシステムを導入しており、完全な統合は容易ではありません。
一元化を一気に進められない場合は、人的資本経営を進めるにあたって最も重要な指標(KPI)を設定し、それらの指標についてのデータマネジメントから取り組んでいくとよいでしょう。

変革は、テクノロジーと意識改革の両輪で
データが集まりやすく、管理しやすい環境づくりが欠かせないのですね。システムのほかに、プロスポーツ型の人事を実現するために大切なことはありますか?
岩本さん
もちろんテクノロジーを導入するだけでは、真の変革は起こりません。
プロスポーツ型の組織づくりを進めるためには、データを活用した能力開発や人材配置に加えて、個人の成果を正しく評価し、能力に応じた報酬や役割を与えることも重要です。そのためには、人事評価制度そのものを年功序列から成果主義に変えていく必要があります。
人事制度のあり方に正解はひとつではなく、年功序列と成果主義、ジョブ型とメンバーシップ型をどう組み合わせるか、企業ごとに試行錯誤が続いています。重要なのは、自社の状況にあわせて柔軟に制度を見直し続けることです。
また、従業員も組織を越えて流動的に働くことを前提に、各自が価値を高めていく——。そうした意識や文化の変化も、テクノロジーの活用と並行して求められているのではないかと思います。
テクノロジーの導入は人材活用の“仕組み”を変え、意識変革はその仕組みを“文化”に変える。両輪で進んで初めて、一人ひとりが活躍できるプロスポーツ型人事が実現するといえるでしょう。
(取材・文/POWER NEWS編集部、写真/横関一浩)